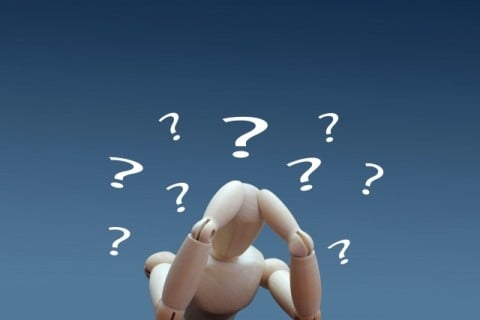【編集後記】12月21日号
1万3千円の牛串
2023年も残すところ一週間あまり。今年を振り返るとコロナ禍からの復活の一年であったと言える。都内にもインバウンドの姿が戻ってきた。
それに伴い、インバウンドビジネスも活況を呈している。築地場外市場に行くとインバウンド向けのテイクアウトグルメの値付けに驚く。
あるステーキ串の販売店では、A5ランクの和牛ステーキにウニをぎっしりと乗せたステーキ串が1万3000円で販売されている。誰が買うのかと店頭を見ると、欧米人が行列を作っているではないか。
WEB上で店舗の口コミを見てみると、外国人による高評価の口コミが多数。「このレベルの和牛をこの価格で食べられるのはお得。ステーキハウスで食べたら数百ドルする」といった内容もあった。
こうした事象から学べるのは、インバウンドビジネスでは、これまで日本人相手に行ってきた商売の常識を捨てることも必要ということ。築地場外市場に足を運ぶ度、価値とは何か考えさせられる。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年12月21日第5148号5面】
2023年も残すところ一週間あまり。今年を振り返るとコロナ禍からの復活の一年であったと言える。都内にもインバウンドの姿が戻ってきた。
それに伴い、インバウンドビジネスも活況を呈している。築地場外市場に行くとインバウンド向けのテイクアウトグルメの値付けに驚く。
あるステーキ串の販売店では、A5ランクの和牛ステーキにウニをぎっしりと乗せたステーキ串が1万3000円で販売されている。誰が買うのかと店頭を見ると、欧米人が行列を作っているではないか。
WEB上で店舗の口コミを見てみると、外国人による高評価の口コミが多数。「このレベルの和牛をこの価格で食べられるのはお得。ステーキハウスで食べたら数百ドルする」といった内容もあった。
こうした事象から学べるのは、インバウンドビジネスでは、これまで日本人相手に行ってきた商売の常識を捨てることも必要ということ。築地場外市場に足を運ぶ度、価値とは何か考えさせられる。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年12月21日第5148号5面】
【編集後記】12月1日号
飲食店の復活を願う
先日、長らく「貸店舗」と張り紙のあった会社近くの空き店舗の前に、「祝・開店」と札の立った生花が所狭しと並んでいるのが目に入ってきた。
元は居酒屋だった居抜き店舗に「すき焼き・しゃぶしゃぶ専門店」の真新しい看板が掲げられ、入口のガラス越しではあったが、来店客で賑わっているようだった。
新型コロナウイルスで最も影響を受けたのが、個人経営の飲食店だ。コロナの5類移行以後、活気が戻りつつある外食業界だが、現在の飲食店倒産件数は「コロナ禍超え」ペースで急増しているという。
コロナ禍中の経営を支えてきた時短協力金や休業補償金などの手厚い公的支援が打ち切られ、資金繰りに行き詰まって経営を断念するケースが目立っている。
コロナ禍によって「家飲み」という食文化は定着したが、ハレの日に手作りではなかなか口にできないプロの料理を食べに出かけるというのは、掛け替えのない楽しみの一つだ。
先頃行われた食品衛生功労者・優良施設の表彰式で来賓として挨拶した山東昭子参議院議員は「日本に訪れた外国人を飲食店にお連れすると、料理の美味しさと共に店内のキレイさに驚かれる。日本の飲食店の衛生レベルは、世界に誇れるもの」と語っている。
世界に誇れる日本の飲食店の復活を心から願う。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年12月1日第5147号13面】
先日、長らく「貸店舗」と張り紙のあった会社近くの空き店舗の前に、「祝・開店」と札の立った生花が所狭しと並んでいるのが目に入ってきた。
元は居酒屋だった居抜き店舗に「すき焼き・しゃぶしゃぶ専門店」の真新しい看板が掲げられ、入口のガラス越しではあったが、来店客で賑わっているようだった。
新型コロナウイルスで最も影響を受けたのが、個人経営の飲食店だ。コロナの5類移行以後、活気が戻りつつある外食業界だが、現在の飲食店倒産件数は「コロナ禍超え」ペースで急増しているという。
コロナ禍中の経営を支えてきた時短協力金や休業補償金などの手厚い公的支援が打ち切られ、資金繰りに行き詰まって経営を断念するケースが目立っている。
コロナ禍によって「家飲み」という食文化は定着したが、ハレの日に手作りではなかなか口にできないプロの料理を食べに出かけるというのは、掛け替えのない楽しみの一つだ。
先頃行われた食品衛生功労者・優良施設の表彰式で来賓として挨拶した山東昭子参議院議員は「日本に訪れた外国人を飲食店にお連れすると、料理の美味しさと共に店内のキレイさに驚かれる。日本の飲食店の衛生レベルは、世界に誇れるもの」と語っている。
世界に誇れる日本の飲食店の復活を心から願う。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年12月1日第5147号13面】
【編集後記】11月11日号
青年部会の進化
10月17日に開催された全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会。大会式典では自由民主党の茂木敏充幹事長が祝辞を述べた他、リングが設置された交流会ではプロレスや堀優衣さんの歌が披露され、全国から参加した青年部員に元気と勇気、感動を与えた。
ここ数年の全国大会を見ても、青年部会は時代の流れに対応し、進化を遂げている。コロナで1年の延期を余儀なくされた第39回大会新潟大会は、初のオンライン開催で2年ぶりの全国大会を実現。昨年の第40回広島大会は、岸田文雄首相のビデオメッセージが会場のスクリーンに映し出され、漬物産業への期待を口にした。
栃木大会は記念誌を発刊せずペーパーレスで実施するなど、SDGsをテーマに持続可能な全国大会の在り方を表現した。
残念ながら来年の第42回宮崎大会以降の開催地は未定で、現行形式による青年部会の全国大会は最後になる可能性がある。
今後については全漬連の組織委員会で協議されるが、どのような形でも漬物業界の将来を担う青年部会員が意見を交換し、業界の未来を創造する機会がなくならないことを願っている。(千葉友寛)
10月17日に開催された全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会。大会式典では自由民主党の茂木敏充幹事長が祝辞を述べた他、リングが設置された交流会ではプロレスや堀優衣さんの歌が披露され、全国から参加した青年部員に元気と勇気、感動を与えた。
ここ数年の全国大会を見ても、青年部会は時代の流れに対応し、進化を遂げている。コロナで1年の延期を余儀なくされた第39回大会新潟大会は、初のオンライン開催で2年ぶりの全国大会を実現。昨年の第40回広島大会は、岸田文雄首相のビデオメッセージが会場のスクリーンに映し出され、漬物産業への期待を口にした。
栃木大会は記念誌を発刊せずペーパーレスで実施するなど、SDGsをテーマに持続可能な全国大会の在り方を表現した。
残念ながら来年の第42回宮崎大会以降の開催地は未定で、現行形式による青年部会の全国大会は最後になる可能性がある。
今後については全漬連の組織委員会で協議されるが、どのような形でも漬物業界の将来を担う青年部会員が意見を交換し、業界の未来を創造する機会がなくならないことを願っている。(千葉友寛)
【2023(令和5)年11月11日第5145号16面】
【編集後記】11月1日号
餃子の寛容さ
全日本漬物協同組合連合会青年部会「第41回全国大会栃木大会」では、餃子に焦点が当てられた。餃子の食べ方といえば、タレと酢とラー油を卓上で調合するというもの。
各店こだわりの皮とタネを、絶妙な焼き加減で提供するという完成された料理のようでありながら、最後の仕上げは各々に任せるという不思議な料理だ。
もっと店が理想の味を押し付けても良いようなものだが、自由にさせてくれる寛容さこそ、餃子が愛されている理由だろう。
この精神は家庭料理にも取り入れて良いのではないか。完璧を目指して作った料理に調味料を足されると、否定されたような気分になることがある。
あえて薄味で、未完成なまま食卓にあげれば塩派も醤油派もソース派も満足。料理にかかるストレスも軽減できるはずだ。(小林悟空)
全日本漬物協同組合連合会青年部会「第41回全国大会栃木大会」では、餃子に焦点が当てられた。餃子の食べ方といえば、タレと酢とラー油を卓上で調合するというもの。
各店こだわりの皮とタネを、絶妙な焼き加減で提供するという完成された料理のようでありながら、最後の仕上げは各々に任せるという不思議な料理だ。
もっと店が理想の味を押し付けても良いようなものだが、自由にさせてくれる寛容さこそ、餃子が愛されている理由だろう。
この精神は家庭料理にも取り入れて良いのではないか。完璧を目指して作った料理に調味料を足されると、否定されたような気分になることがある。
あえて薄味で、未完成なまま食卓にあげれば塩派も醤油派もソース派も満足。料理にかかるストレスも軽減できるはずだ。(小林悟空)
【2023(令和5)年11月11日第5144号4面】
【編集後記】10月21日号
梅干し好きの理由
和歌山県漬物組合連合会が毎年10月に行う「梅干しで元気!!キャンペーン」の取材で、県内の小学校へ訪問した。組合員が、県内の小学校へ紙芝居「梅と梅干しの話」を持参し、クイズを交えながら南高梅の歴史や梅干しの健康性などについて講義した。
今回訪問したのは、白浜町立印南小学校で、小学4年生の児童21名が受講した。「梅干しが好きな人」と先生が質問すると、9割ほど手が挙がった。
なぜ、これほど梅干しが好きなのか。梅干しの味が好き、郷土を代表する食べ物で給食や食卓で頻繁に並ぶから。他県と比べて、梅干しと「頻繁」に接する機会があることは間違いない。
人間は、対象となる人や物に何度も触れているうちに好意の感情が芽生えてくるようで、心理学では「単純接触効果」と呼ぶようだ。
児童やその親、祖父母たちは、梅干しを見て、食べて、語る回数が他県より格段に多くなりやすく、それがきっかけで梅干しを好きになった人は少なくないはずだと感じた。(高澤尚揮)
【2023(令和5)年10月21日第5143号11面】
今回訪問したのは、白浜町立印南小学校で、小学4年生の児童21名が受講した。「梅干しが好きな人」と先生が質問すると、9割ほど手が挙がった。
なぜ、これほど梅干しが好きなのか。梅干しの味が好き、郷土を代表する食べ物で給食や食卓で頻繁に並ぶから。他県と比べて、梅干しと「頻繁」に接する機会があることは間違いない。
人間は、対象となる人や物に何度も触れているうちに好意の感情が芽生えてくるようで、心理学では「単純接触効果」と呼ぶようだ。
児童やその親、祖父母たちは、梅干しを見て、食べて、語る回数が他県より格段に多くなりやすく、それがきっかけで梅干しを好きになった人は少なくないはずだと感じた。(高澤尚揮)
【2023(令和5)年10月21日第5143号11面】
【編集後記】10月1日号
「国内・海外」「伝統・革新」
本紙9月21日号では、「第1回全国こんにゃくサミット」が9月2~3日に群馬県の高崎市で開催されたことを紹介した。
講演を務めた宇都宮大学の神代英昭准教授は、「こんにゃくメーカーは戦略を立案するにあたり、ローカル(国内重視)orグローバル(海外重視)、伝統or革新」と語り、次の4つの戦略パターンを述べた。
<4つの戦略>
①「ローカル・伝統」志向
②「グローバル・伝統」志向
③「ローカル・革新」志向
④「グローバル・革新」志向
こんにゃくに限らず、漬物や佃煮といった伝統食品は本来、定番商品(伝統性)が支持されやすく、また地域性が高いことからローカルな存在である。
けれども、国内の少子高齢化で新しい市場を狙うメーカーが出てきている。ただその場合、日本で愛されてきた味を守ると海外で受容されづらい、しかし革新的な商品にすると伝統性を失うというジレンマに陥ってしまう。
理想は、この4パターンすべてに対応して商品作りを行い、あとは消費者にゆだねることだろう。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年10月1日第5140号3面】
【2023(令和5)年10月1日第5140号3面】
【編集後記】9月21日号
【編集後記】9月11日号
こんにゃくの可能性
第1回「全国こんにゃくサミット」を取材した(1面参照)。全国トップの原料生芋生産を誇る群馬県にメーカー、原料業者、生産農家が一堂に会する貴重な集まりだったが、目玉企画であるグループミーティングで印象的だったのは、海外でのこんにゃく人気が上がっており、輸出額が増加しているという内容だ。
一般財団法人日本こんにゃく協会の清水秀樹理事長の話によると、群馬県におけるこんにゃく加工品の輸出額は、平成24年に約7900万円だったのに対し、令和4年には約4億2220万円と、この10年間でおよそ5倍に増加している(群馬県農畜産物等輸出推進機構調べ)。
県内企業からの聞き取り調査のため全ての企業動向を把握しているものではないが、逆にいえば実際にはもっと多いと考察できる。
海外でのこんにゃく人気が高まっている理由は、〝こんにゃく麺〟の進化だ。最近では太麺、細麺、ちぢれ麺、平打ち麺など、料理メニューに合わせて食べやすく加工された商品が続々と開発されている。
欧米は〝パスタ文化圏〟であり、さらにヴィーガンやベジタリアンが多く、低カロリー・低糖質のこんにゃく麺が、そのニーズに合致しているのだろう。
定番の板こんにゃくや、しらたきも工夫次第で様々な料理に利用できる。こんにゃくには、計り知れない可能性があると感じた。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年9月11日第5139号6面】
第1回「全国こんにゃくサミット」を取材した(1面参照)。全国トップの原料生芋生産を誇る群馬県にメーカー、原料業者、生産農家が一堂に会する貴重な集まりだったが、目玉企画であるグループミーティングで印象的だったのは、海外でのこんにゃく人気が上がっており、輸出額が増加しているという内容だ。
一般財団法人日本こんにゃく協会の清水秀樹理事長の話によると、群馬県におけるこんにゃく加工品の輸出額は、平成24年に約7900万円だったのに対し、令和4年には約4億2220万円と、この10年間でおよそ5倍に増加している(群馬県農畜産物等輸出推進機構調べ)。
県内企業からの聞き取り調査のため全ての企業動向を把握しているものではないが、逆にいえば実際にはもっと多いと考察できる。
海外でのこんにゃく人気が高まっている理由は、〝こんにゃく麺〟の進化だ。最近では太麺、細麺、ちぢれ麺、平打ち麺など、料理メニューに合わせて食べやすく加工された商品が続々と開発されている。
欧米は〝パスタ文化圏〟であり、さらにヴィーガンやベジタリアンが多く、低カロリー・低糖質のこんにゃく麺が、そのニーズに合致しているのだろう。
定番の板こんにゃくや、しらたきも工夫次第で様々な料理に利用できる。こんにゃくには、計り知れない可能性があると感じた。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年9月11日第5139号6面】
【編集後記】8月21日号
夏のスポーツに梅
記録的な暑さが続く中、中学3年生になる記者の次男は夏休みを利用して周辺にある高校を見学し、中学から始めたソフトテニスの練習会にも参加している。
7月30日に千葉県で1、2を争うソフトテニスの強豪校の練習会に参加した時のこと。休憩時に出てきたのが梅干しだった。顧問の先生は大きな容器いっぱいに詰められた梅干しをキャプテンに手渡し、「梅干しが苦手という子にも食べさせて。水分だけでなく、塩分も補給しないといけないから」と声をかけた。
その様子を見ていた記者は顧問の先生に近づき、「選手はいつも梅干しを食べているのですか」と聞くと、「夏はいつも食べています。梅干しは塩分やミネラルを補給できて、疲労回復効果のあるクエン酸も摂れるので。いつも市場で大量に買ってくるんですよ。昔からあるものは良いものしかありませんから」と梅干しと伝統食品の魅力を語ってくれた。
普段、梅干しを食べない次男は、「4、5粒食べた。酸っぱくてしょっぱかったけど、美味しかった」と大粒の汗を拭った。
梅干し効果もあったのか、北海道で行われた夏の全国高校総体で同校の選手(個人)は3回戦まで勝ち進む活躍を見せた。次男とともに貴重な経験ができ、梅の力を改めて感じる一日となった。
7月30日に千葉県で1、2を争うソフトテニスの強豪校の練習会に参加した時のこと。休憩時に出てきたのが梅干しだった。顧問の先生は大きな容器いっぱいに詰められた梅干しをキャプテンに手渡し、「梅干しが苦手という子にも食べさせて。水分だけでなく、塩分も補給しないといけないから」と声をかけた。
その様子を見ていた記者は顧問の先生に近づき、「選手はいつも梅干しを食べているのですか」と聞くと、「夏はいつも食べています。梅干しは塩分やミネラルを補給できて、疲労回復効果のあるクエン酸も摂れるので。いつも市場で大量に買ってくるんですよ。昔からあるものは良いものしかありませんから」と梅干しと伝統食品の魅力を語ってくれた。
普段、梅干しを食べない次男は、「4、5粒食べた。酸っぱくてしょっぱかったけど、美味しかった」と大粒の汗を拭った。
梅干し効果もあったのか、北海道で行われた夏の全国高校総体で同校の選手(個人)は3回戦まで勝ち進む活躍を見せた。次男とともに貴重な経験ができ、梅の力を改めて感じる一日となった。
(千葉友寛)
【2023(令和5)年8月21日号第5138号3面】
【2023(令和5)年8月21日号第5138号3面】
【編集後記】8月11日号
薄れゆくお盆
今年のお盆休みは最大10連休を取れる上、4年ぶりに行動規制がない夏とあって昨年よりも大幅に人出が増えるとの予測だ。
さてこのお盆とは、ご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する行事のこと。仏教に由来する行事であり、厳密には宗派や地域によって呼び名や時期が違うこともあるものの、概ね共通している。
こうした行事に欠かせないのが食である。仏教行事であるため動物性の食品は避け、そうめん、精進揚げ、団子、おはぎなどを食べるのがかつてはマナーとされた。漬物や高野豆腐とはお供え膳において、重要な位置を占める存在だ。
しかし近年はその在り方が変容し、好きなものを食べることを良しとする家庭が増えている。「社会人の夏休み」という認識で、里帰りをしない家庭も多いことだろう。伝統行事が薄れることは食文化も失われてることに直結している。
西洋のお盆と呼ばれるハロウィンはすっかり定着した。正月、節分、ひな祭り…と日本の行事も、もっと発信していきたい。
(小林悟空)
さてこのお盆とは、ご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する行事のこと。仏教に由来する行事であり、厳密には宗派や地域によって呼び名や時期が違うこともあるものの、概ね共通している。
こうした行事に欠かせないのが食である。仏教行事であるため動物性の食品は避け、そうめん、精進揚げ、団子、おはぎなどを食べるのがかつてはマナーとされた。漬物や高野豆腐とはお供え膳において、重要な位置を占める存在だ。
しかし近年はその在り方が変容し、好きなものを食べることを良しとする家庭が増えている。「社会人の夏休み」という認識で、里帰りをしない家庭も多いことだろう。伝統行事が薄れることは食文化も失われてることに直結している。
西洋のお盆と呼ばれるハロウィンはすっかり定着した。正月、節分、ひな祭り…と日本の行事も、もっと発信していきたい。
(小林悟空)
【2023(令和5)年8月11日第5137号17面】
【編集後記】8月1日号
手仕事・職人技はAIに負けない
AIに職が代替され、人間の職が奪われるのではという有識者の意見を新聞や雑誌でよく見かけるようになった。知的難易度が高いと思われてきた士業の仕事がより激減していき、プログラミングもAIがどんどん自動で作業してくれるらしい。
しかし、そんな激変の時代の中で、手作業の大切さがより一層増している。農協を取材する際、農業において植え付けはAI搭載の機械化が進んできたが、収穫は農作物を傷つけないようまだまだ今も手作業で行う。
そのため人手不足が深刻な悩みだと聞く。
海外では和食、特に寿司の人気が年々高くなりつつあり、ニューヨークでは見習いの寿司職人で年収1000万円、腕利きになると3000万円も稼ぐという。ニーズがあるにも関わらず、明らかな人手不足なのだ。
手仕事、職人技に価値を見出す消費者が世界にいる。手作りにこだわりのあるメーカーは、積極的に作業工程を自社のSNS、できれば英語で、世界に発信してみてはどうだろうか。新たな顧客創造に成功するかもしれない。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年8月1日第5136号13面】
【編集後記】7月21日号
ウナギをめぐる状況
7月30日は、土用の丑の日である。浜名湖のある静岡県がウナギでは有名だが、実は養鰻(ようまん)生産量は鹿児島県が全国1位だ。しかし、採捕量は3年連続で減少している。
国内で消費されるウナギはほとんどが養殖。産卵場所や回遊ルートなど未知の部分が多い稚魚のシラスウナギを漁業者が採捕し、それを買い取った養鰻業者が池や生け簀で育て、加工業者や飲食店に出回る。
ところが、国内のシラスウナギの採捕報告数量より、養鰻業者の池入れ報告数量の方が多く、無許可による密漁や指定された出荷先以外への高額転売などが指摘されている。
水産庁では、こうしたシラスウナギの不透明な漁獲・流通対策として、改正漁業法による罰則強化や、知事許可化による漁業管理の強化(令和5年12月)、水産流通適正化法の適用(令和7年12月)で、シラスウナギの適正な流通を目指している。
国際自然保護連合は平成26年に、「ニホンウナギ」を絶滅危惧ランクIB類としてレッドリストに掲載した。そこから10年経った今でさえ、前述のような状況が続いている。ウナギが手軽な庶民の食べ物として食卓に上がるのは、まだまだ先のことになりそうだ。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年7月21日第5135号13面】
国内で消費されるウナギはほとんどが養殖。産卵場所や回遊ルートなど未知の部分が多い稚魚のシラスウナギを漁業者が採捕し、それを買い取った養鰻業者が池や生け簀で育て、加工業者や飲食店に出回る。
ところが、国内のシラスウナギの採捕報告数量より、養鰻業者の池入れ報告数量の方が多く、無許可による密漁や指定された出荷先以外への高額転売などが指摘されている。
水産庁では、こうしたシラスウナギの不透明な漁獲・流通対策として、改正漁業法による罰則強化や、知事許可化による漁業管理の強化(令和5年12月)、水産流通適正化法の適用(令和7年12月)で、シラスウナギの適正な流通を目指している。
国際自然保護連合は平成26年に、「ニホンウナギ」を絶滅危惧ランクIB類としてレッドリストに掲載した。そこから10年経った今でさえ、前述のような状況が続いている。ウナギが手軽な庶民の食べ物として食卓に上がるのは、まだまだ先のことになりそうだ。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年7月21日第5135号13面】
【編集後記】7月11日号
無料提供の限界
サイゼリヤは10日、12日より夏のグランドメニューの改定と粉チーズ(グランモラビア)の無料提供終了を発表した。
消費者にとっては悲報かもしれないが、外食産業やメーカーにとっては朗報で、英断だと言える。原材料価格に加え、エネルギー代、調味資材、物流費、人件費などあらゆるコストが上昇し、製品価格の維持が困難な状況が続いている。
そのような中で、トッピングや付け合わせの無料提供は、以前から限界がきていたが、「これまで無料だったものが有料になる」というハードルは予想以上に高く、なかなか実現には至らなかった。
漬物でも寿司のがり、牛丼の紅生姜、カレーの福神漬などは、いまだに無料提供されているケースが多い。豚骨ラーメンの高菜は有料化が進んでいるが、紅生姜は無料が主流だ。
どの企業もコストダウンが課題となっており、無料提供品にはこれまで以上にコストをかけられなくなる。価格を抑えれば美味しい商品を作ることは難しく、低品質商品を提供し続ければ消費者離れにつながる。有料化にすれば使用量の低下が懸念されるが、より高品質な商品を提供できるようになるため、味や品質など「価値」を訴求することが可能となる。
従来のやり方を続けるか新しい提案を推進するのか。漬物業界は将来を見据え、行動に移す時を迎えている。(千葉友寛)
【2023(令和5)年7月11日第5134号6面】
消費者にとっては悲報かもしれないが、外食産業やメーカーにとっては朗報で、英断だと言える。原材料価格に加え、エネルギー代、調味資材、物流費、人件費などあらゆるコストが上昇し、製品価格の維持が困難な状況が続いている。
そのような中で、トッピングや付け合わせの無料提供は、以前から限界がきていたが、「これまで無料だったものが有料になる」というハードルは予想以上に高く、なかなか実現には至らなかった。
漬物でも寿司のがり、牛丼の紅生姜、カレーの福神漬などは、いまだに無料提供されているケースが多い。豚骨ラーメンの高菜は有料化が進んでいるが、紅生姜は無料が主流だ。
どの企業もコストダウンが課題となっており、無料提供品にはこれまで以上にコストをかけられなくなる。価格を抑えれば美味しい商品を作ることは難しく、低品質商品を提供し続ければ消費者離れにつながる。有料化にすれば使用量の低下が懸念されるが、より高品質な商品を提供できるようになるため、味や品質など「価値」を訴求することが可能となる。
従来のやり方を続けるか新しい提案を推進するのか。漬物業界は将来を見据え、行動に移す時を迎えている。(千葉友寛)
【2023(令和5)年7月11日第5134号6面】
【編集後記】7月1日号
佃煮で恩返し
6月29日「佃煮の日」に合わせて、各地で様々なキャンペーンが実施された。今年は佃煮の日に関連した注目すべきもう一つの話題がある。大河ドラマ「どうする家康」にて、後に佃煮が生まれるきっかけとなる「伊賀越え」のシーンの放送回が迫っているのだ。
本能寺の変により、織田信長が自害し、堺から三河へ逃げ帰ることになった家康一行に、いち早く船を提供したのが、摂津国佃村の漁師達。漁師達は船だけでなく、小魚煮も提供し、家康のピンチを救った。その後、家康は江戸に幕府を開いた際に、その恩義に報いるため、佃村の漁民を江戸に呼び寄せ、一丸となって江戸湾の干潟の一角に築島を築き、これを郷里の地名にちなみ佃島と名付けた。それ以降、佃島で作られた小魚煮を「佃煮」と呼ぶようになった――。これが佃煮誕生までのストーリーだ。
ドラマの中で伊賀越えのシーンがどう描かれるかは定かではない。佃煮との関わりをドラマ内で是非紹介してほしいところだが、それを期待しながら、この歴史的シーンをじっくりと見守りたい。
家康が天下を取ることが出来たのも、佃煮誕生までの一連の出来事を例とする〝恩返し〟が大きな要因になっているのではないか。感謝の意をはっきりと行動で示すことで周囲の人の心を動かし、最終的には時代を動かすに至った。家康のそうした生き様は、恩返しの大切さを教えてくれる。
佃煮は歴史的な恩返しが生んだ産物であり、お中元やお歳暮にお世話になっている人へ佃煮を贈ることは歴史的にも理にかなっている。(藤井大碁)
【2023(令和5)年7月1日第5133号7面】
本能寺の変により、織田信長が自害し、堺から三河へ逃げ帰ることになった家康一行に、いち早く船を提供したのが、摂津国佃村の漁師達。漁師達は船だけでなく、小魚煮も提供し、家康のピンチを救った。その後、家康は江戸に幕府を開いた際に、その恩義に報いるため、佃村の漁民を江戸に呼び寄せ、一丸となって江戸湾の干潟の一角に築島を築き、これを郷里の地名にちなみ佃島と名付けた。それ以降、佃島で作られた小魚煮を「佃煮」と呼ぶようになった――。これが佃煮誕生までのストーリーだ。
ドラマの中で伊賀越えのシーンがどう描かれるかは定かではない。佃煮との関わりをドラマ内で是非紹介してほしいところだが、それを期待しながら、この歴史的シーンをじっくりと見守りたい。
家康が天下を取ることが出来たのも、佃煮誕生までの一連の出来事を例とする〝恩返し〟が大きな要因になっているのではないか。感謝の意をはっきりと行動で示すことで周囲の人の心を動かし、最終的には時代を動かすに至った。家康のそうした生き様は、恩返しの大切さを教えてくれる。
佃煮は歴史的な恩返しが生んだ産物であり、お中元やお歳暮にお世話になっている人へ佃煮を贈ることは歴史的にも理にかなっている。(藤井大碁)
【2023(令和5)年7月1日第5133号7面】
【編集後記】6月16日号
気楽に食べて良い
「朝には佃煮を食べている」。そう言うと、朝からご飯と味噌汁を用意するような、丁寧な暮らしをしているように聞こえるだろうか。
しかし私の実態は正反対の雑なもの。ご飯を炊くのはおろか、食パンを焼くのさえ面倒くさがり、イワシの佃煮を数尾そのまま食べるというもの。電子レンジやトースターも不要、爪楊枝でトレーから直接食べるので洗い物も出ない手軽さだ。
理想的な量には満たないし、野菜もゼロだが、糖質、タンパク質、脂質を摂ることができる。朝食抜きよりはマシなはずだと思っている。
イワシの佃煮を、例えば惣菜売場にある鶏の唐揚げと比較してみたとき、価格やボリューム感に大きな開きはない。佃煮を「唐揚げのように気楽に食べて良い」という方向性のメッセージがあっても良いと感じている。
和食の良さを説明するときには「健康」「季節感」のキーワードが使われがちで、手間のかかるイメージが強い。漬物や佃煮が、調理不要で食べられる和食という視点で発信できれば、和食のイメージに広がりが出るのではないだろうか。(小林悟空)
【2023(令和5)年6月16日第5131号9面】
しかし私の実態は正反対の雑なもの。ご飯を炊くのはおろか、食パンを焼くのさえ面倒くさがり、イワシの佃煮を数尾そのまま食べるというもの。電子レンジやトースターも不要、爪楊枝でトレーから直接食べるので洗い物も出ない手軽さだ。
理想的な量には満たないし、野菜もゼロだが、糖質、タンパク質、脂質を摂ることができる。朝食抜きよりはマシなはずだと思っている。
イワシの佃煮を、例えば惣菜売場にある鶏の唐揚げと比較してみたとき、価格やボリューム感に大きな開きはない。佃煮を「唐揚げのように気楽に食べて良い」という方向性のメッセージがあっても良いと感じている。
和食の良さを説明するときには「健康」「季節感」のキーワードが使われがちで、手間のかかるイメージが強い。漬物や佃煮が、調理不要で食べられる和食という視点で発信できれば、和食のイメージに広がりが出るのではないだろうか。(小林悟空)
【2023(令和5)年6月16日第5131号9面】
【編集後記】6月1日号
未来を支える循環型農業
本屋に立ち寄ると、まず新書、文庫コーナーに立ち寄る。新書コーナーで、5月に発売された「人口減少時代の農業と食」(ちくま新書)を手に取りページをめくると、246ページから次世代の農業法人として、宮崎県都農町の「サンアグリフーズ株式会社」が紹介されていた。
同社は、自社農場や契約農家から調達した原料で、高菜漬やしば漬、大根のつぼ漬等を製造し、食品安全規格「JFS‐B規格」も取得、衛生面への意識が高い。グループ会社のアグテックで和牛の繁殖・肥育を行い、牛の堆肥を畑に還元し、またその畑で牛の飼料を作る循環型農業に力を入れている。
サンアグリフーズ会長で、アグテック代表取締役会長の礒部辰則氏は、「急速な事業拡大は目指していない。その土地を大切にした、畜産と農業の循環を目指している」と話す。
サンアグリフーズを立ち上げたのは2011年。2010年に宮崎で蔓延した口蹄疫で、畜産に変わる柱を模索したことに始まる。今や同社の漬物は、大手コンビニや自社サイト通販でも好評で、地元の農業を牽引する存在となった。
未来の農業は、異業種からの参入や循環型農業が支えていくのかもしれない。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年6月1日第5130号7面】
本屋に立ち寄ると、まず新書、文庫コーナーに立ち寄る。新書コーナーで、5月に発売された「人口減少時代の農業と食」(ちくま新書)を手に取りページをめくると、246ページから次世代の農業法人として、宮崎県都農町の「サンアグリフーズ株式会社」が紹介されていた。
同社は、自社農場や契約農家から調達した原料で、高菜漬やしば漬、大根のつぼ漬等を製造し、食品安全規格「JFS‐B規格」も取得、衛生面への意識が高い。グループ会社のアグテックで和牛の繁殖・肥育を行い、牛の堆肥を畑に還元し、またその畑で牛の飼料を作る循環型農業に力を入れている。
サンアグリフーズ会長で、アグテック代表取締役会長の礒部辰則氏は、「急速な事業拡大は目指していない。その土地を大切にした、畜産と農業の循環を目指している」と話す。
サンアグリフーズを立ち上げたのは2011年。2010年に宮崎で蔓延した口蹄疫で、畜産に変わる柱を模索したことに始まる。今や同社の漬物は、大手コンビニや自社サイト通販でも好評で、地元の農業を牽引する存在となった。
未来の農業は、異業種からの参入や循環型農業が支えていくのかもしれない。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年6月1日第5130号7面】
【編集後記】5月21日号
「生の情報」を交換
全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)では、各ブロックにおいて佃煮・煮豆等の寄贈事業を実施している。
東日本ブロック会(菊池光晃会長)は今年1月、NPO法人埼玉フードパントリーネットワーク(草場澄江理事長)へ佃煮・煮豆を贈った。同ネットワークは、県内69団体が加盟し、食品の支援が必要な家庭に無料で配布する活動を行っているグループだ。
寄贈式の雑談の中で草場理事長が、「支援が必要な家庭は、親御さんの就労形態が弱い」と話した。幼い児童がいる家庭は、子どもの世話や託児施設への迎えなどに時間がとられるため、定時就労が難しい上に、急病などの場合は休まなければならないためだ。
これを聞いた菊池会長は「当組合の加盟企業は、多くが人手不足に悩んでいる。地域の団体に人員募集のマッチングをしてもらえれば、双方の利益になるのではないか」と要望を口にした。
「週のうち数回、1日のうち数時間でも働いてくれればありがたい」と語る。寄贈事業は、こうした現場の「生の情報」を交換できることも利点の一つだと感じたエピソードだった。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年5月21日第5129号5面】
全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)では、各ブロックにおいて佃煮・煮豆等の寄贈事業を実施している。
東日本ブロック会(菊池光晃会長)は今年1月、NPO法人埼玉フードパントリーネットワーク(草場澄江理事長)へ佃煮・煮豆を贈った。同ネットワークは、県内69団体が加盟し、食品の支援が必要な家庭に無料で配布する活動を行っているグループだ。
寄贈式の雑談の中で草場理事長が、「支援が必要な家庭は、親御さんの就労形態が弱い」と話した。幼い児童がいる家庭は、子どもの世話や託児施設への迎えなどに時間がとられるため、定時就労が難しい上に、急病などの場合は休まなければならないためだ。
これを聞いた菊池会長は「当組合の加盟企業は、多くが人手不足に悩んでいる。地域の団体に人員募集のマッチングをしてもらえれば、双方の利益になるのではないか」と要望を口にした。
「週のうち数回、1日のうち数時間でも働いてくれればありがたい」と語る。寄贈事業は、こうした現場の「生の情報」を交換できることも利点の一つだと感じたエピソードだった。
(菰田隆行)
【2023(令和5)年5月21日第5129号5面】
【編集後記】5月11日号
漬物業界に神風 「漬物で野菜を食べよう!」の取組がスタート
4月26日は、漬物業界にとって大きな転機となる日となった。
農林水産省が野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートしたことを同省HPで発表した。
これまでの消費者の漬物に対するイメージは、「漬物は食物繊維を摂取できるけど、塩分が気になる」といったプラスの要素とマイナスの要素を併せ持つことで、積極的に食べようという運動は起きなかった。
だが、令和2年12月から「野菜を食べようプロジェクト」を実施している農林水産省は、野菜不足を補う手段として漬物に着目。全漬連との意見交換を経て、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率良く食物繊維等を摂取できるため、漬物の摂取を推奨する方針を決定。今回の発表に至った。
農水省のチラシには生野菜70gに相当する19種類の漬物の写真と食塩量が掲載されている。約一食分の食塩量に加え、どれくらいの量を食べれば良いのか分かりやすい表示になっている。
国が漬物の摂取を推奨する、というお墨付きを得たことで、健康に寄与する食品として自信を持って漬物の摂取をPRすることができる。漬物業界には追い風以上の神風が吹いている。
あとはどのように消費者に発信していくか。チラシは同省HPより、いつでもどこでも誰でも表示して活用することができる。業界を挙げて千載一遇のチャンスを活かす必要がある。
(千葉友寛)
【2023(令和5)年5月11日第5128号5面】
4月26日は、漬物業界にとって大きな転機となる日となった。
農林水産省が野菜の目標摂取量を補う手段の一つとして、「漬物で野菜を食べよう!」の取組をスタートしたことを同省HPで発表した。
これまでの消費者の漬物に対するイメージは、「漬物は食物繊維を摂取できるけど、塩分が気になる」といったプラスの要素とマイナスの要素を併せ持つことで、積極的に食べようという運動は起きなかった。
だが、令和2年12月から「野菜を食べようプロジェクト」を実施している農林水産省は、野菜不足を補う手段として漬物に着目。全漬連との意見交換を経て、漬物は生の野菜よりもかさが減って効率良く食物繊維等を摂取できるため、漬物の摂取を推奨する方針を決定。今回の発表に至った。
農水省のチラシには生野菜70gに相当する19種類の漬物の写真と食塩量が掲載されている。約一食分の食塩量に加え、どれくらいの量を食べれば良いのか分かりやすい表示になっている。
国が漬物の摂取を推奨する、というお墨付きを得たことで、健康に寄与する食品として自信を持って漬物の摂取をPRすることができる。漬物業界には追い風以上の神風が吹いている。
あとはどのように消費者に発信していくか。チラシは同省HPより、いつでもどこでも誰でも表示して活用することができる。業界を挙げて千載一遇のチャンスを活かす必要がある。
(千葉友寛)
【2023(令和5)年5月11日第5128号5面】
農林水産省 HP
【編集後記】5月1日号
財布の紐をほどく時
相次ぐ値上げにより節約志向が高まる中、売場では1円でも安く買いたい消費者と1円でも高く売りたい事業者のせめぎ合いが続く。
張り詰めた生活防衛意識を和らげ、堅くなった財布の紐をほどくにはどうしたら良いか。消費者は自らと対話しながら売場でその商品を買う正当性を探している。お得だから、健康に良いから、家族が喜ぶから、その人なりに様々な要素を総合的に判断し手に取るか取らないか決めている。
だがこの判断が鈍るのが脳内がワクワクした時。少し高くても普段は買わないものにまで手が伸びる。まだ食べたことがないもの、圧倒的なシズル感があるもの、ユーモアのあるネーミングやパッケージ、そのような商品に出会うとワクワクする。旅行やイベントなど非日常空間もワクワクのスイッチが入りやすい場所だ。
コロナ禍で浮き彫りになったのは、食は人類にとって最大のエンターテイメントであることだ。外出できなくても、人と会えなくても、生きるために食べることは欠かせない。そしてそれはこの上のない喜びでもある。
相次ぐ値上げにより節約志向が高まる中、売場では1円でも安く買いたい消費者と1円でも高く売りたい事業者のせめぎ合いが続く。
張り詰めた生活防衛意識を和らげ、堅くなった財布の紐をほどくにはどうしたら良いか。消費者は自らと対話しながら売場でその商品を買う正当性を探している。お得だから、健康に良いから、家族が喜ぶから、その人なりに様々な要素を総合的に判断し手に取るか取らないか決めている。
だがこの判断が鈍るのが脳内がワクワクした時。少し高くても普段は買わないものにまで手が伸びる。まだ食べたことがないもの、圧倒的なシズル感があるもの、ユーモアのあるネーミングやパッケージ、そのような商品に出会うとワクワクする。旅行やイベントなど非日常空間もワクワクのスイッチが入りやすい場所だ。
コロナ禍で浮き彫りになったのは、食は人類にとって最大のエンターテイメントであることだ。外出できなくても、人と会えなくても、生きるために食べることは欠かせない。そしてそれはこの上のない喜びでもある。
そう考えると、食に対して、節約せずもっとお金を使っても良いと思うのだが。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年5月1日第5127号5面】
(藤井大碁)
【2023(令和5)年5月1日第5127号5面】
【編集後記】4月21日号
まずは食べてもらう
先日、学生時代の友人と花見をしたときのこと。簡単に取り分けられて水気も少ない、おつまみになる漬物として九州の干したくあんスライスを持参した。
「たくあんなんて買ったことないけど美味しい」と大好評だった。中にはラベルの写真を撮って、後日買いたいと言う友人もいた。
その場にいたのは全員が30代前半。漬物の主要購買層と比べると若いが、食べればちゃんと美味しいと思ってくれる。
問題は「買ったことないけど」。美味しさに気づいてもらえなければ、永遠に買ってもらえない。今回は私の口コミがたくあんの美味しさに気づいてもらうきっかけとなれた。まずは食べてもらう機会を作らなければならない。
京都では漬物が観光土産の購入割合3割以上で、トップカテゴリとなっている。試食販売の存在が大きいだろう。京都市では学校給食にも漬物が提供されている。大人になり、買い物をするようになったとき漬物のことを思い出してくれるはずだ。
今回の漬物グランプリではおつまみやサラダ、パスタソースなど、和食の付け合わせ以外の用途の商品が多く受賞している。漬物に触れる間口が拡がっていることに、期待している。
(小林悟空)
【2023(令和5)年4月21日第5126号5面】
先日、学生時代の友人と花見をしたときのこと。簡単に取り分けられて水気も少ない、おつまみになる漬物として九州の干したくあんスライスを持参した。
「たくあんなんて買ったことないけど美味しい」と大好評だった。中にはラベルの写真を撮って、後日買いたいと言う友人もいた。
その場にいたのは全員が30代前半。漬物の主要購買層と比べると若いが、食べればちゃんと美味しいと思ってくれる。
問題は「買ったことないけど」。美味しさに気づいてもらえなければ、永遠に買ってもらえない。今回は私の口コミがたくあんの美味しさに気づいてもらうきっかけとなれた。まずは食べてもらう機会を作らなければならない。
京都では漬物が観光土産の購入割合3割以上で、トップカテゴリとなっている。試食販売の存在が大きいだろう。京都市では学校給食にも漬物が提供されている。大人になり、買い物をするようになったとき漬物のことを思い出してくれるはずだ。
今回の漬物グランプリではおつまみやサラダ、パスタソースなど、和食の付け合わせ以外の用途の商品が多く受賞している。漬物に触れる間口が拡がっていることに、期待している。
(小林悟空)
【2023(令和5)年4月21日第5126号5面】
【編集後記】4月11日号
日配・惣菜は健闘
物価高で消費者の節約志向は高まっている。財布の紐が硬く、賃上げで緩むかも定かでない。嗜好品はともかく、日々の生活に不可欠な「食」といえども買い控えが出ている。巣ごもり需要の記憶が薄れていく。
本紙4月1日号で掲載した食品流通の2月の販売統計調査(スーパーマーケット3団体発表)では、既存店売上が前年比99・1%という数字だ。青果・水産は前年比減、畜産は辛うじて前年並みだった。
一方、日配と惣菜は各102・4%、104・6%と前年越えだ。日本スーパーマーケット協会の江口法生専務理事は「価格が相対的に安い日配と惣菜が健闘したのは、物価高が要因とみられる」と講評している。
買い控えの影響で、逆に日配と惣菜を手に取る機会が増えているとしたら、喜ぶべきことなのだろうか。チャンスと捉えることもできる。触れる機会が増えるということは、需要が確実にあるということで、そこに販促も掛けやすくなる。
次に、「安いから買う」のではなく、「おいしいから買う」と消費者心理を動かせるかは、メーカーの腕の見せ所である。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年4月11日第5125号9面】
本紙4月1日号で掲載した食品流通の2月の販売統計調査(スーパーマーケット3団体発表)では、既存店売上が前年比99・1%という数字だ。青果・水産は前年比減、畜産は辛うじて前年並みだった。
一方、日配と惣菜は各102・4%、104・6%と前年越えだ。日本スーパーマーケット協会の江口法生専務理事は「価格が相対的に安い日配と惣菜が健闘したのは、物価高が要因とみられる」と講評している。
買い控えの影響で、逆に日配と惣菜を手に取る機会が増えているとしたら、喜ぶべきことなのだろうか。チャンスと捉えることもできる。触れる機会が増えるということは、需要が確実にあるということで、そこに販促も掛けやすくなる。
次に、「安いから買う」のではなく、「おいしいから買う」と消費者心理を動かせるかは、メーカーの腕の見せ所である。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年4月11日第5125号9面】
【編集後記】3月21日号
梅がSNSで話題に
和歌山県の梅干しメーカーが今年1月にツイッターで発進した情報が大きな話題となった。
その内容を要約すると、梅干しの年間購入数量が減少しており、同社の倉庫には農家が作った梅干しが行き場のない状態でパンクしている、というもの。
梅干し関連企業に今回の件について感想を聞いたところ、受け取り方は様々だった。ネガティブな意見としては、梅干しの売れ行きが悪くなっているということはイメージダウンになる、原料に余裕があるなら安くしてほしいと言われた、などといった内容。
ポジティブなものでは、梅干しがネットやテレビなどで取り上げられる機会は多くないので話題になって良かった、SNSのコメントで梅干しを食べようといった応援コメントが多かった、と前向きな意見も多かった。
総務省の家計調査によると、2021年の1世帯当たりの梅干しの年間購入数量は約663gで、ピークの2001年(1053g)と比べると約6割減少している。
だが、首都圏のPOSデータを見ると現在の売れ行きは2003年以降、同じ水準となっており、テレビ放送による2018年の大ブームやコロナの影響による巣ごもり消費の増加など、ここ数年は盛り返してきている感すらある。
需要の推移はさておき、紀州梅産地では梅の花が散って小さな梅の実が顔を覗かせており、春の息吹を感じさせている。
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
和歌山県の梅干しメーカーが今年1月にツイッターで発進した情報が大きな話題となった。
その内容を要約すると、梅干しの年間購入数量が減少しており、同社の倉庫には農家が作った梅干しが行き場のない状態でパンクしている、というもの。
梅干し関連企業に今回の件について感想を聞いたところ、受け取り方は様々だった。ネガティブな意見としては、梅干しの売れ行きが悪くなっているということはイメージダウンになる、原料に余裕があるなら安くしてほしいと言われた、などといった内容。
ポジティブなものでは、梅干しがネットやテレビなどで取り上げられる機会は多くないので話題になって良かった、SNSのコメントで梅干しを食べようといった応援コメントが多かった、と前向きな意見も多かった。
総務省の家計調査によると、2021年の1世帯当たりの梅干しの年間購入数量は約663gで、ピークの2001年(1053g)と比べると約6割減少している。
だが、首都圏のPOSデータを見ると現在の売れ行きは2003年以降、同じ水準となっており、テレビ放送による2018年の大ブームやコロナの影響による巣ごもり消費の増加など、ここ数年は盛り返してきている感すらある。
需要の推移はさておき、紀州梅産地では梅の花が散って小さな梅の実が顔を覗かせており、春の息吹を感じさせている。
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
【編集後記】3月1日号
変化のシグナル
「生活者の行動は変わっていないようで変わっている。この価値変容に対応していくことが求められる」。先日開催されたスーパーマーケット・トレードショーの記者会見で全国スーパーマーケット協会の横山会長はこう述べた。
変化とは分かりづらいものだ。自分の生活習慣が変わっていても、それは無意識で、人から指摘されない限り気付かないということも多い。ましてや人の生活習慣の変化に気付くには、鋭い観察力が必要だ。だがこの変化に気付き、いち早く対応できれば時代ニーズを捉えることができる。
東京に初めて緊急自体宣言が発令されたのは3年前の4月のことだ。あれから世界は随分と変わった。マスクの着用、手の消毒、体温の測定。こうした表面的な習慣だけでなく、人との距離感やコミュニケーションの取り方、食事のスタイルまで大きな変化が起こった。だがもっと具体的に何が変わったかを突き詰めていくことが大切だろう。
5月8日のコロナ5類移行から、何が元に戻り、何が元に戻らないか。ひとつ先を予想し、その対策を立てていくことも必要だ。
東京にも外国人観光客が増え、街の景色はコロナ前に戻りつつある。だが、元に戻らないものもたくさんある。横山会員はWEB講演で「本当に変わるのはこれから」と指摘した。変化のシグナルを注意深く読み取りたい。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年3月1日第5121号5面】
「生活者の行動は変わっていないようで変わっている。この価値変容に対応していくことが求められる」。先日開催されたスーパーマーケット・トレードショーの記者会見で全国スーパーマーケット協会の横山会長はこう述べた。
変化とは分かりづらいものだ。自分の生活習慣が変わっていても、それは無意識で、人から指摘されない限り気付かないということも多い。ましてや人の生活習慣の変化に気付くには、鋭い観察力が必要だ。だがこの変化に気付き、いち早く対応できれば時代ニーズを捉えることができる。
東京に初めて緊急自体宣言が発令されたのは3年前の4月のことだ。あれから世界は随分と変わった。マスクの着用、手の消毒、体温の測定。こうした表面的な習慣だけでなく、人との距離感やコミュニケーションの取り方、食事のスタイルまで大きな変化が起こった。だがもっと具体的に何が変わったかを突き詰めていくことが大切だろう。
5月8日のコロナ5類移行から、何が元に戻り、何が元に戻らないか。ひとつ先を予想し、その対策を立てていくことも必要だ。
東京にも外国人観光客が増え、街の景色はコロナ前に戻りつつある。だが、元に戻らないものもたくさんある。横山会員はWEB講演で「本当に変わるのはこれから」と指摘した。変化のシグナルを注意深く読み取りたい。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年3月1日第5121号5面】
【編集後記】2月11日号
「梅干しの現実」3万リツイート
株式会社梅樹園(生田富哉社長、和歌山県日高郡みなべ町)が公式ツイッターで、梅干しの購入数量が減少していることへ危機感を示し話題となった。
梅樹園(@Baijuen_Umebosi)は1月10日のツイートで
株式会社梅樹園(生田富哉社長、和歌山県日高郡みなべ町)が公式ツイッターで、梅干しの購入数量が減少していることへ危機感を示し話題となった。
梅樹園(@Baijuen_Umebosi)は1月10日のツイートで
「梅干しの現実。皆さん、現在梅干し業界がどのような状況かご存じでしょうか。令和元年から令和3年の梅干しの年間消費量※は、1世帯当たり約663gです。(中略)弊社の梅干し倉庫はパンクしており、梅農家さんが作った梅干しの多くは行き場のない状態です」
と綴った(※本紙注:正しくは年間購入数量)。
1月20日時点でリツイートが2・9万、いいねは6・2万と反響を呼んだ。「思っていたよりずっと少ない」「梅干し業界を応援したい」など、梅干しへの愛を込めたコメントも多く寄せられた。
「1世帯当たり約663g」とは総務省家計調査の令和元年~3年の平均値を示したもの。家計調査における梅干しの購入数量のピークは平成13年の1053gであり、約6割にまで減少していることが分かる。
また令和3年のデータで、世帯主の年齢が29歳以下の世帯の平均購入数量は303g、30~39歳で387g、40~49歳で436g…というように年齢が上がるほど梅干しを多く購入している。
梅干し離れが起きているのは事実だが、希望はある。今回、梅樹園の発信が多くの人の心を動かしたように、梅干しを愛する人は多くいる。
また「ニッチ産業」であるため、仮に毎年1パック(約150g)多く買ってもらえるようになるだけで大きなインパクトになる。熱中症対策アイテムなど、需要の掘り起こしに期待したい。
(小林悟空)
【2023(令和5)年2月11日第5119号15面】
1月20日時点でリツイートが2・9万、いいねは6・2万と反響を呼んだ。「思っていたよりずっと少ない」「梅干し業界を応援したい」など、梅干しへの愛を込めたコメントも多く寄せられた。
「1世帯当たり約663g」とは総務省家計調査の令和元年~3年の平均値を示したもの。家計調査における梅干しの購入数量のピークは平成13年の1053gであり、約6割にまで減少していることが分かる。
また令和3年のデータで、世帯主の年齢が29歳以下の世帯の平均購入数量は303g、30~39歳で387g、40~49歳で436g…というように年齢が上がるほど梅干しを多く購入している。
梅干し離れが起きているのは事実だが、希望はある。今回、梅樹園の発信が多くの人の心を動かしたように、梅干しを愛する人は多くいる。
また「ニッチ産業」であるため、仮に毎年1パック(約150g)多く買ってもらえるようになるだけで大きなインパクトになる。熱中症対策アイテムなど、需要の掘り起こしに期待したい。
(小林悟空)
【2023(令和5)年2月11日第5119号15面】
【編集後記】1月21日号
子ども食堂へ支援を
子ども食堂は、貧困家庭が利用しているというイメージをいまだに持たれている。多くの場所で食事の提供は行っているが、それだけではない。子どもの居場所づくり、地域コミュニティーとしての役割を担っている。子ども食堂の認知が高まるにつれ、気軽に立ち寄れる場所になっていくのが理想だ。
4月1日に「こども家庭庁」が設置される。子ども政策の司令塔になり、令和5年度は5兆円規模の予算が付けられた。子ども食堂関連の予算も拡大するとみられ、より活動しやすくなるはずだ。
政府の財政支援に留まらない。企業や個人が対象のNPOに寄付すると税額控除が受けられつつ、支援できる。支援の輪がさらに広がることを期待したい。
(高澤尚揮)
【2023(令和5)年1月21日第5118号5面】
【編集後記】1月11日号
進む二極化
最近、中間価格帯の物が売れなくなっているという話をよく聞く。食品に限らず、衣料品についてもその傾向が見られる。徹底的に安いもの、お得感のあるもの、高くても他にはない価値があるもの、こうしたものが売れているようだ。
注目すべきなのは、消費の二極化が単純に所得と連動していない点だ。同じ消費者が安いものと高いものを買い分けている。自分にとって、本当に必要なものにはお金をかける。平日はとことん節約して、週末はその分少し贅沢したり、冒険したりする。「ケ」と「ハレ」を消費者がうまく使い分けるようになった。
二極化は価格だけに留まらず内容量にも見られる。個食、少量化の流れの中、お得感のある大容量品も売れている。大容量品を購入し、小分けにして冷凍保存したり、知人とシェアして節約するというスタイルが定着した。
こうしたスタイルはミレニアル世代やZ世代が消費の主役となる今後ますます強まっていくことが予想される。
二極化の流れの中、ハレとケ、どちらの市場で戦うか、両方のニーズに対応するか、中途半端を削除した商品戦略が求められる。
(藤井大碁)
注目すべきなのは、消費の二極化が単純に所得と連動していない点だ。同じ消費者が安いものと高いものを買い分けている。自分にとって、本当に必要なものにはお金をかける。平日はとことん節約して、週末はその分少し贅沢したり、冒険したりする。「ケ」と「ハレ」を消費者がうまく使い分けるようになった。
二極化は価格だけに留まらず内容量にも見られる。個食、少量化の流れの中、お得感のある大容量品も売れている。大容量品を購入し、小分けにして冷凍保存したり、知人とシェアして節約するというスタイルが定着した。
こうしたスタイルはミレニアル世代やZ世代が消費の主役となる今後ますます強まっていくことが予想される。
二極化の流れの中、ハレとケ、どちらの市場で戦うか、両方のニーズに対応するか、中途半端を削除した商品戦略が求められる。
(藤井大碁)
【2023(令和5)年1月11日第5117号17面】