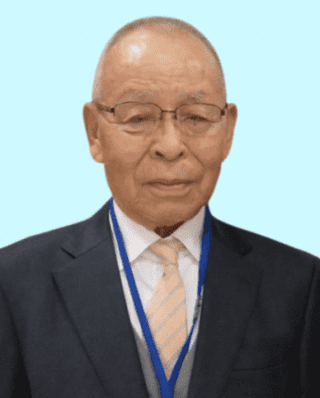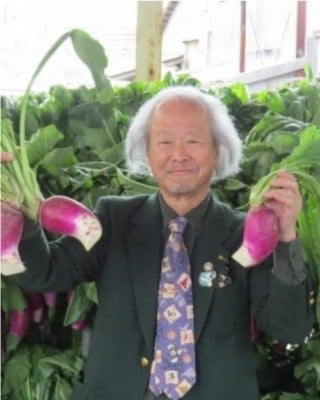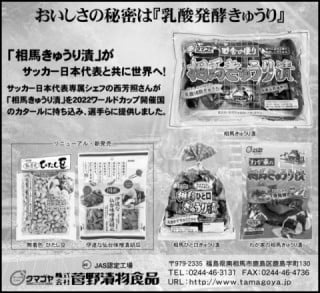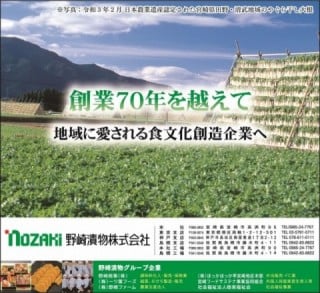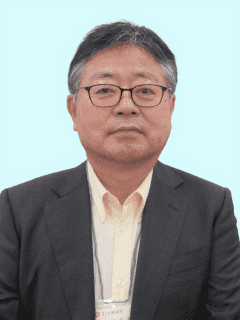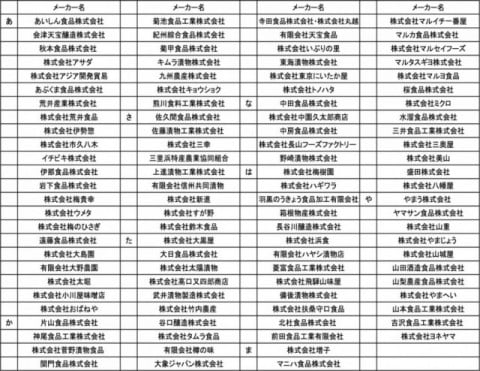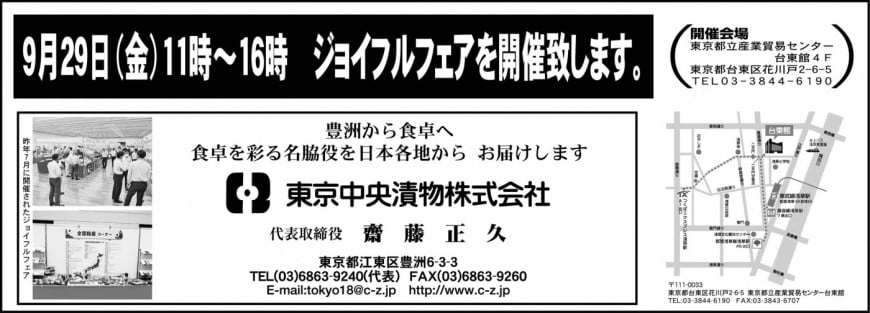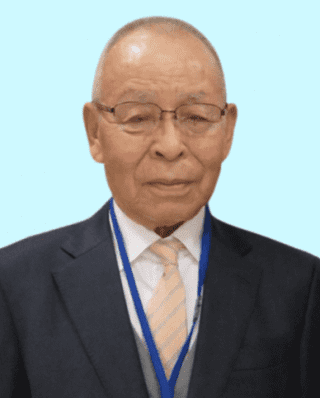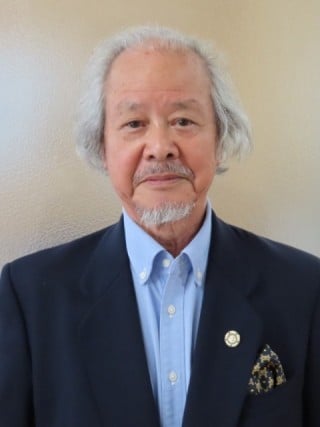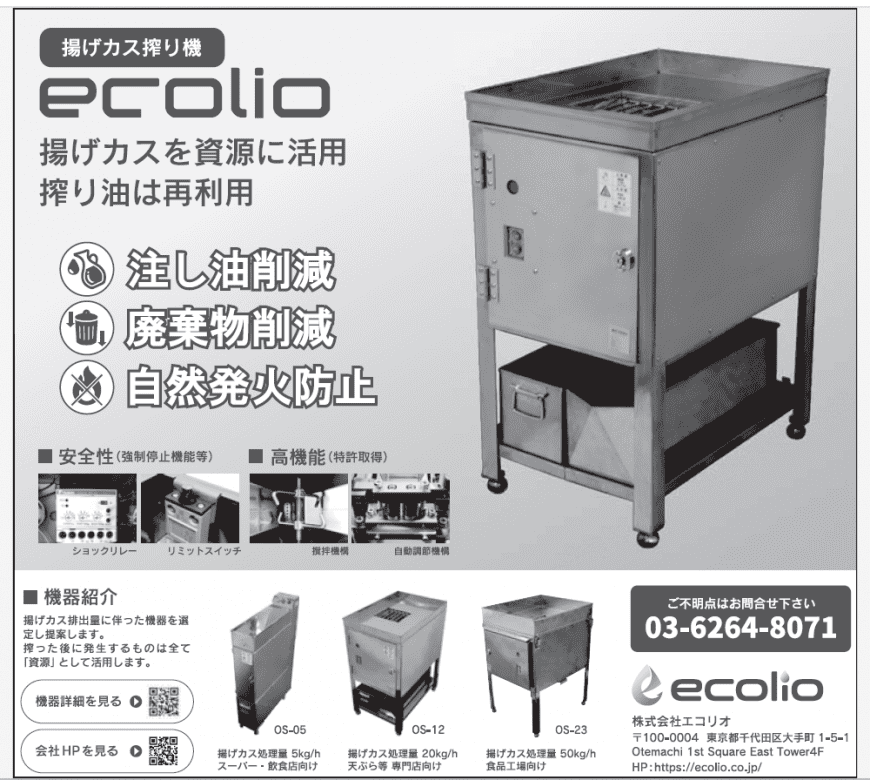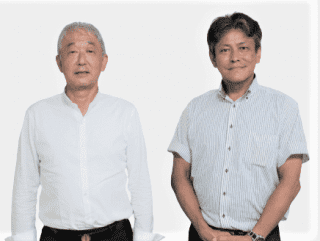12月21日号 霞ヶ浦北浦特集インタビュー
霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合 代表理事組合長 戸田 廣氏
帆引き船ブランド確立
ニーズ捉えピンチをチャンスに
霞ヶ浦北浦では近年不漁が続く。今年もワカサギの漁獲量はほぼゼロに等しい厳しい状況で、地元の湖魚だけでなく、県内や県外の海産物を原料として広く使用していく必要性に迫られている。霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、組合としてPR事業を実施していくことや、現在のニーズに沿った商品開発を行うことで、ピンチをチャンスに変えていきたいと話した。(藤井大碁)
‐近年不漁が続いている。
「ワカサギは一昨年から少なくなって、昨年もとれず、今年はほぼゼロに等しい状況だ。シラウオも昨年より2割くらい悪い。エビに関しては、ほとんどとれていなかった昨年、一昨年と比較すると今年は良くとれている。様々な状況を鑑みると、今後、前浜の漁獲量が増えていく可能性は少ないと考えた方が良い。そのため、我々、水産加工業者は、霞ヶ浦の水産物だけに頼らず、福島から茨城の沿岸地域でとれる“常盤物”や三陸沿岸でとれる“三陸物”のアミやシラス、小女子など海産物を使用していく必要性に迫られている」
‐消費者ニーズの変化。
ニーズ捉えピンチをチャンスに
霞ヶ浦北浦では近年不漁が続く。今年もワカサギの漁獲量はほぼゼロに等しい厳しい状況で、地元の湖魚だけでなく、県内や県外の海産物を原料として広く使用していく必要性に迫られている。霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、組合としてPR事業を実施していくことや、現在のニーズに沿った商品開発を行うことで、ピンチをチャンスに変えていきたいと話した。(藤井大碁)
‐近年不漁が続いている。
「ワカサギは一昨年から少なくなって、昨年もとれず、今年はほぼゼロに等しい状況だ。シラウオも昨年より2割くらい悪い。エビに関しては、ほとんどとれていなかった昨年、一昨年と比較すると今年は良くとれている。様々な状況を鑑みると、今後、前浜の漁獲量が増えていく可能性は少ないと考えた方が良い。そのため、我々、水産加工業者は、霞ヶ浦の水産物だけに頼らず、福島から茨城の沿岸地域でとれる“常盤物”や三陸沿岸でとれる“三陸物”のアミやシラス、小女子など海産物を使用していく必要性に迫られている」
‐消費者ニーズの変化。
「コロナ禍の影響もあり、食生活が変化し、高齢者が買物に行かなくなった。そのため、高齢者が好むワカサギを始めとした姿物が売れなくなった。子育て世代の母親は子どもたちが喜ぶご飯のお供を探しており、弊社では姿物の佃煮からアミなどの小魚を主体としたふりかけに商品展開を切り替えていった。コロナ前はシニア層が主要ターゲットだったが、若い世代にも購入してもらえるようになり、顧客の裾野が広がっている。このように消費者ニーズの変化に素早く対応することで、ピンチをチャンスに変えることができる。そのためには加工業者自らがこれまでのやり方を変える勇気を持つことが必要だ」
‐組合事業について。
「今後はPR事業に力を入れていきたい。前述した通り、前浜の不漁が続く中、沿岸地域の海産物を使用した製品の割合が増えており、現在、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に関する風評被害の賠償交渉も組合として進めている。現在交渉中だが、風評被害の影響があることは事実だ。もし賠償金が出れば、個々の会社ではなく、組合としてお金をもらい、組合のPR事業費として使用していきたい。東京の茨城県アンテナショップなどでイベントを開催し、安全安心で美味しい商品として、霞ヶ浦北浦の水産加工品の魅力を発信していきたいと考えている」
‐霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。
「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞したことを機に、様々なメディアで帆引き船が紹介され、ブランドが確立されてきた。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂くことができるまでになったことに感動している。今年9月には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンし、たくさんの方にご来場頂いている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」
【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】
‐組合事業について。
「今後はPR事業に力を入れていきたい。前述した通り、前浜の不漁が続く中、沿岸地域の海産物を使用した製品の割合が増えており、現在、東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出に関する風評被害の賠償交渉も組合として進めている。現在交渉中だが、風評被害の影響があることは事実だ。もし賠償金が出れば、個々の会社ではなく、組合としてお金をもらい、組合のPR事業費として使用していきたい。東京の茨城県アンテナショップなどでイベントを開催し、安全安心で美味しい商品として、霞ヶ浦北浦の水産加工品の魅力を発信していきたいと考えている」
‐霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。
「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞したことを機に、様々なメディアで帆引き船が紹介され、ブランドが確立されてきた。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂くことができるまでになったことに感動している。今年9月には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンし、たくさんの方にご来場頂いている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」
【2023(令和5)年12月21日第5148号4面】
12月1日号 埼玉特集インタビュー
埼玉県漬物協同組合 理事長 鶴田健次 氏
漬物の価値は無限大
酒造組合と交流会を開催
酒造組合と交流会を開催
マルツ食品株式会社(深谷市岡部)の鶴田健次社長は昨年5月の総会で埼玉県漬物協同組合の理事長に就任。漬物の価値向上に向け、異業種との交流に力を入れていく方針を示す。来春には埼玉県酒造組合との交流会を開催する予定で、日本酒と漬物の組み合わせにより新たな価値創出を目指している。(藤井大碁)
‐理事長に就任して約半年が経過した。
「タイトなスケジュールの中、やりたいことが全くできていない状況だが、異業種との交流に力を注いでいく予定だ。埼玉県食品工業協会の中に、酒造、漬物、煎餅、菓子、味噌、醤油など食に関わる様々な団体が加入している。そうした団体との交流を活発にすることにより、必ず漬物の枠を超えたコラボ商品ができるはずだ。まず酒造組合と漬物組合の会員同士の交流会を来年3月に実施する計画を立てている。酒造組合は34蔵、漬物組合は28社ということで、数的にもほぼ同じ。各地域で連携プレーができるのではないか。単純に酒蔵と漬物屋が組んだ時に何ができるか。日本酒は万能調味料の一つであり、漬物の調味料として使用することもできるし、副産物である酒粕を使った商品開発もできる。また、日本酒を使用した漬物を開発することで、酒蔵ブランドの漬物を作ることにも協力できる。酒造組合と一致団結のもと取り組んでいきたい。将来的には、菓子組合や醤油組合ともコラボしていきたいと考えている」
‐菓子組合とのコラボ。
「菓子製造にも漬物の製造技術を生かすことができる。弊社では、パウンドケーキに刻んだ奈良漬を加えた奈良漬パウンドケーキを菓子メーカーと共同で開発し人気を集めている。他にも、白くなった干し芋を漬け直すことにより、美味しく食べられるようになったり、漬ける技術を様々なシーンで応用できることが分かってきた。漬物産業として生き残っていくためには、我々が持つ技術を最大限に生かしながら、発展していくことが必要。それは価格競争ではない。『技術を買って頂く』という発想で、そうした価値が浸透していけば、漬物産業を良い形で後世に伝えることができるのではないだろうか。漬物産業の衰退が叫ばれる昨今だが、考え方によっては様々な可能性が生まれ、その価値は無限大になる」
‐アスリート向けの漬物。
‐理事長に就任して約半年が経過した。
「タイトなスケジュールの中、やりたいことが全くできていない状況だが、異業種との交流に力を注いでいく予定だ。埼玉県食品工業協会の中に、酒造、漬物、煎餅、菓子、味噌、醤油など食に関わる様々な団体が加入している。そうした団体との交流を活発にすることにより、必ず漬物の枠を超えたコラボ商品ができるはずだ。まず酒造組合と漬物組合の会員同士の交流会を来年3月に実施する計画を立てている。酒造組合は34蔵、漬物組合は28社ということで、数的にもほぼ同じ。各地域で連携プレーができるのではないか。単純に酒蔵と漬物屋が組んだ時に何ができるか。日本酒は万能調味料の一つであり、漬物の調味料として使用することもできるし、副産物である酒粕を使った商品開発もできる。また、日本酒を使用した漬物を開発することで、酒蔵ブランドの漬物を作ることにも協力できる。酒造組合と一致団結のもと取り組んでいきたい。将来的には、菓子組合や醤油組合ともコラボしていきたいと考えている」
‐菓子組合とのコラボ。
「菓子製造にも漬物の製造技術を生かすことができる。弊社では、パウンドケーキに刻んだ奈良漬を加えた奈良漬パウンドケーキを菓子メーカーと共同で開発し人気を集めている。他にも、白くなった干し芋を漬け直すことにより、美味しく食べられるようになったり、漬ける技術を様々なシーンで応用できることが分かってきた。漬物産業として生き残っていくためには、我々が持つ技術を最大限に生かしながら、発展していくことが必要。それは価格競争ではない。『技術を買って頂く』という発想で、そうした価値が浸透していけば、漬物産業を良い形で後世に伝えることができるのではないだろうか。漬物産業の衰退が叫ばれる昨今だが、考え方によっては様々な可能性が生まれ、その価値は無限大になる」
‐アスリート向けの漬物。
「スポーツジム運営会社向けに、発芽にんにくの漬物を提案したところ、含まれている栄養素が、アスリートが必要な栄養分に近いということで採用され、ヒットしている。一般的な市場ではなく、ニッチな分野で求められる商品もある。特定の人たちが求めているニーズを汲み取り、ピンポイントで提案していくことで、今までなかった需要を開拓することができる。漬物メーカーが年々減少を続ける中で、これ以上の減少を食い止めるためにも、新しいことをやっていかなければならない」
‐カップ漬物も好評だ。
「屋外で食事をする際に、少しだけ漬物が欲しいという機会があると思うが、汁物製品だと汁を捨てなければならず出番が少なかった。そこで昨年、汁のこぼれないカップシリーズを発売した。カップには爪楊枝が付いており、電車の中やキャンプ場など場所を選ばずにどこでも手軽に食べられる。現在は秩父きゅうりピクルス3品と新商品の奈良漬クリームチーズを揃えておりお陰様でご好評頂いている。来年には駅弁屋での取り扱いも始まる予定で、さらにたくさんの方に食べてもらえるのではないかと期待している。今後もカップ製品のラインナップを増やしていく予定だ」
‐今後について。
「現在の課題として挙げられるのが、原料不足と人手不足だ。原料供給基地として知られる深谷地区においても、生産者の減少が一番の課題となっている。また、人手不足も深刻で、外国人雇用なども考えていかなければならない。業界全体としては、様々なコストが上昇する中、価格競争を無くし、品質や技術を全面に出すことで、漬物の価値向上に取り組んでいくべきではないだろうか」
‐カップ漬物も好評だ。
「屋外で食事をする際に、少しだけ漬物が欲しいという機会があると思うが、汁物製品だと汁を捨てなければならず出番が少なかった。そこで昨年、汁のこぼれないカップシリーズを発売した。カップには爪楊枝が付いており、電車の中やキャンプ場など場所を選ばずにどこでも手軽に食べられる。現在は秩父きゅうりピクルス3品と新商品の奈良漬クリームチーズを揃えておりお陰様でご好評頂いている。来年には駅弁屋での取り扱いも始まる予定で、さらにたくさんの方に食べてもらえるのではないかと期待している。今後もカップ製品のラインナップを増やしていく予定だ」
‐今後について。
「現在の課題として挙げられるのが、原料不足と人手不足だ。原料供給基地として知られる深谷地区においても、生産者の減少が一番の課題となっている。また、人手不足も深刻で、外国人雇用なども考えていかなければならない。業界全体としては、様々なコストが上昇する中、価格競争を無くし、品質や技術を全面に出すことで、漬物の価値向上に取り組んでいくべきではないだろうか」
【2023(令和5)年12月1日第5147号7面】
マルツ食品
12月1日号 梅トップインタビュー
中田食品株式会社 代表取締役社長 中田吉昭氏
紀州梅の品質や価値を守る
業界として減塩化に対応
中田食品株式会社(和歌山県田辺市)の中田吉昭社長にインタビュー。今夏の梅干しの売れ行きや今後の販売戦略、価格改定の考えなどについて話を聞いた。また、堅調に売れている減塩タイプの梅干しについては、減塩梅干しのリーディングカンパニーとして引き続き梅干しの減塩化に取り組んでいく方針で、正しい情報の発信や漬物業界として対応していく考えを示した。(千葉友寛)
◇ ◇
ー今夏の梅干しの売れ行きは。
「今年の夏は例年以上に暑くなり、残暑も長かったので好調な売れ行きとなった。昨年比で2桁には届かないくらいだったが、11月まで暑い日が続いたので夏に食べた方が習慣として食べるようになり、10月も数%伸びた」
ー価格訴求の動きもある。
「いつの時代も低価格のニーズはある。日本はここ1、2年で物価が上がっており、節約志向が高まっている。メーカーや売場は消費者のニーズに応えようとする動きも出てくるが、品質や価値を守るためにもそれを追いかけるわけにはいかない。今年も含めて紀州梅は良い作柄が3年続いている。販売戦略としては、今年の梅はやや品質が低下しているものの、量に余裕があるので増量企画などを行って需要を喚起していきたいと考えている」
ー製造コストの上昇による価格改定の動きは。
「調味資材や人件費など、あらゆるコストが上昇している。来年4月には物流費も上がる。ただ、紀州梅は良い作柄が続いているので原料価格は安定している。梅干しの価格は原料に占める割合が大きいため、いまのところ価格改定を行う予定はない」
ー減塩梅干しの動きは。
「減塩タイプは定番品とともに売れており、支持されている。各社も減塩に取り組んでいるが、当社は減塩梅干しのリーディングカンパニーとして引き続き梅干しの減塩化を推進していく。漬物と塩分の問題は大きな課題となっているが、その中でも梅干しはやり玉に上がっている。現在販売されている平均的な調味梅干しの塩分は1粒1g前後とそこまで高いものではない。そのような情報を発信していくことが必要で、梅干しだけでなく漬物業界として対応できればと思っている」
ー生産者の高齢化や減少について。
「生産者の高齢化や減少は大きな課題で、これから加速する可能性もある。ただ、若い人が戻ってきて就農するケースもあるので、大幅に減っていくという状況ではない。それでも高齢化が進む農家にとって塩漬や天日干しという作業は重労働のため、ここ数年はメーカーが1次加工を行う流れになってきた。メーカーは全ての作業を行うことができなくても、外注に出したり作業が可能な農家に委託するなど、生産に一歩踏み込んだ対応を行っている。これまではコストを下げるために自社漬けを行うところもあったが、現在は原料を安定的に確保するための手段となっている。この動きはこの5、6年で大分進んだが、今後はその傾向がより強まると見ている」
ー紀州みなべ梅干協同組合と紀州田辺梅干協同組合が行っている紀州特選梅干認定マークの取組について。
「この取組があまり知られていないのは残念だが、特選マークの梅干しは最高品質と認定されたもので品質が圧倒的に違う。食べていただければその違いが分かる。差別化を図り、紀州梅の価値を高めるため、引き続き積極的に取り組んでいきたい」
【2023(令和5)年12月1日第5147号2面】
中田食品
12月1日号 トップに聞く
有限会社土江本店 代表取締役社長 関谷忠之氏
75周年でチャレンジ加速
パウダー事業を新たな柱に
有限会社土江本店(関谷忠之社長、島根県松江市)は、中国・四国地方有数のメーカー・ベンダーで、今年2月に創業75周年を迎えた。日本漬物産業同友会(遠藤栄一会長)の今年の研修旅行先に同社が選ばれ、10月24日には関谷社長自ら出迎えて自社工場や津田かぶの圃場を案内した。原料野菜の自社栽培量を年々拡大させ、冬の津田かぶ漬、夏の青しまね瓜漬が名物になっている。同社の今後の事業戦略についても話を聞いた。
(大阪支社 高澤尚揮)
◇ ◇
ー10月は、日本漬物産業同友会の研修旅行で自社工場や圃場を案内した。
「同友会の研修旅行では、津田かぶ漬の製造工場や津田かぶの圃場をお見せした。津田かぶの自社栽培は、約30年前、私が社長へ就任する時に栽培を開始し、現在は約3000坪にまで拡大した。土作りから栽培管理まですべて自社のスタッフが行っている。津田かぶは栽培する際、土が硬すぎても柔らかすぎても、勾玉状には育たないので、非常に細かい工夫が必要だ。今は農家の高齢化が深刻で、30年前から現在の状況を見越し、自社栽培に踏み切って良かったと思う。今では6次産業化が定番化したものの、全国でも先駆けて実践したことを誇りに思う」
ー冬の津田かぶ、夏の青しまね瓜の魅力とは。
「津田かぶは、鮮やかな紫紅色、勾玉を思わせる曲がった形で、色合い・形ともに縁起の良さを感じさせ、私は『縁結びかぶ』と呼んでいる。八百万の神が集う島根らしい、縁起物だ。その姿漬では、長い葉茎部分はぐるりと『ご縁結び』にしている。若い方からは、浅漬や甘酢漬が支持されている。夏の青しまね瓜は、青縞(あおしま)瓜を当社で独自に呼んだもの。独特の柔らかな食感で、浅漬や麹漬があるが、一番人気は粕漬。瓜を天日干しし、塩漬してから酒粕に漬け込み、オリジナルの氷温庫でじっくり熟成させることで、旨味が増す」
ー漬物以外に干物「奉書干し」の製造も。
「当社の『奉書干し』は、県内の浜田漁港で獲れた鮮魚を干物にしたもの。干物は魚を縦に吊るすと旨味が流れ、横に干すと魚の余分な水分が腐って味が変わってしまう課題があった。そこで、奉書紙で余分な水分を吸い取り、乾燥、発酵熟成させる工程を発案し商標を取得した。発酵熟成は、日本で唯一対応可能な急速冷凍庫を開発し、日々使用している」
ー75周年を記念して新しい試みにチャレンジしている。
「『食生活を豊かにする提案を』という言葉を当社では大事にし、私が社長に就任してからは、漬物卸だけでなくメーカー業にも手を広げ、そのために原料野菜の自社栽培を始めたことは前述の通り。今後は津田かぶ、青しまね瓜に続く、新たな原料野菜の栽培にもチャレンジしていきたい。また、私はSDGsの理念に強く共感しており、その理念に沿って自社はどう実践できるか考えてきた。メーカーが最初にできるのは、フードロスを減らすこと。従来捨てられてきた津田かぶや柿の葉、魚の骨を水蒸気乾燥してパウダー化することにより、ぬか床に入れたりお菓子に入れたりして再利用できる。のどぐろやするめいかなどのパウダーは、展示会等で商談が進んでいる。各地域の名産とコラボレーションしていき、新たな柱にしたいと考えている。関西・関東の都市部への販路拡大へより力を注いでいく」
ー社長は島根愛がとても強い。
「山陰浜田浜っ粉協議会会長を務め、浜田市の応援団、県の遣島使としても活動している。無報酬だが、島根の食や文化など魅力を全国の方々に伝えたい思いで一杯だ」
(大阪支社 高澤尚揮)
◇ ◇
ー10月は、日本漬物産業同友会の研修旅行で自社工場や圃場を案内した。
「同友会の研修旅行では、津田かぶ漬の製造工場や津田かぶの圃場をお見せした。津田かぶの自社栽培は、約30年前、私が社長へ就任する時に栽培を開始し、現在は約3000坪にまで拡大した。土作りから栽培管理まですべて自社のスタッフが行っている。津田かぶは栽培する際、土が硬すぎても柔らかすぎても、勾玉状には育たないので、非常に細かい工夫が必要だ。今は農家の高齢化が深刻で、30年前から現在の状況を見越し、自社栽培に踏み切って良かったと思う。今では6次産業化が定番化したものの、全国でも先駆けて実践したことを誇りに思う」
ー冬の津田かぶ、夏の青しまね瓜の魅力とは。
「津田かぶは、鮮やかな紫紅色、勾玉を思わせる曲がった形で、色合い・形ともに縁起の良さを感じさせ、私は『縁結びかぶ』と呼んでいる。八百万の神が集う島根らしい、縁起物だ。その姿漬では、長い葉茎部分はぐるりと『ご縁結び』にしている。若い方からは、浅漬や甘酢漬が支持されている。夏の青しまね瓜は、青縞(あおしま)瓜を当社で独自に呼んだもの。独特の柔らかな食感で、浅漬や麹漬があるが、一番人気は粕漬。瓜を天日干しし、塩漬してから酒粕に漬け込み、オリジナルの氷温庫でじっくり熟成させることで、旨味が増す」
ー漬物以外に干物「奉書干し」の製造も。
「当社の『奉書干し』は、県内の浜田漁港で獲れた鮮魚を干物にしたもの。干物は魚を縦に吊るすと旨味が流れ、横に干すと魚の余分な水分が腐って味が変わってしまう課題があった。そこで、奉書紙で余分な水分を吸い取り、乾燥、発酵熟成させる工程を発案し商標を取得した。発酵熟成は、日本で唯一対応可能な急速冷凍庫を開発し、日々使用している」
ー75周年を記念して新しい試みにチャレンジしている。
「『食生活を豊かにする提案を』という言葉を当社では大事にし、私が社長に就任してからは、漬物卸だけでなくメーカー業にも手を広げ、そのために原料野菜の自社栽培を始めたことは前述の通り。今後は津田かぶ、青しまね瓜に続く、新たな原料野菜の栽培にもチャレンジしていきたい。また、私はSDGsの理念に強く共感しており、その理念に沿って自社はどう実践できるか考えてきた。メーカーが最初にできるのは、フードロスを減らすこと。従来捨てられてきた津田かぶや柿の葉、魚の骨を水蒸気乾燥してパウダー化することにより、ぬか床に入れたりお菓子に入れたりして再利用できる。のどぐろやするめいかなどのパウダーは、展示会等で商談が進んでいる。各地域の名産とコラボレーションしていき、新たな柱にしたいと考えている。関西・関東の都市部への販路拡大へより力を注いでいく」
ー社長は島根愛がとても強い。
「山陰浜田浜っ粉協議会会長を務め、浜田市の応援団、県の遣島使としても活動している。無報酬だが、島根の食や文化など魅力を全国の方々に伝えたい思いで一杯だ」
【2023(令和5)年12月1日第5147号10面】
土江本店
11月21日号 100周年インタビュー
株式会社楠清 代表取締役社長 楠原幹生氏
複数の柱作った40年
ニッチ市場でこだわり商品を
株式会社楠清(広島市西区中広町)は1923(大正12)年10月に創業して以来、100周年を迎えた。今年で61歳の楠原幹生社長は修行時代も合わせて約40年間、漬物と人生をともにしてきた。前期(10月決算)は増収で着地。厳しい環境でも成長を続ける会社を作ってきたこれまでを振り返り、今後の方針を聞いた。
(大阪支社・小林悟空)
‐まずは直近の動向を。
「10月決算は土産や業務筋の回復、値上げ効果、競合メーカー減少などの影響で増収となった。利益面は、当然諸コスト上昇の影響は大きいが、コロナ禍の期間に設備改修や効率化を推進した成果で黒字を維持できている。当社はメーカー業、ベンダー業を営んでいる他、そごう広島で土産店や菓子店も運営している。事業の柱をいくつも持っており、コロナ禍でも大きく売上を落とさずにこれた」
‐入社当初を振り返って。
「私は関東の漬物メーカーで2年間修行し、24歳で楠清に入社したのだが、当時の売上は現在の4分の1くらいで、メーカー業が大半だった。その頃は漬物がよく売れ、周りの会社が急成長していた時代だったので、20代の頃の私はとにかく自社も大きくしたいという思いが強かった。必死に営業で飛び回ったおかげで徐々に県外へ販路を持てるようになった時期だった」
‐平成5年には工場を新設している。
「私は30代になり、社会的にもちょうど時代の変わり目だったと思う。現代的な工場ができたことを機に、売上を追うばかりでなく衛生管理や品質の安定化の重要性を意識するようになっていった。営業活動が実を結び、生協のベンダー業をいただけるようになった時期でもある。現在の楠清の姿が出来上がってきた時期だ」
‐43歳で社長に就任。
「その頃は引き続きベンダー業が好調で、メーカー業はほどほどに―と思っていた。しかし、転機が訪れた。余剰したらっきょうを引き取ってほしいという話を頂いたので、昭和36年に曽祖父が手書きで執筆したレシピ集を引っ張り出して、その通りに作ってみたところ非常に評判が良く、翌年も作ってほしいという依頼が殺到した。ものづくりの面白さや、本物の漬物の美味しさを改めて実感した出来事だった」
‐メーカーとして大切にしていること。
「一番はもちろん、手間をかかっても美味しいものを作ること。それから独自のこと、少なくとも広島では唯一無二の存在になることを目指している。国産らっきょう漬や国産生姜漬、からし漬などはニッチな市場だが、だからこそ競争にのみ込まれずこだわった商品を作り、独自の立ち位置を築けている」
‐今後の方針は。
「当面は、この一年で増えた顧客へ安定供給するための製造で忙しくなりそうだ。同業者が減り、広島菜漬の製造量が大幅に増えている状態だ。個人的には、世代交代を考える年齢になった。何にでも挑戦できるよう後押しをしていきたい」
(大阪支社・小林悟空)
‐まずは直近の動向を。
「10月決算は土産や業務筋の回復、値上げ効果、競合メーカー減少などの影響で増収となった。利益面は、当然諸コスト上昇の影響は大きいが、コロナ禍の期間に設備改修や効率化を推進した成果で黒字を維持できている。当社はメーカー業、ベンダー業を営んでいる他、そごう広島で土産店や菓子店も運営している。事業の柱をいくつも持っており、コロナ禍でも大きく売上を落とさずにこれた」
‐入社当初を振り返って。
「私は関東の漬物メーカーで2年間修行し、24歳で楠清に入社したのだが、当時の売上は現在の4分の1くらいで、メーカー業が大半だった。その頃は漬物がよく売れ、周りの会社が急成長していた時代だったので、20代の頃の私はとにかく自社も大きくしたいという思いが強かった。必死に営業で飛び回ったおかげで徐々に県外へ販路を持てるようになった時期だった」
‐平成5年には工場を新設している。
「私は30代になり、社会的にもちょうど時代の変わり目だったと思う。現代的な工場ができたことを機に、売上を追うばかりでなく衛生管理や品質の安定化の重要性を意識するようになっていった。営業活動が実を結び、生協のベンダー業をいただけるようになった時期でもある。現在の楠清の姿が出来上がってきた時期だ」
‐43歳で社長に就任。
「その頃は引き続きベンダー業が好調で、メーカー業はほどほどに―と思っていた。しかし、転機が訪れた。余剰したらっきょうを引き取ってほしいという話を頂いたので、昭和36年に曽祖父が手書きで執筆したレシピ集を引っ張り出して、その通りに作ってみたところ非常に評判が良く、翌年も作ってほしいという依頼が殺到した。ものづくりの面白さや、本物の漬物の美味しさを改めて実感した出来事だった」
‐メーカーとして大切にしていること。
「一番はもちろん、手間をかかっても美味しいものを作ること。それから独自のこと、少なくとも広島では唯一無二の存在になることを目指している。国産らっきょう漬や国産生姜漬、からし漬などはニッチな市場だが、だからこそ競争にのみ込まれずこだわった商品を作り、独自の立ち位置を築けている」
‐今後の方針は。
「当面は、この一年で増えた顧客へ安定供給するための製造で忙しくなりそうだ。同業者が減り、広島菜漬の製造量が大幅に増えている状態だ。個人的には、世代交代を考える年齢になった。何にでも挑戦できるよう後押しをしていきたい」
【2023(令和5)年11月21日第5146号6面】
11月11日号 東北オススメ商材特集 インタビュー
秋田県漬物協同組合 理事長 木村 吉伸氏
秋田漬物の魅力発信
「いぶりがっこ」価値訴求へ
秋田県漬物協同組合の木村吉伸理事長(株式会社雄勝野きむらや社長)に組合事業や足元の販売動向などについて聞いた。木村理事長は秋田漬物を代表する「いぶりがっこ」の今後の展開や課題について語った。
(藤井大碁)
◇ ◇
‐組合事業について。
「秋田県漬物協同組合では、県を代表する燻製沢庵『いぶりがっこ』を始め、秋田の野菜、山菜原料から作られる多種多様な“秋田漬物”の伝統と製法を守り、次世代に伝え育むために、品質の向上と時代のニーズに合わせた環境整備などを行っている。今期は食品衛生法の改正に合わせて、保健所からの許可が各社取れるようHACCPに基づく衛生管理の推進など衛生面の取組を主に活動している」
‐GI認証の周知にも取り組んでいる。
「『いぶりがっこ』の地理的表示(GI)認証を多くの人に知ってもらえるよう力を入れている。GI認証を活かした海外輸出にも継続して力を注ぎ、『いぶりがっこ』を海外でも食べてもらえるようPRしていく。輸出に関しては、現地に赴き直接PRすることが重要なので、国の補助も活用して、組合員で力を合わせて、需要を創出していきたい」
‐「いぶりがっこ」の販売動向。
「『いぶりがっこ』は、もともと秋田県の内陸南部地方に伝わる郷土漬物だが、その独特の風味が人気を集め、関東はもとより関西圏など県外でも広く食べられるようになった。近年は、料理に燻製の香りや歯切れの良い食感を加えられる食材として、業務用の刻み製品も伸長している。コロナ禍で打撃を受けた土産物も、観光シーズンを迎えた8月以降は回復傾向にあり、ようやくコロナ前と同水準まで動きが戻ってきている」
‐秋田漬物の魅力。
「秋田県の漬物と言えば『いぶりがっこ』のイメージが強いが、他にも魅力的な漬物がたくさんある。菊を使用した県南地区伝承の漬物『花ずし』、大根の生漬け『なた漬け』、その他にも、大根や胡瓜、山菜を使用した味噌漬、醤油漬、酒粕漬など様々な特産漬物がある。県内の漬物文化を伝承していくためにも、こうした秋田漬物の魅力を発信していきたい」
‐現状の課題。
「『いぶりがっこ』の需要が堅調に推移している半面、供給面は厳しい環境にある。大根原料の不足に加え、燃料光熱費や資材、漬け材料、原料栽培での資材費など様々なコストが引き続き高騰しており、事業者を苦しめている。猛暑の影響で山が傷んでおり、山菜やきのこも少なく、あらゆる原料が不足している。また慢性的な人手不足も大きな課題となっている」
‐今後について。
『「いぶりがっこ」の商品価値をしっかりと訴求し、コスト上昇分を吸収できるよう付加価値を付けて販売していくことが求められている。それと同時に、もう少しサイズダウンした規格を値ごろ感のある価格で提供することで、初めて食べる人やたまに食べたい人が購入しやすい環境を作っていくことも必要だ。近年ニーズが拡大している業務用刻み製品に関しては、傷が付いたり、小さすぎたりして一本物で提供出来ない原料を活用することで、ロスを無くし、全体の生産量を増やしていきたい。原料が不足する中、たくさんの方にいぶりがっこを食べてもらえるよう知恵を絞り取り組んでいく」
【2023(令和5)年11月11日第5145号10面】
秋田県漬物協同組合
山形県漬物協同組合 理事長 鈴木 尚彦氏
来年2月に山形県漬物品評会開催
共栄の精神で事業を継続
今年4月の総会で山形県漬物協同組合の新理事長に就任した三和漬物食品株式会社(山形県東置賜郡高畠町)社長の鈴木尚彦氏にインタビュー。22年に亘って理事長を務めた近清剛前理事長の後任となった鈴木新理事長は、来年2月に開催される第15回山形県漬物展示品評会に向け、10月25日と26日に長野県漬物品評会の審査会を視察。長野県漬物協同組合の古越三幸理事長らと情報交換を行った。同品評会はコロナで2年延期となっており、6年ぶりの開催に向けて県外の取組も参考に新しい切り口を考えていることを明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年4月の総会で理事長に就任した。
「業界の顔でもある近前理事長の後任ということで、大変身が引き締まる思いで理事長職を拝命させていただいた。プレッシャーは大きいが、業界があるから企業は事業をすることができていると思っているので、業界が良くならないと企業も良くならない。微力ながら業界が少しでも良くなるためのお手伝いができればと思っている」
‐組合の課題は。
「会員数の減少だ。平成元年は34社が加盟していたが、現在は17社と半分になってしまった。だが、県内で漬物製造の届出を行っているところは1500に上る。漬物製造業は来年6月から許可業種になるため、その前後で組合への加盟につなげられればと考えている」
‐山形県漬物展示品評会が2年延期された。
「コロナで延期を余儀なくされたのだが、来年2月22日に第15回品評会を開催する。山形県の品評会は4年に一度の開催なので、実に6年ぶりの開催となる。5月の総会以降、毎月打ち合わせを行っており、毎回10人程度集まっている。伝統を継承しながら全員参加型の組合活動を行っていきたい。近前理事長をはじめ、先代たちが守ってきた品評会を若い力を生かして新しい切り口で開催したいと考えている」
‐新しい切り口の考え方について。
「長野県漬物協同組合の古越三幸理事長にお願いし、10月25日と26日に長野を訪問して長野県漬物品評会の審査会を視察させていただいた。25日の夜には長野県漬物協同組合の皆さんのご厚意で懇親会を開催していただき、両組合で情報交換をさせていただいた。山形の品評会は4年に一度の開催だが、長野県は毎年開催している。どうやって毎年開催しているのか、運営や事務局はどのような形になっているのか、漬物組合の関わり方などを教えていただき、大変勉強になった。山形の品評会に活かしたいと思っている。長野県は発酵長寿を謳っており、漬物だけではなく、味噌、醤油、酒など、県を挙げて取組を続けている。山形の加工品も負けていないと思っているので、長野の方たちと交流を続けながら県内商品の品質を高めていきたい」
‐山形特産の青菜の作柄は。
「夏の猛暑と雨不足で種の蒔き直しもあり、最大7割減になると見ている。11月下旬には霜が降りるので、遅れて出てくるということもない。今年は限られた原料を大事に販売する1年になる。各社にも言えることだが、企業努力はすでにやり切っている。上昇しているコストは製品価格に転嫁する必要がある。時代は競争から共走に移ってきている。そのため、組合員がそれぞれの価値観を深めることができる勉強会を行っていこうと思っている。共栄の精神がなければ事業を継続していくことは困難な状況だと強く感じている」
【2023(令和5)年11月11日第5145号11面】
山形県漬物協同組合
https://www.tsukemono-japan.org/yamagata/kumiai/index.htm
共栄の精神で事業を継続
今年4月の総会で山形県漬物協同組合の新理事長に就任した三和漬物食品株式会社(山形県東置賜郡高畠町)社長の鈴木尚彦氏にインタビュー。22年に亘って理事長を務めた近清剛前理事長の後任となった鈴木新理事長は、来年2月に開催される第15回山形県漬物展示品評会に向け、10月25日と26日に長野県漬物品評会の審査会を視察。長野県漬物協同組合の古越三幸理事長らと情報交換を行った。同品評会はコロナで2年延期となっており、6年ぶりの開催に向けて県外の取組も参考に新しい切り口を考えていることを明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年4月の総会で理事長に就任した。
「業界の顔でもある近前理事長の後任ということで、大変身が引き締まる思いで理事長職を拝命させていただいた。プレッシャーは大きいが、業界があるから企業は事業をすることができていると思っているので、業界が良くならないと企業も良くならない。微力ながら業界が少しでも良くなるためのお手伝いができればと思っている」
‐組合の課題は。
「会員数の減少だ。平成元年は34社が加盟していたが、現在は17社と半分になってしまった。だが、県内で漬物製造の届出を行っているところは1500に上る。漬物製造業は来年6月から許可業種になるため、その前後で組合への加盟につなげられればと考えている」
‐山形県漬物展示品評会が2年延期された。
「コロナで延期を余儀なくされたのだが、来年2月22日に第15回品評会を開催する。山形県の品評会は4年に一度の開催なので、実に6年ぶりの開催となる。5月の総会以降、毎月打ち合わせを行っており、毎回10人程度集まっている。伝統を継承しながら全員参加型の組合活動を行っていきたい。近前理事長をはじめ、先代たちが守ってきた品評会を若い力を生かして新しい切り口で開催したいと考えている」
‐新しい切り口の考え方について。
「長野県漬物協同組合の古越三幸理事長にお願いし、10月25日と26日に長野を訪問して長野県漬物品評会の審査会を視察させていただいた。25日の夜には長野県漬物協同組合の皆さんのご厚意で懇親会を開催していただき、両組合で情報交換をさせていただいた。山形の品評会は4年に一度の開催だが、長野県は毎年開催している。どうやって毎年開催しているのか、運営や事務局はどのような形になっているのか、漬物組合の関わり方などを教えていただき、大変勉強になった。山形の品評会に活かしたいと思っている。長野県は発酵長寿を謳っており、漬物だけではなく、味噌、醤油、酒など、県を挙げて取組を続けている。山形の加工品も負けていないと思っているので、長野の方たちと交流を続けながら県内商品の品質を高めていきたい」
‐山形特産の青菜の作柄は。
「夏の猛暑と雨不足で種の蒔き直しもあり、最大7割減になると見ている。11月下旬には霜が降りるので、遅れて出てくるということもない。今年は限られた原料を大事に販売する1年になる。各社にも言えることだが、企業努力はすでにやり切っている。上昇しているコストは製品価格に転嫁する必要がある。時代は競争から共走に移ってきている。そのため、組合員がそれぞれの価値観を深めることができる勉強会を行っていこうと思っている。共栄の精神がなければ事業を継続していくことは困難な状況だと強く感じている」
【2023(令和5)年11月11日第5145号11面】
山形県漬物協同組合
https://www.tsukemono-japan.org/yamagata/kumiai/index.htm
青森県漬物組合 組合長 小村 彰夫氏
「青森県漬物フェア」を継続
県内スーパーで組合員の漬物販売
青森県漬物組合の小村彰夫氏(コムラ醸造株式会社社長)に組合事業や青森県の漬物の魅力などについてインタビュー。小村組合長は漬物需要活性化のため、昨年スタートした「青森県漬物フェア」を継続し、県内の漬物を広くPRしていく方針を示した。
(藤井大碁)
◇ ◇
‐青森県漬物組合の事業について。
「今年度は、HACCP制度化や漬物製造業の許可制への移行に際し、HACCP勉強会の開催など、衛生面の知識について学ぶための取組を強化している。勉強会には青森県漬物組合の全組合員である8社が出席し、最新の衛生知識を学びながら、情報交換を行った。県内には組合に加入していない漬物事業者もある中、我々組合員が衛生管理などにおいて県の漬物事業者の模範になれるよう取り組んでいかなければならないと考えている」
‐PR事業として「青森県漬物フェア」を実施している。
「昨年に引き続き県内スーパーの店内にコーナーを設けて、組合員8社の漬物を販売してもらっている。県内の漬物製造業者が製造した漬物をより多くの県民の方に知ってもらいたいという思いから昨年スタートした企画であるが、開始から約一年が経過し、おかげ様で売場に浸透し、好評を博している。今年度は、コロナの影響がなくなったことで、売場にマネキンを付けることもできるようになり、試食を行うことで、さらに売場の活性化に繋がっている。この取組を継続していくことで、青森県民の皆様にもっと漬物に親しんでもらい、県内の漬物需要の底上げにつなげていきたい」
‐この一年で組合員が一社増えた。
「新たに株式会社北都が加入し、青森県漬物組合の組合員は8社になった。北都さんの『赤かぶと菊芋漬』が、漬物グランプリ2023にて地域特産品特別賞を受賞し、青森県の漬物が全国にPRできたことは大変嬉しいことだ。より一層青森県の漬物が全国に知れ渡り、愛されるようになることを願っている」
‐最後に。
「青森県には新鮮な野菜を使用した様々な漬物がある。古くから受け継がれてきた青森県の漬物を伝承し、県内だけでなく県外にも幅広くPRを行っていく。日本伝統の漬物文化をしっかりと守っていけるよう今後も取り組んでいきたい」
【2023(令和5)年11月11日第5145号13面】
青森県漬物組合
https://aomori.tsukemono-japan.org/
「昨年に引き続き県内スーパーの店内にコーナーを設けて、組合員8社の漬物を販売してもらっている。県内の漬物製造業者が製造した漬物をより多くの県民の方に知ってもらいたいという思いから昨年スタートした企画であるが、開始から約一年が経過し、おかげ様で売場に浸透し、好評を博している。今年度は、コロナの影響がなくなったことで、売場にマネキンを付けることもできるようになり、試食を行うことで、さらに売場の活性化に繋がっている。この取組を継続していくことで、青森県民の皆様にもっと漬物に親しんでもらい、県内の漬物需要の底上げにつなげていきたい」
‐この一年で組合員が一社増えた。
「新たに株式会社北都が加入し、青森県漬物組合の組合員は8社になった。北都さんの『赤かぶと菊芋漬』が、漬物グランプリ2023にて地域特産品特別賞を受賞し、青森県の漬物が全国にPRできたことは大変嬉しいことだ。より一層青森県の漬物が全国に知れ渡り、愛されるようになることを願っている」
‐最後に。
「青森県には新鮮な野菜を使用した様々な漬物がある。古くから受け継がれてきた青森県の漬物を伝承し、県内だけでなく県外にも幅広くPRを行っていく。日本伝統の漬物文化をしっかりと守っていけるよう今後も取り組んでいきたい」
【2023(令和5)年11月11日第5145号13面】
青森県漬物組合
https://aomori.tsukemono-japan.org/
福島県漬物協同組合 理事長 森藤 洋一氏
県産漬物をブランディング
高塩のイメージ払拭へ
福島県漬物協同組合の森藤洋一理事長(森藤食品株式会社社長)にインタビュー。食品産業を取り巻く環境や組合の取組などについて話を聞いた。同組合では県産漬物のブランディングを継続することで商品の価値を高めることが重要だと語った。また、漬物の消費拡大に向けては塩分の問題を解消していく必要性を強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐食品産業を取り巻く環境について。
「10月3日に中央会の主催で各産業の会長や理事長が集まって会合が行われた。その中で電気代や燃料、原材料などのコストが上がっているのに値上げができない、という話が多かった。その一番の理由は売場を取られてしまうから、ということだった。様々なコストが上昇し続ける中、漬物業界も値上げの動きが鈍く、当組合会員企業も価格面で苦労していると思う」
‐観光客の動きは。
「観光地や道の駅にも多くの人が訪れており、土産品の動きも良くなっているが、人も物もコロナ前の水準には届いていない。お土産を買って近所の人に渡す、という習慣がなくなってきているため、土産品も従来のままでの販売形態では尻すぼみになる」
‐新たな取組について。
「当社では7月にデザイン変更に伴い、10品前後の内容量調整を行った。これまでの内容量は200g前後だったのだが、150gに変更した。これはコスト増による実質値上げというよりも、減少している世帯人数、つまり必要とされる内容量と合っていないという考えのもとに行った。内容量が減ったことで売価も下げたところ、商品の回転数が増加した。結果的には取組を進めて良かった」
‐組合の課題は。
「どこのエリアも同じだと思うが、会員数が減少していることで組合の事業はおろか存続させていくことも難しい状況だ。休会という話も出てきているが、先代たちが築いてきた組合をなくすわけにはいかないと考えている。組合に加盟していてもメリットがない、という話も聞くが、当組合では2年前から組合が認定する福島県漬物協同組合推奨品マークの取組を行っており、認定された商品はマークを貼付して販売することができるので、差別化を図った販売を行うことができる。また、多くの県内企業が製造している『いか人参』を新たな特産品に育てるため組合で商標登録を申請するなど、ブランディングの取組を継続して商品の価値を高めていくことが重要だ」
‐漬物業界の課題は。
「先日、DMを送っていたお客様から血圧が高いので病院に行ったら医者に漬物は食べないでください、と言われたのでDMは送らないでください、という連絡があった。昔と比べれば漬物は大分減塩しているのだが、医者も含めていまだに塩分が高いというイメージをもたれている。この問題を解消しない限り、漬物の消費が増えることはない。原料の確保や人手不足といった課題もあるが、このような問題にも取り組んでいくことが重要だ。それは一社でできることではなく、組合として農水省や厚労省と連携しながら進めていくことが望ましい。今後も皆さんの協力と理解をいただきながら、事業を進めていきたい」
【2023(令和5)年11月11日第5145号14面】
福島県漬物協同組合
10月21日号 おせち特集インタビュー
全国調理食品工業協同組合 副理事長 佐々 重雄氏
年末商品は5、6%値上げ 事業領域拡大で売上増やす
全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。おせち、年末商品の価格改定、昆布や栗などの原料状況、今後の戦略などについては話を聞いた。原料、燃料、人件費、物流費とあらゆるコストが上昇する中、製品価格への転嫁を進めながら棚を守るために事業領域を拡大し、新しい提案をし続ける必要性があることを強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐価格改定の動きは。
「原料は海外産のものも多く、現地のメーカーから値上げ要請がある。さらに円安の影響も大きく、製品価格に転嫁する必要が生じており、昨年に続いて今年もほぼ全ての商品で価格改定を行った。おせちや年末商品は平均5、6%の値上げとなっている」
‐各種原料について。
「国内の昆布は大不作となった昨年よりは良いものの、ここ数年の生産量は減少傾向にある。今年は雨が多く波が高かったため漁に出ることができず、減産となったことで価格が上昇した。また、昆布巻きについては昆布を干瓢で巻く巻き手の確保ができなくなってきており、量の確保も難しくなっている。国産、中国産、韓国産の原料を使用する栗は、韓国産の価格が高騰しているため、韓国産を使用するメリットがなくなりつつある。中国産は品質も良好で今年は比較的豊作で安定した価格となっているが、為替を含めて計算すると昨年とほぼ同じ価格となっている」
‐さつまいも原料は。
「認知度が高まっていた安納芋は、昨年から続く基腐病の影響で確保することができない。栗きんとんの餡となるさつまいもは、商品を差別化する素材となっているだけに、原料を確保できなければ商品の規格を作って提案することができず、各社対応に苦労している」
‐今後の戦略について。
「当社は9月決算で売上は前年比102%と何とか前年をクリアした。数量ベースでは下がっているが、値上げした分、数字を確保することができた。しかし、今後のことを考えると燃料費、人件費、原料価格の上昇によるコストアップは大きな不安要素だ。物価高で節約志向が高まり、消費者は商品の購入数を減らすなど、商品を選別する目も厳しくなっている。取引先は値上げして売れなくなると商品を切り替える。棚を守るためには新しい商品を開発し、既存の商品に代わる商品を提案しなければならない。商品のバリエーションを増やしたり、これまで扱っていなかった商品を供給するなど、事業領域を拡大しないと売上を増やすことはできない。得意先を取った、取られた、という前にお客様を飽きさせない取組を行うことが重要。そのような意味では競合との勝負というよりも自分たちとの勝負になる」
‐年末商戦の予想は。
「円安のため海外旅行に行く人は少ないと見ており、国内では旅行や外食の他、中食の需要が高まると予想している。当社のセット商品の注文は比較的良い数字となっている。ただ、全体的な動きを見ると、量販店の発注はやや弱含みとなっている。年始は休む店舗が増えており、ロスを出さないようにするために12月30日に売り切って翌31日はプロパーの商品に戻す、というような動きになりそうだ。そのため、これから発注数が急激に増えることは考えにくい状況だ」
‐これからの方針。
「今年も各社が値上げを行っていることからも分かるように、様々なコストが上がっていることに加えて人手不足や2024年物流問題などの課題も抱える中、事業を継続していくことは難しくなってきている。メーカーとしては利益を確保しながら、日本の食文化を次の世代に伝えていくために最大限の努力をし続けていく必要がある」
【2023(令和5)年10月21日第5143号2面】
全国調理食品工業協同組合(岩田功理事長)の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。おせち、年末商品の価格改定、昆布や栗などの原料状況、今後の戦略などについては話を聞いた。原料、燃料、人件費、物流費とあらゆるコストが上昇する中、製品価格への転嫁を進めながら棚を守るために事業領域を拡大し、新しい提案をし続ける必要性があることを強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐価格改定の動きは。
「原料は海外産のものも多く、現地のメーカーから値上げ要請がある。さらに円安の影響も大きく、製品価格に転嫁する必要が生じており、昨年に続いて今年もほぼ全ての商品で価格改定を行った。おせちや年末商品は平均5、6%の値上げとなっている」
‐各種原料について。
「国内の昆布は大不作となった昨年よりは良いものの、ここ数年の生産量は減少傾向にある。今年は雨が多く波が高かったため漁に出ることができず、減産となったことで価格が上昇した。また、昆布巻きについては昆布を干瓢で巻く巻き手の確保ができなくなってきており、量の確保も難しくなっている。国産、中国産、韓国産の原料を使用する栗は、韓国産の価格が高騰しているため、韓国産を使用するメリットがなくなりつつある。中国産は品質も良好で今年は比較的豊作で安定した価格となっているが、為替を含めて計算すると昨年とほぼ同じ価格となっている」
‐さつまいも原料は。
「認知度が高まっていた安納芋は、昨年から続く基腐病の影響で確保することができない。栗きんとんの餡となるさつまいもは、商品を差別化する素材となっているだけに、原料を確保できなければ商品の規格を作って提案することができず、各社対応に苦労している」
‐今後の戦略について。
「当社は9月決算で売上は前年比102%と何とか前年をクリアした。数量ベースでは下がっているが、値上げした分、数字を確保することができた。しかし、今後のことを考えると燃料費、人件費、原料価格の上昇によるコストアップは大きな不安要素だ。物価高で節約志向が高まり、消費者は商品の購入数を減らすなど、商品を選別する目も厳しくなっている。取引先は値上げして売れなくなると商品を切り替える。棚を守るためには新しい商品を開発し、既存の商品に代わる商品を提案しなければならない。商品のバリエーションを増やしたり、これまで扱っていなかった商品を供給するなど、事業領域を拡大しないと売上を増やすことはできない。得意先を取った、取られた、という前にお客様を飽きさせない取組を行うことが重要。そのような意味では競合との勝負というよりも自分たちとの勝負になる」
‐年末商戦の予想は。
「円安のため海外旅行に行く人は少ないと見ており、国内では旅行や外食の他、中食の需要が高まると予想している。当社のセット商品の注文は比較的良い数字となっている。ただ、全体的な動きを見ると、量販店の発注はやや弱含みとなっている。年始は休む店舗が増えており、ロスを出さないようにするために12月30日に売り切って翌31日はプロパーの商品に戻す、というような動きになりそうだ。そのため、これから発注数が急激に増えることは考えにくい状況だ」
‐これからの方針。
「今年も各社が値上げを行っていることからも分かるように、様々なコストが上がっていることに加えて人手不足や2024年物流問題などの課題も抱える中、事業を継続していくことは難しくなってきている。メーカーとしては利益を確保しながら、日本の食文化を次の世代に伝えていくために最大限の努力をし続けていく必要がある」
【2023(令和5)年10月21日第5143号2面】
菊池食品工業株式会社 代表取締役社長 菊池光晃氏
おせち文化を海外へ
インバウンドにビジネスチャンス
煮豆、佃煮、惣菜の大手として知られる菊池食品工業株式会社(東京都板橋区大山)の代表取締役社長兼COOの菊池光晃氏にインタビュー。今年のおせち商戦や今後の見通しについて聞いた。菊池社長は様々なコストが上昇する中、適正価格での販売の必要性を強調すると共に、海外に向けたおせちビジネスの可能性についても語った。(藤井大碁)
◇ ◇
ー今年のおせち商戦の見通し。
「コロナ5類移行後初のおせち商戦となるが、現実的には、昨年末もかなりの人が動いており、昨年の数字がベースとなると考えている。足元の円安により、海外旅行に行く人もそこまで多くはないだろう。国内移動は昨年より活発化し、帰省が増える分、地方の店舗の売上は上昇するのではないか」
ー近年のおせち商戦。
「弊社では、おせち関連の売上が一昨年過去最高となった。様々な課題はあるものの、コロナ禍を経て、おせちを食べる習慣が見直されたこともあり、売上は順調に推移している。だが、製造コストは上昇し続けており、利益面は非常に厳しい状況だ。今年もアイテムによりけりだが、平均で約5~10%程の値上げを予定している。通常であれば値上げにより数量は減少するが、今年は北海道のメーカーが廃業した影響で、北海道におけるおせち関連商品の売上が増加する見通しで、全体の数量は前年比微増、売上も5%増を見込んでいる」
ー値上げの影響。
「不漁、不作に加え、為替の影響を含んだ原料の高騰、砂糖、包装資材の度重なる値上げなど、今年も製造コストの大幅な上昇が続いており、価格据え置きはできない。値上げの方法については、価格改定か、規格変更か、その両方か、アイテムごとに社内で議論を重ねた。その結果、売れ筋商品については、規格変更を行い、プライスラインを守って販売していくことを決めた。おせちは一年の始めに食べる特別な食事であり、品質を落とすことはできない。製造コストが上昇を続ける中、適正価格での販売を行い、高品質な商品を安定供給することで、おせち文化の伝承に努めていきたい」
ー原料不足と人手不足が課題になっている。
「原料面では、田作りの原料が不漁により枯渇している。今年は特に厳しい状況になっており、既存の取引先に提供することがやっとで、新規の取引は難しい。来年の漁に期待するしかない。昆布巻に関しては、昆布は今年、例年よりとれたが、巻き手の不足により製造量が減少している。黒豆は北海道、丹波ともに炊くと皮が剥けてしまう裂皮の影響が拡大している。一方、人手不足に関しては、昨年より状況はいい。弊社では埼玉工場、函館工場ともに想定人数は確保できている。すきま時間を利用して働くことができる新しい雇用形態の活用や、中途社員の採用などを積極的に推進している」
【2023(令和5)年10月21日第5143号3面】
菊池食品工業
三河佃煮工業協同組合 理事長 小林利生氏
物価高や円安で節約志向
年末商戦の販促に商機見出す
三河佃煮工業協同組合の小林利生理事長(㈱小林つくだ煮社長)におせち商戦や原料状況について聞いた。小林理事長は、物価高や円安による節約志向で、年末年始の海外・国内旅行の大幅な拡大は起こりづらいと予想。おせち全体の売れ行きは、昨年並みか微減で着地するのではないかと語る。佃煮メーカーは、毎年のおせち動向に左右されず、年間を通して安定的に製品を販売し、また新たな商機も見出していく必要があると話した。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
ーおせち商戦の動向について。
「おせち製品の受注はここまで昨年と同程度、大きく変わることなく推移しているが、単品では田作りが若干増えそうだ。原料である片口いわしの入手に毎年苦労しているものの、田作りの供給は可能な限り対応できるよう努めていく。今年は5月に新型コロナが5類に移行してから、国内観光の勢いはコロナ前に戻りつつある。今年の年末年始の帰省による人流は昨年越えという見立てには賛同できる。ただ、年末年始の旅行については、昨今の物価高で節約志向が高まっていることから、微増程度だろう。原油高や円安も容易に収まらず、海外旅行の大幅な拡大は起こらないのでは。全体的に見て、おせちの需要は昨年並みか微減で着地するのではないか。重詰めについては、帰省による地方での需要増加で、大人数タイプの受注数が増え、堅調だろう」
ー原料状況。
「様々な原料が非常に厳しい状況となっている。小女子は近年不漁続きで、価格も高騰している。中国の小女子も冷凍技術の進化で品質は上がっているが、為替の影響もあり国産とそう価格が変わらなくなってきた。昆布巻きは巻き手が減少し、栗きんとんや黒豆を扱っているメーカーからは、ニーズはあるものの、作れば作るほど利益の確保が困難という話を聞く。新しい製品を開発していきたい気持ちはあるが、伝統食品は変わり種を出しても、なかなか売れないマーケットであるため、その判断に苦慮している」
ー佃煮の需要。
「各種販売データを見て、佃煮の需要は堅調と見ている。資材価格や電気代の高騰などで、利益確保のために価格改定は関係各位の理解を得ながら、当社でも引き続き適切に実施していく。佃煮は本来、嗜好性が高いものであり、『ちょっとした贅沢品』と、付加価値を感じられる存在に戻していく必要があるだろう。年間を通してコンスタントに佃煮が消費者から求められるのが望ましい。年末商戦は財布の紐がゆるみやすい時期であり、この機会に年越しそば用のにしん甘露煮に加えて各種提案していくことで商機を見出せると期待している。他シーズンも模索しつつ、佃煮以外の食品や他業界製品との競争の中で、佃煮を手に取ってもらうきっかけをメーカーが率先して作っていくことが迫られていると感じる」
ー組合では、11月に子ども食堂へあさり佃煮を寄贈する。
「青年部組織の豊橋佃志会と連携して、豊橋市内の子ども食堂へ一昨年はおせちを寄贈、今年一月には節分に合わせていわし甘露煮を寄贈し子ども食堂の方々にお弁当にしていただいて提供できた。今回はあさり佃煮を寄贈し『あさり押し寿司』弁当にしてもらう。東三河地域の佃煮屋の多くは元々、創業時に渥美半島のあさりを佃煮にして販売していたところが多い。その意味で、あさり佃煮は東三河地域で最も歴史のある佃煮だ。郷土料理『あさりの押し寿司』は、むきあさりを甘辛く炊き酢飯に載せたもので、祭りや祝い事の時に親しまれてきた。今回はその押し寿司をイメージしている。食育に最適であり、何より子どもたちの笑顔を見るのが楽しみだ」
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
ーおせち商戦の動向について。
「おせち製品の受注はここまで昨年と同程度、大きく変わることなく推移しているが、単品では田作りが若干増えそうだ。原料である片口いわしの入手に毎年苦労しているものの、田作りの供給は可能な限り対応できるよう努めていく。今年は5月に新型コロナが5類に移行してから、国内観光の勢いはコロナ前に戻りつつある。今年の年末年始の帰省による人流は昨年越えという見立てには賛同できる。ただ、年末年始の旅行については、昨今の物価高で節約志向が高まっていることから、微増程度だろう。原油高や円安も容易に収まらず、海外旅行の大幅な拡大は起こらないのでは。全体的に見て、おせちの需要は昨年並みか微減で着地するのではないか。重詰めについては、帰省による地方での需要増加で、大人数タイプの受注数が増え、堅調だろう」
ー原料状況。
「様々な原料が非常に厳しい状況となっている。小女子は近年不漁続きで、価格も高騰している。中国の小女子も冷凍技術の進化で品質は上がっているが、為替の影響もあり国産とそう価格が変わらなくなってきた。昆布巻きは巻き手が減少し、栗きんとんや黒豆を扱っているメーカーからは、ニーズはあるものの、作れば作るほど利益の確保が困難という話を聞く。新しい製品を開発していきたい気持ちはあるが、伝統食品は変わり種を出しても、なかなか売れないマーケットであるため、その判断に苦慮している」
ー佃煮の需要。
「各種販売データを見て、佃煮の需要は堅調と見ている。資材価格や電気代の高騰などで、利益確保のために価格改定は関係各位の理解を得ながら、当社でも引き続き適切に実施していく。佃煮は本来、嗜好性が高いものであり、『ちょっとした贅沢品』と、付加価値を感じられる存在に戻していく必要があるだろう。年間を通してコンスタントに佃煮が消費者から求められるのが望ましい。年末商戦は財布の紐がゆるみやすい時期であり、この機会に年越しそば用のにしん甘露煮に加えて各種提案していくことで商機を見出せると期待している。他シーズンも模索しつつ、佃煮以外の食品や他業界製品との競争の中で、佃煮を手に取ってもらうきっかけをメーカーが率先して作っていくことが迫られていると感じる」
ー組合では、11月に子ども食堂へあさり佃煮を寄贈する。
「青年部組織の豊橋佃志会と連携して、豊橋市内の子ども食堂へ一昨年はおせちを寄贈、今年一月には節分に合わせていわし甘露煮を寄贈し子ども食堂の方々にお弁当にしていただいて提供できた。今回はあさり佃煮を寄贈し『あさり押し寿司』弁当にしてもらう。東三河地域の佃煮屋の多くは元々、創業時に渥美半島のあさりを佃煮にして販売していたところが多い。その意味で、あさり佃煮は東三河地域で最も歴史のある佃煮だ。郷土料理『あさりの押し寿司』は、むきあさりを甘辛く炊き酢飯に載せたもので、祭りや祝い事の時に親しまれてきた。今回はその押し寿司をイメージしている。食育に最適であり、何より子どもたちの笑顔を見るのが楽しみだ」
【2023(令和5)年10月21日第5143号4面】
丸千千代田水産株式会社 加工品部加工品課 課長代理 横山拓氏
高付加価値商品に力
旬うたえる商品の提案求む
丸千千代田水産株式会社(石橋秀子社長、東京都江東区豊洲)加工品部加工品課課長代理の横山拓氏に今年のおせち商戦の見通しや主要アイテムの動向などについて聞いた。横山氏は価格改定の影響が昨年より強まることを危惧しながらも、高付加価値商品や佃煮おせちのセット物の提案に力を入れることで売上アップにつなげていきたいと語った。
(藤井大碁)
◇ ◇
ー今年のおせち商戦の見通し。
「佃煮おせちは、今年もほぼ全ての品目で価格改定が実施され、その影響が大きくなっている。値上げ幅も最大20%程と、10%程であった昨年と比較すると大きい。価格改定により、おせち全体の販売数量は昨年より若干鈍ると予想しているが、単価アップにより、売上は昨年並から微増を見込んでいる」
ー今年特に力を入れる取組。
「高付加価値商品と佃煮おせちのセット物の提案に力を入れる。例えば、栗きんとんのあん部分にさつまいもあんではなく栗あんを使用した栗きんとんは、9月の展示会で〝モンブランのような味わい〟と話題を集めた。また産地にこだわった北海道産の新物たらこと北海道産昆布を使用した北海道たらこ昆布もやはり展示会で試食が好評だった。こうした明確な味の違いや産地のこだわりを打ち出せる高付加価値商品を積極的に提案する。またセット物の提案にも例年以上に注力する。3品、4品、6品、9品など豊富なラインナップを揃え、幅広いニーズに対応する。近年人気を集めいている佃煮おつまみセットも引き続き販売していく」
ー昨年はおせちプラス一品の提案が好評だった。
「年越しそばなどの麺類や中華惣菜などをおせち商材と共に関連販売し、おせちプラスアルファの売上をつくることに成功した。今年もその流れに乗って、全国のご当地そばの提案を行う他、横浜、神戸、長崎の全国三大中華街の中華まんの提案を行う」
ー主要アイテムの動向について。
「栗きんとんは昨年より値上げ幅が大きく、値上げのインパクトは大きい。値上げや量目変更など各社の対応は様々だが、各社の値上げ幅に差があるため、今年は例年より売場におけるアイテム変更の可能性が高まっている。商品の傾向としては、五郎島金時や紫芋を芋あんに使用することで、栗だけでなく、芋あんで差別化する商品が登場している。黒豆は他のカテゴリーに比べ値上げ幅は小さく、今年も主力製品として販売していくものの、丹波の黒豆のブランドである篠山産の原料が減少しており、特徴を打ち出せる商品が少なくなっている。田作りは先月の時点でも、原料がまだ揃っていないメーカーもあり、原料の状況が例年以上に悪い。原料と共に、需要も年々少しずつ減少している状況で、値上げや量目変更を行いながら、限られた原料を大切に販売していくことが求められている。昆布巻きは春先からの昆布の不漁で全体的な値上げが実施される。一本物の需要が落ちこむ一方、鮭と鰊といった2種類の味わいを同時に楽しめるアベック商品が伸びている。その他の佃煮おせち商材では、串物の値上げ幅も大きく、栗きんとん、黒豆、田作り、昆布巻きの主要4品への集約がさらに進んでいきそうだ」
ー通常品としての佃煮製品の動き。
「弊社では昨年よりスタートした〝旬の佃煮の提案〟が好評で、通常品の佃煮の売上は堅調に推移している。春から夏シーズンにかけて、しらす、あみ、川海老、秋から冬シーズンは、たらこ、節分のいわし、雛祭りの蛤など、旬の食材を訴求することや、イベントに合わせた提案をすることで、売上アップにつながっている」
ー今後について。
「『さかなの日』や『佃煮の日』に合わせた提案も含めて、佃煮売場の活性化に引き続き力を入れていく。売場で旬をうたえる商品があれば、是非ご提案頂きたい」
◇ ◇
ー今年のおせち商戦の見通し。
「佃煮おせちは、今年もほぼ全ての品目で価格改定が実施され、その影響が大きくなっている。値上げ幅も最大20%程と、10%程であった昨年と比較すると大きい。価格改定により、おせち全体の販売数量は昨年より若干鈍ると予想しているが、単価アップにより、売上は昨年並から微増を見込んでいる」
ー今年特に力を入れる取組。
「高付加価値商品と佃煮おせちのセット物の提案に力を入れる。例えば、栗きんとんのあん部分にさつまいもあんではなく栗あんを使用した栗きんとんは、9月の展示会で〝モンブランのような味わい〟と話題を集めた。また産地にこだわった北海道産の新物たらこと北海道産昆布を使用した北海道たらこ昆布もやはり展示会で試食が好評だった。こうした明確な味の違いや産地のこだわりを打ち出せる高付加価値商品を積極的に提案する。またセット物の提案にも例年以上に注力する。3品、4品、6品、9品など豊富なラインナップを揃え、幅広いニーズに対応する。近年人気を集めいている佃煮おつまみセットも引き続き販売していく」
ー昨年はおせちプラス一品の提案が好評だった。
「年越しそばなどの麺類や中華惣菜などをおせち商材と共に関連販売し、おせちプラスアルファの売上をつくることに成功した。今年もその流れに乗って、全国のご当地そばの提案を行う他、横浜、神戸、長崎の全国三大中華街の中華まんの提案を行う」
ー主要アイテムの動向について。
「栗きんとんは昨年より値上げ幅が大きく、値上げのインパクトは大きい。値上げや量目変更など各社の対応は様々だが、各社の値上げ幅に差があるため、今年は例年より売場におけるアイテム変更の可能性が高まっている。商品の傾向としては、五郎島金時や紫芋を芋あんに使用することで、栗だけでなく、芋あんで差別化する商品が登場している。黒豆は他のカテゴリーに比べ値上げ幅は小さく、今年も主力製品として販売していくものの、丹波の黒豆のブランドである篠山産の原料が減少しており、特徴を打ち出せる商品が少なくなっている。田作りは先月の時点でも、原料がまだ揃っていないメーカーもあり、原料の状況が例年以上に悪い。原料と共に、需要も年々少しずつ減少している状況で、値上げや量目変更を行いながら、限られた原料を大切に販売していくことが求められている。昆布巻きは春先からの昆布の不漁で全体的な値上げが実施される。一本物の需要が落ちこむ一方、鮭と鰊といった2種類の味わいを同時に楽しめるアベック商品が伸びている。その他の佃煮おせち商材では、串物の値上げ幅も大きく、栗きんとん、黒豆、田作り、昆布巻きの主要4品への集約がさらに進んでいきそうだ」
ー通常品としての佃煮製品の動き。
「弊社では昨年よりスタートした〝旬の佃煮の提案〟が好評で、通常品の佃煮の売上は堅調に推移している。春から夏シーズンにかけて、しらす、あみ、川海老、秋から冬シーズンは、たらこ、節分のいわし、雛祭りの蛤など、旬の食材を訴求することや、イベントに合わせた提案をすることで、売上アップにつながっている」
ー今後について。
「『さかなの日』や『佃煮の日』に合わせた提案も含めて、佃煮売場の活性化に引き続き力を入れていく。売場で旬をうたえる商品があれば、是非ご提案頂きたい」
【2023(令和5)年10月21日第5143号5面】
丸千千代田水産
会長に聞く 11月3日は高野豆腐の日
全国凍豆腐工業協同組合連合会 会長 木下博隆氏
レシピコンテスト開催へ
植物性タンパク市場急拡大
11月3日は「高野豆腐の日」。年末ムードの高まる「文化の日」に、高野豆腐(凍り豆腐)が和食の代表的な食品であることを伝えたい想いから全国凍豆腐工業協同組合連合会(木下博隆会長=旭松食品社長)が2020年に制定した。今年はNPO法人への商品寄贈や、レシピサイト「Nadia」上でアレンジレシピコンテスト開催し、需要喚起を目指す。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー高野豆腐の市場動向は。
「組合調査による原料大豆使用量は、テレビ効果で特需のあった2018、19年から減少傾向となっている。今年も9月時点で前年比減となっている。物価高騰による消費者の買い控えも考えられることから、需要喚起は切実な課題となっている」
ー需要喚起に向けて。
「『高野豆腐の日』には、昨年までに引き続き長野県内のNPO法人の子ども応援プロジェクトへ商品を寄付する。タンパク質やカルシウムが豊富で噛む力を鍛えられる高野豆腐は子どもの健康にうってつけ。子どもの頃から高野豆腐に慣れ親しんで欲しい願いも込めている。また今年はレシピサイト『Nadia』上でアレンジレシピコンテストを12月に開催する」
ーレシピコンテストの狙い。
「これまで各社でレシピ発信してきて、健康やダイエットに関心のある方々には知名度が高まってきた。今回、利用者層の若い『Nadia』に場所をお借りしてコンテストという形で能動的に参加してもらうことで、より多くの方に高野豆腐の新たな可能性を感じていただけると期待している」
ー機能性研究に力を入れている。
「これまで食後中性脂肪上昇抑制、脂質代謝改善、糖尿病改善・予防効果などを実証してきた。今後は若年層に感心の高い、腸活・美容の分野での研究も強化していく方針だ。高野豆腐は単に大豆粉を固めたものではなく、凍結・低温熟成する過程でレジスタントプロテインという成分が増加しているので、他の大豆加工品との差別化も容易といえる」
ー海外発信にも取り組む。
「旭松食品での活動になるが、ヨーロッパでの定着を進めている。大豆ミートのようなアレンジレシピや、粉にしてパンへの活用などを提案している。研究拠点としているオランダでは、タンパク質摂取源の割合が現状で動物性6、植物性4くらい。数年以内の逆転が目指されており、海外においては植物性タンパク質市場は急拡大している。この流れは日本でもいずれ本格化するはずであり、引き続きレシピ開発や機能性研究を進め準備しておきたい」
【全国凍豆腐工業協同組合連合会加盟企業(6社)】旭松食品㈱、㈱みすずコーポレーション、登喜和冷凍食品㈱、㈱信濃雪、羽二重豆腐㈱、高原㈱(順不同)
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー高野豆腐の市場動向は。
「組合調査による原料大豆使用量は、テレビ効果で特需のあった2018、19年から減少傾向となっている。今年も9月時点で前年比減となっている。物価高騰による消費者の買い控えも考えられることから、需要喚起は切実な課題となっている」
ー需要喚起に向けて。
「『高野豆腐の日』には、昨年までに引き続き長野県内のNPO法人の子ども応援プロジェクトへ商品を寄付する。タンパク質やカルシウムが豊富で噛む力を鍛えられる高野豆腐は子どもの健康にうってつけ。子どもの頃から高野豆腐に慣れ親しんで欲しい願いも込めている。また今年はレシピサイト『Nadia』上でアレンジレシピコンテストを12月に開催する」
ーレシピコンテストの狙い。
「これまで各社でレシピ発信してきて、健康やダイエットに関心のある方々には知名度が高まってきた。今回、利用者層の若い『Nadia』に場所をお借りしてコンテストという形で能動的に参加してもらうことで、より多くの方に高野豆腐の新たな可能性を感じていただけると期待している」
ー機能性研究に力を入れている。
「これまで食後中性脂肪上昇抑制、脂質代謝改善、糖尿病改善・予防効果などを実証してきた。今後は若年層に感心の高い、腸活・美容の分野での研究も強化していく方針だ。高野豆腐は単に大豆粉を固めたものではなく、凍結・低温熟成する過程でレジスタントプロテインという成分が増加しているので、他の大豆加工品との差別化も容易といえる」
ー海外発信にも取り組む。
「旭松食品での活動になるが、ヨーロッパでの定着を進めている。大豆ミートのようなアレンジレシピや、粉にしてパンへの活用などを提案している。研究拠点としているオランダでは、タンパク質摂取源の割合が現状で動物性6、植物性4くらい。数年以内の逆転が目指されており、海外においては植物性タンパク質市場は急拡大している。この流れは日本でもいずれ本格化するはずであり、引き続きレシピ開発や機能性研究を進め準備しておきたい」
【全国凍豆腐工業協同組合連合会加盟企業(6社)】旭松食品㈱、㈱みすずコーポレーション、登喜和冷凍食品㈱、㈱信濃雪、羽二重豆腐㈱、高原㈱(順不同)
【2023(令和5)年10月21日第5143号7面】
10月21日号 八郎潟特集インタビュー
秋田県佃煮組合 組合長 千田 清隆氏
秋田県佃煮組合(千田清隆組合長)は、秋田県内8社の佃煮メーカーが加入、八郎潟産のわかさぎを始めとした新鮮な魚介を炊き上げる〝秋田佃煮”の魅力を発信している。千田組合長(千田佐市商店社長)は地元道の駅でのPR事業や若い世代への食育事業に力を入れ、佃煮文化を伝承していきたいと話した。(藤井大碁)
‐今年の漁模様。
「9月より始まった今年の八郎湖のわかさぎ漁は、ここまで不漁傾向で、例年より漁獲量が少なくなる見通しだ。高齢化による漁師の減少に加え、大雨や猛暑といったこれまでにない異常気象も影響を及ぼしていると考えられる。だが今年の状況は厳しいものの、近年の漁獲量を平均すれば、八郎湖では安定して獲れていると言うことができる」
‐今年の漁模様。
「9月より始まった今年の八郎湖のわかさぎ漁は、ここまで不漁傾向で、例年より漁獲量が少なくなる見通しだ。高齢化による漁師の減少に加え、大雨や猛暑といったこれまでにない異常気象も影響を及ぼしていると考えられる。だが今年の状況は厳しいものの、近年の漁獲量を平均すれば、八郎湖では安定して獲れていると言うことができる」
‐漁師が減少している。
「組合では年3回、漁師との話し合いの場を設けている。燃料や漁網などの関連資材が値上がりし、漁業経費が上昇している中、物価上昇に合わせて漁師からの買い取り価格を上乗せしていく必要があり、価格に関しての協議を行っている。またインボイス登録していない漁師も多く、組合でどう対応していくかというのも難しい問題になっている。これに関しては経過措置がある2029年までの6年間を目処に、状況を見ながら対応を進めていく。漁師が魚を獲ってくれなければ我々も商売にならないので、共存共栄できる方法を模索していきたい」
‐組合活動について。
「今年6月の『佃煮の日』に合わせて、毎年恒例となっている佃煮キャンペーンを開催した。潟上市内の小学校で、八郎潟産のわかさぎ佃煮を配布すると共に、佃煮についての授業をクイズ形式で実施した。継続的に実施することで、若い世代に佃煮を食べてもらうきっかけにしていきたい。また地元道の駅『ブルーメッセあきた(道の駅しょうわ)』では、組合員全社の佃煮が販売されているので、商品や製造方法を説明したポップを用意して、組合員の佃煮のPRをしていきたいと考えている。さらに道の駅の多目的ホールにおいて、八郎潟や佃煮の歴史を説明したパネル展示を行い、なぜここに佃煮組合があるのか、一般の方に伝えていくことも計画している。今後の取組としては、近年、コロナ禍により実施できていなかった視察研修を年明けに久しぶり開催する予定で、現在、研修先の検討を行っている」
‐販売動向について。
「佃煮や唐揚げの動きは堅調だが、原料の手当てに各社が苦労している。わかさぎや小女子の不漁、いかの高騰など、主力商品の原料に関する問題で、価格転嫁ができるか以前に、そもそも製品が作れるかどうかという大きな問題を抱えている。休売せざるを得ない商品も出てきており、各社がそれに代わるものを開発する必要性に迫られている。秋田を代表する魚である〝はたはた”も獲れておらず、様々な原料が不足する中、代わりとなる原料を探すのも簡単ではない」
‐今後について。
「秋田県は佃煮を良く食べる県ではあるが、若い世代に佃煮の魅力を伝えていかなければ、佃煮の食文化が失われていってしまう。『佃煮の日』に合わせて組合で実施している小学校での食育事業のような取組がとても重要になる。弊社においては、昨年、文化事業部を立ち上げ、北東北初の国際音楽祭の開催に関わり、音楽祭で佃煮の販売を行うなど新たな取組も始めた。9月に潟上市で開催された音楽フェスでも、ブースを出展し、佃煮を使用したおにぎりを販売したところ大変好評で、若い世代への佃煮のアピールに手応えを感じている」
「組合では年3回、漁師との話し合いの場を設けている。燃料や漁網などの関連資材が値上がりし、漁業経費が上昇している中、物価上昇に合わせて漁師からの買い取り価格を上乗せしていく必要があり、価格に関しての協議を行っている。またインボイス登録していない漁師も多く、組合でどう対応していくかというのも難しい問題になっている。これに関しては経過措置がある2029年までの6年間を目処に、状況を見ながら対応を進めていく。漁師が魚を獲ってくれなければ我々も商売にならないので、共存共栄できる方法を模索していきたい」
‐組合活動について。
「今年6月の『佃煮の日』に合わせて、毎年恒例となっている佃煮キャンペーンを開催した。潟上市内の小学校で、八郎潟産のわかさぎ佃煮を配布すると共に、佃煮についての授業をクイズ形式で実施した。継続的に実施することで、若い世代に佃煮を食べてもらうきっかけにしていきたい。また地元道の駅『ブルーメッセあきた(道の駅しょうわ)』では、組合員全社の佃煮が販売されているので、商品や製造方法を説明したポップを用意して、組合員の佃煮のPRをしていきたいと考えている。さらに道の駅の多目的ホールにおいて、八郎潟や佃煮の歴史を説明したパネル展示を行い、なぜここに佃煮組合があるのか、一般の方に伝えていくことも計画している。今後の取組としては、近年、コロナ禍により実施できていなかった視察研修を年明けに久しぶり開催する予定で、現在、研修先の検討を行っている」
‐販売動向について。
「佃煮や唐揚げの動きは堅調だが、原料の手当てに各社が苦労している。わかさぎや小女子の不漁、いかの高騰など、主力商品の原料に関する問題で、価格転嫁ができるか以前に、そもそも製品が作れるかどうかという大きな問題を抱えている。休売せざるを得ない商品も出てきており、各社がそれに代わるものを開発する必要性に迫られている。秋田を代表する魚である〝はたはた”も獲れておらず、様々な原料が不足する中、代わりとなる原料を探すのも簡単ではない」
‐今後について。
「秋田県は佃煮を良く食べる県ではあるが、若い世代に佃煮の魅力を伝えていかなければ、佃煮の食文化が失われていってしまう。『佃煮の日』に合わせて組合で実施している小学校での食育事業のような取組がとても重要になる。弊社においては、昨年、文化事業部を立ち上げ、北東北初の国際音楽祭の開催に関わり、音楽祭で佃煮の販売を行うなど新たな取組も始めた。9月に潟上市で開催された音楽フェスでも、ブースを出展し、佃煮を使用したおにぎりを販売したところ大変好評で、若い世代への佃煮のアピールに手応えを感じている」
【2023(令和5)年10月21日第5143号8面】
有限会社佐藤徳太郎商店 代表取締役 佐藤 進幸氏
有限会社佐藤徳太郎商店(秋田県潟上市)では、昭和22年の創業以来、70年以上にわたり八郎潟伝統の佃煮を作り続けている。佐藤進幸社長に販売動向や原料状況などについてインタビュー。佐藤社長は原料不足や人手不足など様々な課題がある中、訪れる危機に備え、次の一手を常に考えることが、経営者の役割として大切なことと語った。(藤井大碁)
‐足元の販売動向。
「春先の小女子が不漁のため販売できず、その分がマイナスとなったが、県内スーパーで〝いかあられ”などの佃煮製品の販売が好調で、売上をカバーした。WEB通販に関しては送料の大幅アップにより、計画通りにはいかなかった。直営店は、駐車場を広くしたことで、来店しやすくなったことも追い風となり微増で推移している。全体的には、ここまで前年比で増収増益を達成している」
‐様々なコストが上昇している。
「社員が現場で、どうすればさらに効率化できるかを常に考えてくれている。現在、資材が高止まりしているが、工夫して節約できる仕組みを取り入れコストダウンを図っている。先代が作った分業制の仕組みを、現場の社員が自ら進化させ、〝ムリ・ムダ・ムラ”を徹底的に省くよう、常に向上心を持ち続けてやってくれていることに感謝している。結果が出た分は、インセンティブとして社員に還元する制度を作り、日頃の努力に報いるよう努めている」
‐わかさぎ漁が解禁した。
「今年のわかさぎ漁はここまで不漁となっている。昨年は平年より少し多かったが、今年は、去年の半分ほどしか獲れていない。昨年は、八郎湖が日本で一番わかさぎが獲れた湖だったと聞いている。近年、日本の他の湖で不漁が続いている中で、八郎湖だけ獲れ続けるということは考えづらい。暑さや大雨の影響もあると思う。近年、自社で船舶免許を取得し、今年も漁の練習をしている。教えてもらっている漁師と共に行ったある日の漁では、網を上げたら多い時には200キロ獲れるわかさぎが、わずか200グラムしか入っていなかった。燃料代が上昇する中で、これでは大赤字になってしまう。漁師がしっかりとした収入を得られる持続可能な漁を実現するためには、獲れる時に全て獲るのではなく、適正な量をとって、資源を長い目でみて保護していくことも必要だ」
‐他の原料状況について。
「原料はほぼ全て不安定な状況だ。弊社では、小女子漁が盛んな北海道寿都町にも工場があるが、小女子は今年史上初の水揚げゼロとなった。街がこれまで小女子で潤っていたため、不漁により、食堂、ガソリンスタンド、ホームセンターなどの売上も落ち、街全体の経済が停滞してしまっている。だが、確保できる原料を使い、色々な工夫をして、新しいビジネスをスタートしている加工業者もあり、厳しい環境下でも、知恵を絞り、生み出せる価値があるということも同時に学んでいる。絶えず訪れる危機に対して、次の一手を常に考えることが、経営者としての役割として最も大切なことだ」
‐足元の販売動向。
「春先の小女子が不漁のため販売できず、その分がマイナスとなったが、県内スーパーで〝いかあられ”などの佃煮製品の販売が好調で、売上をカバーした。WEB通販に関しては送料の大幅アップにより、計画通りにはいかなかった。直営店は、駐車場を広くしたことで、来店しやすくなったことも追い風となり微増で推移している。全体的には、ここまで前年比で増収増益を達成している」
‐様々なコストが上昇している。
「社員が現場で、どうすればさらに効率化できるかを常に考えてくれている。現在、資材が高止まりしているが、工夫して節約できる仕組みを取り入れコストダウンを図っている。先代が作った分業制の仕組みを、現場の社員が自ら進化させ、〝ムリ・ムダ・ムラ”を徹底的に省くよう、常に向上心を持ち続けてやってくれていることに感謝している。結果が出た分は、インセンティブとして社員に還元する制度を作り、日頃の努力に報いるよう努めている」
‐わかさぎ漁が解禁した。
「今年のわかさぎ漁はここまで不漁となっている。昨年は平年より少し多かったが、今年は、去年の半分ほどしか獲れていない。昨年は、八郎湖が日本で一番わかさぎが獲れた湖だったと聞いている。近年、日本の他の湖で不漁が続いている中で、八郎湖だけ獲れ続けるということは考えづらい。暑さや大雨の影響もあると思う。近年、自社で船舶免許を取得し、今年も漁の練習をしている。教えてもらっている漁師と共に行ったある日の漁では、網を上げたら多い時には200キロ獲れるわかさぎが、わずか200グラムしか入っていなかった。燃料代が上昇する中で、これでは大赤字になってしまう。漁師がしっかりとした収入を得られる持続可能な漁を実現するためには、獲れる時に全て獲るのではなく、適正な量をとって、資源を長い目でみて保護していくことも必要だ」
‐他の原料状況について。
「原料はほぼ全て不安定な状況だ。弊社では、小女子漁が盛んな北海道寿都町にも工場があるが、小女子は今年史上初の水揚げゼロとなった。街がこれまで小女子で潤っていたため、不漁により、食堂、ガソリンスタンド、ホームセンターなどの売上も落ち、街全体の経済が停滞してしまっている。だが、確保できる原料を使い、色々な工夫をして、新しいビジネスをスタートしている加工業者もあり、厳しい環境下でも、知恵を絞り、生み出せる価値があるということも同時に学んでいる。絶えず訪れる危機に対して、次の一手を常に考えることが、経営者としての役割として最も大切なことだ」
【2023(令和5)年10月21日第5143号8面】
10月11日号 浅漬キムチ インタビュー
秋本食品株式会社 代表取締役社長 秋本 善明氏
労働集約型の事業から脱却 共配で販売エリア拡大へ
秋本食品株式会社(神奈川県綾瀬市)の秋本善明氏にインタビュー。浅漬やキムチの売れ行き、原料状況などについて話を聞いた。原料や人手の不足、2024年物流問題など、業界を取り巻く環境は厳しさを増す中、社長就任から5カ月が経過した秋本社長は、社内の選択と集中を推進して収益性の改善を図っていく方針を強調。下半期の課題については、販売エリアの拡大を目指して共配も視野に入れた取組を進めていく考えを明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐浅漬の売れ行きは。
「全般的に良くないが、白菜の姿ものや刻み、ゆず風味の商品はまずまずの動きとなっている。物価高で生活防衛意識が高まっている中、高価格帯ではなくボリューム感もあるので支持されている。節約意識が高い時は新しい商品ではなく無難な定番商品の方が売れる。今がその流れだと思っている」
‐キムチの売れ行きについて。
「今期の前半は量目調整の影響で苦戦したが、直近の動きは良くなっている。消費者が量目調整した商品に慣れてきて、ここ3カ月は前年を上回った。全体でも上半期は前年をクリアした。以前より生活防衛意識は高まっている状況で、浅漬感覚で食べられるライトなキムチが浅漬に置き換わって浅漬のシェアを取っている部分もあると思う。このような状況でも安定して売れているのはブランド力のある商品。価格訴求に付き合っても不毛なので、我々が持っている商品で収益性を高める努力を続けていく」
‐原料状況は。
「大根は契約分でぎりぎり収まっているが、かぶと胡瓜は厳しい状況だ。かぶは半ば過分が出る覚悟で契約率を100%以上にする取組を行っていたが、品質低下などで不足している。秋は小かぶが売れるので採算が合わなくてもやらないといけない。今年の原料の作柄が悪いのは長引いた猛暑の影響が大きい。夏大根は北海道と青森が主力となるが、どこも人手不足で生産者も減っている。仮に生産を行うことができても運賃などの問題もある。これ以上産地の緯度を上げることはできないので、標高を上げるしかない。かぶも含めて現在の産地だけではリスクが高い。現在、当社では標高の高い産地の開拓も進めている」
‐人手不足について。
「人手の確保は本当に大変だ。当社では昨年から特定技能のベトナム人を受け入れており、今年も面接して3人にOKを出した。当然、その3人は会社で働いてくれるものだと思っていたのだが、辞退されてしまった。つまり、当社と他社を天秤にかけ、より条件が良い企業を選んだということだ。当社では特定技能外国人に仕事の内容を覚えてもらい、これから受け入れる外国人技能実習生の指導役になってもらう予定を立てているのだが、関東でも特定技能外国人が取り合いになっている」
‐社長就任から5カ月が経過した。
「意識に変化はないが、漬物業界と市場の環境は不安要素が大きい。来年は物流問題もあり、運賃が2、3割上がると言われている。自社だけで全て解決することはできないので、他社の協力をいただきながら進めていくしかない。また、自社の足場を固めるという意味では社内の選択と集中を推進し、不採算となっている商品の見直しや工場にもメスを入れながら無駄なものを排除する取組を行っている。個人としては他地域の方や得意先の方との交流の機会を増やし、コロナ禍ではできなかった交流の機会を増やしたいと考えている」
‐下半期の課題は。
「コストはさらに上がり続けていくので、どれだけ生産性を向上させることができるか。機械化はもちろん、労働集約型からの脱却を図ることが重要だ。基本的な考えとしては、主力商品の品質を維持しながら収益性を上げる施策を行っていく。また、販売エリアを広げるため、主力商品の地方発送もポイントになる。競合の壁にとらわれず、共配という選択も模索する。東西で互いにメリットを見い出せれば実現することは可能だろう」
【2023(令和5)年10月11日第5142号2面】
【バイヤー必見】イチ押し商品! 会員
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/896/
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/896/
食料新聞電子版 「プロが売りたい!地域セレクション」特別会員
株式会社ピックルスホールディングス 代表取締役社長 影山 直司氏
アイテム集約で利益確保 冷凍の鍋や総菜を開発
株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に浅漬とキムチの販売動向、2024年2月期第2四半期の業績が好調となった要因、価格改定の動き、今後の販売戦略、課題と対応策、2024年12月に稼働予定の茨城工場(仮称)などについて話を聞いた。物価高や人手不足、来年は物流問題など多くの課題を抱える中、影山社長はアイテムの集約や不採算商品の見直しを図っていく方針を明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐浅漬とキムチの売れ行きは。
「8月で中間を締めたのだが、トータルの売り上げは前年比でプラスとなっている。だが、浅漬は前年割れとなっており、厳しい状況が続いている。キムチは持ち直してプラスとなっているが、浅漬とキムチを合わせても前年をクリアできていないので、キムチのプラスで浅漬のマイナス分は埋められていない」
‐浅漬が苦戦している理由は。
「物価高の影響が大きいと思っている。物価の上昇で消費者の財布の紐が固くなっている。買い物のかごから外れるものが出てきており、ご飯周りの商品が減ってきている印象だ。残念ながら浅漬はその中に入ってしまっている状況だ。夏場の胡瓜の動きは良かったが、それ以外の商品は厳しかった。また、当社で言えば長芋の原料仕入価格が高騰したため、商品を絞ったことも影響した。主力の白菜や胡瓜の価格は若干上がっており、売上が増えても原料や資材関係の価格が上がり続けているので、利益の確保は難しくなってきている」
‐2024年2月期第2四半期の業績が好調だった。
「コンビニエンスストアにおいて5月に実施されたフェアに当社商品が導入された影響もあって売り上げが良かった。様々なコストが上がっているのだが、増収効果によってコストを吸収することができ、利益を出すことができた。量販店については浅漬の状況に変わりはないが、秋口はプラスで推移しており、惣菜も伸びているのでプラスになると見ている」
‐価格改定の動きについて。
「春から夏にかけて、茄子や胡瓜の価格や量目の見直しを行った。キムチについては引き続き据え置きでやっていて動きは順調。他社が夏に行っていた増量企画を実施することはできなかったが、原料が安定する11月頃の増量企画を検討している。昨年同時期の増量キャンペーンは1アイテムだったが、今回はシリーズ3アイテムで実施する予定。企業としてはギリギリのラインだが、物価高の中、家計応援のコンセプトで実施したい。また、ご飯がススムキムチ公式キャラクター『ススムくん』のLINEスタンプのプレゼント企画も同時に実施し、200万人から300万人の登録を目指している」
‐漬物の需要拡大に向けた取組について。
「浅漬を料理の素材として活用し、メニュー提案を行っていく。一例をあげると、浅漬を液ごと使用した鍋つゆいらずのメニュー提案を行う。生の白菜を使用した鍋も美味しいが、調味液ごと浅漬を使用した鍋は、だしが効いていて肉や野菜を入れるだけで簡単に美味しい鍋ができる。コロナ禍ではマネキン販売をすることができなかったが、今年の冬は試食の提供を行う他、HPとSNSによる食べ方提案を推進していきたいと考えている」
‐今後の販売戦略について。
「価格訴求はできない状況だ。ボリュームがあって価格が安い、という商品ではなく、料理として食べていただけるなど、付加価値を訴求していくことが重要だ。量販店の動きを見ても、良いものを売っていこうという企業の業績が良い。ディスカウント店だけが伸びているわけではない。今後はより付加価値のある商品を提案していくことが大切だ」
‐今後の課題と対応策について。
「人手が足りずコストも上がっている中で、コストがかかりすぎているところを優先して見直している。売上だけではなく利益を確保することが重要で、今のラインナップを見て手間がかかっているもの、出荷までの時間がタイトなもの、コストがかかりすぎているものを確認し、アイテムを集約していく。当社は現在、昼間だけではなく夜間の製造も行っており、人件費は割増しになってしまっている。夜間製造の必要性などを再確認し、日勤の製造に集約していく。当社は多くのOEM製造を行っているが、実情に合わせた規格の見直しを進めていく必要がある」
‐2024年12月に茨城県に稼働予定の新工場について。
「予定より少し遅れているが、ラインの自動化など先のことを見据えて省人化の工場を建設する。これまでは人が野菜の葉の1枚1枚を選別していたが、AIカメラを活用した選別機などを導入し、既存の工場以上に機械化を進めて省人化する」
‐今後強化していく事業は。
「昨年3月に立ち上げたピックルスファームで生産したさつまいもを今年9月に設立した合弁会社のべジパルで加工販売する。さつまいもの生産はあまり手間がかからず、焼き芋や干し芋など、さつまいもの加工品も人気があるので、事業の柱になることを期待している。また、年明け頃を目標に『ご飯がススムキムチ』の冷凍鍋を発売する。冷凍食品はロングライフなので食品ロス削減や便利に使えることが支持されて伸びているし、これからも伸びていくカテゴリー。今後は冷凍惣菜の開発も進めていく」
【2023(令和5)年10月11日第5142号7面】
株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に浅漬とキムチの販売動向、2024年2月期第2四半期の業績が好調となった要因、価格改定の動き、今後の販売戦略、課題と対応策、2024年12月に稼働予定の茨城工場(仮称)などについて話を聞いた。物価高や人手不足、来年は物流問題など多くの課題を抱える中、影山社長はアイテムの集約や不採算商品の見直しを図っていく方針を明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐浅漬とキムチの売れ行きは。
「8月で中間を締めたのだが、トータルの売り上げは前年比でプラスとなっている。だが、浅漬は前年割れとなっており、厳しい状況が続いている。キムチは持ち直してプラスとなっているが、浅漬とキムチを合わせても前年をクリアできていないので、キムチのプラスで浅漬のマイナス分は埋められていない」
‐浅漬が苦戦している理由は。
「物価高の影響が大きいと思っている。物価の上昇で消費者の財布の紐が固くなっている。買い物のかごから外れるものが出てきており、ご飯周りの商品が減ってきている印象だ。残念ながら浅漬はその中に入ってしまっている状況だ。夏場の胡瓜の動きは良かったが、それ以外の商品は厳しかった。また、当社で言えば長芋の原料仕入価格が高騰したため、商品を絞ったことも影響した。主力の白菜や胡瓜の価格は若干上がっており、売上が増えても原料や資材関係の価格が上がり続けているので、利益の確保は難しくなってきている」
‐2024年2月期第2四半期の業績が好調だった。
「コンビニエンスストアにおいて5月に実施されたフェアに当社商品が導入された影響もあって売り上げが良かった。様々なコストが上がっているのだが、増収効果によってコストを吸収することができ、利益を出すことができた。量販店については浅漬の状況に変わりはないが、秋口はプラスで推移しており、惣菜も伸びているのでプラスになると見ている」
‐価格改定の動きについて。
「春から夏にかけて、茄子や胡瓜の価格や量目の見直しを行った。キムチについては引き続き据え置きでやっていて動きは順調。他社が夏に行っていた増量企画を実施することはできなかったが、原料が安定する11月頃の増量企画を検討している。昨年同時期の増量キャンペーンは1アイテムだったが、今回はシリーズ3アイテムで実施する予定。企業としてはギリギリのラインだが、物価高の中、家計応援のコンセプトで実施したい。また、ご飯がススムキムチ公式キャラクター『ススムくん』のLINEスタンプのプレゼント企画も同時に実施し、200万人から300万人の登録を目指している」
‐漬物の需要拡大に向けた取組について。
「浅漬を料理の素材として活用し、メニュー提案を行っていく。一例をあげると、浅漬を液ごと使用した鍋つゆいらずのメニュー提案を行う。生の白菜を使用した鍋も美味しいが、調味液ごと浅漬を使用した鍋は、だしが効いていて肉や野菜を入れるだけで簡単に美味しい鍋ができる。コロナ禍ではマネキン販売をすることができなかったが、今年の冬は試食の提供を行う他、HPとSNSによる食べ方提案を推進していきたいと考えている」
‐今後の販売戦略について。
「価格訴求はできない状況だ。ボリュームがあって価格が安い、という商品ではなく、料理として食べていただけるなど、付加価値を訴求していくことが重要だ。量販店の動きを見ても、良いものを売っていこうという企業の業績が良い。ディスカウント店だけが伸びているわけではない。今後はより付加価値のある商品を提案していくことが大切だ」
‐今後の課題と対応策について。
「人手が足りずコストも上がっている中で、コストがかかりすぎているところを優先して見直している。売上だけではなく利益を確保することが重要で、今のラインナップを見て手間がかかっているもの、出荷までの時間がタイトなもの、コストがかかりすぎているものを確認し、アイテムを集約していく。当社は現在、昼間だけではなく夜間の製造も行っており、人件費は割増しになってしまっている。夜間製造の必要性などを再確認し、日勤の製造に集約していく。当社は多くのOEM製造を行っているが、実情に合わせた規格の見直しを進めていく必要がある」
‐2024年12月に茨城県に稼働予定の新工場について。
「予定より少し遅れているが、ラインの自動化など先のことを見据えて省人化の工場を建設する。これまでは人が野菜の葉の1枚1枚を選別していたが、AIカメラを活用した選別機などを導入し、既存の工場以上に機械化を進めて省人化する」
‐今後強化していく事業は。
「昨年3月に立ち上げたピックルスファームで生産したさつまいもを今年9月に設立した合弁会社のべジパルで加工販売する。さつまいもの生産はあまり手間がかからず、焼き芋や干し芋など、さつまいもの加工品も人気があるので、事業の柱になることを期待している。また、年明け頃を目標に『ご飯がススムキムチ』の冷凍鍋を発売する。冷凍食品はロングライフなので食品ロス削減や便利に使えることが支持されて伸びているし、これからも伸びていくカテゴリー。今後は冷凍惣菜の開発も進めていく」
【2023(令和5)年10月11日第5142号7面】
株式会社ピックルスホールディングス HP
10月1日号 理事長に聞く
福岡県漬物工業協同組合 理事長 熊川 稔也氏
消費税の二重払いを懸念 全組合員に管理士2級推奨
福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。
(福岡支局 菰田隆行)
◇ ◇
‐原料不足の中での製品動向は。
「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」
‐インボイス制度の導入について。
「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」
‐組合事業について。
「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」
‐漬物業界の将来は。
「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」
【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】
福岡県漬物工業協同組合の熊川稔也理事長にインタビュー。ここ数年、九州産高菜原料は不作が続いており、各社とも原料の確保に苦しむ。新規の商談は難しく、既存の取引先への出荷調整や、数品目の休売を決めているメーカーもある。また、10月から導入された「インボイス制度」の影響も懸念材料だ。熊川理事長に製品動向、原料農家との対応、組合事業運営などについて話を聞いた。
(福岡支局 菰田隆行)
◇ ◇
‐原料不足の中での製品動向は。
「6月から8月にかけては、売上は前年比で25%以上プラスとなり、コロナ前に戻っている。これは諸コストの高騰で、今年に入って値上げを実施したためだ。売上増となってはいるが、支払い額も上がっているので、とても全て吸収できてはいない。消費者は、あらゆる食品が値上がりしている状況に慣れておらず、買い控えにつながっている。外資系の大型店、DS、ドラッグストアの売上が好調なのがそれを物語っている。新規取引の商談はコロナ後に活発になってきたが、取引できるかどうかは中身をよく聞いて、最終的には量的にこなせるかどうかが判断材料となってくる」
‐インボイス制度の導入について。
「一番問題となるのは、消費税の二重払いだ。インボイス制度下では、インボイスの非登録事業者に支払った消費税の『仕入税額控除』が認めてもらえないため、非登録者へ支払った消費税を税務署にも支払うことになり、消費税の二重払いとなってしまう。ほとんどのメーカーでは原料を仕入れている農家が非登録事業者で、この二重払いが大きな問題だ。経過措置を設けてはあるが、この問題は軽視できない。国には登録事業者とならない農家に対してもっと真剣に、かつ具体的にどうすれば良いかを指導してほしいと思う」
‐組合事業について。
「我々漬物業者にとって、最も深刻なのは人手不足だ。それは原料の収穫や漬け込みという仕事が発生するからで、他の業態とは違う深刻さが潜んでいる。そこで県内組合員ではまだ外国人実習生を採用していない企業も多いため、いつでも外国人実習生を採用できるよう、社内に漬物製造管理士2級の有資格者を持ってもらうことを推奨していく。受検費用を組合費で補填し、今年から来年初めにかけて加盟企業15社全てに、有資格社員を置いていただこうと考えている」
‐漬物業界の将来は。
「AIやロボットが普及していくと、人間の仕事が減るという指摘がある。しかし、漬物は原料漬け込みや製造に手がかかり、ロボットではなかなかこなせないのではないかと考えている。そうすると、人手がかかっている商品は自然と値が上がるため、手をかけた物の価値が消費者に理解してもらえるのだろうか、という懸念というか、心配ばかりが最近頭をよぎっている。仕事の悩みは一企業では解決できないことの方が多く、業界全体で考えていく必要がある。そのためにも組合組織は重要で、大手企業ではない小規模事業者の意見が通る業界にしていきたい」
【2023(令和5)年10月1日第5141号8面】
10月1日号 社長に聞く
株式会社イヌイ 取締役社長 松石 健郎氏
「漬物語りⓇ」認知度向上へ 直売所建設でもう一つの柱に
株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。
(福岡支局・菰田隆行)
◇ ◇
‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。
「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」
‐グループ会社の外食事業は。
「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」
‐イヌイの今後の方針は。
「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」
【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】
イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/
株式会社イヌイ(福岡県久留米市)は明治20年頃、福岡県瀬高町(現みやま市)に農産物関連事業として発足。昭和39年3月に漬物製造販売の個人商店として、創業者・松石吉昭氏が事業をスタートした。同45年3月に鬼丸商事株式会社を設立。平成元年3月、福岡県久留米市に北野工場(現イヌイ本社)を開設し、同時に株式会社イヌイを設立した。同4年6月に鬼丸商事他関連会社4社が合併し、株式会社マツイシに社名を変更(マツイシ・グループ本社)。翌年4月に漬物・惣菜の2工場をイヌイに移管し、北野工場での惣菜製造を本格化した。その後イヌイは、産地開拓や「漬物語りⓇ」という新ブランドを立ち上げるなど、新進気鋭の取組で伸長している。同社の松石健郎社長に、コロナ渦中から現在までの動向や、今後の方針について話を聞いた。
(福岡支局・菰田隆行)
◇ ◇
‐コロナ下から5類に移行して以後の状況は。
「外食向けの業務用や、空港などで販売していたお土産向けは、コロナの影響によって売上が減少し、コンビニ向けも苦戦していた。一方、取引が大きい持ち帰り弁当向け商材はプラスを保っていたため、お陰様でプラマイはゼロだった。昨年6月の会計年度スタート時に、原材料費や諸コスト高騰で値上げを実施した。それでも追い付かなかったため、今年の5月までに再値上げを実施させていただいた。この間、売上は前年比100%を超えていたが利益は減少し、増収減益だった。今期に入ってからの6月~9月は売上も戻っており、2度の価格改定によって利益も改善してきている」
‐グループ会社の外食事業は。
「お好み焼きの“どんどん亭”は、確かにコロナ禍では厳しかったが、比較的(売上は)もっていたと言える。一番打撃を受けたのが居酒屋業態だった。昨年あたりから、外食全般で80%ほどまで回復が見え始め、今年に入ってからはコロナ前のほぼ100%に戻っている。そば茶屋やつけ麺など新業態もプラスアルファとなっていて、グループ全体では完全回復といっていい状況だ」
‐イヌイの今後の方針は。
「今年の6月、初めて工場直売会を開催した。地域の皆様への感謝の意味を込めて行ったが、多くのお客様に来ていただき、社員も感激していた。何より高菜漬という商品の人気を直接肌で感じられたのが、一番の収穫だった。今後は、国から『事業再構築補助金』の採択を受けたので、年内にも本社敷地内に直売所を建設する予定だ。また、近年トレンドになっている“自販機”での販売も考えており、自販機用商品の開発にも着手する。それ用の冷凍設備や計量器なども、補助金を使って導入を予定している。自社ブランドとして開発し、登録商標も取っている『漬物語りⓇ』の認知度を上げ、業務用惣菜との両輪として、もう一つの柱に育てていきたいと考えている」
【2023(令和5)年10月1日第5141号10面】
イヌイ 食料新聞電子版「九州うまかモン」
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/1374/
9月21日号 全漬連会長に聞く
全日本漬物協同組合連合会会長 中園雅治氏
高塩分の誤解払拭最優先 若手が活躍する組織作りを
今年5月、株式会社中園久太郎商店の中園雅治社長が全日本漬物協同組合連合会の会長に就任した。中園会長は、漬物が高塩分という誤解を解き『消費拡大』に繋げること、若者の漬物離れの原因を探り『漬物文化継承』を実現することに意欲を示す。
(大阪支社 小林悟空)
◇ ◇
‐目標は。
「野﨑伸一前会長は賦課金算出方法の見直しや若手の登用といった改革を行った。また漬物議連の発足や外国人技能実習制度の進展などに尽力いただいた。漬物の産業としての土台がようやく固まったところだと思う。次に全国組織として取り組むべきは『消費拡大』と『漬物文化継承』だと考えている。これらを実現できれば給与改善や人手不足緩和、農業振興といった課題にも貢献できる」
‐消費拡大策の方針は。
「最優先で取り組むべきは漬物が持つマイナスイメージ、すなわち高塩分であるという誤解を払拭すること。漬物は発酵食品であり、食物繊維をはじめ多くの栄養を効率的に摂れる食品であることなどPRできる点はたくさんあるのだが、高塩分という誤解がある限り効果は半減してしまう」
‐漬物の塩分について。
「野菜の日(8月31日)に農林水産省の主催で『漬物から野菜の消費拡大を考える』と題したWebシンポジウムが開催された。そこで当連合会の宮尾茂雄顧問が指摘した通り、漬物は製造技術や流通システムの発達によって低塩化している。日本標準成分表の数字も改訂されているのだが、古い知識のまま『漬物は高血圧の敵』という論調が見受けられる。もちろん塩分ゼロではないがそれは野菜にドレッシングを掛けたり、スープに入れたりする場合も同様のこと。野菜摂取量に対しての漬物の塩分量は決して多くないと分かるはずだ」
‐料理への活用も推進している。
「ご飯のお供だけでは一度に食べる量に限界がある。調味料兼具材として料理に使ってもらえれば、格段に使用量は増える。そこでまずは自社で試してみようと、指宿市内の飲食店の協力を得て漬物を使ったメニューを開発していただいた。想像以上に用途が広く、料理人の発想力に驚かされた。消費者の反応も良かったようだ。こうした事例は積極的に共有していきたい」
‐漬物文化継承について。
「20代で漬物を食している人の割合はたったの20%という統計数字が出ている。若者のことだから塩分以外に原因があるということになる。米食が減ったから…など安易に浮かぶ理由以外にもあるかもしれない。学識者や調査機関など外部の協力を得て、先入観に囚われず原因を精査すれば、新たな対策も見えてくるのではないか」
‐原料面の取組は。
「原料対策については各地域、各社でそれぞれの契約や習慣に沿った取組を基本とし、全漬連としてはそれらのサポートをしていく。最近の傾向として原料不足により需要があっても対応しきれないという事態が増えているので、情報共有や行政との連携等にも取り組まねばならない」
‐全漬連の運営について。
「前会長の発案で、役員に全国枠を設けて若手や女性理事の登用を実現できた。またPR、原料対策など課題ごとに委員会を設けており、そちらも第一線で活躍する若手経営者たちが積極的に参加してくれているのは非常にありがたいこと。若手の方々が発言しやすい組織となり、会員の役に立つ組織であることを常に目指し、臨機応変な事業を心がけたい」
(大阪支社 小林悟空)
◇ ◇
‐目標は。
「野﨑伸一前会長は賦課金算出方法の見直しや若手の登用といった改革を行った。また漬物議連の発足や外国人技能実習制度の進展などに尽力いただいた。漬物の産業としての土台がようやく固まったところだと思う。次に全国組織として取り組むべきは『消費拡大』と『漬物文化継承』だと考えている。これらを実現できれば給与改善や人手不足緩和、農業振興といった課題にも貢献できる」
‐消費拡大策の方針は。
「最優先で取り組むべきは漬物が持つマイナスイメージ、すなわち高塩分であるという誤解を払拭すること。漬物は発酵食品であり、食物繊維をはじめ多くの栄養を効率的に摂れる食品であることなどPRできる点はたくさんあるのだが、高塩分という誤解がある限り効果は半減してしまう」
‐漬物の塩分について。
「野菜の日(8月31日)に農林水産省の主催で『漬物から野菜の消費拡大を考える』と題したWebシンポジウムが開催された。そこで当連合会の宮尾茂雄顧問が指摘した通り、漬物は製造技術や流通システムの発達によって低塩化している。日本標準成分表の数字も改訂されているのだが、古い知識のまま『漬物は高血圧の敵』という論調が見受けられる。もちろん塩分ゼロではないがそれは野菜にドレッシングを掛けたり、スープに入れたりする場合も同様のこと。野菜摂取量に対しての漬物の塩分量は決して多くないと分かるはずだ」
‐料理への活用も推進している。
「ご飯のお供だけでは一度に食べる量に限界がある。調味料兼具材として料理に使ってもらえれば、格段に使用量は増える。そこでまずは自社で試してみようと、指宿市内の飲食店の協力を得て漬物を使ったメニューを開発していただいた。想像以上に用途が広く、料理人の発想力に驚かされた。消費者の反応も良かったようだ。こうした事例は積極的に共有していきたい」
‐漬物文化継承について。
「20代で漬物を食している人の割合はたったの20%という統計数字が出ている。若者のことだから塩分以外に原因があるということになる。米食が減ったから…など安易に浮かぶ理由以外にもあるかもしれない。学識者や調査機関など外部の協力を得て、先入観に囚われず原因を精査すれば、新たな対策も見えてくるのではないか」
‐原料面の取組は。
「原料対策については各地域、各社でそれぞれの契約や習慣に沿った取組を基本とし、全漬連としてはそれらのサポートをしていく。最近の傾向として原料不足により需要があっても対応しきれないという事態が増えているので、情報共有や行政との連携等にも取り組まねばならない」
‐全漬連の運営について。
「前会長の発案で、役員に全国枠を設けて若手や女性理事の登用を実現できた。またPR、原料対策など課題ごとに委員会を設けており、そちらも第一線で活躍する若手経営者たちが積極的に参加してくれているのは非常にありがたいこと。若手の方々が発言しやすい組織となり、会員の役に立つ組織であることを常に目指し、臨機応変な事業を心がけたい」
【2023(令和5)年9月21日第5140号1面】
9月21日号 トップに聞く
株式会社太陽漬物 代表取締役社長 寺田知弘氏
原料確保が勝負の分け目 大根・高菜を一貫して自社管理
株式会社太陽漬物(鹿児島県曽於市末吉町)は、九州特産の沢庵(干し・生漬)のトップメーカー。寺田知弘社長は大根原料の不足が続く中、農業から一貫した自社管理を行うことで適正在庫を維持し、需要に応え続けることが同社の強みだと語る。(小林悟空)
◇ ◇
-沢庵の市場動向は。
「当社は順調に推移しており、前期(8月決算)は計画通りで着地できた。市場全体で見ても悪くない状況で、スーパーでは簡便性の高い刻みタイプの伸びが大きい。当社の売上トップは『しそ味L』が堅持しているが『九州つぼ漬』が猛追している状況だ。中外食業界からの引き合いも多い。しかしそれ以上に、大根原料の不足が続いており、当社に需要が流れているという面が大きかった。原料確保が勝負の分け目、という時代が来ている」
-原料確保について。
「九州は昨年9月、播種直後に台風に襲われて撒き直しとなり生大根が不足。年明けには強烈な寒波があり、干し大根にも影響が出た。北関東や東北方面も不作だった。そのような中、当社は契約農家に種の提供から行い、収穫できた大根は元漬業者様に頼らず、全て自社で漬込んでいる。農業から一貫して自社管理し、緻密な販売計画を立てていることが安定供給に繋がっている」
-4月には価格改定を実施した。
「全てのコストが値上がりしているため、避けられない判断だった。今年は大根原料の仕入れ価格を引き上げるため、さらなる価格改定も視野に入る。当社製品は現時点でもアッパー気味の価格帯であり、価格よりも味で評価いただいているものとして、品質を維持できる適正価格を追求しなければならない」
-高菜について。
「高菜漬の比率は年々増え、干し沢庵、生沢庵に続く第3の柱に成長している。高菜原料の生産量では、鹿児島が日本一。そのメリットを生かしていく。干し大根の“干し作業”は高齢者には大変な負担で、そうした農家には高菜の栽培に回ってもらうなど柔軟な立ち回りもできるのは土地に恵まれている。これからも大局的な見地を持ち、農家との対話を続けながら的確な判断をしていきたい」
-SDGsの取組は。
「刻み製品の比率を上げることで原料のロスを少なくし、これまで端材となっていた物を使用すれば、残渣を減らすことができる。原料、資材、人件費などあらゆる経費が高騰している現状で、効率化を図っていくことがSDGsの取組に合致してくると思う」
◇ ◇
-沢庵の市場動向は。
「当社は順調に推移しており、前期(8月決算)は計画通りで着地できた。市場全体で見ても悪くない状況で、スーパーでは簡便性の高い刻みタイプの伸びが大きい。当社の売上トップは『しそ味L』が堅持しているが『九州つぼ漬』が猛追している状況だ。中外食業界からの引き合いも多い。しかしそれ以上に、大根原料の不足が続いており、当社に需要が流れているという面が大きかった。原料確保が勝負の分け目、という時代が来ている」
-原料確保について。
「九州は昨年9月、播種直後に台風に襲われて撒き直しとなり生大根が不足。年明けには強烈な寒波があり、干し大根にも影響が出た。北関東や東北方面も不作だった。そのような中、当社は契約農家に種の提供から行い、収穫できた大根は元漬業者様に頼らず、全て自社で漬込んでいる。農業から一貫して自社管理し、緻密な販売計画を立てていることが安定供給に繋がっている」
-4月には価格改定を実施した。
「全てのコストが値上がりしているため、避けられない判断だった。今年は大根原料の仕入れ価格を引き上げるため、さらなる価格改定も視野に入る。当社製品は現時点でもアッパー気味の価格帯であり、価格よりも味で評価いただいているものとして、品質を維持できる適正価格を追求しなければならない」
-高菜について。
「高菜漬の比率は年々増え、干し沢庵、生沢庵に続く第3の柱に成長している。高菜原料の生産量では、鹿児島が日本一。そのメリットを生かしていく。干し大根の“干し作業”は高齢者には大変な負担で、そうした農家には高菜の栽培に回ってもらうなど柔軟な立ち回りもできるのは土地に恵まれている。これからも大局的な見地を持ち、農家との対話を続けながら的確な判断をしていきたい」
-SDGsの取組は。
「刻み製品の比率を上げることで原料のロスを少なくし、これまで端材となっていた物を使用すれば、残渣を減らすことができる。原料、資材、人件費などあらゆる経費が高騰している現状で、効率化を図っていくことがSDGsの取組に合致してくると思う」
【2023(令和5)年9月21日第5140号4面】
太陽漬物 HP
9月21日号 トップに聞く
株式会社タカハシ 代表取締役 髙橋 晃氏
コロナ後は動向活発化 素材のカット法で新提案も
食品用機械と設備の総合メーカー、株式会社タカハシ(東京都中野区)は、独自設計の〝垂直裁断方式〟による「タカハシ式高速裁断機」で著名。その高い処理能力に加え操作性、安全性、衛生面においてもワンランク上の作業環境を実現する。同社の裁断機は漬物・佃煮・珍味をはじめ、給食・食品・ペットフード・製薬業界まで、多方面で活躍している。同社代表取締役の髙橋晃氏に、コロナ後の各業界の動向や課題、今後の見通しなどについて話を聞いた。(菰田隆行)
◇ ◇
‐コロナ後の動向は。
「新型コロナウイルスの分類が第5類に引き下げられ、人も物も動き出し、取引先の業種を問わず〝気分〟が変わってきていると思う。コロナで先が見えなかったが生産の見通しが立つようになり、量産体制を図る企業もある。そのため、これまで止まっていた機械の入れ替えや更新が必要となってきているようで、問い合わせが増えている。また、どの業種も人手不足に悩まされているため、機械頼りという一面がある。これまでは、カットするだけだったものを次の工程で手間を省けるように、素材を倒してバラけさせてほしいなどといった要望も出てきている。なるべく人手をかけないで済むようオートメーション化やライン化の要望も多く、それらについては他社とのコラボレーションで対応し、進めていきたい」
‐6月に出展された「FOOMA JAPAN2023」も盛況だった。
「展示会で情報を収集したいという要望のため入場者も多く、活発に商談ができた。お蔭様で成約に結び付いたところもある。どの業界にしても、コロナ下ではこちらから働きかけてもなかなか動きはなかったが、今は先方から問い合わせてくるようになっている」
‐人手不足への対応は。
「コロナで停滞していた時は手が回らなかったが、今後はどういう形で募集するか、どうしたら来てくれるようになるかを考えていきたい。機械の製造現場でいうと、例えばこれまでは土台となる部分の溶接まで全て自社で行っていたが、これを外注して自社では組み上げるだけの作業にすれば、各段に効率化できる。また、機械の仕様自体も見直しており、部品一つにしてもこれまでは独自規格のネジやシャフト等を使用していたが、それらも市販品を利用すれば調達も楽になるし、なにより納入先でのメンテナンス作業が効率化できる。その他、営業面では委託も視野に入れて考えている」
‐カット技術には絶大な定評がある。
「他のスライサー等で難しい素材のカットも、どうすればできるかという技術と、その対応力には自信がある。どんな素材でも、今までとは違う料理に利用できるような切り方があれば、それを実現することで消費者がより購入しやすくなるかもしれない。レシピに合わせたカット方法のアイデアがあれば、ぜひ当社に相談してみてほしい」
【2023(令和5)年9月21日第5140号8面】
食料新聞電子版 工場長・店長必見!関連資材機器・原料
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/502/
食品用機械と設備の総合メーカー、株式会社タカハシ(東京都中野区)は、独自設計の〝垂直裁断方式〟による「タカハシ式高速裁断機」で著名。その高い処理能力に加え操作性、安全性、衛生面においてもワンランク上の作業環境を実現する。同社の裁断機は漬物・佃煮・珍味をはじめ、給食・食品・ペットフード・製薬業界まで、多方面で活躍している。同社代表取締役の髙橋晃氏に、コロナ後の各業界の動向や課題、今後の見通しなどについて話を聞いた。(菰田隆行)
◇ ◇
‐コロナ後の動向は。
「新型コロナウイルスの分類が第5類に引き下げられ、人も物も動き出し、取引先の業種を問わず〝気分〟が変わってきていると思う。コロナで先が見えなかったが生産の見通しが立つようになり、量産体制を図る企業もある。そのため、これまで止まっていた機械の入れ替えや更新が必要となってきているようで、問い合わせが増えている。また、どの業種も人手不足に悩まされているため、機械頼りという一面がある。これまでは、カットするだけだったものを次の工程で手間を省けるように、素材を倒してバラけさせてほしいなどといった要望も出てきている。なるべく人手をかけないで済むようオートメーション化やライン化の要望も多く、それらについては他社とのコラボレーションで対応し、進めていきたい」
‐6月に出展された「FOOMA JAPAN2023」も盛況だった。
「展示会で情報を収集したいという要望のため入場者も多く、活発に商談ができた。お蔭様で成約に結び付いたところもある。どの業界にしても、コロナ下ではこちらから働きかけてもなかなか動きはなかったが、今は先方から問い合わせてくるようになっている」
‐人手不足への対応は。
「コロナで停滞していた時は手が回らなかったが、今後はどういう形で募集するか、どうしたら来てくれるようになるかを考えていきたい。機械の製造現場でいうと、例えばこれまでは土台となる部分の溶接まで全て自社で行っていたが、これを外注して自社では組み上げるだけの作業にすれば、各段に効率化できる。また、機械の仕様自体も見直しており、部品一つにしてもこれまでは独自規格のネジやシャフト等を使用していたが、それらも市販品を利用すれば調達も楽になるし、なにより納入先でのメンテナンス作業が効率化できる。その他、営業面では委託も視野に入れて考えている」
‐カット技術には絶大な定評がある。
「他のスライサー等で難しい素材のカットも、どうすればできるかという技術と、その対応力には自信がある。どんな素材でも、今までとは違う料理に利用できるような切り方があれば、それを実現することで消費者がより購入しやすくなるかもしれない。レシピに合わせたカット方法のアイデアがあれば、ぜひ当社に相談してみてほしい」
【2023(令和5)年9月21日第5140号8面】
食料新聞電子版 工場長・店長必見!関連資材機器・原料
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/502/
9月21日号 トップに聞く
立花容器株式会社 代表取締役社長 岡野邦男氏
今年で創業108年目の老舗・立花容器株式会社(岡野邦男社長、岡山県小田郡矢掛町)。創業当初は酒蔵へ樽を納めていたところから、その後プラスチック製品、PET製品へと事業を拡大。そして現在は「チアフルライフ」を事業目的に据え、楽器やキャンプアイテムなど、容器以外へも事業領域を拡げている。岡野社長は、風通しが良く自主性のある風土が容器の製造、販売にも好影響を与えていると話す。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー御社が事業目的としているチアフルライフについて。
「まず当社の歴史を振り返ると創業当初は酒蔵向けの木樽製造を営んでいた。プラスチック樽を開発し、漬物や味噌、珍味など取引先を大きく拡大したのが第2創業期、そしてPET製品に着手し、医療用品などにも進出したのが第3創業期。順調に業容を拡大してきた一方で、BtoBに限定されていたとも言える。そこで2015年に創業100周年を迎えたタイミングに、それまでの枠に囚われず社員も、お客様(消費者)もワクワクするような新しい提案をできる会社へ進化していこうと我が社の事業目的を『チアフルライフ』とした。以来、楽器やキャンプ用品など様々な分野に取組を広げている」
ーその成果は。
「入社1年目からアイデアを出し、製品化への道筋を模索していく機会が得られるようになり、会社全体に風通しの良い、活気ある風土が生まれている。SNSやイベントを一般消費者の方と直接つながる場も生まれ、人材採用にも好影響が出てくると思う。またBtoBにおいても、当社の技術の幅広さやフットワークの軽さが伝わるようになり、幅広いご相談をいただけるようになった。コラボ企画なども進行しているところだ」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー御社が事業目的としているチアフルライフについて。
「まず当社の歴史を振り返ると創業当初は酒蔵向けの木樽製造を営んでいた。プラスチック樽を開発し、漬物や味噌、珍味など取引先を大きく拡大したのが第2創業期、そしてPET製品に着手し、医療用品などにも進出したのが第3創業期。順調に業容を拡大してきた一方で、BtoBに限定されていたとも言える。そこで2015年に創業100周年を迎えたタイミングに、それまでの枠に囚われず社員も、お客様(消費者)もワクワクするような新しい提案をできる会社へ進化していこうと我が社の事業目的を『チアフルライフ』とした。以来、楽器やキャンプ用品など様々な分野に取組を広げている」
ーその成果は。
「入社1年目からアイデアを出し、製品化への道筋を模索していく機会が得られるようになり、会社全体に風通しの良い、活気ある風土が生まれている。SNSやイベントを一般消費者の方と直接つながる場も生まれ、人材採用にも好影響が出てくると思う。またBtoBにおいても、当社の技術の幅広さやフットワークの軽さが伝わるようになり、幅広いご相談をいただけるようになった。コラボ企画なども進行しているところだ」
ー容器については。
「『楽器メーカーになるの?』とイジられることもあるが、容器もしっかり続けるのでご安心ください(笑)。容器はテイクアウト・デリバリーや、環境負荷低減など次々と新たなニーズが生まれており、新製品開発のネタが尽きることはない。一方、プラスチック原料高騰など利益面では厳しい状況が続くが、そういうピンチの中にこそチャンスを見出せる。ガラス瓶業界など隣接業界も供給不足に陥っているため、当社は代替として耐熱性のあるPET容器を開発した。75℃充填まで使用できる『PET‐TT21‐100ml』をドレッシングやオイル向けに提案している。ガラス瓶より軽くコスト面削減につながるため大変好評で、200mlタイプも開発中だ」
「『楽器メーカーになるの?』とイジられることもあるが、容器もしっかり続けるのでご安心ください(笑)。容器はテイクアウト・デリバリーや、環境負荷低減など次々と新たなニーズが生まれており、新製品開発のネタが尽きることはない。一方、プラスチック原料高騰など利益面では厳しい状況が続くが、そういうピンチの中にこそチャンスを見出せる。ガラス瓶業界など隣接業界も供給不足に陥っているため、当社は代替として耐熱性のあるPET容器を開発した。75℃充填まで使用できる『PET‐TT21‐100ml』をドレッシングやオイル向けに提案している。ガラス瓶より軽くコスト面削減につながるため大変好評で、200mlタイプも開発中だ」
ー環境負荷低減について。
「色々なアプローチがあって、一つは直接的にプラスチック使用量を減らすこと。植物由来原料や、紙、炭酸カルシウムなどを混成した容器を開発している。外観、強度、価格といった容器の評価基準に環境負荷が加わり、顧客ニーズは多様化している。また生分解性を持たせて焼却の燃料を削減したり海洋汚染を防いだり、とプラスチックのサイクル全体へのアプローチも盛んだ。発想次第で容器はまだまだ進化できるので、食品メーカーの皆様にはぜひお悩みを聞かせてほしい」
「色々なアプローチがあって、一つは直接的にプラスチック使用量を減らすこと。植物由来原料や、紙、炭酸カルシウムなどを混成した容器を開発している。外観、強度、価格といった容器の評価基準に環境負荷が加わり、顧客ニーズは多様化している。また生分解性を持たせて焼却の燃料を削減したり海洋汚染を防いだり、とプラスチックのサイクル全体へのアプローチも盛んだ。発想次第で容器はまだまだ進化できるので、食品メーカーの皆様にはぜひお悩みを聞かせてほしい」
【2023(令和5)年9月21日第5140号9面】
立花容器
9月11日号 トップに聞く
株式会社みやまえ 代表取締役社長 宮前有一郎氏
第3次価格改定も視野に
生姜原料の価格が過去最高へ
株式会社みやまえ(宮前有一郎社長、奈良県生駒郡平群町)は生姜商品の総合メーカーとして全国でトップクラスのシェアを持つ。物価上昇により生姜漬も数度にわたって値上げを実施せざるを得ない前例のない状況下、宮前社長は生姜漬文化の維持へ危機感を示す。価格に頼らない価値の提案へ力を注ぐとともに、漬物の素材利用や、生姜を軸とした商品開発を強化している。
(大阪支社・高澤尚揮)
ー生姜原料の動向について。
「タイ産は今年干ばつの影響で植え付けが5月中旬頃になり、例年より1カ月遅れた。7月から雨が降り出したものの、生鮮生姜の価格は高値のままだ。塩蔵向けは小粒で、過去最高の価格になると見ている。中国福建省の農家は生鮮に目がいき、塩蔵用の主力は雲南省に移ってきた。今年の雲南省は干ばつ気味だったが、栽培面積が一昨年の3倍ほどに拡大していることから、原料の調達までは不安視していない。塩蔵向けの量は、タイ産が年々減ってきた結果、中国南部とそう変わらなくなってきた。山東省産では、ガリといえるほどの柔らかい規格が著しく少なくなっているのが現状だ」
ー業務用生姜製品の販売状況。
「業務用が回復しており、コロナ前の水準に売上は回復しているものの、利益面では厳しい。しかし、中国加工メーカーの製品の質が低いことを理由に、当社製品へ切り替えたいというニーズはある。またここ最近は、中国からのガリ完成品を扱っていたところが、政情不安定による欠品を避けるため、当社など国内加工メーカーに新規問い合わせが相次いでいる。当社では、スポットでの注文でなく、平時から20%はみやまえの生姜製品を利用してもらえるようお願いはしている」
ー価格改定について。
「昨年7月、今年2月と続けて実施した。近いうちに3度目の値上げも覚悟しなければならない。年末または来年の始め頃の実施を検討している段階だ。生姜原料と副資材、電気代等全てが値上がり続け、現在もコスト上昇や円安が進行し続けていることは辛い。これまで築いてきた生姜漬文化を維持していくには、価格以外の『価値』を訴えていく必要がある」
ー生姜漬文化の維持。
「生姜漬は無料提供が当然視されている節があり、値上げをすると、有料での提供となるか、最悪の場合外されてしまう。その場合、需要の減少から流通量が減少し、産地を含む産業としての維持に危機感を覚える。最も危惧しているのは、コスト削減のために低品質な生姜漬へ切り替えられ、生姜漬全体のイメージが悪くなり、消費者の心が離れていくこと。当社としては、味はもちろんのこと、サポート体制などの強みを磨いて差別化を図っていく」
ー新しい取組は。
「添え物としての利用だけでなく、惣菜の素材としての利用を拡大することに注力している。惣菜市場自体が成長産業であるため、まだまだ提案の余地がある。揚げ物や練り物では、多様化が進んでおり、紅生姜の色どりの良さやスパイシーさを求める方が確実にいる。コロナで急増した家飲み需要も落ち着いたものの、いまだに手堅く需要はある」
ー2025年大阪・関西万博への期待。
「既に訪日外国人の来日理由として『食』がトップに挙がっている。万博で訪日観光客が増えることで、日本に美食を求めている方に、本物の和食を知ってもらえるチャンスだ。付随してガリや紅生姜と触れることを期待している。消費者が本物の和食を知って帰国すると、お店の調理方法や料理素材への評価も厳しくなり、健全な競争が生まれるだろう。国内加工メーカー製品の海外需要は大いにポテンシャルがある」
【2023(令和5)年9月11日第5139号5面】
みやまえ
9月11日号 トップに聞く
東京中央漬物株式会社 代表取締役社長 齋藤 正久氏
9月29日にジョイフルフェア
3品目のPB商品をお披露目
東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。9月29日に東京都台東区の東京都立産業貿易センター台東館で開催する『2023 C‐Z ジョイフルフェア』について話を聞いた。例年7月に開催していた展示会の会期を変えることで、秋冬向け商品から年末向け商品の提案が主なテーマとなる。今回の出展社数は昨年を20社以上上回る102社。得意先はもちろん、得意先の二次店、三次店のバイヤーも来場予定で、新規顧客獲得や新しい需要の開拓につながる展示会として大きな期待が寄せられている。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年のジョイフルフェアは9月29日に開催する。
「ジョイフルフェアは毎年7月に開催していたが、秋本食品さんの展示会と時期が重なることもあり、テスト的な意味合いも込めてお盆過ぎに開催しようということで9月に実施する。今回は出展社の新規顧客獲得をテーマに、得意先の二次店、三次店のお客様にも声をかけてお越しいただく。得意先の先の得意先のところで新しい話があるかもしれないので、新しい商談が生まれることを期待している」
‐会場の変化は。
「新しい試みとしてメーカーをカテゴリー別に分けず、あいうえお順に設定した。また、出展社は昨年の80社に対し102社と20社以上増えた。この20社は当社の荷主だが、こちらの要望で初めて出展する企業もある。来場される方はこれまで見る機会がなかった企業や商品に出会うことで、新しい需要が生まれる可能性があると思っている」
3品目のPB商品をお披露目
東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。9月29日に東京都台東区の東京都立産業貿易センター台東館で開催する『2023 C‐Z ジョイフルフェア』について話を聞いた。例年7月に開催していた展示会の会期を変えることで、秋冬向け商品から年末向け商品の提案が主なテーマとなる。今回の出展社数は昨年を20社以上上回る102社。得意先はもちろん、得意先の二次店、三次店のバイヤーも来場予定で、新規顧客獲得や新しい需要の開拓につながる展示会として大きな期待が寄せられている。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年のジョイフルフェアは9月29日に開催する。
「ジョイフルフェアは毎年7月に開催していたが、秋本食品さんの展示会と時期が重なることもあり、テスト的な意味合いも込めてお盆過ぎに開催しようということで9月に実施する。今回は出展社の新規顧客獲得をテーマに、得意先の二次店、三次店のお客様にも声をかけてお越しいただく。得意先の先の得意先のところで新しい話があるかもしれないので、新しい商談が生まれることを期待している」
‐会場の変化は。
「新しい試みとしてメーカーをカテゴリー別に分けず、あいうえお順に設定した。また、出展社は昨年の80社に対し102社と20社以上増えた。この20社は当社の荷主だが、こちらの要望で初めて出展する企業もある。来場される方はこれまで見る機会がなかった企業や商品に出会うことで、新しい需要が生まれる可能性があると思っている」
‐展示会の商品構成は。
「秋冬の商談は終わっているので、年末向けの商品がメーンとなる。得意先の話を聞いても高付加価値の商品を置きたい、というニーズが根強くある。特に年末年始はその志向が強くなるので、全国名産コーナーをなくし、初となる『高付加価値商品コーナー』を作って価値のある商品を提案していきたいと考えている」
‐展示会のテーマは。
「テーマは『激変する社会に対応する食生活』。食生活はコロナの影響で大きく変わり、5類移行後も再び変化している。時代の移り変わりは予想を上回る速さで進んでいる。現在は物価高で節約志向が高まっており、試し買いや衝動買いのような遊びの部分がなくなってきている。商品の生き残りもシビアになってきていて、定番商品でも値上げして動きが悪くなると入れ替わるケースもある。展示会では現在のニーズに即しながら様々な商品を提案する」
‐魅力のある売場とは。
「理想はワクワク感のある売場。見ているだけで楽しくなるような売場を作ることができればお客様の支持を得ることができ、リピートにもつながる。見た目という意味では季節感や新商品も重要だが、売場を総合的にプロデュースできるように提案力を強化していく方針だ。お客様が足を止めて商品を手に取るようなコーナーを作るなど、売場提案を積極的に行っていきたい」
‐価格競争からの脱却について。
「当社は製造していないので、様々なニーズに応じて各社のNB商品を売り込むことが主な業務となるのだが、NB商品だけに頼ると価格競争になる。PBのようなオリジナル商品があると新規の営業も行きやすくなるし、会社の強みにもなる。当社では現在2品のPB商品(フレッシュザーサイ、野沢菜本造り)があるが、昨年から開発している3品目が完成間近で、展示会でお披露目できる予定だ。発売は10月半ば頃で、一部SMで試験販売を実施する。若い世代向けにSNSによる情報発信もスタートしたが、時代のニーズに合わせて様々なことにチャレンジしていきたいと考えている」
「秋冬の商談は終わっているので、年末向けの商品がメーンとなる。得意先の話を聞いても高付加価値の商品を置きたい、というニーズが根強くある。特に年末年始はその志向が強くなるので、全国名産コーナーをなくし、初となる『高付加価値商品コーナー』を作って価値のある商品を提案していきたいと考えている」
‐展示会のテーマは。
「テーマは『激変する社会に対応する食生活』。食生活はコロナの影響で大きく変わり、5類移行後も再び変化している。時代の移り変わりは予想を上回る速さで進んでいる。現在は物価高で節約志向が高まっており、試し買いや衝動買いのような遊びの部分がなくなってきている。商品の生き残りもシビアになってきていて、定番商品でも値上げして動きが悪くなると入れ替わるケースもある。展示会では現在のニーズに即しながら様々な商品を提案する」
‐魅力のある売場とは。
「理想はワクワク感のある売場。見ているだけで楽しくなるような売場を作ることができればお客様の支持を得ることができ、リピートにもつながる。見た目という意味では季節感や新商品も重要だが、売場を総合的にプロデュースできるように提案力を強化していく方針だ。お客様が足を止めて商品を手に取るようなコーナーを作るなど、売場提案を積極的に行っていきたい」
‐価格競争からの脱却について。
「当社は製造していないので、様々なニーズに応じて各社のNB商品を売り込むことが主な業務となるのだが、NB商品だけに頼ると価格競争になる。PBのようなオリジナル商品があると新規の営業も行きやすくなるし、会社の強みにもなる。当社では現在2品のPB商品(フレッシュザーサイ、野沢菜本造り)があるが、昨年から開発している3品目が完成間近で、展示会でお披露目できる予定だ。発売は10月半ば頃で、一部SMで試験販売を実施する。若い世代向けにSNSによる情報発信もスタートしたが、時代のニーズに合わせて様々なことにチャレンジしていきたいと考えている」
【2023(令和5)年9月11日第5139号2面】
東京中央漬物 HP
プロが売りたい! 地域セレクション 特別会員
8月21日号 トップに聞く
株式会社日本東泉 代表取締役社長 李忠儒氏
山東省生姜は価格上昇 産地の強みで安定供給
株式会社日本東泉(大阪市住之江区)の李忠儒社長にインタビュー。同社は中国最大の生姜産地である山東省に、自社工場として現地法人「龍口東寶(ドンパオ)食品有限公司」を有し、生姜の契約栽培から加工までを一貫して行う。原料卸としては生姜、にんにく等の中国農産物を塩蔵、冷凍、漬物完成品などの形態で供給している。今年の山東省産生姜の作柄は良好であるものの、漬物用原料は価格が上昇する見通し。そのような中でも同社は安定供給を果たすべく努めている。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐山東省生姜の状況は。
「漬物用の収穫は8月18日頃から始まり、作柄は良好。作付面積は昨年より2~3割拡大したが、これは昨年が縮小していたので平年並みに戻った形。3月下旬~4月半ばの植え付け時期は干ばつ気味で不作予想も出ていたのだが、その後の天候が良く豊作傾向に転じた。ただし豊作だからといって漬物用原料を十分に確保するのは容易ではなく、価格も上昇する年になると見ている」
‐価格上昇の原因。
「青果用が高騰しているのが大きな要因。生姜の収穫は若掘りのガリ用から始まりハーフ用、刻み用、青果用と続くが、青果が高ければ農家としてはそちらに回したいため、漬物用の量は減ることになる。また青果生姜が高いため種代も高くなっていることに加え、肥料や資材機器等コストが上昇していることも重なって、昨年より高くなるのは確実と見ている。なお現在の青果生姜の高騰は投機目的によるもので、需要と供給のバランスを逸脱している。今年の豊作で、来年は正常化していくと期待している」
‐御社の対応は。
「当社は山東省に自社農場、契約農場で生姜を栽培している。契約栽培では固定価格ではなく、相場下落時は保証ラインで、相場上昇時には相場に連動させて買い取る形を取ることで農家が損をしない仕組みを作っている。今年のように漬物用が少なくなる年でも当社はしっかりと確保し、安定供給に努めていく。コロナが明けて需要も回復しているが、現地青果生姜の価格が上昇しているので確実に供給していくためにも早めの注文をいただけるとありがたい」
‐「ホワイトガリ」が著名。
「当社の中でも最高級品が『ホワイトガリ』。土壌作りから品種改良まで独自開発した方法で栽培した生姜を、極若掘りし、無漂白で伝統の押し漬け方法を守り続けている。ほどよい辛さとシャキシャキとした柔らかな食感が自慢のガリだ。そのホワイトガリ原料は大手メーカー様からも長年利用いただいている」
‐食の安全性追求のため様々な認証を取得している。
「中国農産物というと残留農薬など心配される方も多いが、当社は2003年には肥料・農薬に厳しい制限を定める緑色食品A級を、2007年にはグローバルGAPを取得した。また漬物メーカーとしてもHACCPシステムを導入し、ISO9001、FSSC22000取得の工場で製造を行っている。世界基準の管理で、日本だけでなく世界中へ輸出できる体制となっているので安心していただきたい。生姜以外にもにんにくや唐辛子も扱っている」
‐今年で30回目の漬込みになる。
「私は韓国生まれの台湾華僑だが、近畿大学農学部に入学したことをきっかけに日本の人々や文化と出会えた。そのときの学友の縁から生姜漬の世界を知り、後押しをいただいて起業した。本物の生姜漬の味を追求し、日本のユーザーの厳しい基準に応えられる品質を作り続けてきた。これからも安全安心な生姜原料をお届けしていきたい」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐山東省生姜の状況は。
「漬物用の収穫は8月18日頃から始まり、作柄は良好。作付面積は昨年より2~3割拡大したが、これは昨年が縮小していたので平年並みに戻った形。3月下旬~4月半ばの植え付け時期は干ばつ気味で不作予想も出ていたのだが、その後の天候が良く豊作傾向に転じた。ただし豊作だからといって漬物用原料を十分に確保するのは容易ではなく、価格も上昇する年になると見ている」
‐価格上昇の原因。
「青果用が高騰しているのが大きな要因。生姜の収穫は若掘りのガリ用から始まりハーフ用、刻み用、青果用と続くが、青果が高ければ農家としてはそちらに回したいため、漬物用の量は減ることになる。また青果生姜が高いため種代も高くなっていることに加え、肥料や資材機器等コストが上昇していることも重なって、昨年より高くなるのは確実と見ている。なお現在の青果生姜の高騰は投機目的によるもので、需要と供給のバランスを逸脱している。今年の豊作で、来年は正常化していくと期待している」
‐御社の対応は。
「当社は山東省に自社農場、契約農場で生姜を栽培している。契約栽培では固定価格ではなく、相場下落時は保証ラインで、相場上昇時には相場に連動させて買い取る形を取ることで農家が損をしない仕組みを作っている。今年のように漬物用が少なくなる年でも当社はしっかりと確保し、安定供給に努めていく。コロナが明けて需要も回復しているが、現地青果生姜の価格が上昇しているので確実に供給していくためにも早めの注文をいただけるとありがたい」
‐「ホワイトガリ」が著名。
「当社の中でも最高級品が『ホワイトガリ』。土壌作りから品種改良まで独自開発した方法で栽培した生姜を、極若掘りし、無漂白で伝統の押し漬け方法を守り続けている。ほどよい辛さとシャキシャキとした柔らかな食感が自慢のガリだ。そのホワイトガリ原料は大手メーカー様からも長年利用いただいている」
‐食の安全性追求のため様々な認証を取得している。
「中国農産物というと残留農薬など心配される方も多いが、当社は2003年には肥料・農薬に厳しい制限を定める緑色食品A級を、2007年にはグローバルGAPを取得した。また漬物メーカーとしてもHACCPシステムを導入し、ISO9001、FSSC22000取得の工場で製造を行っている。世界基準の管理で、日本だけでなく世界中へ輸出できる体制となっているので安心していただきたい。生姜以外にもにんにくや唐辛子も扱っている」
‐今年で30回目の漬込みになる。
「私は韓国生まれの台湾華僑だが、近畿大学農学部に入学したことをきっかけに日本の人々や文化と出会えた。そのときの学友の縁から生姜漬の世界を知り、後押しをいただいて起業した。本物の生姜漬の味を追求し、日本のユーザーの厳しい基準に応えられる品質を作り続けてきた。これからも安全安心な生姜原料をお届けしていきたい」
【2023(令和5)年8月21日第5139号3面】
日本東泉 HP http://lisgroup.jp/ja/
8月11日号 トップに聞く
株式会社マルヤナギ小倉屋 代表取締役社長 柳本勇治氏
従業員の健康意識アップへ
食育型カンパニーとして成長
蒸し豆・国産蒸しもち麦・煮豆・佃煮の製造・販売を行う株式会社マルヤナギ小倉屋(柳本勇治社長、神戸市東灘区)では、柳本勇治氏が社長に就任し、1年半が過ぎた。同氏は、日本初の蒸し大豆商品や、国産もち麦商品の開発・販売を主導してきたことで知られる。多くの人に「食と健康に対する関心」をより高めてほしいと語り、社内の意識向上を図っている。柳本社長に各種取組について話しを聞いた。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
-従業員の健康維持・増進に取り組んでいる。
「当社では食を通じて人々の健康に奉仕するためには、社員自らが健康に関心を高めて増進する必要があると考えている。当社では、2018年に『健康経営と食育推進室』を設置し、2020年には初めての『マルヤナギ健康白書』を作成、白書は今年で4回目となる。白書では毎年、前年の結果から今後の取組事項をまとめて公開することで、従業員の健康維持増進を目指している。循環器疾患と糖尿病対策の強化、禁煙および受動喫煙防止対策の強化、従業員の健康意識のアップを大きな柱としている」
-より具体的には。
「循環器疾患と糖尿病は命に関わる病気でありながら、生活習慣病に起因することも多く、ある程度早くから予防することができる。社内セミナーを開催したり個別面談でフォローしたりしてきた。2022年からは、兵庫県立大学と共同研究を行い、健康診断結果と食事調査の結果から、職種等に合わせた従業員指導を行っている。禁煙については、2022年より非喫煙者には『いきいき応援手当』として毎月500円を支給しており、今年4月1日からは喫煙可能時間の設定と営業車の車内禁煙を実施、最終的には敷地内全面禁煙を目指している。従業員の健康意識アップでは、食生活アドバイザーの資格取得フォローを継続しているのと、今年4月1日から社内で自社製品の『蒸し大豆』や『蒸しもち麦』が自由に食べられる『オフィスもち麦・蒸し豆』をスタートさせ、好評だ。生活習慣の改善となった社員の話も聞く」
‐新商品など自社製品について。
「佃煮や煮豆製品が長らく主力であったが、当社がパイオニアである『蒸し豆』『蒸しもち麦』が今や定番化し消費者に支持されている。設備投資や販路開拓を着実に行ってきたことが功を奏している。大豆やもち麦のおいしさを引き続きPRしていきたい。3月に発売した『蒸しひきわり大豆』はひきわりにした大豆を蒸しているため水戻し不要で、かつハンバーグ、ミートソース、キーマカレー等、幅広く使えるので使い勝手が良く、順調な売れ行きだ。長いスパンで見て、認知度が高まり、定着化していきそうだと期待を込めている」
‐もち麦のポテンシャルや地域連携。
「当社で加工するもち麦の健康機能性の研究には、加東市役所の職員の方々にご協力いただき、現在は市内の子どもたちの腸内細菌叢を調査している。加東市との地域連携としては6月に加東市で行われた『かとうもち麦収穫祭』でもち麦商品やもち麦おはぎを販売した。さらに、もち麦の派生製品として、全国の小売店で当社のもち麦うどんやもち麦パスタを取り扱っていただき、新しい顧客を創出できている。もち麦のPR面では、7月に自社で情報サイト『もちむぎ村』をスタートさせた。産地の取組やもち麦を活用したお店の情報などを順次掲載していくのが狙いだ。既存ファンサイト『蒸し大豆タウン』で得た知見を投入している。当社のメインテーマ『伝統食材の素晴らしさを次の世代へ』をまさに体現した試みだ。『新しい食の提案に取り組む食育型カンパニー』として成長するのを応援していただきたい」
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
-従業員の健康維持・増進に取り組んでいる。
「当社では食を通じて人々の健康に奉仕するためには、社員自らが健康に関心を高めて増進する必要があると考えている。当社では、2018年に『健康経営と食育推進室』を設置し、2020年には初めての『マルヤナギ健康白書』を作成、白書は今年で4回目となる。白書では毎年、前年の結果から今後の取組事項をまとめて公開することで、従業員の健康維持増進を目指している。循環器疾患と糖尿病対策の強化、禁煙および受動喫煙防止対策の強化、従業員の健康意識のアップを大きな柱としている」
-より具体的には。
「循環器疾患と糖尿病は命に関わる病気でありながら、生活習慣病に起因することも多く、ある程度早くから予防することができる。社内セミナーを開催したり個別面談でフォローしたりしてきた。2022年からは、兵庫県立大学と共同研究を行い、健康診断結果と食事調査の結果から、職種等に合わせた従業員指導を行っている。禁煙については、2022年より非喫煙者には『いきいき応援手当』として毎月500円を支給しており、今年4月1日からは喫煙可能時間の設定と営業車の車内禁煙を実施、最終的には敷地内全面禁煙を目指している。従業員の健康意識アップでは、食生活アドバイザーの資格取得フォローを継続しているのと、今年4月1日から社内で自社製品の『蒸し大豆』や『蒸しもち麦』が自由に食べられる『オフィスもち麦・蒸し豆』をスタートさせ、好評だ。生活習慣の改善となった社員の話も聞く」
‐新商品など自社製品について。
「佃煮や煮豆製品が長らく主力であったが、当社がパイオニアである『蒸し豆』『蒸しもち麦』が今や定番化し消費者に支持されている。設備投資や販路開拓を着実に行ってきたことが功を奏している。大豆やもち麦のおいしさを引き続きPRしていきたい。3月に発売した『蒸しひきわり大豆』はひきわりにした大豆を蒸しているため水戻し不要で、かつハンバーグ、ミートソース、キーマカレー等、幅広く使えるので使い勝手が良く、順調な売れ行きだ。長いスパンで見て、認知度が高まり、定着化していきそうだと期待を込めている」
‐もち麦のポテンシャルや地域連携。
「当社で加工するもち麦の健康機能性の研究には、加東市役所の職員の方々にご協力いただき、現在は市内の子どもたちの腸内細菌叢を調査している。加東市との地域連携としては6月に加東市で行われた『かとうもち麦収穫祭』でもち麦商品やもち麦おはぎを販売した。さらに、もち麦の派生製品として、全国の小売店で当社のもち麦うどんやもち麦パスタを取り扱っていただき、新しい顧客を創出できている。もち麦のPR面では、7月に自社で情報サイト『もちむぎ村』をスタートさせた。産地の取組やもち麦を活用したお店の情報などを順次掲載していくのが狙いだ。既存ファンサイト『蒸し大豆タウン』で得た知見を投入している。当社のメインテーマ『伝統食材の素晴らしさを次の世代へ』をまさに体現した試みだ。『新しい食の提案に取り組む食育型カンパニー』として成長するのを応援していただきたい」
【2023(令和5)年8月11日第5137号8面】
マルヤナギ小倉屋
8月11日号 理事長に聞く
新潟県漬物工業協同組合 理事長 佐久間大輔氏
組合内でBCPを推進
タイムリーな情報発信
5月の総会で留任した新潟県漬物工業協同組合の佐久間大輔理事長にインタビュー。組合の課題や今後の活動予定などについて話を聞いた。同組合では年間を通して活発な活動を行っているが、会う機会を増やすことで「本音で話し合える」と関係性の強化につながっていると強調。今後もタイムリーな情報発信を行いつつ、BCP(事業継続計画)推進などで組合加盟のメリットを打ち出していく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
―5月の総会で留任となった。
「今回の役員改選で大分若返った。どこの県も組合員の減少や後継者が問題となっているが、新潟は先を見据えて一歩前に進めていると思っている。若い世代も多く、活発に活動を行っている。また、企業規模の大小に関わらず組合員同士の仲が良く、原料を融通する時もしてもらう時もある。売場としては競合になるのだが、組合の中では大事な仲間。これからもその部分は大事にしていきたいと思っている」
ー組合活動について
「今年の年間のスケジュールとしては、5月に総会、8月に外国人技能評価試験、9月に組合講習会、10月~12月は沢庵メーカーが忙しいので活動を休み、2月に流通講演会と新春懇談会を開催する。また、その間に酒の陣などへのイベント出店でPR活動を実施する予定だ」
―年間で多くの活動を実施している。
「他県と比較すると活動の回数はやや多くなっていると思うが、会う機会が増えれば仲良くなるし、本音で話し合える場面も出てくる。当組合では2004年の中越地震後に策定されたBCP(事業継続計画)も推進しており、実際にどこまでできるか分からない部分もあるが、そのような協力体制を整えている」
―組合の課題は。
「組合に新しい人が入ってくることは期待できない。ある組合未加盟企業に組合に入って勉強すればいい、と声をかけていたのだが、その企業は少し前に倒産してしまった。以前は味噌メーカーや醤油メーカーも加盟していたのだが、それぞれの組合での活動に専念するため退会した。現在、組合に加盟している企業は後継者もいることもあり、当面は組合員数が減少することはないと見ている。だが、組合に入っているメリットがなければ減少の流れを止めることはできない。最近ではHACCPやインボイス制度に関する勉強会を行うなど、タイムリーな情報を発信している。今後もそのような視点で活動していきたい」
―新潟の魅力は。
「山海漬、沢庵漬、味噌漬、にんにく漬、茄子漬など、海の幸と山の幸を活かした幅広い漬物及び加工食品を製造、販売し、特徴のある企業が多い。各企業の商品は品質が高く、味も良い。全国的に支持されている商品も多い」
―昨秋の大根が不作だった。
「昨秋は大根の作柄が悪かったので、春作を実施した。農家は春作に乗り気ではなかったが、企業の方で収穫を行うので種を蒔いてもらった。企業によっては欠品、出荷調整を行っていたが、原料の不足感は解消された。農家は毎年減ってきており、作付面積も減ってきている。そのような中、組合の部会では大根の優良品種の選定を行い、品質の向上を目指している。組合で協力し、農家の減少を技術でカバーする、という取組を10年以上に亘って行っている」
―今後の取組について。
「小学校への出前講座など、若い世代にどのようにアプローチしていくか、ということが重要だ。子供の時に漬物を食べていなければ、大人になってから食べることもないだろう。そのような意味でも酒の陣や食の陣に出店し、試食販売を通して漬物のPRを継続的に行っていきたい」
【2023(令和5)年8月11日第5137号14面】
8月1日号 新理事長に聞く
鹿児島県漬物商工業協同組合 理事長 堂園春樹氏
世代交代表す役員人事
組合員のためになる事業を
鹿児島県漬物商工業協同組合では、本年5月26日の通常総会で役員改選が行われ、中園雅治理事長に代わって堂園春樹氏(上園食品常務取締役)が新理事長に就任。また、新専務理事には水溜光一氏(水溜食品代表取締役社長)が就任した。堂園新理事長は昭和56年6月7日生まれの42歳、水溜新専務理事は昭和61年5月10日生まれの37歳と、まさに世代交代を絵に描いたような役員人事で新たなスタートを切った。新理事長に就任した堂園氏に現在の鹿児島県漬物業界の動向や、今後の事業展開について話を聞いた。
組合員のためになる事業を
鹿児島県漬物商工業協同組合では、本年5月26日の通常総会で役員改選が行われ、中園雅治理事長に代わって堂園春樹氏(上園食品常務取締役)が新理事長に就任。また、新専務理事には水溜光一氏(水溜食品代表取締役社長)が就任した。堂園新理事長は昭和56年6月7日生まれの42歳、水溜新専務理事は昭和61年5月10日生まれの37歳と、まさに世代交代を絵に描いたような役員人事で新たなスタートを切った。新理事長に就任した堂園氏に現在の鹿児島県漬物業界の動向や、今後の事業展開について話を聞いた。
(菰田隆行)
◇ ◇
―新理事長に就任した現在の心境は。
「中園前理事長が、全日本漬物協同組合連合会(全漬連)会長に就任された。そのタイミングで、鹿児島でもちょうど新しい体制に変革を求められている時期だったこともあり、中園前理事長から『ぜひ、やってほしい』と要請を受けたので、お引き受けすることになった。また併せて組合の定款を変更し、青年部長が親会の理事に就任する規定を設けた。そこで青年部長の水溜光一氏には、専務理事を引き受けていただくことになった。中園前理事長のご英断で若返りの人選となったが、これまでの理事の皆様にも残っていただいているので、その点は非常に心強く思っている。諸先輩方のご意見も尊重しながら、今年一年で流れを引き継ぎ、事業を進めていきたいと思っている」
―現在の業界の課題は。
「やはり人手不足と原料対策。人員の確保については、鹿児島でも外国人実習生の受け入れ数が数年前から増加し、ある会員企業さんは約30名を受け入れている。ただし、外国人実習生制度の見直しも検討されているようで、今後どうなるかは不透明な部分だと言える。原料対策の面では、天候との闘いが顕在化してきていて、手の打ちようがない部分もある。九州は、台風が来る時期と沢庵用大根の作付時期が重なるため、台風の襲来で大きな打撃を受けることが多い。それが、以前と比べると台風が九州を通過するルートが変わってきていて、九州全体が被害を受けてしまうことが増えてきた。例えば鹿児島は被害を受けたが宮崎は大丈夫だった、ということであれば融通も利くが、全体が被害を受けると絶対量が足りなくなってくる」
―農家の現状は。
「農家の高齢化は、日本の農業全体で深刻化しているものの、当社の契約農家では息子が就職先からリターンして農業を継いでいるところもあり、いい流れもある。ただ、例えば大根の栽培については冷凍の大根おろし用の需要が増えていて、沢庵用よりも単価が良いのでそちらに切り替えた、といった話も聞くし、焼酎用の芋は収入が上がるので農家にとっては魅力がある。沢庵用大根の買取価格は各社がそれぞれ上げているが、販売価格との兼ね合いもあり、農家にとって魅力のある作物にできるかどうかはなかなか難しい」
―今後の組合事業については。
「行政関係や全漬連事業の情報については、メール配信網が整備されているので、しっかりと発信していく。また、当県独自の取組である『かごしま漬物大使』は“なりたい”という方もおられ、今年14名から15名に増えた。こうした取組も継続しながら、組合員のためになる事業を進めて行きたい」
【2023(令和5)年8月1日第5136号11面】
◇ ◇
―新理事長に就任した現在の心境は。
「中園前理事長が、全日本漬物協同組合連合会(全漬連)会長に就任された。そのタイミングで、鹿児島でもちょうど新しい体制に変革を求められている時期だったこともあり、中園前理事長から『ぜひ、やってほしい』と要請を受けたので、お引き受けすることになった。また併せて組合の定款を変更し、青年部長が親会の理事に就任する規定を設けた。そこで青年部長の水溜光一氏には、専務理事を引き受けていただくことになった。中園前理事長のご英断で若返りの人選となったが、これまでの理事の皆様にも残っていただいているので、その点は非常に心強く思っている。諸先輩方のご意見も尊重しながら、今年一年で流れを引き継ぎ、事業を進めていきたいと思っている」
―現在の業界の課題は。
「やはり人手不足と原料対策。人員の確保については、鹿児島でも外国人実習生の受け入れ数が数年前から増加し、ある会員企業さんは約30名を受け入れている。ただし、外国人実習生制度の見直しも検討されているようで、今後どうなるかは不透明な部分だと言える。原料対策の面では、天候との闘いが顕在化してきていて、手の打ちようがない部分もある。九州は、台風が来る時期と沢庵用大根の作付時期が重なるため、台風の襲来で大きな打撃を受けることが多い。それが、以前と比べると台風が九州を通過するルートが変わってきていて、九州全体が被害を受けてしまうことが増えてきた。例えば鹿児島は被害を受けたが宮崎は大丈夫だった、ということであれば融通も利くが、全体が被害を受けると絶対量が足りなくなってくる」
―農家の現状は。
「農家の高齢化は、日本の農業全体で深刻化しているものの、当社の契約農家では息子が就職先からリターンして農業を継いでいるところもあり、いい流れもある。ただ、例えば大根の栽培については冷凍の大根おろし用の需要が増えていて、沢庵用よりも単価が良いのでそちらに切り替えた、といった話も聞くし、焼酎用の芋は収入が上がるので農家にとっては魅力がある。沢庵用大根の買取価格は各社がそれぞれ上げているが、販売価格との兼ね合いもあり、農家にとって魅力のある作物にできるかどうかはなかなか難しい」
―今後の組合事業については。
「行政関係や全漬連事業の情報については、メール配信網が整備されているので、しっかりと発信していく。また、当県独自の取組である『かごしま漬物大使』は“なりたい”という方もおられ、今年14名から15名に増えた。こうした取組も継続しながら、組合員のためになる事業を進めて行きたい」
【2023(令和5)年8月1日第5136号11面】
佐賀県漬物工業協同組合 理事長 広瀬忠伸氏
海産物と陸産物の両輪
コラボギフト等で連携も
佐賀県漬物工業協同組合では、本年5月19日に開催した第60回通常総会で川原啓秀理事長に代わって、専務理事の広瀬忠伸氏が新理事長に就任した。広瀬氏は、佐賀県の伝統野菜“相知高菜”を復活させた企業の1社である広瀬仙吉商店(佐賀県唐津市)の代表で、「伝統食品相知高菜漬け推進協賛会」の会長も務めている。「漬物の消費拡大に寄与したい」と語る広瀬新理事長に、現在の業界動向、今後の抱負などについて話を聞いた。
(菰田隆行)
◇ ◇
―理事長に就任の心境は。
「佐賀県の漬物には鯨の軟骨や貝柱、海茸ほかの海産物粕漬等と、高菜漬や梅干し、柚子こしょうなど陸産物を加工した商品がある。これは言ってみれば我が県漬物業界の“両輪”だ。分断されているのではなく、土俵が別々なのでお互いが切磋琢磨して事業を行えている。また、『土俵が違うから』とお互いを排除したり、仲違いすることもない。これは、歴代理事長の時代からの伝統で、それを連綿と築いてこられた歴史がある。これは他県ではあまり見られない、佐賀県独特の伝統だと思う。大企業が有るわけではなく、こじんまりとした企業がまとまっていて、皆さんと仲良くさせていただいている」
―県の支援も手厚い。
「おっしゃる通りで、佐賀県中小企業団体中央会様には、総会の資料なども作成して頂いており、主要産業として認めていただいているのは、とてもありがたく思っている」
―現在の佐賀県内の業界動向は。
「コロナ禍であったこの3年半の間は、お土産や贈答用が主体である海産物漬物の落ち込みが大きく、痛手となった。コロナが第5類に引き下げられ、人の流れも徐々に回復してきたので、今後に期待したい。一方、陸産物の漬物に関しては天候不順によって高菜など不作が続いている。原料の確保が一番の課題だ」
―需要回復の施策は。
「海産物の漬物メーカー各社が、それぞれ自社の商品を持ち寄り、ギフトセットの販売を企画している。例えば将来的に、それに陸産物を組み合わせたコラボギフトを企画してみても面白いのではないか。また、我が社で製造している“相知高菜”が今年、文化庁が制定した『100年フード』に認定された。こういった追い風も活かし、PRしていければと考えている」
―今後の抱負を。
「昨年までは新型コロナウイルスの影響で、わが県が担当して行う予定だった九州漬物協会の80周年記念式典が2年続けて延期となり、ようやく昨年6月に開催できた。まさにコロナに振り回された3年間だった。この間は、毎年恒例で行っていた“漬物の日”の販売イベントも中止せざるを得なかったので、今年から来年にかけてそれらを復活させ、PR事業に力を入れたいと思っている」
【2023(令和5)年8月1日第5136号12面】
8月1日号 <霞ヶ浦北浦特集> 組合長に聞く
霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合 代表理事組合長 戸田 廣氏
従来のやり方変える勇気を
霞ヶ浦“帆引き船”にブランド力
茨城県の霞ヶ浦、北浦では今年も7月21日にワカサギ漁が解禁を迎えた。近年の不漁の流れは変わることなく、今年もワカサギの漁獲量はここまで低調に推移している。地元でワカサギがとれない厳しい環境が続く中、霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、加工業者が今までの意識を変え、付加価値を付けた製品販売にシフトしていく必要性を指摘した。
(藤井大碁)
―ワカサギ漁が解禁となった。
「温暖化の影響によりワカサギがとれない。水温28度がワカサギの生きられる限界とされており、近年は水温が30~31度あるため、ワカサギが孵化しても生きることができない。辛うじてとれているのは、水深5~6メートルの水深の深いところだけだ。川エビも近年不漁が続いている。アメリカナマズの繁殖により、捕食されている。アメリカナマズを駆除しない限りは川エビも当分の間は回復が難しい。そうなると、霞ヶ浦でとれるのはシラウオだけとなり、貴重な資源は取り合いになってしまう。漁業者、加工業者共に大変な状況になっており、このままでは原料がとれないため、休業状態となる組合員が増えてしまう」
―不漁が続く中で打開策はあるか。
「県でも様々な不漁対策や支援策を打ち出してくれているが、加工業者自らがこれまでのやり方を変える勇気を持つことが必要だ。弊社では、30年前から量販店との取引を開始し、直営店を展開、数年前にはネットショップを開設するなど時代に応じて新しい取組を行ってきた。また、原料確保が難しくなることを鑑み、他の産地から原料を手当てするルートも築いてきた。厳しい中にも道はあるはずだ」
―漁業者の減少も続く。
「漁業者の後継者をどう育てるかという会議を県の関係者らと共に数年前から行っている。後継者を増やすためには、後継者になりたいと思う漁業形態にしていくことが必要だ。漁期である半年間で1000万円~1500万円くらいの収入があれは脱サラしてやろうという人もでてくるだろう。それをどう実現していくかが課題だ。例えば、現在キロ500円で販売している魚を1000円にする。ここまで漁獲量が下がってしまった現在は、漁業者、加工業者にとって生きるか死ぬかの瀬戸際だ。覚悟を決めて、そうした価値観を持って取り組んでいくしかない。それを実現するために、帆引き船でシラウオをとるというアイデアがある。生きたままの新鮮なシラウオを帆引き船でとり、加工漁業が高値で買い、ストーリーを付けて販売する。夢みたいな事と言う人もいるかもしれないが、かつては実際に帆引き船で漁を行っていた。そのくらい柔軟な発想で物事を考えなければ、この環境でやっていくことはできないと考えている」
―消費者ニーズの変化も著しい。
「コロナ禍の影響もあり、食生活が変化し、高齢者が買物に行かなくなった。そのため、高齢者が好むワカサギを始めとした姿物が売れなくなった。子育て世代の母親は子どもたちが喜ぶご飯のお供を探しており、弊社では姿物の佃煮から小魚を主体としたふりかけに商品展開を切り替えていった。最初は小売側から商品価値がないなど、厳しい言葉ももらったが、売場に置くと良く売れ、今では人気商品として定着し、姿物の売上減少分をカバーしている。直営店があったため、消費者の生の声を聞くことができ、ニーズの変化に素早く対応することができた」
―付加価値を付けた商品。
「近年、霞ヶ浦の帆引き船は、サントリー地域文化賞を受賞するなどブランド力が高まっている。弊社では現在、帆引き船の名称を冠した“海老せん”を商標登録をとり販売しているが、この帆引き船ブランドを拡大しシリーズ化していく予定だ。付加価値をつけた商品展開に力を入れる」
―霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。
「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞した。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂けたことに感動している。8月中旬には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンする予定で準備を進めている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」
【2023(令和5)年8月1日第5136号14面】
茨城県の霞ヶ浦、北浦では今年も7月21日にワカサギ漁が解禁を迎えた。近年の不漁の流れは変わることなく、今年もワカサギの漁獲量はここまで低調に推移している。地元でワカサギがとれない厳しい環境が続く中、霞ヶ浦北浦水産加工業協同組合の戸田廣代表理事組合長は、加工業者が今までの意識を変え、付加価値を付けた製品販売にシフトしていく必要性を指摘した。
(藤井大碁)
―ワカサギ漁が解禁となった。
「温暖化の影響によりワカサギがとれない。水温28度がワカサギの生きられる限界とされており、近年は水温が30~31度あるため、ワカサギが孵化しても生きることができない。辛うじてとれているのは、水深5~6メートルの水深の深いところだけだ。川エビも近年不漁が続いている。アメリカナマズの繁殖により、捕食されている。アメリカナマズを駆除しない限りは川エビも当分の間は回復が難しい。そうなると、霞ヶ浦でとれるのはシラウオだけとなり、貴重な資源は取り合いになってしまう。漁業者、加工業者共に大変な状況になっており、このままでは原料がとれないため、休業状態となる組合員が増えてしまう」
―不漁が続く中で打開策はあるか。
「県でも様々な不漁対策や支援策を打ち出してくれているが、加工業者自らがこれまでのやり方を変える勇気を持つことが必要だ。弊社では、30年前から量販店との取引を開始し、直営店を展開、数年前にはネットショップを開設するなど時代に応じて新しい取組を行ってきた。また、原料確保が難しくなることを鑑み、他の産地から原料を手当てするルートも築いてきた。厳しい中にも道はあるはずだ」
―漁業者の減少も続く。
「漁業者の後継者をどう育てるかという会議を県の関係者らと共に数年前から行っている。後継者を増やすためには、後継者になりたいと思う漁業形態にしていくことが必要だ。漁期である半年間で1000万円~1500万円くらいの収入があれは脱サラしてやろうという人もでてくるだろう。それをどう実現していくかが課題だ。例えば、現在キロ500円で販売している魚を1000円にする。ここまで漁獲量が下がってしまった現在は、漁業者、加工業者にとって生きるか死ぬかの瀬戸際だ。覚悟を決めて、そうした価値観を持って取り組んでいくしかない。それを実現するために、帆引き船でシラウオをとるというアイデアがある。生きたままの新鮮なシラウオを帆引き船でとり、加工漁業が高値で買い、ストーリーを付けて販売する。夢みたいな事と言う人もいるかもしれないが、かつては実際に帆引き船で漁を行っていた。そのくらい柔軟な発想で物事を考えなければ、この環境でやっていくことはできないと考えている」
―消費者ニーズの変化も著しい。
「コロナ禍の影響もあり、食生活が変化し、高齢者が買物に行かなくなった。そのため、高齢者が好むワカサギを始めとした姿物が売れなくなった。子育て世代の母親は子どもたちが喜ぶご飯のお供を探しており、弊社では姿物の佃煮から小魚を主体としたふりかけに商品展開を切り替えていった。最初は小売側から商品価値がないなど、厳しい言葉ももらったが、売場に置くと良く売れ、今では人気商品として定着し、姿物の売上減少分をカバーしている。直営店があったため、消費者の生の声を聞くことができ、ニーズの変化に素早く対応することができた」
―付加価値を付けた商品。
「近年、霞ヶ浦の帆引き船は、サントリー地域文化賞を受賞するなどブランド力が高まっている。弊社では現在、帆引き船の名称を冠した“海老せん”を商標登録をとり販売しているが、この帆引き船ブランドを拡大しシリーズ化していく予定だ。付加価値をつけた商品展開に力を入れる」
―霞ヶ浦の帆引き船に注目が集まっている。
「2021年に『霞ヶ浦の帆引き船・帆引き網漁法の保存活動』が、サントリー地域文化賞を受賞した。保存会の代表者として贈呈式に出席したが、感無量の思いだった。24年前に帆引き船が記憶から消えてしまうという危機感を憶え、個人的な活動として保存会を育ててきたのが始まりで、このような賞を頂けたことに感動している。8月中旬には、2001年から開催している『霞ヶ浦帆引き船フォトコンテスト』の作品を一般公開するギャラリーを土浦ピアタウン内にオープンする予定で準備を進めている。100年後に今以上の帆引き船が残せるよう活動を続けていきたい」
【2023(令和5)年8月1日第5136号14面】
7月21日号 塩特集
株式会社天塩 代表取締役社長 鈴木恵氏
7月11日に創業50周年
“地産地消”訴求しブランド化
株式会社天塩(鈴木恵社長、東京都新宿区)は、江戸時代から続くにがりを含ませた塩づくり“差塩製法”を継承した「塩づくり」にこだわり、日本の伝統食文化の良さを未来に繋げている。同社は赤穂化成株式会社が製造する「赤穂の天塩」および関連商品の販売会社である。「赤穂の塩づくり」は文化庁より日本遺産に認定され、その歴史的な価値が証明されている。同社では、今年7月11日に創立50周年を迎えた。2026年には赤穂で塩田が開墾されてから400年のメモリアルイヤーが控えており、今年から4年間をかけ、“赤穂の塩作り”の啓蒙を行っていく。同社代表取締役社長の鈴木恵氏に塩の動向や50周年の取組について聞いた。(藤井大碁)
‐塩の動き。
「6月については、7月からの値上げを前にした駆け込み需要と、梅の需要期が重なったこともあり好調に推移した。今年は梅が豊作で、価格が安かったこともあり、梅が店頭に並び始めてから、それと連動するかたちで塩の動きが良くなっている。暑い夏が予想されているので、さらに塩の需要が伸ばせるよう積極的な販促活動を展開していく」
‐値上げの状況。
「輸入する天日塩が大幅に上昇し電気代などの燃料代の高騰も影響が大きいため、7月より2019年以来となる値上げを実施した。塩業界だけの値上げではないので、影響は一部だと考えているが、今後の動向を注視していく」
‐業務用の引き合いが増えている。
「赤穂の天塩を使用することにより自社商品の味わいが変わる、という認識が広がっている。単に焼塩でも、にがりの量のバランスによって、食品に与える特性が大きく変わる。企業の研究が進み、こうした特性を理解して赤穂の天塩を使用してもらえるケースが増えている」
‐塩の購入単価が上がっている。
「塩は一世帯あたりの購入数量は減っているが、購入単価は上がっている。健康への意識や美味しさといったこだわりから付加価値の高い塩を選ぶ人が増えていると思う。マーケティングに力を入れることにより、こうした需要を的確に捉え、消費者に支持される商品を開発していく。地方では一世帯当たりの消費量は、都会の数倍の需要がまだある。販売エリアにおける特徴を考慮しながら、メリハリのある、販売施策を実施して売り上げを維持したいと考えている」
‐塩にも地域ごとの特性がある。
「塩はその土地の海水や製法などの違いで、それぞれがオリジナルな特徴を持っている。原料でも海水には産地表示がある。単に海水は日本全国どこでも同じという訳ではない。その部分をもっと消費者にアピールすることでブランドの成長に繋げたい」
‐食育教室やイベント開催を積極的に実施している。
「昨年から塩づくり体験の企画をいろいろな場面で開催している。消費者の方に“塩とは?”をもっと知っていただきたい。人が生きるためには、絶対に必要なのは分かっているのだが、それがどのように作られ、何が大切かを知っていただくことで、単に減塩という風潮が進んでいる状況に歯止めをかけたい。戦略として地道な地上戦ではあるが、塩づくりに参加して、“よかった”のお声を頂く機会は多く、もっと多くの方々に参加してもらえるよう継続していきたい」
‐50周年を迎えて。
「私自身が塩の街・赤穂で生まれ、幼少の頃から塩田の風景を見て育ってきた。塩の街に生まれ、塩の会社にいる身であり、自分の人生の役割は塩の訴求をしていくことだと理解している。これからは今までと矛先を変えて、塩の価値や魅力を世の中に発信していく。地産地消のイメージを訴求し、フランスの“ゲランド”に負けないくらいのブランドに“赤穂の天塩”を育てていきたい。そのために大切なのは美味しさと、情熱を持って伝えられる語り部の存在であり、そうした取組にも力を入れる。赤穂の塩作りの歴史400年、天塩50周年を機に、塩の可能性を信じて、その価値を改めて発信していく」
【2023(令和5)年7月21日第5135号10面】
天塩
“地産地消”訴求しブランド化
株式会社天塩(鈴木恵社長、東京都新宿区)は、江戸時代から続くにがりを含ませた塩づくり“差塩製法”を継承した「塩づくり」にこだわり、日本の伝統食文化の良さを未来に繋げている。同社は赤穂化成株式会社が製造する「赤穂の天塩」および関連商品の販売会社である。「赤穂の塩づくり」は文化庁より日本遺産に認定され、その歴史的な価値が証明されている。同社では、今年7月11日に創立50周年を迎えた。2026年には赤穂で塩田が開墾されてから400年のメモリアルイヤーが控えており、今年から4年間をかけ、“赤穂の塩作り”の啓蒙を行っていく。同社代表取締役社長の鈴木恵氏に塩の動向や50周年の取組について聞いた。(藤井大碁)
‐塩の動き。
「6月については、7月からの値上げを前にした駆け込み需要と、梅の需要期が重なったこともあり好調に推移した。今年は梅が豊作で、価格が安かったこともあり、梅が店頭に並び始めてから、それと連動するかたちで塩の動きが良くなっている。暑い夏が予想されているので、さらに塩の需要が伸ばせるよう積極的な販促活動を展開していく」
‐値上げの状況。
「輸入する天日塩が大幅に上昇し電気代などの燃料代の高騰も影響が大きいため、7月より2019年以来となる値上げを実施した。塩業界だけの値上げではないので、影響は一部だと考えているが、今後の動向を注視していく」
‐業務用の引き合いが増えている。
「赤穂の天塩を使用することにより自社商品の味わいが変わる、という認識が広がっている。単に焼塩でも、にがりの量のバランスによって、食品に与える特性が大きく変わる。企業の研究が進み、こうした特性を理解して赤穂の天塩を使用してもらえるケースが増えている」
‐塩の購入単価が上がっている。
「塩は一世帯あたりの購入数量は減っているが、購入単価は上がっている。健康への意識や美味しさといったこだわりから付加価値の高い塩を選ぶ人が増えていると思う。マーケティングに力を入れることにより、こうした需要を的確に捉え、消費者に支持される商品を開発していく。地方では一世帯当たりの消費量は、都会の数倍の需要がまだある。販売エリアにおける特徴を考慮しながら、メリハリのある、販売施策を実施して売り上げを維持したいと考えている」
‐塩にも地域ごとの特性がある。
「塩はその土地の海水や製法などの違いで、それぞれがオリジナルな特徴を持っている。原料でも海水には産地表示がある。単に海水は日本全国どこでも同じという訳ではない。その部分をもっと消費者にアピールすることでブランドの成長に繋げたい」
‐食育教室やイベント開催を積極的に実施している。
「昨年から塩づくり体験の企画をいろいろな場面で開催している。消費者の方に“塩とは?”をもっと知っていただきたい。人が生きるためには、絶対に必要なのは分かっているのだが、それがどのように作られ、何が大切かを知っていただくことで、単に減塩という風潮が進んでいる状況に歯止めをかけたい。戦略として地道な地上戦ではあるが、塩づくりに参加して、“よかった”のお声を頂く機会は多く、もっと多くの方々に参加してもらえるよう継続していきたい」
‐50周年を迎えて。
「私自身が塩の街・赤穂で生まれ、幼少の頃から塩田の風景を見て育ってきた。塩の街に生まれ、塩の会社にいる身であり、自分の人生の役割は塩の訴求をしていくことだと理解している。これからは今までと矛先を変えて、塩の価値や魅力を世の中に発信していく。地産地消のイメージを訴求し、フランスの“ゲランド”に負けないくらいのブランドに“赤穂の天塩”を育てていきたい。そのために大切なのは美味しさと、情熱を持って伝えられる語り部の存在であり、そうした取組にも力を入れる。赤穂の塩作りの歴史400年、天塩50周年を機に、塩の可能性を信じて、その価値を改めて発信していく」
【2023(令和5)年7月21日第5135号10面】
天塩
伯方塩業株式会社 代表取締役社長 石丸一三氏
改定後価格定着へ販促策
日経POS1位は人材の力で
「伯方の塩」で著名な伯方塩業株式会社(愛媛県松山市)の石丸一三社長へインタビュー。同社はこの7月から4年ぶりの価格改定を実施。消費者の節約意識が高まっていることから、創業50周年キャンペーンや、得意先と協力して改定後価格を定着させるような取組を強化していく。石丸社長は、その成否を分ける重要な要素は人材の力であると強調する。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐価格改定の進捗は。
「4月から案内を開始し、7月1日出荷分から改定後価格となった。市販用商品は希望小売価格に対して6~11%、業務用商品は出荷価格に対して2~10%の改定率とした。業務筋においてはほぼ全て、改定後も継続してお取引いただけそうだ。市販用についても同様に得意先からはご理解いただけているのだが、心配なのは消費者個人の節約意識。塩は売場を見て買う商品を決める浮動層が多いため販促策が必要だと考えている」
‐販促策について。
「現在は50周年企画として『ご縁を結ぶプレゼントキャンペーン』を実施している。間もなく、多くの方に注目いただけるような企画も発表できるので楽しみに待っていただきたい。また各チェーン別での対応となるが、ポイント増量セールへ協賛し改定後価格を定着させていくことも計画している。日経POSセレクションの食塩カテゴリで『伯方の塩1㎏』は4年連続1位を受賞しているので、維持できるよう努力が必要だ」
‐2019年の価格改定が、1位に躍り出た契機だった。
「今年ほどの規模ではないが、2019年は当社を含め複数の塩メーカーが価格改定をした年だった。その際に様々な施策へ社員が全力で取り組んだことが功を奏した。1位になったことで売場が広がるという好循環も生まれた。塩は商品の流動性が低いため、人材の力やブランドに左右される部分は大きい。中長期計画でも、人材育成や組織改革、ブランド育成へ重点的に取り組んでいる」
‐中長期計画について。
「2019年に立てた10年ビジョンの最大の核は『社員が自らの仕事に誇りを持ちイキイキと働ける会社を目指そう』ということ。このビジョンに向かって取組を進める過程や結果を通して、顧客サービスの向上や地域社会への貢献を達成し、周囲からの評判が上がり、自然と伯方塩業というブランドが認知されることを目指している」
【2023(令和5)年7月21日第5135号11面】
日経POS1位は人材の力で
「伯方の塩」で著名な伯方塩業株式会社(愛媛県松山市)の石丸一三社長へインタビュー。同社はこの7月から4年ぶりの価格改定を実施。消費者の節約意識が高まっていることから、創業50周年キャンペーンや、得意先と協力して改定後価格を定着させるような取組を強化していく。石丸社長は、その成否を分ける重要な要素は人材の力であると強調する。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐価格改定の進捗は。
「4月から案内を開始し、7月1日出荷分から改定後価格となった。市販用商品は希望小売価格に対して6~11%、業務用商品は出荷価格に対して2~10%の改定率とした。業務筋においてはほぼ全て、改定後も継続してお取引いただけそうだ。市販用についても同様に得意先からはご理解いただけているのだが、心配なのは消費者個人の節約意識。塩は売場を見て買う商品を決める浮動層が多いため販促策が必要だと考えている」
‐販促策について。
「現在は50周年企画として『ご縁を結ぶプレゼントキャンペーン』を実施している。間もなく、多くの方に注目いただけるような企画も発表できるので楽しみに待っていただきたい。また各チェーン別での対応となるが、ポイント増量セールへ協賛し改定後価格を定着させていくことも計画している。日経POSセレクションの食塩カテゴリで『伯方の塩1㎏』は4年連続1位を受賞しているので、維持できるよう努力が必要だ」
‐2019年の価格改定が、1位に躍り出た契機だった。
「今年ほどの規模ではないが、2019年は当社を含め複数の塩メーカーが価格改定をした年だった。その際に様々な施策へ社員が全力で取り組んだことが功を奏した。1位になったことで売場が広がるという好循環も生まれた。塩は商品の流動性が低いため、人材の力やブランドに左右される部分は大きい。中長期計画でも、人材育成や組織改革、ブランド育成へ重点的に取り組んでいる」
‐中長期計画について。
「2019年に立てた10年ビジョンの最大の核は『社員が自らの仕事に誇りを持ちイキイキと働ける会社を目指そう』ということ。このビジョンに向かって取組を進める過程や結果を通して、顧客サービスの向上や地域社会への貢献を達成し、周囲からの評判が上がり、自然と伯方塩業というブランドが認知されることを目指している」
【2023(令和5)年7月21日第5135号11面】
伯方塩業
ナイカイ塩業株式会社 代表取締役社長 野﨑泰彦氏
世界一の安全安心を守る
脱炭素へ海外・他業種を研究
ナイカイ塩業株式会社(野﨑泰彦社長、岡山県倉敷市)は1829年創業の国内製塩大手。年間18万トンの生産能力を有し、業務筋へ供給。グループ企業の日本家庭用塩株式会社(岡山県玉野市)は「瀬戸のほんじお®」の製造元として著名だ。野﨑社長は1991年に社長へ就任して以来、塩業界の変動とともに歩んできた。現在は一般社団法人日本塩工業会代表理事も務め、日本の塩の安全性発信やカーボンニュートラルへの対応にも取り組む。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐これまでの振り返りを。
「社長に就任した1991年は塩の専売制度廃止の議論只中にあった。97年には実際に廃止されることとなり他社や海外塩との競争が始まった。その後も減塩化の風潮が強まり、2010年頃から人口減少に転じるようになり、塩の総需要は右肩下がりに減っていった。そして現在は石炭価格を始めとした諸コストの急騰と、常に課題と向き合う32年間だった」
‐市場競争への対応。
「塩の専売廃止から現在に至るまで第一に優先したのが安全安心な塩を届けること。塩は腐ることはなくとも、汚染物質や異物の混入等のリスクは存在する。塩工業会では、イオン交換膜を通して製塩する日本の塩は『世界一安全安心な塩』を標榜しているが、当社はその中でも設備刷新や管理レベル向上を図ってきた。これまでに品質マネジメントシステムのISO9001、環境マネジメントシステムのISO14001、さらに昨年には食品安全マネジメントシステムのFSSC22000認証を取得し、実態のある安全を追求してきた」
‐塩の総需要減少について。
「塩は流行り廃りのあるものでなく、人口減少とともに今後も減少していく。しかし塩は人間にとって欠かすことのできないものであり製品寿命が尽きることもない。長期的視点に立って、品質改善や生産性の向上といった基本に忠実であり続けることが大切。当社は塩田時代の1829年から続く製塩企業として、塩業歴史館の公開、工場見学の受入など塩の価値を伝えることにも取り組んでいく」
‐昨年2度の価格改定を実施した。
「製塩には、莫大なエネルギーがかかる。イオン交換膜でかん水を作った後は水分を蒸発させる必要があり、当社の場合、製品原価の最大費目は石炭代だ。さらに物流費や包装資材などの価格上昇が厳しく、昨年度は社長就任以来初めて赤字転落となったように、価格改定なしでは事業継続が困難だった。この事情をほぼ全てのお客様からご理解いただき、心から感謝している」
‐日本塩工業会の活動は。
「世界一の安全と品質を守るため、厳格な自主規格の制定と定期的な検査に取り組んできた。また現在、最大の課題となっているのがカーボンニュートラルへの対応。ボイラーの入れ替えやメガソーラー設置、共同物流によるCO2排出量の削減策に加えて、CO2の回収・貯留技術の模索や植林による吸収まで検討している。国外や他業種にも知恵を求め研究しているところだ」
【2023(令和5)年7月21日第5135号12面】
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐これまでの振り返りを。
「社長に就任した1991年は塩の専売制度廃止の議論只中にあった。97年には実際に廃止されることとなり他社や海外塩との競争が始まった。その後も減塩化の風潮が強まり、2010年頃から人口減少に転じるようになり、塩の総需要は右肩下がりに減っていった。そして現在は石炭価格を始めとした諸コストの急騰と、常に課題と向き合う32年間だった」
‐市場競争への対応。
「塩の専売廃止から現在に至るまで第一に優先したのが安全安心な塩を届けること。塩は腐ることはなくとも、汚染物質や異物の混入等のリスクは存在する。塩工業会では、イオン交換膜を通して製塩する日本の塩は『世界一安全安心な塩』を標榜しているが、当社はその中でも設備刷新や管理レベル向上を図ってきた。これまでに品質マネジメントシステムのISO9001、環境マネジメントシステムのISO14001、さらに昨年には食品安全マネジメントシステムのFSSC22000認証を取得し、実態のある安全を追求してきた」
‐塩の総需要減少について。
「塩は流行り廃りのあるものでなく、人口減少とともに今後も減少していく。しかし塩は人間にとって欠かすことのできないものであり製品寿命が尽きることもない。長期的視点に立って、品質改善や生産性の向上といった基本に忠実であり続けることが大切。当社は塩田時代の1829年から続く製塩企業として、塩業歴史館の公開、工場見学の受入など塩の価値を伝えることにも取り組んでいく」
‐昨年2度の価格改定を実施した。
「製塩には、莫大なエネルギーがかかる。イオン交換膜でかん水を作った後は水分を蒸発させる必要があり、当社の場合、製品原価の最大費目は石炭代だ。さらに物流費や包装資材などの価格上昇が厳しく、昨年度は社長就任以来初めて赤字転落となったように、価格改定なしでは事業継続が困難だった。この事情をほぼ全てのお客様からご理解いただき、心から感謝している」
‐日本塩工業会の活動は。
「世界一の安全と品質を守るため、厳格な自主規格の制定と定期的な検査に取り組んできた。また現在、最大の課題となっているのがカーボンニュートラルへの対応。ボイラーの入れ替えやメガソーラー設置、共同物流によるCO2排出量の削減策に加えて、CO2の回収・貯留技術の模索や植林による吸収まで検討している。国外や他業種にも知恵を求め研究しているところだ」
【2023(令和5)年7月21日第5135号12面】
ナイカイ塩業
7月11日号「宮崎特集」 トップに聞く
野崎漬物株式会社 代表取締役社長 野﨑偉世氏
メーカー売上1・5倍へ 「働き方改革」が仕事呼び込む
野崎漬物株式会社(宮崎市)の野﨑偉世社長は、2021年10月の社長就任時の5カ年計画で、①漬物事業、②おせち事業、③新規事業の三本柱でメーカーとしての売上を1・5倍に拡大することを目標に掲げた。野﨑社長はメーカー業務の拡大において最大の課題は原料不足と人手不足であり、働き方改革に注力していると話した。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐製造重視の理由。
「大手商社が日配品を扱うようになった今、ベンダー業だけで対抗することは難しく、メーカーとして独自の色を出して行かなければ太刀打ちできない。15年ほど前までは売上高のうち自社製品は3~4割で、仕入れ商品の方が大きかったのだが、現在では製造が65%と逆転した。漬物事業、おせち事業、新規事業の3本を拡大している」
‐漬物事業の拡大は。
「営業面でいえば業務筋への提案強化や、PBの受注などを強化している。しかし根本的な課題は原料不足と人手不足。需要があっても応えきれない、というチャンスロスが度々発生してきた。他社でも同様だと思うので、これらを解消できれば自ずと当社に舞い込んでくる仕事は増えていくはずだと考えている」
‐原料、人手不足の対応策。
「一言で言えば働き方改革。社内雰囲気の改善や休憩室の整備、人事評価制度の改訂など働きやすい職場作りに改めて取り組んでいる。製造面でも事務仕事でもオートメーション化できることはまだまだあり、将来的には本社工場の建て替えも視野に入れている。また、注目いただいているのが女子ソフトボール部『野崎漬物フーディーズ』の結成と、サーファーの雇用。従来に縛られない新しい雇用形態を模索している」
‐ソフトボール部について。
「以前から軟式野球部や陸上部を社内で結成し、コミュニケーションの円滑化や健康増進に繋げてきた。この部活制度を女性の登用促進にも活用しようということで考案したのが女子ソフトボール部で、現在3名が所属し、来春4名入社予定。彼女たちにはソフトボール引退後も働いてもらいたいし、女性管理職も今後増やしていきたい」
‐サーファーの雇用は。
「当社の仕事は沢庵の漬込みが秋冬季に集中する。そこで宮崎県への移住者にはもともとサーファーが多いということに着目し、秋冬の期間は大根栽培で就農してもらい、夏季はライフセーバーやプールの監視員などに出向してもらう契約社員として募ると、全国から反響があった。農業の魅力にハマり、独立を希望している方もいる」
‐おせち事業について。
「関連会社の一ツ葉フーズで行っている。これまで生おせちが主力だったが、今年から、製造時期を分散できる冷凍おせちにも進出する。今年は、生・冷凍で2万5000セットほどを見込んでいるが、5万セットを目標としている」
‐新規事業は。
「昨年9月に初めてのお菓子商品として『鶏の炭火焼きせんべい』を発売した。また沢庵の端材を活用した『大根チップス』を来春発売予定。他にも他社と共同し、漬物の端材を活用した商品開発も検討している。SDGsを取り入れることが発想の転換や原料問題の解決にも繋がっている。事業の多角化で人材が増え、出来ることも広がってきている」
【2023(令和5)年7月11日第5134号4面】
食料新聞電子版 九州うまかモン 野崎漬物
7月11日号「宮崎特集」 新会長に聞く
九州漬物協会 会長 大久保次郎氏
原料対策が最重要課題
息揃えて農業変革を主導
株式会社大久保商店(宮崎県延岡市櫛津町)の大久保次郎社長が6月、九州漬物協会会長並びに全日本漬物協同組合連合会副会長に就任した。大久保社長は原料対策を最重要課題として、漬物業界が農業の変革を主導していく必要性を説いた。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐九州漬協会長就任の心境は。
「漬物業界にとって非常に厳しい環境での就任となった。今、九州漬協や全漬連で加盟者が年々減っていて、全国に根付く漬物文化が消えていくことに危機感を感じている。中園雅治前会長が全漬連会長に就任されたので、全漬連とも連携しながら加盟者の助けになる事業に取り組んでいきたい」
‐重点事業は。
「原料不足、人手不足、消費停滞など様々な課題があるが、一番の大元である原料がなければ漬物を作って売ることすらできなくなる。九州漬協では干そう沢庵部会、高菜部会として情報交換を行ってきたが、今後はできるだけこの頻度を高めていくことが重要になる」
‐情報交換に期待すること。
「例えば野菜の栽培方法や工場へ運ぶまでのルーチンなどは各地で差があるが、現代の気候や物流に最適化した形を、県をまたいで模索していく必要がある。我々メーカーが息を揃えれば、新しい仕組みを提示するようなこともできるようになると思う。また現状、情報交換はメンバーが固定されてきているので、出席していない方へも内容をオープンにすることで関心を持っていただけるようにすべきだと考えている」
息揃えて農業変革を主導
株式会社大久保商店(宮崎県延岡市櫛津町)の大久保次郎社長が6月、九州漬物協会会長並びに全日本漬物協同組合連合会副会長に就任した。大久保社長は原料対策を最重要課題として、漬物業界が農業の変革を主導していく必要性を説いた。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
‐九州漬協会長就任の心境は。
「漬物業界にとって非常に厳しい環境での就任となった。今、九州漬協や全漬連で加盟者が年々減っていて、全国に根付く漬物文化が消えていくことに危機感を感じている。中園雅治前会長が全漬連会長に就任されたので、全漬連とも連携しながら加盟者の助けになる事業に取り組んでいきたい」
‐重点事業は。
「原料不足、人手不足、消費停滞など様々な課題があるが、一番の大元である原料がなければ漬物を作って売ることすらできなくなる。九州漬協では干そう沢庵部会、高菜部会として情報交換を行ってきたが、今後はできるだけこの頻度を高めていくことが重要になる」
‐情報交換に期待すること。
「例えば野菜の栽培方法や工場へ運ぶまでのルーチンなどは各地で差があるが、現代の気候や物流に最適化した形を、県をまたいで模索していく必要がある。我々メーカーが息を揃えれば、新しい仕組みを提示するようなこともできるようになると思う。また現状、情報交換はメンバーが固定されてきているので、出席していない方へも内容をオープンにすることで関心を持っていただけるようにすべきだと考えている」
‐販促面は。
「農水省が発信された『漬物で野菜を食べよう!』には強く共感している。ただ、そのポスターが発表された直後に漬物の塩分が高いと指摘するメディアもあった。漬物業界としては以前から、漬物は低塩化してきていること、野菜に含まれるカリウムがナトリウムの排出を促してくれることなどを発信してきたが、まだまだ一般の方に届いていないという証拠。塩分以外の面でみても食物繊維や乳酸菌が豊富であることなど健康に役立てられる要素は多い。否定的な意見が出たこともチャンスと捉えて、議論を深めていければ良いのではないか」
「農水省が発信された『漬物で野菜を食べよう!』には強く共感している。ただ、そのポスターが発表された直後に漬物の塩分が高いと指摘するメディアもあった。漬物業界としては以前から、漬物は低塩化してきていること、野菜に含まれるカリウムがナトリウムの排出を促してくれることなどを発信してきたが、まだまだ一般の方に届いていないという証拠。塩分以外の面でみても食物繊維や乳酸菌が豊富であることなど健康に役立てられる要素は多い。否定的な意見が出たこともチャンスと捉えて、議論を深めていければ良いのではないか」
‐大久保商店について。
「各種浅漬や本漬、佃煮など様々な商品を扱っているが、いずれも地域性を重視して商品開発している。原料が希少なため数量は限られるが、延岡市島野浦産の宗田鰹のかつお節を用いて、延岡市北方町産の筍を醤油ベースで漬けた『節だし筍』や、同じく延岡市産のかつお節にうるめいわし、さば節と北方町産の高菜を合わせた『節だし高菜』は、地域ブランドの『延岡すばなもん』にも認定されている。九州は山の幸、海の幸に恵まれているのが最大の強み。協会活動で原料対策をしていくことが、各社の事業にも直結していくと確信している」
【2023(令和5)年7月11日第5134号5面】
大久保商店 HP
http://okubosyoten.com/
「各種浅漬や本漬、佃煮など様々な商品を扱っているが、いずれも地域性を重視して商品開発している。原料が希少なため数量は限られるが、延岡市島野浦産の宗田鰹のかつお節を用いて、延岡市北方町産の筍を醤油ベースで漬けた『節だし筍』や、同じく延岡市産のかつお節にうるめいわし、さば節と北方町産の高菜を合わせた『節だし高菜』は、地域ブランドの『延岡すばなもん』にも認定されている。九州は山の幸、海の幸に恵まれているのが最大の強み。協会活動で原料対策をしていくことが、各社の事業にも直結していくと確信している」
【2023(令和5)年7月11日第5134号5面】
大久保商店 HP
http://okubosyoten.com/
五味商店 第18回こだわり商品展示会 7月19日に浜松町で開催
株式会社五味商店 代表取締役社長 寺谷健治氏
「安全安心」「美味しい」「本物」「健康」といったテーマにおいて、全国から厳選した“こだわり食品”を有名百貨店や高質スーパーなどに納入する株式会社五味商店(寺谷健治社長、千葉県我孫子市)は、7月19日に東京都港区の東京都立産業貿易センター浜松町館にて「第18回こだわり商品展示会」を開催する。コロナ禍により3年ぶりの開催となった昨年の展示会には、過去最高となる約400名のバイヤーや関係者らが来場し、個々のブースでは内容の濃い商談が行われた。食品の値上げが続く中、付加価値提案は大きなテーマとなっており、こだわり食品への注目度は上昇している。寺谷健治社長に今回の見どころや現在の消費動向について聞いた。(藤井大碁)
‐18回目の展示会開催となる。
「今回の展示会には107社が出展、このうち34社が新規出展となる。毎回ご好評頂いている“営業マン イチ押しコーナー”では『昭和レトロ』『タイパ』『瓶もの生活』『五味商店のヒット商品』といった4つのテーマで商品を紹介する。今回も会場で新たな商品との出会いがあると思うので是非ご来場頂きたい」
‐こだわり商品の動き。
「今回の展示会には107社が出展、このうち34社が新規出展となる。毎回ご好評頂いている“営業マン イチ押しコーナー”では『昭和レトロ』『タイパ』『瓶もの生活』『五味商店のヒット商品』といった4つのテーマで商品を紹介する。今回も会場で新たな商品との出会いがあると思うので是非ご来場頂きたい」
‐こだわり商品の動き。
「商品によりけりだが、値上げの影響は比較的少なく、堅調な動きを示している。物価上昇により可処分所得が減少する中、節約できるものは徹底的に節約し、自分の好きなものにお金を使う“メリハリ消費”が浸透している。毎日の生活の中で、味噌汁や出汁など普段使いするものは特に美味しいものを食べたいという傾向が強くなっている。あらゆるものが値上がりしているが、食べ物に関しては一度美味しいものを食べてしまうと、品質を下げることが難しく、以前の食生活に戻れなくなるという側面もある。高すぎるものは売れないが、高くても大容量で一食あたりの単価が安ければ売れる。消費者は賢くなっており、しっかりと単価を計算し、お得だと分かれば購入するのも最近の傾向だ」
‐特に好調な商品は。
「今回イチ押しコーナーのテーマの一つにもなっている“瓶もの製品”は、手軽で美味しいという特徴が改めて評価され、コロナ下で冷凍食品と共に伸長したカテゴリーだ。特に、高付加価値の瓶もの製品が人気を集めている。今回の展示会にも出展するキッコーマンこころダイニングの『サクサクしょうゆアーモンド』は高単価だが今までになかった新しい味わいが好評で良く売れている。展示会では他にも様々な高付加価値の瓶もの製品をご紹介する」
‐3月決算について。
「近年、こだわり商品への支持が広がったことで、売上は年々上昇を続けてきたが、前期は百貨店の閉店などの影響で、売上は前年比2%減となった。雑貨店などの非食品市場は引き続き堅調だ。食品を品揃えすることで集客に繋がっており、導入店舗が増加している。また最近では、農協の直営店舗にこだわり商品を納入する流れがある。各地の農作物直売所では生鮮品については地元農家から仕入れられるが、加工品の品揃えに課題を持つ店舗も多い。弊社が商品納入に加え、棚割りや従業員教育もサポートすることにより売場を変革していこうというプロジェクトが進んでいる。現在は神奈川、和歌山の店舗に納入しており、今後は全国の店舗へ広がっていく予定だ」
‐現在の消費者ニーズ。
‐特に好調な商品は。
「今回イチ押しコーナーのテーマの一つにもなっている“瓶もの製品”は、手軽で美味しいという特徴が改めて評価され、コロナ下で冷凍食品と共に伸長したカテゴリーだ。特に、高付加価値の瓶もの製品が人気を集めている。今回の展示会にも出展するキッコーマンこころダイニングの『サクサクしょうゆアーモンド』は高単価だが今までになかった新しい味わいが好評で良く売れている。展示会では他にも様々な高付加価値の瓶もの製品をご紹介する」
‐3月決算について。
「近年、こだわり商品への支持が広がったことで、売上は年々上昇を続けてきたが、前期は百貨店の閉店などの影響で、売上は前年比2%減となった。雑貨店などの非食品市場は引き続き堅調だ。食品を品揃えすることで集客に繋がっており、導入店舗が増加している。また最近では、農協の直営店舗にこだわり商品を納入する流れがある。各地の農作物直売所では生鮮品については地元農家から仕入れられるが、加工品の品揃えに課題を持つ店舗も多い。弊社が商品納入に加え、棚割りや従業員教育もサポートすることにより売場を変革していこうというプロジェクトが進んでいる。現在は神奈川、和歌山の店舗に納入しており、今後は全国の店舗へ広がっていく予定だ」
‐現在の消費者ニーズ。
「コロナでお金を使わなかった分、個人資産は増加傾向にあるが、将来への不安があり、使いたくないと考える人が多い。そうした中、売場では、どういう価値を提案すれば、財布からお金を出してもらえるか、という攻防戦が続いている。現在、“毎日食べるものは美味しいものが食べたい”というニーズがあることは確かで、そのニーズに沿って、価値のある製品を提案していく必要がある」
‐売場の変化。
「百貨店の売場が減少し、その分、百貨店のオンラインショップにシフトしている。スーパーは、老舗スーパーや地域スーパーが苦戦しており、チェーンごとの格差が広がっている。こだわり商品の売行きは堅調だが、スーパー自体の商品開発のレベルが上がったことで、高質スーパーの優位性が薄まっている。品質の良い商品をただ並べるだけでは生き残れなくなってきた。だが、厳しい環境下で、売上が二桁伸びている地域スーパーもある。新しい食材や価値ある商品を発掘し、POPやSNSなどで、その商品価値を伝えることが大切で、それができている店舗は伸びている。今後、人口減少が進む中、今何をしていかなければならないか。価値は時代と共に変わっていく。いつの時代もその価値を捉え、時代に合った売場づくりを行っていくことが求められている」
‐売場の変化。
「百貨店の売場が減少し、その分、百貨店のオンラインショップにシフトしている。スーパーは、老舗スーパーや地域スーパーが苦戦しており、チェーンごとの格差が広がっている。こだわり商品の売行きは堅調だが、スーパー自体の商品開発のレベルが上がったことで、高質スーパーの優位性が薄まっている。品質の良い商品をただ並べるだけでは生き残れなくなってきた。だが、厳しい環境下で、売上が二桁伸びている地域スーパーもある。新しい食材や価値ある商品を発掘し、POPやSNSなどで、その商品価値を伝えることが大切で、それができている店舗は伸びている。今後、人口減少が進む中、今何をしていかなければならないか。価値は時代と共に変わっていく。いつの時代もその価値を捉え、時代に合った売場づくりを行っていくことが求められている」
【2023(令和5)年6月26日第5132号3面】
6月26日号「新理事長に聞く」
京都府漬物協同組合 理事長 土井健資氏
食育と漬物の再定義を
「京漬物」ブランドは努力の賜物
土井志ば漬本舗株式会社の土井健資社長は今年5月の総会で、京都府漬物協同組合の理事長に就任した。土井志ば漬本舗は、しば漬発祥の地・大原で伝統的な製法を守り成長を続けてきた。その一方で、農家の高齢化による原料確保の課題や、大原全体のしば漬生産量減少は進行している。こうした課題は京都漬協の全員に共通するものと土井社長は指摘。食育事業や、漬物の価値の再定義、京漬物のブランド力向上による消費振興策へ取り組む意欲を見せた。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ーしば漬は京の三大漬物の一つ。
「大原の里人によって千年も前から親しまれてきた伝統食であり、当社はその発展への思いを込めて『志ば漬』と呼んできた。味の要である赤しそは全て大原産。生産農家の少子高齢化は全国同様ここ大原でも深刻となっているため、8割を自社栽培している。漬物メーカーは商売人であるとともに文化の担い手であるという責任感をもって取り組んでいる」
ー販売動向は。
「新型コロナウイルス流行下は、観光土産を主力とする京都の漬物業界にとって厳しい3年間だった。今年に入ってからは2019年並、5月連休はそれ以上の売上で推移した。今夏のしば漬は昨年より2割増で漬け込む予定だ。ただ、当社が着実に成長を続けられている一方で、大原全体でのしば漬生産量やメーカー数は減っている。全漬連の加盟者も700を割ったとのことで、漬物の消費振興策が不可欠だ」
ー消費振興策について。
「日本人にもっと漬物を食べてもらうための当組合の施策の一つが食育事業。京都で育つ子どもたちにとって漬物が馴染み深く、また誇りを持てる存在となれることを目指している。小学生への漬物教室や、『京都こども宅食プロジェクト』への協力、京都市の学校給食へ漬物納入などに取り組んでいる。給食には様々な制約があるが、組合の先輩方が粘り強く対応し実現された。今後も京都市外や中学校などより広い範囲で給食へ提供できるよう協議を進めていく」
ー海外発信は。
「輸出の壁の一つが価格であり、それを乗り越えるには和食や京漬物とは何かを再定義し、その価値を伝えていかなければいけない。また和食が世界中でブームとなっているため、漬物を料理素材として提案することには大きな可能性がある。日本料理業界との連携や、京都府立大学と包括連携協定を結べたことを活かし、ストーリー性のある発信をしていきたい」
ー組合活動への意気込みは。
「『京漬物』というブランドができたのは偶然ではなく、組合の努力の賜物。京都の土産購入率で漬物が菓子や工芸品を上回り、トップとなっていることがその証明だ。組合活動に取り組むことが、自社を含め加盟者に好影響を与えると自信を持って言える。これからさらにブランド力を高めていくためにも、地域や周辺団体との連携、新たなPR事業を計画していきたい」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ーしば漬は京の三大漬物の一つ。
「大原の里人によって千年も前から親しまれてきた伝統食であり、当社はその発展への思いを込めて『志ば漬』と呼んできた。味の要である赤しそは全て大原産。生産農家の少子高齢化は全国同様ここ大原でも深刻となっているため、8割を自社栽培している。漬物メーカーは商売人であるとともに文化の担い手であるという責任感をもって取り組んでいる」
ー販売動向は。
「新型コロナウイルス流行下は、観光土産を主力とする京都の漬物業界にとって厳しい3年間だった。今年に入ってからは2019年並、5月連休はそれ以上の売上で推移した。今夏のしば漬は昨年より2割増で漬け込む予定だ。ただ、当社が着実に成長を続けられている一方で、大原全体でのしば漬生産量やメーカー数は減っている。全漬連の加盟者も700を割ったとのことで、漬物の消費振興策が不可欠だ」
ー消費振興策について。
「日本人にもっと漬物を食べてもらうための当組合の施策の一つが食育事業。京都で育つ子どもたちにとって漬物が馴染み深く、また誇りを持てる存在となれることを目指している。小学生への漬物教室や、『京都こども宅食プロジェクト』への協力、京都市の学校給食へ漬物納入などに取り組んでいる。給食には様々な制約があるが、組合の先輩方が粘り強く対応し実現された。今後も京都市外や中学校などより広い範囲で給食へ提供できるよう協議を進めていく」
ー海外発信は。
「輸出の壁の一つが価格であり、それを乗り越えるには和食や京漬物とは何かを再定義し、その価値を伝えていかなければいけない。また和食が世界中でブームとなっているため、漬物を料理素材として提案することには大きな可能性がある。日本料理業界との連携や、京都府立大学と包括連携協定を結べたことを活かし、ストーリー性のある発信をしていきたい」
ー組合活動への意気込みは。
「『京漬物』というブランドができたのは偶然ではなく、組合の努力の賜物。京都の土産購入率で漬物が菓子や工芸品を上回り、トップとなっていることがその証明だ。組合活動に取り組むことが、自社を含め加盟者に好影響を与えると自信を持って言える。これからさらにブランド力を高めていくためにも、地域や周辺団体との連携、新たなPR事業を計画していきたい」
【2023(令和5)年6月26日第5132号5面】
京都府漬物協同組合 http://www.kyo-tsukemono.com/
土井志ば漬本舗 https://www.doishibazuke.co.jp/
6月26日号 愛知特集「青年会長に聞く」
愛知県漬物協会青年会 会長 山田耕平氏
設立60周年で記念式典
「集う」「漬ける」の意義問い直す
愛知県漬物協会青年会の山田耕平会長(株式会社若菜社長)にインタビュー。同青年会は今年度で設立60周年を迎え、来年3月30日にANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋(名古屋市中区)にて記念式典を開催する。山田社長は「集う」こと、「漬ける」ことの意義を問い直す必要性を強調する。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
-記念式典の計画は。
「昨年会長の任を拝命して掲げたテーマが『集う、を新たに』。青年会の役割は同業者が集まることで親睦を深め、情報交換を活発化させること。そこで今回の記念式典は、現役の青年会員だけでなく前後の世代の橋渡しの場にしようと考えている。OBや、まだ入会していない後継者、ご家族にも開けた式典としていく計画だ。青年会の人数が減ってきている今『集う』ことの意義をしっかり示せる式典を目指したい」
-青年会の維持へ。
「現在の経営環境は非常に厳しい中で、時間を取って活動に参加してもらうからにはメリットを感じてもらわなければいけない。青年会の主な活動として、イベントに出店して各社から持ち寄った商品のPR販売を行っているが、毎年同じイベントへ慣例的に参加しているだけでは漫然とした時間になってしまう。しかし前回は商品を試食し合う時間を設けてみたところ、お互いへ理解が深まって意見交換が生まれ、販売にも力が入った。一つ一つの活動を問い直し新たな意味を見出す努力をすれば、小さな変化でも大きな効果を生み出していける」
-自社でも「漬ける、を新たに」を掲げている。
「『漬ける』ということは野菜の独特な食感や、熟成による深い風味を生み出す一つの調理方法と捉えることができる。それと同時に非常に技術が必要で時間と手間がかかり、他業界から新規参入し難い手法ともいえる。この独自性を大切にしながら、現代のニーズに合わせていくことが当社の生き残る道。『フルーツ大根』や『銀座のチーズ』が伸長しているのは、漬けることの価値を示せていると思う」
-今後の方針は。
「漬物の魅力が周りにも広まっていくようなギフト・手土産の対応を強化していく。本来、家庭の味であり、自家需要型の漬物をギフト品にしていくには難しさもあるが、掘り起こす余地はまだまだある。人に贈りたくなるような独自性を追求していきたい」
「集う」「漬ける」の意義問い直す
愛知県漬物協会青年会の山田耕平会長(株式会社若菜社長)にインタビュー。同青年会は今年度で設立60周年を迎え、来年3月30日にANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋(名古屋市中区)にて記念式典を開催する。山田社長は「集う」こと、「漬ける」ことの意義を問い直す必要性を強調する。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
-記念式典の計画は。
「昨年会長の任を拝命して掲げたテーマが『集う、を新たに』。青年会の役割は同業者が集まることで親睦を深め、情報交換を活発化させること。そこで今回の記念式典は、現役の青年会員だけでなく前後の世代の橋渡しの場にしようと考えている。OBや、まだ入会していない後継者、ご家族にも開けた式典としていく計画だ。青年会の人数が減ってきている今『集う』ことの意義をしっかり示せる式典を目指したい」
-青年会の維持へ。
「現在の経営環境は非常に厳しい中で、時間を取って活動に参加してもらうからにはメリットを感じてもらわなければいけない。青年会の主な活動として、イベントに出店して各社から持ち寄った商品のPR販売を行っているが、毎年同じイベントへ慣例的に参加しているだけでは漫然とした時間になってしまう。しかし前回は商品を試食し合う時間を設けてみたところ、お互いへ理解が深まって意見交換が生まれ、販売にも力が入った。一つ一つの活動を問い直し新たな意味を見出す努力をすれば、小さな変化でも大きな効果を生み出していける」
-自社でも「漬ける、を新たに」を掲げている。
「『漬ける』ということは野菜の独特な食感や、熟成による深い風味を生み出す一つの調理方法と捉えることができる。それと同時に非常に技術が必要で時間と手間がかかり、他業界から新規参入し難い手法ともいえる。この独自性を大切にしながら、現代のニーズに合わせていくことが当社の生き残る道。『フルーツ大根』や『銀座のチーズ』が伸長しているのは、漬けることの価値を示せていると思う」
-今後の方針は。
「漬物の魅力が周りにも広まっていくようなギフト・手土産の対応を強化していく。本来、家庭の味であり、自家需要型の漬物をギフト品にしていくには難しさもあるが、掘り起こす余地はまだまだある。人に贈りたくなるような独自性を追求していきたい」
【2023(令和5)年6月26日第5132号6面】
6月26日号 山陰特集インタビュー「トップに聞く」
有限会社土江本店 代表取締役社長 関谷忠之氏
有限会社土江本店(島根県松江市)の関谷忠之社長にインタビュー。同社は、中国・四国地方有数のメーカー・ベンダー。今年、創業75周年を迎えるにあたり、改めて関谷社長のバックグランドやこれまでの取組を振り返り、今思うことや今後の事業展開について話を聞いた。飽くなき探求心とチャレンジ精神が、ひしひしと伝わってくる。
(大阪支社・高澤尚揮)
ー関谷社長のバックグランドは。
「地元の松江高校を卒業後、幼少期から憧れていた米国に渡った。米国ではご縁がありアニメーション制作の仕事を行い、コロンビアカレッジでアニメーションの学位・修士を取得した。アニメの仕事をしていたことで、私は今でも『アニメイト』という言葉を大切にしている。『物を活かすこと』が原義で、注目を浴びていなかったものに光を当てるイメージだ。妻の実家が漬物卸の土江本店で、事業を手伝うため40代で当社へ入社した。それからは常に『自社をどうアニメイトできるか』、すなわちどう魅せるか、を考えて実践してきた」
ー社長が取り組まれてきたことは。
「『食生活を豊かにする提案を』という言葉を大事にし、漬物卸だけでなくメーカー業にも手を広げたこと、そのために原料野菜の自社栽培をスタートしたことは誇りに思っている。夏場の青しまね瓜(青縞瓜)、冬場の津田かぶの自社栽培量は年々拡大している。6次産業が今や有名になったが、目を付けて実際に着手したのは早い方だと自負している。今後は、きゅうりと大根等も栽培していきたい」
ー漬物以外に干物「奉書干し」の製造も。
「当社の看板商品の1つ『奉書干し』は、県内の浜田漁港で獲れた鮮魚を干物にしたものだ。干物は魚を縦に吊るすと旨味が流れ、横に干すと魚の余分な水分が腐って味が変わってしまう課題があった。そこで、奉書紙で余分な水分を吸い取り、乾燥、発酵熟成させる工程を発案し、商標を取得した。発酵熟成は、日本で唯一対応可能な急速冷凍庫を開発し、日々使用している」
ー75周年で新しい試みもされている。
「SDGsの理念に強く共感しており、その理念に沿って自社はどう実践できるか考えてきた。メーカーが最初にできるのは、フードロスを減らすことだ。従来捨てられてきた津田かぶや柿の葉、魚の骨を水蒸気乾燥してパウダー化することにより、ぬか床に入れたりお菓子に入れたりして再利用できる。今は、のどぐろや梅貝、アジなどのパウダー化に成功しており、すでに商談を行い、取引が始まろうとしているところだ。各地域の名産とコラボレーションしていきたいと考えている。チャレンジを加速させる年だ」
ー社長は島根愛がとても強い。
「パウダーの普及を地元から推進する『山陰浜田浜っ粉協議会』会長を務め、浜田市の応援団、県の遣島使としても活動している。無報酬だが、島根の食や文化など魅力を全国の方々に伝えたい思いで一杯だ」
【2023(令和5)年6月26日第5132号8面】
土江本店 HP
6月16日号 わさび関連特集インタビュー「理事長に聞く」
全日本漬物協同組合連合会副会長 静岡県漬物商工業協同組合理事長 望月 啓行氏
わさび漬を若い世代へ
バラエティ展開や食べ方提案で
バラエティ展開や食べ方提案で
静岡県漬物商工業協同組合の望月啓行理事長(田丸屋本店社長)は、5月30日に開催された全日本漬物協同組合連合会の総会において全漬連副会長に就任。わさび漬の需要拡大のため、製品のバラエティ展開や食べ方提案に力を入れていく方針を示した。(藤井大碁)
――商品動向について。
「静岡のわさび関連の売上は観光需要が大きいため、コロナ禍で大きな影響を受けたが、人流の回復と共に状況は好転している。弊社でも駅や高速道路の売場が回復してきており、売上はコロナ前の9割程まで戻っている。インバウンドについても、中国からの観光客はまだ本格的に復活していないが、欧米や韓国からの来店客が増えている」
――5月にタイの展示会に出展した。
「海外では日本原産のユニークな香辛料の一つとしてわさびに注目が集まっている。展示会にはタイ周辺の東南アジアの国々からも大勢の人が来場し、弊社の商品がアジア全体に広められる良い機会になった。特に人気だったのがチューブ入りわさびなど賞味期限が長く、使い勝手の良い調味料だ。現在、弊社では欧米やアジアなど約10カ国にわさび製品を輸出しているが、前年比120~130%と高い伸び率を示している。世界的にわさびの認知度は上昇しており、今後も輸出事業は伸びが期待できると考えている」
――原料動向について。
「昨年の台風の影響と海外需要の増加によりわさび原料が高騰している。例年は需要が高まる年末に最高値となり、その後少しずつ価格が落ち着いてくるのだが、今年に関しては未だ落ち着く気配がなく、現在も例年の倍近い価格となっている。生産者も一時的には高くても良いが、高値が続くと需要が減退するという危機感を持ち始めている。今後の動きを注視していく必要がある」
――わさび漬の需要拡大への施策。
「現在、わさびの辛みがより長持ちするわさび漬の開発に取り組んでいる。どうしても辛みは揮発性で抜けやすく、チルドのわさび漬は商品開発に限界があり、味のバラエティ展開が難しかった。だが近年、開発担当者の努力もあり、少しずつ賞味期限を伸ばすことができるようになった。今後は、今まで味は良くても賞味期限が短かすぎるため商品化できなかったものを商品化し、わさび漬のバラエティ展開を図っていく。粕漬ではないチルド製品もラインナップすることで、わさび漬に抵抗がある若い世代にもアプローチしていきたい」
――わさび漬の新しい食べ方も提案している。
「今年2月にリニューアルした紺屋町本店ではイートインスペースを設け、山葵漬丼を提供している。山葵漬丼は、ひつまぶしのように、一度に様々な食べ方でわさび漬を味わってもらうメニュー。最後に出し汁をかけてお茶漬風に食べてもらうことで風味が増し、今までと違った楽しみ方ができる。こうした食べ方提案にも力を入れて、わさび漬の魅力をアピールしていく」
――地域活性化のための新たな取組。
「県内の小規模農家や飲食店などを対象にした加工食品のOEM製造をスタートする。静岡には豊富な農作物や水産物があるが、小規模事業者はそれを加工する施設や技術がなかった。弊社にはFSSC22000を取得した品質管理体制があり、食品加工を通して地域活性化に貢献できると考えている。地域の食材を地域で加工する静岡サイクルの新しいスキームを作っていきたい」
――全漬連副会長に就任した。
「2年間の任期をしっかり務められるように努力していく。コロナも明けたので静岡漬協でも漬物の魅力をPRする新しい事業を行っていきたい」
――今後について。
「コロナの時期に様々な取組を行い、紺屋町本店では物販からイートインへシフトするなど、モノからコトへの転換を進めてきた。商品の作り方、アプローチの仕方も学んだので、これをしっかり活用しながら、コロナ前以上にわさびの魅力を伝えていきたい」
――商品動向について。
「静岡のわさび関連の売上は観光需要が大きいため、コロナ禍で大きな影響を受けたが、人流の回復と共に状況は好転している。弊社でも駅や高速道路の売場が回復してきており、売上はコロナ前の9割程まで戻っている。インバウンドについても、中国からの観光客はまだ本格的に復活していないが、欧米や韓国からの来店客が増えている」
――5月にタイの展示会に出展した。
「海外では日本原産のユニークな香辛料の一つとしてわさびに注目が集まっている。展示会にはタイ周辺の東南アジアの国々からも大勢の人が来場し、弊社の商品がアジア全体に広められる良い機会になった。特に人気だったのがチューブ入りわさびなど賞味期限が長く、使い勝手の良い調味料だ。現在、弊社では欧米やアジアなど約10カ国にわさび製品を輸出しているが、前年比120~130%と高い伸び率を示している。世界的にわさびの認知度は上昇しており、今後も輸出事業は伸びが期待できると考えている」
――原料動向について。
「昨年の台風の影響と海外需要の増加によりわさび原料が高騰している。例年は需要が高まる年末に最高値となり、その後少しずつ価格が落ち着いてくるのだが、今年に関しては未だ落ち着く気配がなく、現在も例年の倍近い価格となっている。生産者も一時的には高くても良いが、高値が続くと需要が減退するという危機感を持ち始めている。今後の動きを注視していく必要がある」
――わさび漬の需要拡大への施策。
「現在、わさびの辛みがより長持ちするわさび漬の開発に取り組んでいる。どうしても辛みは揮発性で抜けやすく、チルドのわさび漬は商品開発に限界があり、味のバラエティ展開が難しかった。だが近年、開発担当者の努力もあり、少しずつ賞味期限を伸ばすことができるようになった。今後は、今まで味は良くても賞味期限が短かすぎるため商品化できなかったものを商品化し、わさび漬のバラエティ展開を図っていく。粕漬ではないチルド製品もラインナップすることで、わさび漬に抵抗がある若い世代にもアプローチしていきたい」
――わさび漬の新しい食べ方も提案している。
「今年2月にリニューアルした紺屋町本店ではイートインスペースを設け、山葵漬丼を提供している。山葵漬丼は、ひつまぶしのように、一度に様々な食べ方でわさび漬を味わってもらうメニュー。最後に出し汁をかけてお茶漬風に食べてもらうことで風味が増し、今までと違った楽しみ方ができる。こうした食べ方提案にも力を入れて、わさび漬の魅力をアピールしていく」
――地域活性化のための新たな取組。
「県内の小規模農家や飲食店などを対象にした加工食品のOEM製造をスタートする。静岡には豊富な農作物や水産物があるが、小規模事業者はそれを加工する施設や技術がなかった。弊社にはFSSC22000を取得した品質管理体制があり、食品加工を通して地域活性化に貢献できると考えている。地域の食材を地域で加工する静岡サイクルの新しいスキームを作っていきたい」
――全漬連副会長に就任した。
「2年間の任期をしっかり務められるように努力していく。コロナも明けたので静岡漬協でも漬物の魅力をPRする新しい事業を行っていきたい」
――今後について。
「コロナの時期に様々な取組を行い、紺屋町本店では物販からイートインへシフトするなど、モノからコトへの転換を進めてきた。商品の作り方、アプローチの仕方も学んだので、これをしっかり活用しながら、コロナ前以上にわさびの魅力を伝えていきたい」
【2023(令和5)年6月16日第5131号10面】
田丸屋本店 HP
6月16日号 インタビュー「トップに聞く」
株式会社エコリオ 代表取締役 CEO 浦野 由紀夫氏
揚げカス搾り機“エコリオ”
環境対策とコスト削減を両立
環境対策とコスト削減を両立
株式会社エコリオ(東京都千代田区)では揚げカスを活用した資源循環システムの構築に取り組む。同社が開発する揚げカス搾り機“エコリオ”は、揚げカスを搾り油と搾りカスに圧縮分離し、体積を減量することで食品残渣リサイクル法の法定基準を達成することを目的として開発された機器。導入により、油のリサイクルによる新油の注し油軽減や産業廃棄物処理量の削減によるコストダウンなど様々なメリットが得られる。同社では大手企業との連携を進めることで信用力の強化を図るだけでなく、エコリオ導入へのハードルを下げるため新たに初期費用ゼロのサブスクリプションモデルをスタートしている。現在、500件以上のスーパーマーケットを始め、惣菜工場や食品加工工場などへ全国で1000台以上を導入。SDGs対応や油の高騰が課題となる中、環境対策とコスト削減を両立できる機器としてエコリオに大きな注目が集まっている。なお同社は一般社団法人全国スーパーマーケット協会の賛助会員でもある。代表取締役CEOの浦野由紀夫氏に導入のメリットや今後のビジョンについて聞いた。(藤井大碁)
――開発のきっかけ。
「もともと空調メンテナンス会社に勤務し、エンジニアとして様々な外食店の設備を担当していた。その中で、ある天丼チェーンから、揚げカスの処理について相談があったことが開発のきっかけ。揚げカスをフライヤー近くに設置したエコリオに投入することにより圧力をかけ、搾り油と搾りカスに分離する。搾った油は再び調理油としてフライヤーに戻して再利用できる。また搾りカスは我々が買い取り、新資源として電気と飼料に変える。揚げカスに含まれる油は、とても質の良い油だが、これまでは搾油方法が無かったため、産業廃棄物としてお金を払って処理する必要があった。焼却することでCO2を排出し、地球温暖化にも繋がっていた。エコリオ導入により、こうした課題を解決することができる」
――導入のメリット。
「油の購入費削減、産廃費削減、発火防止といったメリットがある。揚げカスに含まれる再利用可能な油を約50%搾油分離することでフライヤーへの新油の注し油が軽減される。エコリオで搾油した油は油槽内の油と同品質だ。また、今まで発火防止のために加えていた水や廃油といった産業廃棄物の量を75%削減できる。注し油の軽減と産業廃棄物の削減はコスト削減に直結する。1日に揚げカスが5㎏排出される店舗で試算すると、年間で約29万円のコストダウンにつながる。その他、揚げカスをエコリオで処理することにより自然発火の危険性が無くなるため、安全面や労働環境改善にも貢献できる」
――新たにサブスクリプションモデルを導入した。
――開発のきっかけ。
「もともと空調メンテナンス会社に勤務し、エンジニアとして様々な外食店の設備を担当していた。その中で、ある天丼チェーンから、揚げカスの処理について相談があったことが開発のきっかけ。揚げカスをフライヤー近くに設置したエコリオに投入することにより圧力をかけ、搾り油と搾りカスに分離する。搾った油は再び調理油としてフライヤーに戻して再利用できる。また搾りカスは我々が買い取り、新資源として電気と飼料に変える。揚げカスに含まれる油は、とても質の良い油だが、これまでは搾油方法が無かったため、産業廃棄物としてお金を払って処理する必要があった。焼却することでCO2を排出し、地球温暖化にも繋がっていた。エコリオ導入により、こうした課題を解決することができる」
――導入のメリット。
「油の購入費削減、産廃費削減、発火防止といったメリットがある。揚げカスに含まれる再利用可能な油を約50%搾油分離することでフライヤーへの新油の注し油が軽減される。エコリオで搾油した油は油槽内の油と同品質だ。また、今まで発火防止のために加えていた水や廃油といった産業廃棄物の量を75%削減できる。注し油の軽減と産業廃棄物の削減はコスト削減に直結する。1日に揚げカスが5㎏排出される店舗で試算すると、年間で約29万円のコストダウンにつながる。その他、揚げカスをエコリオで処理することにより自然発火の危険性が無くなるため、安全面や労働環境改善にも貢献できる」
――新たにサブスクリプションモデルを導入した。
「これまでは機器の販売のみを行ってきたが、新たに初期投資0円でお試し頂くことができるレンタルサービスを始めた。必要なのは機器利用料のお支払いのみで、設置費用やメンテナンス費用はかからない。発生した搾りカスは弊社が有価買取させて頂く。削減されたお客様のコストメリットに応じて課金させて頂くため、使った分だけお得になる。機器の導入ハードルを下げなければ、検討して頂いている間に資源がどんどん捨てられ、CO2が排出されていく。それを防ぐため、今回こうしたモデルを導入した。試して頂いた後に、導入しないという判断ももちろんできるので是非トライして頂きたい」
――「エコリオステーション」が注目を集めている。
――「エコリオステーション」が注目を集めている。
「昨年、埼玉県熊谷市に『エコリオステーション』を開設した。エコリオステーションは、エコリオにより分離した搾りカスを集め、“飼料”と“電気”に変えるための工場。搾りカスは、工場内でバイオディーゼル燃料やバイオコークス、飼料といった資源に生まれ変わる。バイオディーゼル燃料は持続可能な航空燃料“SAF(サフ)”として使用することもでき、新しい資源回収循環システムとして注目を浴びている。温暖化対策(CO2削減)と飼料の国内自給率の改善など、社会に大きく貢献できるシステムであると思うので、小売業界や食品業界など関係者の方々と共にこのプロジェクトを推進していきたい」
――大手企業との連携が始まっている。
「我々はベンチャー企業なので、これまで様々な企業がプロジェクトへ参加したいという意向があっても、信用力や体力面で不安が残るというご意見を頂いていた。だが足元では、大手商社との連携がスタートし、安心してプロジェクトにご参加頂ける地盤が整った。今後はプロジェクトに、さらに多くのスーパーマーケットや外食チェーン、食品メーカーに参加して頂き、排出された揚げカスを大手商社とエコリオの連合体に供給して頂くことで、資源回収循環システムの規模を拡大していきたい」
――今後について。
「プロジェクトにとにかく多くの企業に参画してもらうことを目指している。そのために、大手企業との連携をさらに強め、安心して参画できるスキームを作っていく。現在、CO2を排出している大手企業は、排出した分のカーボンクレジットを購入することで帳尻を合わせているが、エコリオステーションに投資をしてプロジェクトに参画して頂くことで、カーボンクレジットの創出側に回ることができる。エコリオステーションは熊谷に続く次の候補地も決まり、大手メーカーも関わったプロジェクトが動いている。是非この資源循環プロジェクトにご参画頂きたい」
――大手企業との連携が始まっている。
「我々はベンチャー企業なので、これまで様々な企業がプロジェクトへ参加したいという意向があっても、信用力や体力面で不安が残るというご意見を頂いていた。だが足元では、大手商社との連携がスタートし、安心してプロジェクトにご参加頂ける地盤が整った。今後はプロジェクトに、さらに多くのスーパーマーケットや外食チェーン、食品メーカーに参加して頂き、排出された揚げカスを大手商社とエコリオの連合体に供給して頂くことで、資源回収循環システムの規模を拡大していきたい」
――今後について。
「プロジェクトにとにかく多くの企業に参画してもらうことを目指している。そのために、大手企業との連携をさらに強め、安心して参画できるスキームを作っていく。現在、CO2を排出している大手企業は、排出した分のカーボンクレジットを購入することで帳尻を合わせているが、エコリオステーションに投資をしてプロジェクトに参画して頂くことで、カーボンクレジットの創出側に回ることができる。エコリオステーションは熊谷に続く次の候補地も決まり、大手メーカーも関わったプロジェクトが動いている。是非この資源循環プロジェクトにご参画頂きたい」
【2023(令和5)年6月16日第5131号4面】
エコリオ HP
6月16日号 酢漬特集 インタビュー
株式会社みやまえ 代表取締役社長 宮前有一郎氏
文化維持へ価値提案
素材利用やOEM商品も
素材利用やOEM商品も
株式会社みやまえ(宮前有一郎社長、奈良県生駒郡平群町)は生姜商品の総合メーカーとして全国でトップクラスのシェアを持つ。物価上昇により生姜漬も値上げを実施せざるを得ない状況下、宮前社長は生姜漬文化の維持へ危機感を示す。価格に頼らない価値の提案へ力を注ぐとともに、漬物の素材利用や、生姜を軸とした商品開発を強化している。
(大阪支社・小林悟空)
――生姜漬の動向は。
「ガリ、紅しょうがとも外食産業が回復してきたことで、当社の主力である業務用製品も動き始めた。本年度はコロナ前と同等の営業目標を掲げているが、5月末時点ではそれを超えて推移している。一方利益面については価格改定をしてもなお圧迫されている」
――価格改定について。
「今年2月に、昨年春に続いて実施した。生姜原料と副資材、電気代等全てが高止まりしていることからその判断に至った。しかし現在もコスト上昇や円安が進行し続けていること、そして今年産の原料は高くなる見通しであることを考えれば、3度目の値上げの可能性も覚悟しなければならない。これまで築いてきた生姜漬文化を維持していくには、価格以外の価値を訴えていく必要がある」
――生姜漬文化の維持について。
「生姜漬は多くが無料提供されてきたが、コスト面の問題から、有料化や量の制限という判断が現実に行われている。またそれ以上に避けたいのは、コスト削減のために低品質な生姜漬へ切り替えられ、生姜漬全体のイメージが悪くなり、消費者の心が離れていくこと。当社としては味はもちろんのこと、サポート体制などの強みを磨いて差別化を図っていく」
――新しい取組は。
「添え物としての利用だけでなく、惣菜の素材としての利用を拡大することに注力している。惣菜市場自体が成長産業であるため、まだまだ提案の余地がある。当社の強みはカット幅や添加物の種類、包装形態など多様な規格を揃えていること。調理オペレーションの削減に繋がる提案もできるため、価格以上の価値を感じて頂けている」
――漬物以外にも取り組まれている。
「2013年に発売した『冷凍刻み生姜』は調理現場の作業削減へニーズが年々高まり評価いただいている。また協力工場でのOEM商品開発も進めているところで、生姜を軸としながら様々な商品を扱える会社を目指している」
――原料の見通しは。
「今年は円ベースで価格が上昇する可能性が高いと見ている。昨年から青果生姜が異常に高騰した結果、種生姜も高くなっており、その分が価格に上乗せされていく。さらに種生姜が高すぎて作付けを控えた農家も多く、全体として作付け面積は減少した。産地で価格を吊り上げようとする動きもみられる。かつての『2年高くて4年安い』というサイクルは崩れてしまった」
(大阪支社・小林悟空)
――生姜漬の動向は。
「ガリ、紅しょうがとも外食産業が回復してきたことで、当社の主力である業務用製品も動き始めた。本年度はコロナ前と同等の営業目標を掲げているが、5月末時点ではそれを超えて推移している。一方利益面については価格改定をしてもなお圧迫されている」
――価格改定について。
「今年2月に、昨年春に続いて実施した。生姜原料と副資材、電気代等全てが高止まりしていることからその判断に至った。しかし現在もコスト上昇や円安が進行し続けていること、そして今年産の原料は高くなる見通しであることを考えれば、3度目の値上げの可能性も覚悟しなければならない。これまで築いてきた生姜漬文化を維持していくには、価格以外の価値を訴えていく必要がある」
――生姜漬文化の維持について。
「生姜漬は多くが無料提供されてきたが、コスト面の問題から、有料化や量の制限という判断が現実に行われている。またそれ以上に避けたいのは、コスト削減のために低品質な生姜漬へ切り替えられ、生姜漬全体のイメージが悪くなり、消費者の心が離れていくこと。当社としては味はもちろんのこと、サポート体制などの強みを磨いて差別化を図っていく」
――新しい取組は。
「添え物としての利用だけでなく、惣菜の素材としての利用を拡大することに注力している。惣菜市場自体が成長産業であるため、まだまだ提案の余地がある。当社の強みはカット幅や添加物の種類、包装形態など多様な規格を揃えていること。調理オペレーションの削減に繋がる提案もできるため、価格以上の価値を感じて頂けている」
――漬物以外にも取り組まれている。
「2013年に発売した『冷凍刻み生姜』は調理現場の作業削減へニーズが年々高まり評価いただいている。また協力工場でのOEM商品開発も進めているところで、生姜を軸としながら様々な商品を扱える会社を目指している」
――原料の見通しは。
「今年は円ベースで価格が上昇する可能性が高いと見ている。昨年から青果生姜が異常に高騰した結果、種生姜も高くなっており、その分が価格に上乗せされていく。さらに種生姜が高すぎて作付けを控えた農家も多く、全体として作付け面積は減少した。産地で価格を吊り上げようとする動きもみられる。かつての『2年高くて4年安い』というサイクルは崩れてしまった」
【2023(令和5)年6月16日第5131号6面】
みやまえ HP
6月16日号 漬物MEN
京きさらぎ漬ゑんけい 代表 中本祐作氏
高槻駅前にカフェ風漬物店
元シェフ・若手店主の感性で
元シェフ・若手店主の感性で
『きさらぎ漬』で著名な有限会社丹波からの暖簾分けで独立した新進気鋭の漬物店が、JR高槻駅前に店舗を構える「京きさらぎ漬ゑんけい」(中本祐作代表、本社工場=京都府亀岡市)だ。
独立後も変わらず大切にしている『きさらぎ漬』とは、昆布(アミノ酸)に加えて干ししいたけなどに含まれる核酸系の旨みを利かせる独自の製法を取っている。種類の違う旨みを組み合わせることで相乗効果が生まれ、ご飯やお酒と相性抜群なやみつきの味わいとなる。
「ゑんけい」の店舗はJR高槻前の商業施設に隣接している。京都市と大阪市の中間に位置する有数のベッドタウンという立地もあり、普段づかいに買い求める人が後を絶たない。昨年10月には、店舗をリニューアル。お洒落で清潔感のある店内には30代の若い世代が多く訪れている。
使用する野菜の一部は本社のある亀岡市で自社栽培している。中でも自信を持つのが赤蕪漬だ。赤蕪を新鮮なうちに漬け込んだ風味となめらかな歯ざわりで、食卓を華やがせてくれる。
中本代表は1986年生まれの37歳。15歳から料理の道を志し、専門学校を卒業後はホテルやレストランでフレンチの修行を重ね、また創作居酒屋でも並行して腕を振るってきた。
しかし20代半ばの頃、丹波の職人である父の誘いがあり漬物作りを体感。漬物の奥深さや、農業から一貫して携わることのできる魅力にのめり込んでいき、独立へ至った。
中本代表は「30~40代の同世代にもっと漬物の魅力を広めていこうと、カフェのような雰囲気の店へリニューアルした。フレンチの経験を生かした漬物にも挑戦して、独自の味を追求すれば漬物のイメージを変えていけると思う。将来的には2店舗目の出店も目指したい」と意欲的だ。
なお、同社は今年から京都府漬物協同組合(土井健資理事長)の加盟企業となった。
独立後も変わらず大切にしている『きさらぎ漬』とは、昆布(アミノ酸)に加えて干ししいたけなどに含まれる核酸系の旨みを利かせる独自の製法を取っている。種類の違う旨みを組み合わせることで相乗効果が生まれ、ご飯やお酒と相性抜群なやみつきの味わいとなる。
「ゑんけい」の店舗はJR高槻前の商業施設に隣接している。京都市と大阪市の中間に位置する有数のベッドタウンという立地もあり、普段づかいに買い求める人が後を絶たない。昨年10月には、店舗をリニューアル。お洒落で清潔感のある店内には30代の若い世代が多く訪れている。
使用する野菜の一部は本社のある亀岡市で自社栽培している。中でも自信を持つのが赤蕪漬だ。赤蕪を新鮮なうちに漬け込んだ風味となめらかな歯ざわりで、食卓を華やがせてくれる。
中本代表は1986年生まれの37歳。15歳から料理の道を志し、専門学校を卒業後はホテルやレストランでフレンチの修行を重ね、また創作居酒屋でも並行して腕を振るってきた。
しかし20代半ばの頃、丹波の職人である父の誘いがあり漬物作りを体感。漬物の奥深さや、農業から一貫して携わることのできる魅力にのめり込んでいき、独立へ至った。
中本代表は「30~40代の同世代にもっと漬物の魅力を広めていこうと、カフェのような雰囲気の店へリニューアルした。フレンチの経験を生かした漬物にも挑戦して、独自の味を追求すれば漬物のイメージを変えていけると思う。将来的には2店舗目の出店も目指したい」と意欲的だ。
なお、同社は今年から京都府漬物協同組合(土井健資理事長)の加盟企業となった。
【2023(令和5)年6月16日第5131号3面】
京きららぎ漬 ゑんけい HP
6月1日号 徳島特集 インタビュー
青年部合流し交流強化
産地維持へ危機感持ち対策
産地維持へ危機感持ち対策
徳島県漬物加工販売協同組合理事長を務める辰巳屋食品株式会社(板野郡藍住町)の田中民夫社長にインタビュー。徳島県は出荷額全国一位の「白瓜」をはじめ、全国の漬物業界を支える原料産地だが、生産農家の少子高齢化が続いていることを田中社長は危惧する。こうした中、辰巳屋食品では奈良漬や甘酢漬の製造に加え、農業や一次加工原料卸の部門を強化し対策を講じている。(小林悟空)
◇ ◇
‐今夏の漬物原料は。
「白瓜は6月半ば頃から収穫が始まるが、今のところ適度な降雨があり順調。胡瓜や茄子も、台風がなければ良い作柄となりそうだ。ただ、白瓜は昨年までコロナを悲観して作付を減らした農家もあったのだが、昨年後半から観光が回復してきたため在庫はどこも不足気味。今年は作付けを増やしたかったのだが、引退された農家もあるため、差し引きで微増程度に収まってしまった。たとえ豊作になっても余裕のある状況ではない」
‐農業の少子高齢化について。
「儲かる農業を実現できなければ、今の流れは止まらない。昨年からはさらに輪をかけて塩や肥料、各資材機器が値上がりしている。インボイス制度で負担が増える小規模農家もある。我々メーカーは買取価格を上げなければいけないが消費への影響を考えれば商品価格へ全て転嫁するわけにもいかず、値上げが渋滞状態になっている。農業が衰退すれば漬物も苦しくなる。業界全体で考えていくべき課題になっている」
‐農業部門を強化されている。
「当社で契約している農家さんも引退が増えてきていて、危機感を持って取り組んでいる。漬物原料だけでなく人参やカボチャも生産している。組合加盟企業も多くが農業に着手されているようだ。当社は漬物メーカーとしては夏の奈良漬と、冬の甘酢漬(千枚漬・菊花蕪漬)が主力。その谷間を埋めるように農業や、それを一次加工した原料卸へ注力できるので、収益源の多角化、仕事量の平準化に繋がっている」
‐組合活動は。
「各社とも世代交代で組合の名簿登録者を変更され、メンバーの重複が多くなってきたため青年部を休止した。地域イベントへの出展、PR活動は青年部が担っていたが、親会へ一本化していく。親会・青年部の垣根がなくなったので改めて交流の場を増やしたい。当組合は資材の共同購入や、外国人技能実習生の受入など、社業に直結する事業を行っているので、多くの方が参加したくなる組合を目指したい」
◇ ◇
‐今夏の漬物原料は。
「白瓜は6月半ば頃から収穫が始まるが、今のところ適度な降雨があり順調。胡瓜や茄子も、台風がなければ良い作柄となりそうだ。ただ、白瓜は昨年までコロナを悲観して作付を減らした農家もあったのだが、昨年後半から観光が回復してきたため在庫はどこも不足気味。今年は作付けを増やしたかったのだが、引退された農家もあるため、差し引きで微増程度に収まってしまった。たとえ豊作になっても余裕のある状況ではない」
‐農業の少子高齢化について。
「儲かる農業を実現できなければ、今の流れは止まらない。昨年からはさらに輪をかけて塩や肥料、各資材機器が値上がりしている。インボイス制度で負担が増える小規模農家もある。我々メーカーは買取価格を上げなければいけないが消費への影響を考えれば商品価格へ全て転嫁するわけにもいかず、値上げが渋滞状態になっている。農業が衰退すれば漬物も苦しくなる。業界全体で考えていくべき課題になっている」
‐農業部門を強化されている。
「当社で契約している農家さんも引退が増えてきていて、危機感を持って取り組んでいる。漬物原料だけでなく人参やカボチャも生産している。組合加盟企業も多くが農業に着手されているようだ。当社は漬物メーカーとしては夏の奈良漬と、冬の甘酢漬(千枚漬・菊花蕪漬)が主力。その谷間を埋めるように農業や、それを一次加工した原料卸へ注力できるので、収益源の多角化、仕事量の平準化に繋がっている」
‐組合活動は。
「各社とも世代交代で組合の名簿登録者を変更され、メンバーの重複が多くなってきたため青年部を休止した。地域イベントへの出展、PR活動は青年部が担っていたが、親会へ一本化していく。親会・青年部の垣根がなくなったので改めて交流の場を増やしたい。当組合は資材の共同購入や、外国人技能実習生の受入など、社業に直結する事業を行っているので、多くの方が参加したくなる組合を目指したい」
【2023(令和5)年6月1日第5130号4面】
5月21日号 キムチ浅漬 インタビュー
秋本食品株式会社 代表取締役社長 秋本善明氏
選択と集中で生産性向上へ
価格力ではなく商品力を磨く
5月10日付で代表取締役社長に就任した秋本食品株式会社(神奈川県綾瀬市)の秋本善明氏にインタビュー。浅漬やキムチの売れ行き、今後の営業戦略などについて話を聞いた。製造コストが上昇する中、アイテムの集約化を図って生産効率を上げる取組や食品ロス削減の観点から賞味期限を延長するなど商品力を磨く方針を強調。6月13日、14日の展示会開催をアドバンテージとし、漬物の供給を通して農家や産地を守っていく意思を示した。
(取材日:4月28日、千葉友寛)
◇ ◇
‐浅漬の売れ行きは。
「浅漬はここ半年は芳しくなく、数%減で推移している。以前の浅漬売場は季節商品がしっかり並んでいたが、いまはアイテム数が減少傾向にある。この数年の間にオクラやブロッコリーなど、これまでになかった素材で新しい商品も出てきて勢いもあったが、その後は新しい商品が出にくい環境となっており、動きも落ち着いている。ベーシックな商品に偏っていると感じている」
‐キムチの動きは。
「昨年のキムチの数字は2021年よりプラスとなっており、巣ごもり需要の反動減も見られた中で盛り返してきている。特に後半の動きは良かった。市場としてもプラスになっている。当社では昨今の製造コスト上昇に伴い、昨秋から規格変更を他社に先駆ける形で行った。実質的な値上げで売れ行きを心配していた部分もあるが、大きな影響はなく推移しており、お客様から支持されていることを感じている。その一方で、一部メーカーが昨年から価格を下げてきており、商品力というよりも価格力で売場を取りに来ている動きもある。そのため、キムチは昨年から価格競争が激しくなってきており、特にボリュームゾーンは熾烈な戦いとなっている。あらゆる製造コストが上昇する中、価格訴求の動きは業界の寡占化や市場のシュリンクを加速させることにつながりかねない。価格競争は業界が一番望まないことで、生産者も含めて誰も喜ぶ人はいない」
‐原料の課題は。
「当社が主力とする白菜は、夏場になると産地が茨城から長野に移る。その長野では今夏から1ケース10%程度の値上げになるという話が出ている。特に夏場は産地が限られるので、ある程度の値上げを受けなければ原料が入ってこない。市場の競争が激しくなる中で、原料面も厳しくなる見通しだ」
‐今後の営業戦略について。
「競合の動きを見ると、ある程度価格が引っ張られてしまうことを想定しなければならない。当社ではこれまでもコスト削減に取り組んできたが、さらに生産性を上げる努力をし続けなければならない。取組の一つとしてはアイテムの集約化。幅広いアイテムを持っていると見栄えが良く、売場としての提案もできるのだが、1つの商品が複数のチェーンに入るケースは少なく、一つ一つの商品の数が売れるわけでもない。可能な部分は機械化を進め、手間がかかったり採算が合わない商品については止める覚悟も必要。工場の生産状況も考慮しながら選択と集中を推進していきたい。また、賞味期限を延長するなど商品力を磨く努力も引き続き行っていく」
‐6月13日と14日に展示会を開催する。
「これまでになかったような新しい商品など、大きな変化や提案はできないかもしれないが、得意先のバイヤーが春にかなり代わった。展示会は昨年から開催できているのだが、全国の漬物が一堂に会して紹介できる場は他にない。当社と取引すればこれだけのものを扱うことができる、と感じていただければ大きなアドバンテージになる」
‐漬物業界の未来像について。
「個人的な考えとしては、長期的な視野で見ると日本は競争力が低下する。優秀な技術者は海外に流出して技術力が弱まり、輸出も期待できなくなる。悲観的な見解を述べたが、そのような中でも一次産業はなくなることはない。これまで輸入に頼っていたものを国内で賄う必要があり、国内生産で供給されている売場はなくなることはないだろう。農家は減少し続けているが、農家や産地を守ることは我々の使命。国産にこだわり続け、産地と消費者を結びつける役割を担っている。農家を未来永劫守っていくためにも商品の供給を通じて我々が市場をリードしていければ良いと思っている。世界が認める長寿国である日本の食文化の中には漬物も入っている。我々は日本人の健康を支えてきたという自負を持ってこれからも漬物を作り続けていく」
【2023(令和5)年5月21日第5129号3面】
バイヤー必見!イチ押し商品 秋本食品ページ
株式会社ピックルスホールディングス 代表取締役社長 影山 直司氏
旬の素材を旬の時期に提供
冷凍食品でロングライフ対応
株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に2023年2月期の決算や中長期的な戦略などについて話を聞いた。2023年2月期決算は減収減益となったが、季節によって野菜の仕入れ価格が大きく異なる商品の販売方法を見直し、旬の素材を旬の時期に提供することを基本路線とし、利益を確保する。また、ニーズが高まっているロングライフに対応し、惣菜と冷凍食品の開発及び提案を強化していく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
‐2023年2月期の総括を。
「2023年2月期は新しい会計基準を適用しているため、売上高は前期の450億600万円から4110億5200万円まで下がっているのだが、旧基準で見ると約3%減。売上高は節約志向の影響を受けて減収となった。利益面も減収や原材料費、光熱費、物流費などの高騰により減益となり、厳しい1年だった」
‐コロナの影響による巣ごもり需要が落ち着いてきた中で、キムチと浅漬の売れ行きは。
「キムチは、前半は厳しかったが、後半から復調の兆しが見えてきた。浅漬はまだ前年の数字まで戻ってきておらず、厳しい状況が続いている。物価が上がって財布の紐が固くなり、食べたいものと控えるものの線引きがより明確になってきている。節約志向の高まりで食品全般に影響がある。生活に必要な食品への需要は戻っており、安い商品へのシフトも進んでいる。スーパーでは買い上げ点数が減っており、例えば、これまで購入していた4点が3点に減り、その1点に浅漬が入ってしまったという印象だ。キムチはおかずやおつまみの位置付けで戻りが早かった。当社では昨年11月に増量を行ったところ、前年比で2桁伸びた。冬は白菜の契約を多くしていたので、今年の2月、3月も生活応援キャンペーンとして実施し、ご好評をいただいた」
‐製造コストが上昇している状況が続いているが、利益を生み出す体制作りについて。
「当社の商品の中に利益が出ていない商品もある。年間を通して見ると、野菜の価格は一定ではない。そのため、通年販売は利益が出る時期と出ない時期があり、旬の時期に提供する形を基本にしたいと考えている。規格や価格についても昨年と同じ価格で販売するのではなく、その時の原材料などを考慮して季節ごとに規格を変える。季節ごとに見直しをする中で、採算が合わない商品は止めていく方針だ。売上の減少が予想されるが、その分は違う商品で売上を伸ばしていく。旬の時期に利益を出せるように季節感のあるものを積極的に提案していく」
‐昨年3月に農作物の生産、加工及び販売を行う株式会社ピックルスファームを設立した狙いは。
「ピックルスファームは、工場で使用する全ての原料を生産するということではなく、農作物をどのように作っているのか、どのような大変さがあるのかということを学ぶ意味もあり、新入社員研修でも活用している。現在、ピックルスファームでは小松菜やさつまいも、小麦を生産しており、小麦はOH!!!で提供を予定しているパンの原料として栽培している。また、さつまいもは焼きいもがブームになっていることもあり、非常に可能性がある素材だと思っている。昨年は冷たいまま食べられる冷凍の焼きいもを販売し、好評だった」
‐原料の安定供給について。
「SDGsの観点からも野菜の加工を通じて持続可能な農業の実現を目標としている。契約農家にも持続可能な事業を行ってほしい、ということでJGAP認証を取得している事業者との契約を優先するようにしている。そのため、各工場の工場長や原料調達を担当している社員にはJGAPの指導員の資格を取得してもらい、契約農家への指導と支援を行っている。現在、弊社でJGAP指導員の資格を持っている社員は38名。契約農家との連携を強化し、工場ごとに原料を購入する体制を整えている。野菜の生産で一番大変なのが収穫。植え付けや畑の管理はできても、高齢化のため収穫はできない、という農家が増えている。そのため、ピックルスファームでは収穫作業を請け負う事業を行う予定で、原料の安定供給、持続可能な農業の構築を目指している。また、社会貢献として農福連携の取組も視野に入れている」
‐惣菜市場における御社の戦略は。
「惣菜と冷凍食品はこれからも売れていくだろう。弊社の惣菜の売上は100億円を突破し、柱の一つになっている。惣菜は基本的に今日買ってその日に食べるものでロスが発生しやすいため、長期間保存できる食品のニーズがある。弊社では、ガス置換により、商品のロングライフ化を実現。現在は、切り干し大根、ひじき煮、卯の花、きんぴらなどがあり、量販店でテスト販売している。また、冷凍食品については、昨年、冷凍のキムチ鍋をスーパーでテスト販売したところ、大変評判が良かった。今年は冷凍のアヒージョも展開する予定。今後もおつまみ需要などに対応した商品を開発していく」
‐漬物業界も倒産、廃業が続いている。
「下請け的な仕事をしている、価格が合わない商品を製造している、自社ブランドの商品を作っていない、などの事業を行っている企業は経営が厳しくなってきていると感じている。当社グループは全国に拠点があり、全国展開しているスーパーやCVS、ドラッグストアに同じ品質の商品を供給することができる。仕入れ商品もあるので、幅広い商品提案も可能だ。今後も全国ネットワークを活かした営業戦略を推進していく。弊社の漬物市場シェアは15%を目標としている」
‐主力商品の値上げについて。
「『ご飯がススムキムチ』の値上げはまだ行っていない。もちろん製造コストは上がっているが、同商品は発売から値上げは一度も行っておらず、もう少しやれることがないか常に考えながら対応している。だが、この先も値上げしない、とは言い切れない状況だ。また、大手企業が関東に拠点を作ったことで、価格面での競争が激しくなる可能性もあると考えている」
【2023(令和5)年5月21日第5129号12面】
冷凍食品でロングライフ対応
株式会社ピックルスホールディングス(埼玉県所沢市)代表取締役社長の影山直司氏に2023年2月期の決算や中長期的な戦略などについて話を聞いた。2023年2月期決算は減収減益となったが、季節によって野菜の仕入れ価格が大きく異なる商品の販売方法を見直し、旬の素材を旬の時期に提供することを基本路線とし、利益を確保する。また、ニーズが高まっているロングライフに対応し、惣菜と冷凍食品の開発及び提案を強化していく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
‐2023年2月期の総括を。
「2023年2月期は新しい会計基準を適用しているため、売上高は前期の450億600万円から4110億5200万円まで下がっているのだが、旧基準で見ると約3%減。売上高は節約志向の影響を受けて減収となった。利益面も減収や原材料費、光熱費、物流費などの高騰により減益となり、厳しい1年だった」
‐コロナの影響による巣ごもり需要が落ち着いてきた中で、キムチと浅漬の売れ行きは。
「キムチは、前半は厳しかったが、後半から復調の兆しが見えてきた。浅漬はまだ前年の数字まで戻ってきておらず、厳しい状況が続いている。物価が上がって財布の紐が固くなり、食べたいものと控えるものの線引きがより明確になってきている。節約志向の高まりで食品全般に影響がある。生活に必要な食品への需要は戻っており、安い商品へのシフトも進んでいる。スーパーでは買い上げ点数が減っており、例えば、これまで購入していた4点が3点に減り、その1点に浅漬が入ってしまったという印象だ。キムチはおかずやおつまみの位置付けで戻りが早かった。当社では昨年11月に増量を行ったところ、前年比で2桁伸びた。冬は白菜の契約を多くしていたので、今年の2月、3月も生活応援キャンペーンとして実施し、ご好評をいただいた」
‐製造コストが上昇している状況が続いているが、利益を生み出す体制作りについて。
「当社の商品の中に利益が出ていない商品もある。年間を通して見ると、野菜の価格は一定ではない。そのため、通年販売は利益が出る時期と出ない時期があり、旬の時期に提供する形を基本にしたいと考えている。規格や価格についても昨年と同じ価格で販売するのではなく、その時の原材料などを考慮して季節ごとに規格を変える。季節ごとに見直しをする中で、採算が合わない商品は止めていく方針だ。売上の減少が予想されるが、その分は違う商品で売上を伸ばしていく。旬の時期に利益を出せるように季節感のあるものを積極的に提案していく」
‐昨年3月に農作物の生産、加工及び販売を行う株式会社ピックルスファームを設立した狙いは。
「ピックルスファームは、工場で使用する全ての原料を生産するということではなく、農作物をどのように作っているのか、どのような大変さがあるのかということを学ぶ意味もあり、新入社員研修でも活用している。現在、ピックルスファームでは小松菜やさつまいも、小麦を生産しており、小麦はOH!!!で提供を予定しているパンの原料として栽培している。また、さつまいもは焼きいもがブームになっていることもあり、非常に可能性がある素材だと思っている。昨年は冷たいまま食べられる冷凍の焼きいもを販売し、好評だった」
‐原料の安定供給について。
「SDGsの観点からも野菜の加工を通じて持続可能な農業の実現を目標としている。契約農家にも持続可能な事業を行ってほしい、ということでJGAP認証を取得している事業者との契約を優先するようにしている。そのため、各工場の工場長や原料調達を担当している社員にはJGAPの指導員の資格を取得してもらい、契約農家への指導と支援を行っている。現在、弊社でJGAP指導員の資格を持っている社員は38名。契約農家との連携を強化し、工場ごとに原料を購入する体制を整えている。野菜の生産で一番大変なのが収穫。植え付けや畑の管理はできても、高齢化のため収穫はできない、という農家が増えている。そのため、ピックルスファームでは収穫作業を請け負う事業を行う予定で、原料の安定供給、持続可能な農業の構築を目指している。また、社会貢献として農福連携の取組も視野に入れている」
‐惣菜市場における御社の戦略は。
「惣菜と冷凍食品はこれからも売れていくだろう。弊社の惣菜の売上は100億円を突破し、柱の一つになっている。惣菜は基本的に今日買ってその日に食べるものでロスが発生しやすいため、長期間保存できる食品のニーズがある。弊社では、ガス置換により、商品のロングライフ化を実現。現在は、切り干し大根、ひじき煮、卯の花、きんぴらなどがあり、量販店でテスト販売している。また、冷凍食品については、昨年、冷凍のキムチ鍋をスーパーでテスト販売したところ、大変評判が良かった。今年は冷凍のアヒージョも展開する予定。今後もおつまみ需要などに対応した商品を開発していく」
‐漬物業界も倒産、廃業が続いている。
「下請け的な仕事をしている、価格が合わない商品を製造している、自社ブランドの商品を作っていない、などの事業を行っている企業は経営が厳しくなってきていると感じている。当社グループは全国に拠点があり、全国展開しているスーパーやCVS、ドラッグストアに同じ品質の商品を供給することができる。仕入れ商品もあるので、幅広い商品提案も可能だ。今後も全国ネットワークを活かした営業戦略を推進していく。弊社の漬物市場シェアは15%を目標としている」
‐主力商品の値上げについて。
「『ご飯がススムキムチ』の値上げはまだ行っていない。もちろん製造コストは上がっているが、同商品は発売から値上げは一度も行っておらず、もう少しやれることがないか常に考えながら対応している。だが、この先も値上げしない、とは言い切れない状況だ。また、大手企業が関東に拠点を作ったことで、価格面での競争が激しくなる可能性もあると考えている」
【2023(令和5)年5月21日第5129号12面】
株式会社ピックルスホールディングス HP
5月1日号 漬物の素・夏の甘酒特集インタビュー
日本いりぬか工業会 会長 足立昇司氏
「ぬか漬けの日」をPR
今年は体制作りに注力
今年は体制作りに注力
昨年3月の総会で日本いりぬか工業会の会長に就任し、2年目を迎えた足立昇司会長(株式会社伊勢惣専務取締役)にインタビュー。コロナ禍で昨年度までは思うような活動ができなかったが、今年度は5月8日の「ぬか漬けの日」に合わせて業界紙の電子媒体やSNSなどを活用し、情報発信、プレゼントキャンペーンなどを行う計画。来年以降、ぬか漬教室などのイベントを継続的に実施するため、今年は体制作りに注力する意向を示した。(千葉友寛)
‐ぬか床製品の売れ行きは。
「ぬか床の売れ行きについては、コロナ禍で巣ごもり消費が増加したことに加え、テレビなどのメディアでぬか床やぬか漬が紹介されたことで需要が大幅に増加し、市場も拡大した。健康や美容といった観点以外にも家庭で手軽にできる趣味など、多くの魅力を感じていただきぬか床の利用者が増えた。コロナが落ち着いた現在は落ち着いた状態となっているが、この3年でぬか床やぬか漬に対する認知度はかなり高まったと感じている」
‐ブームとなった甘酒の動きは。
「甘酒は2016年あたりから需要が拡大した。2011年に大ヒットした塩麹の登場によって麹を利用した商品への関心が高まり、甘酒も大きな脚光を浴びた。その流れで新規参入する企業が増加し、市場も一気に拡大した。だが、ブーム的な動きは時間とともに弱含みとなり、全体の需要も減少傾向にあった。だが、昨年の売れ行きは前年並みに推移し、ようやく下げ止まった動きとなっている。全体的に売場のアイテム数は減っている状況だが、逆に甘酒を全く販売していない店舗もない。つまり、売場で定番になっているということは、普段の生活に取り入れることが習慣となっている消費者がいるということを示している。甘酒の市場は10年前と比べてもかなり大きくなっている。美味しくて栄養、健康、美容の3要素が揃っている甘酒にはまだまだ伸び代があると思っている」
‐ぬか床や甘酒の値上げについて。
「残念なことにどちらの品目も昨今の値上げラッシュの波に乗ることができず、値上げは進んでいない。その要因は市場で大きなシェアを持つカテゴリーリーダーのような企業が存在しないことが大きいと思っている。中小企業で構成されるぬか床と甘酒は競争が激しく、値上げするとその他の企業に棚を取られてしまう。ぬか床については米ぬかの価格が上がっていることに加え、包装資材や電気代などの製造コストが上昇しており、利益を圧迫している。値上げをしたいのはどの企業も同じだと思うが、棚を失うリスクが高いため動きたくても動けないという状況が続いている。濃縮タイプの甘酒も同様に競争が激しいため値上げはできていない。ブランド力や差別化された商品があれば値上げをすることができると思うが、そのような商品は現在の売場にはない。商品開発やブランドを磨く努力が必要なのだが、現在は我慢比べの様相となっている」
‐日本いりぬか工業会の活動について。
「工業会としてはまずぬか床やぬか漬のことを一般の方に認知してもらうため、5月8日の『ぬか漬けの日』に合わせ、業界紙の電子媒体やSNSなどを活用し、情報発信、プレゼントキャンペーンなどを行う。今年の事業計画には入れられなかったが、来年以降はぬか漬教室などのイベントを継続的に実施したいと考えている。今年は来年以降に向けた体制作りに注力したいと思っており、会員企業の理解と協力をいただきながら業界の活性化につながるような活動をしていきたい」
‐ぬか床製品の売れ行きは。
「ぬか床の売れ行きについては、コロナ禍で巣ごもり消費が増加したことに加え、テレビなどのメディアでぬか床やぬか漬が紹介されたことで需要が大幅に増加し、市場も拡大した。健康や美容といった観点以外にも家庭で手軽にできる趣味など、多くの魅力を感じていただきぬか床の利用者が増えた。コロナが落ち着いた現在は落ち着いた状態となっているが、この3年でぬか床やぬか漬に対する認知度はかなり高まったと感じている」
‐ブームとなった甘酒の動きは。
「甘酒は2016年あたりから需要が拡大した。2011年に大ヒットした塩麹の登場によって麹を利用した商品への関心が高まり、甘酒も大きな脚光を浴びた。その流れで新規参入する企業が増加し、市場も一気に拡大した。だが、ブーム的な動きは時間とともに弱含みとなり、全体の需要も減少傾向にあった。だが、昨年の売れ行きは前年並みに推移し、ようやく下げ止まった動きとなっている。全体的に売場のアイテム数は減っている状況だが、逆に甘酒を全く販売していない店舗もない。つまり、売場で定番になっているということは、普段の生活に取り入れることが習慣となっている消費者がいるということを示している。甘酒の市場は10年前と比べてもかなり大きくなっている。美味しくて栄養、健康、美容の3要素が揃っている甘酒にはまだまだ伸び代があると思っている」
‐ぬか床や甘酒の値上げについて。
「残念なことにどちらの品目も昨今の値上げラッシュの波に乗ることができず、値上げは進んでいない。その要因は市場で大きなシェアを持つカテゴリーリーダーのような企業が存在しないことが大きいと思っている。中小企業で構成されるぬか床と甘酒は競争が激しく、値上げするとその他の企業に棚を取られてしまう。ぬか床については米ぬかの価格が上がっていることに加え、包装資材や電気代などの製造コストが上昇しており、利益を圧迫している。値上げをしたいのはどの企業も同じだと思うが、棚を失うリスクが高いため動きたくても動けないという状況が続いている。濃縮タイプの甘酒も同様に競争が激しいため値上げはできていない。ブランド力や差別化された商品があれば値上げをすることができると思うが、そのような商品は現在の売場にはない。商品開発やブランドを磨く努力が必要なのだが、現在は我慢比べの様相となっている」
‐日本いりぬか工業会の活動について。
「工業会としてはまずぬか床やぬか漬のことを一般の方に認知してもらうため、5月8日の『ぬか漬けの日』に合わせ、業界紙の電子媒体やSNSなどを活用し、情報発信、プレゼントキャンペーンなどを行う。今年の事業計画には入れられなかったが、来年以降はぬか漬教室などのイベントを継続的に実施したいと考えている。今年は来年以降に向けた体制作りに注力したいと思っており、会員企業の理解と協力をいただきながら業界の活性化につながるような活動をしていきたい」
【2023(令和5)年5月1日第5127号6面】
日本いりぬか工業会 副会長 山﨑理香子氏
提案型の売り方が鍵
いりぬかは伸びるアイテム
いりぬかは伸びるアイテム
日本いりぬか工業会の山﨑理香子副会長(国城産業㈱代表取締役社長)にインタビュー。山﨑副会長は、いりぬか製品の動向や値上げ状況を語ると共に、5月8日「ぬか漬けの日」に絡めた提案型の売り場作りがぬか漬け関連製品の売上増加に繋がると指摘した。(藤井大碁)
――いりぬか製品の動向。
「いりぬか製品は2020年4月に緊急事態宣言が発令された後から、急激に需要が増加した。巣ごもりにより時間ができたことでぬか漬けにチャレンジする人が増えた。また緊急事態宣言のタイミングが、ぬか漬けシーズンのスタート時期とも重なったため、郊外型の大型店を中心に特設コーナーで販売され、それが一般的な食品スーパーにも波及し売上が伸びた。パンやパスタが品薄になる中で、ご飯を食べようという流れも追い風になり、ピーク時の出荷量は例年の約2倍に拡大。2020年、2021年の2年間はコロナ前と比較して150~160%で推移した。2022年は巣ごもりの減少と共に、いりぬか製品の需要も落ち着き、現在に至るまでコロナ前と同水準で推移している。足元では、気温の高低差が激しいことも影響し、ぬか漬けシーズンスタートの出足は例年より鈍い。これから本格的なシーズンインとなるので、需要拡大に期待したい」
――値上げについて。
「弊社では4月より10%程の値上げを実施した。全てのコストが上昇しているが、特に米ぬか原料と物流費の高騰のインパクトが大きい。米ぬか原料は、輸入飼料の価格上昇に伴い、それに引っ張られる格好で国内飼料として使用されている米ぬかが上昇、一年間で約3倍近い価格になっている。米ぬかは近年人気が拡大している米油の原料としても引き合いが多く、この先も原料価格が下がる要素はない。物流費も一年間で15%程上がっており影響は大きい。いりぬかは、使う人は使う、使わない人は使わないという嗜好性の高い商品なので、値上げの影響は比較的少ない部類であると考えているが、今後の動きを注視して慎重に対応していきたい」
――ぬか漬けファンは増加傾向にある。
「健康性や発酵食品としての認知度上昇に加え、近年はSNSを通じて、若い世代にもぬか漬けの魅力が広がり、コロナ禍を経て、新たなユーザーが増加した。コロナ特需は落ち着いたが、そういう意味でも、いりぬか製品は、売り方によって今後まだまだ伸びるアイテムだと考えている。小売店において、いりぬかやぬか床製品を購入する場合、現在はいりぬか製品(ドライタイプ)はグロッサリー売場、ぬか床製品(ウェットタイプ)は青果売場というように、ぬか漬け関連製品の売場が分かれてしまっている。これを青果売場に統一し、POPなどで使い方を分かりやすく明記することによりぬか漬け関連製品の売上を伸ばしていけると考えている。特設コーナーを展開した店舗の売上が伸びていることを見ると、“ぬか漬けを始めませんか”という提案型の売り方が鍵になる。健康性や、食品ロス削減といったSDGsの要素の他、5月8日の『ぬか漬けの日』を絡めた売場での販促を提案していきたい」
――他社のいりぬかメーカーが、いりぬか以外の製品を幅広く取り扱う中、貴社では50年間いりぬか一筋を貫いてきた。
「『いりぬか』ならどこのものでも一緒と思われがちな商品であるが、国内唯一のいりぬか専業メーカーとしては、いりぬかの質が最も重要であると考えている。お米の種類やその年の出来具合により、ぬかの質は変わる。その違いを見極め、製造していくことで、お客様に長く愛される商品を作り、日本固有の食文化“ぬか漬け”を守り続けていくために今後も努力していきたい」
――いりぬか製品の動向。
「いりぬか製品は2020年4月に緊急事態宣言が発令された後から、急激に需要が増加した。巣ごもりにより時間ができたことでぬか漬けにチャレンジする人が増えた。また緊急事態宣言のタイミングが、ぬか漬けシーズンのスタート時期とも重なったため、郊外型の大型店を中心に特設コーナーで販売され、それが一般的な食品スーパーにも波及し売上が伸びた。パンやパスタが品薄になる中で、ご飯を食べようという流れも追い風になり、ピーク時の出荷量は例年の約2倍に拡大。2020年、2021年の2年間はコロナ前と比較して150~160%で推移した。2022年は巣ごもりの減少と共に、いりぬか製品の需要も落ち着き、現在に至るまでコロナ前と同水準で推移している。足元では、気温の高低差が激しいことも影響し、ぬか漬けシーズンスタートの出足は例年より鈍い。これから本格的なシーズンインとなるので、需要拡大に期待したい」
――値上げについて。
「弊社では4月より10%程の値上げを実施した。全てのコストが上昇しているが、特に米ぬか原料と物流費の高騰のインパクトが大きい。米ぬか原料は、輸入飼料の価格上昇に伴い、それに引っ張られる格好で国内飼料として使用されている米ぬかが上昇、一年間で約3倍近い価格になっている。米ぬかは近年人気が拡大している米油の原料としても引き合いが多く、この先も原料価格が下がる要素はない。物流費も一年間で15%程上がっており影響は大きい。いりぬかは、使う人は使う、使わない人は使わないという嗜好性の高い商品なので、値上げの影響は比較的少ない部類であると考えているが、今後の動きを注視して慎重に対応していきたい」
――ぬか漬けファンは増加傾向にある。
「健康性や発酵食品としての認知度上昇に加え、近年はSNSを通じて、若い世代にもぬか漬けの魅力が広がり、コロナ禍を経て、新たなユーザーが増加した。コロナ特需は落ち着いたが、そういう意味でも、いりぬか製品は、売り方によって今後まだまだ伸びるアイテムだと考えている。小売店において、いりぬかやぬか床製品を購入する場合、現在はいりぬか製品(ドライタイプ)はグロッサリー売場、ぬか床製品(ウェットタイプ)は青果売場というように、ぬか漬け関連製品の売場が分かれてしまっている。これを青果売場に統一し、POPなどで使い方を分かりやすく明記することによりぬか漬け関連製品の売上を伸ばしていけると考えている。特設コーナーを展開した店舗の売上が伸びていることを見ると、“ぬか漬けを始めませんか”という提案型の売り方が鍵になる。健康性や、食品ロス削減といったSDGsの要素の他、5月8日の『ぬか漬けの日』を絡めた売場での販促を提案していきたい」
――他社のいりぬかメーカーが、いりぬか以外の製品を幅広く取り扱う中、貴社では50年間いりぬか一筋を貫いてきた。
「『いりぬか』ならどこのものでも一緒と思われがちな商品であるが、国内唯一のいりぬか専業メーカーとしては、いりぬかの質が最も重要であると考えている。お米の種類やその年の出来具合により、ぬかの質は変わる。その違いを見極め、製造していくことで、お客様に長く愛される商品を作り、日本固有の食文化“ぬか漬け”を守り続けていくために今後も努力していきたい」
【2023(令和5)年5月1日第5127号8面】
厚生産業株式会社 代表取締役社長 里村俊介氏
業界のトップを目指す
発酵食品の素晴らしさ伝える
昭和34年創業、米麹・甘酒・漬物の素を製造販売する厚生産業株式会社(岐阜県揖斐郡大野町)は4月1日付で、里村俊介専務取締役が新たに代表取締役社長に就任した。里村社長は「漬物の素 名実ともにナンバーワン」、「誰からも認められる 麹の第一人者企業となる」を目標に掲げる。その先に見据えるのは業界のリーディング企業となり発酵食品の素晴らしさを次代へ伝えていくことだ。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー略歴は。
大学卒業後ブルドックソース㈱(東京都中央区)に入社し営業職として勤務した。同じ食品メーカーであり貴重な経験を得ることができた。同社は東日本ではリーディング企業だが、西日本ではまだ挑戦者の立場。両方のエリアを経験できたことは良い経験だった。7年間勤め、2011年に厚生産業に入社した。
ー漬物の素、麹のトップ企業を目標に掲げた。
単に売上を増やすということではなく『誰からも認められる』リーディング企業となり、説得力のある発信をしていくことに主眼を置いている。当社の使命は発酵食品の素晴らしさや手作りの楽しさを次代へ伝えること。大きく果てしない使命なので、具体的な道標としてこの目標を掲げた。
ー「漬物の素」事業について。
創業当初はJAの婦人部で講習会を行い販売しつつ、ご意見を商品開発に生かしてきた。そのノウハウを今も生かし、現在は対面の講習会だけでなく「漬けるドットコム」や「簡単&時短 発酵レシピ」の運営に繋げている。その後、生協や量販店等へ販路を広げてきた。日経POSセレクション2021では「コミローナ 熟成ぬか床1㎏」が「1つ星」に選出されたように、順調にシェアを伸ばせている。
ー漬物の素の現状と方針は。
全体的にはダウントレンドで、特にたくあん漬などの保存漬は急減しているのが現状。その一方でぬか漬は発酵食品ブームという新しい価値観に合致し市場拡大した。マンネリを打破できる商品があれば、漬物の素はまだまだ期待が持てるということ。この度発売した「洋風ぬか漬の素」も、ぬか漬の固定観念を崩していく狙いがある。
ー麹事業について。
業務筋への素材提供を主力にしている。麹菌は数千もの株が発見されていて、例えば酵素を産出する力などに差がある。味噌や酒、甘酒など用途に応じて提案するのが当社の役割。最近では農業活性化の一環として大豆や麦を麹化することにも需要が出てきている。麹の研究をさらに深めて提案の幅を広げること、要望に応えるだけでなく能動的な提案を強化していくことに取り組んでいく。
ー新規分野にも積極的だ。
麹を化粧品分野へ提供している。化粧品分野では食品以上にエビデンスや“ストーリー性”を求められる。これに対応する中で研究面、営業面ともにレベルアップしてきた。他にもプラントベースフード等、当社の調味技術や発酵の研究力を生かした新規事業に挑戦していきたい。
【里村俊介社長】
1982年2月21日生まれ。明治大学農学部卒業。2004年ブルドックソース入社。2011年厚生産業入社、2015年取締役経営管理部長、2017年専務取締役。
【2023(令和5)年5月1日第5127号9面】
4月21日号 泉州水なす特集インタビュー
大阪府漬物事業協同組合 理事長 林野雅史氏
水なす漬は成長続く
伝統野菜に特化し差別化図る
大阪府漬物事業協同組合理事長を務める、堺共同漬物株式会社(林野雅史社長、大阪府堺市)の林野雅史社長にインタビュー。林野社長は泉州水なす漬が今も成長を続けているとし、水なすやなにわ伝統野菜へ集中し地域性を追求することが同社の生き残りに必要不可欠であると話す。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
―昨年の水なす漬の実績は。
「定着率の高い関西の市場をしっかり維持しながら、関東など他地域への販売を増やすことができた。水なす原料は産地が限定され、天候に左右されやすいため急な増産はできないが、右肩上がりの成長を続けられている。漬物全般が苦戦している中で水なす漬は稀有な存在だと言える」
―今期の原料状況は。
「3月までに予想外に温かい日が続いたことで成長が進んだため、4月現在は原料を確保でき良いスタートを切れた。その分、5月に途切れる不安があるが、結局は天候次第なので柔軟に対応していくしかない。原料価格については加温ハウス用の燃料や肥料など農業コストも上昇しているため、高止まりしている。当社も価格改定して望む年となる」
―今後の販売拡大には栽培拡大が必要だ。
「水なすは他作物から転換する農家も多く、また若い方も就農してくれている。それは大阪漬協全体で水なす漬を安売りしなかった、つまり原料価格を適正に保ってきた成果だ。無理に栽培を急拡大させるのではなく、我々が漬物の販売実績を重ねていき、農家の方々に『作りたい』と思っていただく流れを作り自然に栽培が増えていくのが望ましい」
―今年の販売戦略は。
「浅漬は引き続き販売拡大を目指していく。関西は大阪はもちろん周辺府県でも完全に定着したと言えるが、関東ではまだまだ新規導入を増やしていける。またSDGsの観点で取引先様から再評価を受けているのが水なすのしば漬や茶漬といった本漬商品。傷ついたり、余ったりして浅漬に出来ない原料を使用するので食品ロス削減になり、生産農家の収入の底上げにもなっている。SDGsは今後、取引先だけでなく消費者へ向けたアピールもしていきたい」
―漬物以外にも着手している。
「水なす漬の天ぷらや『みずなすカレー』など惣菜からレトルト食品まで幅広く挑戦している。生の水なすではなく漬物を素材としているので、当社だけの商品として提案できる。漬物以外の商品を扱うようになったことで、漬物にも新しい視点を取り入れられるようになってきている。将来的には、水なすを漬物に収まらない一つのカテゴリに育てていくことが目標。その先例が梅干しで、菓子や飲料、ソースなどの派生品も多く確固たる地位を築けている。水なすは他の茄子と一線を画す唯一無二の素材のため、ポテンシャルは十分にあると思う」
―今後の方針は。
「物価上昇や大手企業がシェアを広げている状況下、これまでと同じことをしていては事業継続は難しくなる。当社としては今まで以上に水なすを始めとしたなにわ伝統野菜へリソースを集中させていき、はっきりと棲み分けることが生き残りの道だと考えている。漬物を軸とした伝統野菜の加工業という立ち位置で、狭く深く特化していく方針だ」
【2023(令和5)年4月21日第5126号4面】
伝統野菜に特化し差別化図る
大阪府漬物事業協同組合理事長を務める、堺共同漬物株式会社(林野雅史社長、大阪府堺市)の林野雅史社長にインタビュー。林野社長は泉州水なす漬が今も成長を続けているとし、水なすやなにわ伝統野菜へ集中し地域性を追求することが同社の生き残りに必要不可欠であると話す。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
―昨年の水なす漬の実績は。
「定着率の高い関西の市場をしっかり維持しながら、関東など他地域への販売を増やすことができた。水なす原料は産地が限定され、天候に左右されやすいため急な増産はできないが、右肩上がりの成長を続けられている。漬物全般が苦戦している中で水なす漬は稀有な存在だと言える」
―今期の原料状況は。
「3月までに予想外に温かい日が続いたことで成長が進んだため、4月現在は原料を確保でき良いスタートを切れた。その分、5月に途切れる不安があるが、結局は天候次第なので柔軟に対応していくしかない。原料価格については加温ハウス用の燃料や肥料など農業コストも上昇しているため、高止まりしている。当社も価格改定して望む年となる」
―今後の販売拡大には栽培拡大が必要だ。
「水なすは他作物から転換する農家も多く、また若い方も就農してくれている。それは大阪漬協全体で水なす漬を安売りしなかった、つまり原料価格を適正に保ってきた成果だ。無理に栽培を急拡大させるのではなく、我々が漬物の販売実績を重ねていき、農家の方々に『作りたい』と思っていただく流れを作り自然に栽培が増えていくのが望ましい」
―今年の販売戦略は。
「浅漬は引き続き販売拡大を目指していく。関西は大阪はもちろん周辺府県でも完全に定着したと言えるが、関東ではまだまだ新規導入を増やしていける。またSDGsの観点で取引先様から再評価を受けているのが水なすのしば漬や茶漬といった本漬商品。傷ついたり、余ったりして浅漬に出来ない原料を使用するので食品ロス削減になり、生産農家の収入の底上げにもなっている。SDGsは今後、取引先だけでなく消費者へ向けたアピールもしていきたい」
―漬物以外にも着手している。
「水なす漬の天ぷらや『みずなすカレー』など惣菜からレトルト食品まで幅広く挑戦している。生の水なすではなく漬物を素材としているので、当社だけの商品として提案できる。漬物以外の商品を扱うようになったことで、漬物にも新しい視点を取り入れられるようになってきている。将来的には、水なすを漬物に収まらない一つのカテゴリに育てていくことが目標。その先例が梅干しで、菓子や飲料、ソースなどの派生品も多く確固たる地位を築けている。水なすは他の茄子と一線を画す唯一無二の素材のため、ポテンシャルは十分にあると思う」
―今後の方針は。
「物価上昇や大手企業がシェアを広げている状況下、これまでと同じことをしていては事業継続は難しくなる。当社としては今まで以上に水なすを始めとしたなにわ伝統野菜へリソースを集中させていき、はっきりと棲み分けることが生き残りの道だと考えている。漬物を軸とした伝統野菜の加工業という立ち位置で、狭く深く特化していく方針だ」
【2023(令和5)年4月21日第5126号4面】
株式会社天政松下 代表取締役社長 松下雄哉氏
水なす漬200万P販売
「野菜が摂れる」は新形態で支持
株式会社天政松下(松下雄哉社長、大阪市西淀川区)は昨年、水なす漬の販売約200万パックを達成。関東での販売拡大が原動力となった。今期は量販店で主力となる切漬商品に大小2サイズの新商品を投入する。また漬物グランプリ2023で金賞以上を受賞した「野菜が摂れる10品目。」が内容量変更後に販売が伸長し始めた。松下社長は商品特性に合わせたジャストサイズを探る必要性を強調する。(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
―水なす漬の動向は。
「地元関西では水なす漬は完全に定着しているが、関東を始め他地域ではまだまだ拡大の余地がある。一昨年の販売実績は約190万パック、昨年は約200万パックと伸ばせた。当社は群馬に関東工場がある強みを生かしていける。原料面に限りがあるので急拡大は出来ないが、少しずつ全国へ広めていきたい」
―商品展開は。
「関西では姿物のぬか漬と切り漬の2アイテムが基本だが、他地域では切漬タイプのみの販売が多い。今期から切漬タイプから新たにカップ入り新商品2品を発売する。大判サイズの『泉州水なす切漬100g』、食べ切りサイズの『泉州水なす切漬60g』。既存商品の袋入り『水なすのお漬物90g』と合わせて3サイズを展開することで、細かなニーズに対応可能となる」
―商品形態を重視している。
「やはり多様化に対応していく必要がある。ユニット、簡便性、個食だけでも資材や内容量で何パターンも組み合わせが出てくる。出来るだけ手に取って食べてもらえるよう工夫し続けないといけない。昨年からの値上げで商品改廃をせざるを得ない状況もある。この機会に長年売ってきた商品でもそれが当たり前と思わずに、消費者に支持されるものがどこにあるのかさらに向き合っていきたい」
―漬物グランプリで「野菜が摂れる10品目。」が金賞以上の受賞となった。
「元々は約10年前に発売した商品でサラダ感覚漬物として最初は大ヒットしたがその後は勢いを落とし伸び悩んだ。10年間試行錯誤しながら容器形態、内容量、原材料も変化させながら販売を続けてきた。今回は開発事業課の小山が容器形態を丸カップのバージョンにし、量目を過去最低の130gまで抑えた。値頃感のある価格設定にしたところ、再び量販店での導入が増え、出荷数が大幅に伸びてきている。やはり内容量と売価が嵌れば反応も大きく変わる。あらためて商品開発の奥の深さを感じている」
―動画SNSに力を入れている。
「商品宣伝よりも、リクルートに重点を置いている。求職者は社内のリアルな情報を知りたいので『どんな人が働いているのか?』『事務所の雰囲気は?』『年齢層は?』『社長はどんな人?』などはSNSを活用して補っている。漬物の内容があまりないのは求職者が欲しい情報は、そこではないと思うから。先日、某求人媒体と求人募集のデータを分析したところ、他社に比べて200%近い募集率となっており、SNSがリクルートに影響がある事を少し裏付けることができた。仮説を実証するにはまだまだサンプル数が少ないので、どれくらいリクルートに効果的なのかはこれから引き続き検証していきたい」
【2023(令和5)年4月21日第5126号5面】
天政松下 HP
https://www.tenmasamatsushita.co.jp/
「野菜が摂れる」は新形態で支持
株式会社天政松下(松下雄哉社長、大阪市西淀川区)は昨年、水なす漬の販売約200万パックを達成。関東での販売拡大が原動力となった。今期は量販店で主力となる切漬商品に大小2サイズの新商品を投入する。また漬物グランプリ2023で金賞以上を受賞した「野菜が摂れる10品目。」が内容量変更後に販売が伸長し始めた。松下社長は商品特性に合わせたジャストサイズを探る必要性を強調する。(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
―水なす漬の動向は。
「地元関西では水なす漬は完全に定着しているが、関東を始め他地域ではまだまだ拡大の余地がある。一昨年の販売実績は約190万パック、昨年は約200万パックと伸ばせた。当社は群馬に関東工場がある強みを生かしていける。原料面に限りがあるので急拡大は出来ないが、少しずつ全国へ広めていきたい」
―商品展開は。
「関西では姿物のぬか漬と切り漬の2アイテムが基本だが、他地域では切漬タイプのみの販売が多い。今期から切漬タイプから新たにカップ入り新商品2品を発売する。大判サイズの『泉州水なす切漬100g』、食べ切りサイズの『泉州水なす切漬60g』。既存商品の袋入り『水なすのお漬物90g』と合わせて3サイズを展開することで、細かなニーズに対応可能となる」
―商品形態を重視している。
「やはり多様化に対応していく必要がある。ユニット、簡便性、個食だけでも資材や内容量で何パターンも組み合わせが出てくる。出来るだけ手に取って食べてもらえるよう工夫し続けないといけない。昨年からの値上げで商品改廃をせざるを得ない状況もある。この機会に長年売ってきた商品でもそれが当たり前と思わずに、消費者に支持されるものがどこにあるのかさらに向き合っていきたい」
―漬物グランプリで「野菜が摂れる10品目。」が金賞以上の受賞となった。
「元々は約10年前に発売した商品でサラダ感覚漬物として最初は大ヒットしたがその後は勢いを落とし伸び悩んだ。10年間試行錯誤しながら容器形態、内容量、原材料も変化させながら販売を続けてきた。今回は開発事業課の小山が容器形態を丸カップのバージョンにし、量目を過去最低の130gまで抑えた。値頃感のある価格設定にしたところ、再び量販店での導入が増え、出荷数が大幅に伸びてきている。やはり内容量と売価が嵌れば反応も大きく変わる。あらためて商品開発の奥の深さを感じている」
―動画SNSに力を入れている。
「商品宣伝よりも、リクルートに重点を置いている。求職者は社内のリアルな情報を知りたいので『どんな人が働いているのか?』『事務所の雰囲気は?』『年齢層は?』『社長はどんな人?』などはSNSを活用して補っている。漬物の内容があまりないのは求職者が欲しい情報は、そこではないと思うから。先日、某求人媒体と求人募集のデータを分析したところ、他社に比べて200%近い募集率となっており、SNSがリクルートに影響がある事を少し裏付けることができた。仮説を実証するにはまだまだサンプル数が少ないので、どれくらいリクルートに効果的なのかはこれから引き続き検証していきたい」
【2023(令和5)年4月21日第5126号5面】
天政松下 HP
https://www.tenmasamatsushita.co.jp/
4月11日号 調理食品インタビュー
全国調理食品工業協同組合 副理事長 佐々 重雄氏
変化するプライスライン
惣菜市場には伸び代がある
全国調理食品工業協同組合の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。調理食品、惣菜、佃煮の売れ行きや原料状況、製品の値上げの動きなどについて話を聞いた。物価高で節約志向が高まる中、佐々副理事長は必要とされる商品を供給すれば買い控えの対象にはならないと明言。惣菜の市場についても「まだまだ伸び代がある」と前向きな見解を示した。
惣菜市場には伸び代がある
全国調理食品工業協同組合の佐々重雄副理事長(株式会社佐々商店代表取締役社長)にインタビュー。調理食品、惣菜、佃煮の売れ行きや原料状況、製品の値上げの動きなどについて話を聞いた。物価高で節約志向が高まる中、佐々副理事長は必要とされる商品を供給すれば買い控えの対象にはならないと明言。惣菜の市場についても「まだまだ伸び代がある」と前向きな見解を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐調理食品や惣菜の売れ行きは。
「売価が上がっているので数量は多少落ちている。数量ベースは5%減で、金額ベースでは2、3%増となっているが、スーパーによっては数量も落ちていないところがある。物価高で節約志向が高まっている状況だが、お客様の方でも製造コストが上昇していることへの理解が浸透している部分もある。お客様のニーズをとらえ、必要とされる商品を提供することができれば多少の値上げでは買い控えの対象にはならないと考えている」
‐値上げの動きは。
「調理食品業界では昨年から今年の春にかけて昨今の製造コストの上昇及び為替の影響を受けて多くの企業が値上げを実施している。弊社も1月からほぼ全ての商品で値上げを行った。商品によっては量目調整もあるが、量が減ると商品が貧弱に見えてしまうので基本的には価格改定でお客様にお願いしている。改定率は5~10%。本来ならば改定率はもっと高めたいというのが本音だが、お客様が離れてしまう可能性が出てくるので最小限に留めている。これまでのスーパーのプライスラインは198円、298円だったが、そのラインは崩れてきており、維持できる環境ではなくなってきている」
‐昨年から続く値上げの主な要因は。
「他の食品メーカーと同様で、原材料、油、調味料、包装資材などに加え、物流費やエネルギーコストも上昇している。とても自助努力で吸収できるものではなく、価格転嫁しなければ赤字製造となる。我々の業界においては、水産物を原料とする商品も多く、天候要因などの影響で原料が獲れなくなってきている。さらに、原料を獲る人も減少しているため、大変深刻な問題となっている。その他、中国産のタケノコや栗の価格は30%以上上がっている。原料を仕入れる我々も原料メーカーの値上げを認めなければ原料が入ってこなくなり、商品の供給ができなくなる。物が作れなくなる、ということは企業にとって死活問題だ。販売先様はもちろん、原料の仕入先様もより重要な存在となる。お客様のニーズに対応し、お客様が取り扱うことが難しい原料を仕入れて売れる商品を作ることが大事。水産物にしても農産物にしてもこれまでのように安定して仕入れることができなくなっており、原料の目利きが重要になる」
‐調理食品や惣菜の市場について。
「惣菜はコロナ禍で需要が増えたが、コロナが落ち着いてきても惣菜のマーケットは広がっている。単身世帯の増加や女性の社会進出などで、家庭で料理を作る時間は減少傾向にあり、電気、ガス、油の価格が上がっていることも影響している。ひじき煮や筑前煮を食べたいと思っても、自宅で作る人は少ない。そのようなことを考えれば惣菜の市場はまだまだ伸び代があると言える。ただ、物価高で節約志向が高まっており、商品に求められる品質や価格はより厳しくなっていくと思うが、佃煮や惣菜などお客様の必要とされる商品を提供してくことが重要だ。これまで日本の食品は低価格が価値の一つとされていたが、現在は安い商品を作ることができない。価値ある素材を使ってお客様を飽きさせることなく、適正価格での販売を目指していかなければならない」
【2023(令和5)年4月11日第5125号3面】
◇ ◇
‐調理食品や惣菜の売れ行きは。
「売価が上がっているので数量は多少落ちている。数量ベースは5%減で、金額ベースでは2、3%増となっているが、スーパーによっては数量も落ちていないところがある。物価高で節約志向が高まっている状況だが、お客様の方でも製造コストが上昇していることへの理解が浸透している部分もある。お客様のニーズをとらえ、必要とされる商品を提供することができれば多少の値上げでは買い控えの対象にはならないと考えている」
‐値上げの動きは。
「調理食品業界では昨年から今年の春にかけて昨今の製造コストの上昇及び為替の影響を受けて多くの企業が値上げを実施している。弊社も1月からほぼ全ての商品で値上げを行った。商品によっては量目調整もあるが、量が減ると商品が貧弱に見えてしまうので基本的には価格改定でお客様にお願いしている。改定率は5~10%。本来ならば改定率はもっと高めたいというのが本音だが、お客様が離れてしまう可能性が出てくるので最小限に留めている。これまでのスーパーのプライスラインは198円、298円だったが、そのラインは崩れてきており、維持できる環境ではなくなってきている」
‐昨年から続く値上げの主な要因は。
「他の食品メーカーと同様で、原材料、油、調味料、包装資材などに加え、物流費やエネルギーコストも上昇している。とても自助努力で吸収できるものではなく、価格転嫁しなければ赤字製造となる。我々の業界においては、水産物を原料とする商品も多く、天候要因などの影響で原料が獲れなくなってきている。さらに、原料を獲る人も減少しているため、大変深刻な問題となっている。その他、中国産のタケノコや栗の価格は30%以上上がっている。原料を仕入れる我々も原料メーカーの値上げを認めなければ原料が入ってこなくなり、商品の供給ができなくなる。物が作れなくなる、ということは企業にとって死活問題だ。販売先様はもちろん、原料の仕入先様もより重要な存在となる。お客様のニーズに対応し、お客様が取り扱うことが難しい原料を仕入れて売れる商品を作ることが大事。水産物にしても農産物にしてもこれまでのように安定して仕入れることができなくなっており、原料の目利きが重要になる」
‐調理食品や惣菜の市場について。
「惣菜はコロナ禍で需要が増えたが、コロナが落ち着いてきても惣菜のマーケットは広がっている。単身世帯の増加や女性の社会進出などで、家庭で料理を作る時間は減少傾向にあり、電気、ガス、油の価格が上がっていることも影響している。ひじき煮や筑前煮を食べたいと思っても、自宅で作る人は少ない。そのようなことを考えれば惣菜の市場はまだまだ伸び代があると言える。ただ、物価高で節約志向が高まっており、商品に求められる品質や価格はより厳しくなっていくと思うが、佃煮や惣菜などお客様の必要とされる商品を提供してくことが重要だ。これまで日本の食品は低価格が価値の一つとされていたが、現在は安い商品を作ることができない。価値ある素材を使ってお客様を飽きさせることなく、適正価格での販売を目指していかなければならない」
【2023(令和5)年4月11日第5125号3面】
全調食東日本ブロック会 会長 菊池 光晃氏
“佃煮煮豆の価値”見直す時
知恵と行動で荒波乗り越える
全調食東日本ブロック会の菊池光晃会長(菊池食品工業社長兼COO)に、昨年のおせち商戦や値上げの状況などについてインタビュー。菊池会長は様々なコストが高騰し、調理食品メーカーの経営環境が悪化する中、佃煮・煮豆の価値を見直す時期が来ていると語った。
知恵と行動で荒波乗り越える
全調食東日本ブロック会の菊池光晃会長(菊池食品工業社長兼COO)に、昨年のおせち商戦や値上げの状況などについてインタビュー。菊池会長は様々なコストが高騰し、調理食品メーカーの経営環境が悪化する中、佃煮・煮豆の価値を見直す時期が来ていると語った。
(藤井大碁)
◇ ◇
―昨年のおせち商戦。
「数量は前年を割り込んだが、売上は値上げを実施した影響により前年並みで着地した。一昨年、首都圏のスーパーではロスが多かったため、当初から数量ベースで前年比95%、売上100%前後で計画しているところが多く、そのトレンド通りの結果となった。抑え気味の発注となったため、昨年はロスがほとんどなかった一方で、売場から早めに商品が無くなり、追加注文を頂く機会も多かった。品切れによるチャンスロスもかなりあったようだ。カテゴリー別では、栗きんとん、黒豆、昆布巻き、たづくりの主力4品の売上は堅調だったが、原料面では、栗の手配が厳しく、昆布巻も年々巻き手の減少により原料手当てが難しくなっている」
―昨年のおせち商材は原価計算が難しかった。
「商談に合わせて早めのタイミングで原価計算が必要で、それなりのコスト増を見越して算出したものの、それ以降に想定を上回るコスト増が何度も押し寄せ、最初に計算していた原価とは大きな乖離が生まれた。昨年のおせち商材は各メーカーが平均5%程の値上げを実施したが、結果的には、約20%の値上げを実施しなければ原価を下回ってしまう状況だった。為替の影響に加え、全てのコストが値上がりする中、特に電気代、ガス代、段ボール、調味料の値上げのインパクトが大きかった。これからさらに、物流費、冷蔵庫などの蔵賃などが上昇する見込みで、さらなる値上げが必要になる。調理食品業界では、これまで通りのことを普通にやっていては、利益が全く出ない状況だ」
―今年のおせちの見通しは。
「特に栗に関しては、円安が最も進んでいた昨年の仕入れのため、大幅な値上げを実施せざるを得ない。栗きんとんの売れ筋は1000円が主流だが、内容量を変えずに単純に価格転嫁すれば、昨年1000円で販売していたものを1300円から1400円で販売する必要がある。おせちは一年の始めに食べる特別な食事なので、美味しくなければいけない。美味しいものを作るためにも、ある程度のコストアップが必要になるということをご理解いただくと共に、内容量と価格のバランスをどうしていくか、今後熟考していかなければならない」
―通常品の値上げ。
「4月より、昨年10月以来の値上げを実施する。これにより収支が少しでも改善することを期待したい。値上げにより、数量はある程度落ちると思うが、社内努力で耐えられる状況ではないので、会社存続のため、やらざるを得ない。もちろん値上げするだけでなく、美味しさの追求など商品のグレードアップにも力を注いでいく。佃煮・煮豆の価格は、長年変わっていない。様々なコストアップにより、調理食品メーカーの経営環境は限界に差し掛かってきており、事業継続が不可能になれば、廃業や倒産が続出してしまう。伝統文化を守るためにも、佃煮・煮豆の価値を見直す時期に来ているのではないか」
―北海道2社廃業の影響は。
「栗きんとんを道内で量産供給できるメーカーがほとんど無くなってしまった。北海道へ本州以南から商品を供給するのは物流費の割合が大きいため難しい。弊社は函館工場があるため、どうにか対応することができる。4月から札幌に営業所を開設し、体制を整える。道内の佃煮、おせち需要にしっかりと応えられるよう、安定供給に努めていきたい」
―今後に向けて。
「環境が良い時は、会社は伸びないと言われる。環境が厳しくなった時に、どうやって生き残るか。社員と一緒に考え、乗り越えていくことで、会社が成長するのではないか。今は厳しいが、この環境はみんな一緒。ここを乗り越えたところが、この業界で生きていけるものと考えている。この厳しさを自分たちの磨き石だと捉え、知恵と行動により荒波を乗り越えていきたい」
【2023(令和5)年4月11日第5125号4面】
◇ ◇
―昨年のおせち商戦。
「数量は前年を割り込んだが、売上は値上げを実施した影響により前年並みで着地した。一昨年、首都圏のスーパーではロスが多かったため、当初から数量ベースで前年比95%、売上100%前後で計画しているところが多く、そのトレンド通りの結果となった。抑え気味の発注となったため、昨年はロスがほとんどなかった一方で、売場から早めに商品が無くなり、追加注文を頂く機会も多かった。品切れによるチャンスロスもかなりあったようだ。カテゴリー別では、栗きんとん、黒豆、昆布巻き、たづくりの主力4品の売上は堅調だったが、原料面では、栗の手配が厳しく、昆布巻も年々巻き手の減少により原料手当てが難しくなっている」
―昨年のおせち商材は原価計算が難しかった。
「商談に合わせて早めのタイミングで原価計算が必要で、それなりのコスト増を見越して算出したものの、それ以降に想定を上回るコスト増が何度も押し寄せ、最初に計算していた原価とは大きな乖離が生まれた。昨年のおせち商材は各メーカーが平均5%程の値上げを実施したが、結果的には、約20%の値上げを実施しなければ原価を下回ってしまう状況だった。為替の影響に加え、全てのコストが値上がりする中、特に電気代、ガス代、段ボール、調味料の値上げのインパクトが大きかった。これからさらに、物流費、冷蔵庫などの蔵賃などが上昇する見込みで、さらなる値上げが必要になる。調理食品業界では、これまで通りのことを普通にやっていては、利益が全く出ない状況だ」
―今年のおせちの見通しは。
「特に栗に関しては、円安が最も進んでいた昨年の仕入れのため、大幅な値上げを実施せざるを得ない。栗きんとんの売れ筋は1000円が主流だが、内容量を変えずに単純に価格転嫁すれば、昨年1000円で販売していたものを1300円から1400円で販売する必要がある。おせちは一年の始めに食べる特別な食事なので、美味しくなければいけない。美味しいものを作るためにも、ある程度のコストアップが必要になるということをご理解いただくと共に、内容量と価格のバランスをどうしていくか、今後熟考していかなければならない」
―通常品の値上げ。
「4月より、昨年10月以来の値上げを実施する。これにより収支が少しでも改善することを期待したい。値上げにより、数量はある程度落ちると思うが、社内努力で耐えられる状況ではないので、会社存続のため、やらざるを得ない。もちろん値上げするだけでなく、美味しさの追求など商品のグレードアップにも力を注いでいく。佃煮・煮豆の価格は、長年変わっていない。様々なコストアップにより、調理食品メーカーの経営環境は限界に差し掛かってきており、事業継続が不可能になれば、廃業や倒産が続出してしまう。伝統文化を守るためにも、佃煮・煮豆の価値を見直す時期に来ているのではないか」
―北海道2社廃業の影響は。
「栗きんとんを道内で量産供給できるメーカーがほとんど無くなってしまった。北海道へ本州以南から商品を供給するのは物流費の割合が大きいため難しい。弊社は函館工場があるため、どうにか対応することができる。4月から札幌に営業所を開設し、体制を整える。道内の佃煮、おせち需要にしっかりと応えられるよう、安定供給に努めていきたい」
―今後に向けて。
「環境が良い時は、会社は伸びないと言われる。環境が厳しくなった時に、どうやって生き残るか。社員と一緒に考え、乗り越えていくことで、会社が成長するのではないか。今は厳しいが、この環境はみんな一緒。ここを乗り越えたところが、この業界で生きていけるものと考えている。この厳しさを自分たちの磨き石だと捉え、知恵と行動により荒波を乗り越えていきたい」
【2023(令和5)年4月11日第5125号4面】
第32回調理食品青年交流会東京大会 大会会長 笈川陽平氏
「東京大会」9月12日に
『仲間が集うTOKYO』テーマ
『仲間が集うTOKYO』テーマ
「第32回調理食品青年交流会・東京大会」が9月12日に浅草花劇場で開催される。大会テーマは「『仲間が集うTOKYO』~創り出そう新たな時代~」。当日は大会セレモニーや代表者会議の他、一般社団法人ニッポンおかみさん会会長で協同組合浅草おかみさん会理事長の冨永照子氏による講演会や東京湾を遊覧する屋形船を貸し切っての懇親会などが実施される。大会会長を務めるフードネットワーク関東の笈川陽平代表(有限会社丸安商店専務取締役)に東京大会の見所や佃煮の可能性について聞いた。(藤井大碁)
◇ ◇
ー大会テーマに込めた思い。
「コロナ禍やウクライナ侵攻などにより世界情勢は混乱続きで、原料価格やエネルギー費用など様々なコストが過去類を見ないほど上昇している。想定していない出来事が次々と起こり、今までの常識が通用しない時代が到来している。そうした中、世界各国からたくさんの人が集まる浅草の地に調理食品業界の仲間が集結し、新たな時代に向けて、活発な情報交換を行うと共に、改めて一致団結し協力関係を築きたい、という思いを大会テーマに込めた」
ー東京大会の見所について。
「会場となる浅草花劇場は浅草のシンボルである“花やしき”の施設内に2019年にオープンした新施設で、会場周辺は江戸情緒溢れる浅草の街並みが広がっている。講演会では、浅草おかみさん会の冨永照子理事長にお話をして頂く。冨永理事長は、浅草サンバカーニバルやロンドンバスなど様々な企画により、戦後衰退していた浅草の街を復興させた中心人物として知られる。浅草の街の復興は、コロナ後の復興という意味で、現在と重なる部分も多い。アフターコロナに向けたくさんのヒントが得られるのではないだろうか」
ー懇親会は屋形船で実施する。
「東京湾を遊覧する屋形船は、江戸の風物詩であり、美しい夜景や江戸料理も楽しんで頂くことができる。コロナも落ち着いてきたので、是非、大勢の方に東京大会にご参加頂きたい。準備をしっかり進めて、皆様をおもてなししたいと考えている」
ー丸安商店では佃煮の直売が人気を呼んでいる。
「本社工場では10年前から直売を始めていたが、コロナ禍で地元を散策する人が増え、売上はコロナ前の2倍に増加した。路地裏の目立たない場所にあるが、近隣のマンションに住む20~30代の若い世代が買いに来てくれるようになった。そのきっかけとなっているのが“クランベリークルミ”の存在。店前の看板にクランベリークルミの取扱いを記載してから、若い世代が興味を持って店に寄ってくれるようになった。最初はクランベリークルミのみを購入していったお客様が次第に魚介佃煮の美味しさを知り、リピーターになってくれている。1品500円という値段設定や、お客様自身がSNSで発信してくれる宣伝効果も大きいと思う。今後もクランベリークルミのような若い世代に興味を持ってもらえる商品を開発し、それをきっかけに様々な佃煮の美味しさをたくさんの方に知ってもらいたい」
【2023(令和5)年4月11日第5125号5面】
全調食東海北陸ブロック会 会長 平松賢介氏
消費者ニーズに合わせた販路拡大
6月の研修会はベトナムへ
全調食東海北陸ブロック会の平松賢介会長(平松食品社長)にインタビュー。平松食品では2022年に開催された全国水産加工たべもの展において「Teriyaki Fish Jerky いわし」が水産庁長官賞を受賞するなど「Teriyaki Fish」シリーズが新しいスタイルを提案するつくだ煮として、注目を集めている。平松会長は、コスト増が続く中、消費者のニーズに合わせ、販路の拡大や販売方法の変化を仕掛けていく必要があると語った。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
ー昨年の年末・おせち商戦。
「行動制限の緩和があり、年末・おせち関連の売上は落ち着くかと思ったが、結果的にはまずまずの成績で着地した。弊社で扱う甘露煮の市場はある程度集約されているため、飛び抜けて動くことはないが、にしん甘露煮については、年越しそばの具材として近年コンスタントに推移している。おせちの売上を牽引したのが、地元三河産の本はぜ甘露煮だ。昨年開催した三河湾産マハゼを釣り人から買い取る『ハゼ釣りんピック』のスキームは成功で、今年も実施する。近年、地元漁師の減少により、おせち原料として使用する三河湾産マハゼが不安定になっていたが、この取組により原料確保への道筋が見えた。安定した原料が見込めれば、戦略が組めるため、今後は甘露煮やそれに付随するマーケットへ提案を行っていきたい」
ー2月の節分いわしの動向。
「3月から全体的に5%ほど値上げを実施する、と事前案内していたので、1月と2月に駆け込みがあると予想していたが、あまりその動きは少なく、いわし甘露煮金ごま包みがけん引した。節分いわしは各地域で年々売上を伸ばしており、発祥の地と言われる関西はもとより、東海や関東圏も伸びてきているので、いかに需要に応えていくか、生産体制を整えるかが課題だ」
ー平松食品のブランドを高めている。
「自社商品は『豊川ブランド』を取得しており、地元でも評価が高い。4月4日、イオンモール豊川がオープンし、豊川市観光協会でブース出展するので、自社の商品も陳列してもらっている。これら地元で知名度が上がることで認知度が拡大し、『平松食品で働きたい』と思ってもらえる企業にしていき、求人活動の支援にもつなげていきたい」
ー海外輸出にも力を入れている。
「ベトナムが有望と思っている。継続した経済成長、勤勉な国民性ともに平均年齢も若く、将来有望だ。現在同国のイオン全店に当社の製品が導入され、滞在している日本人に加え、現地の方にも手に取ってもらっている。しかし、水産加工品の輸出には、日本とベトナムの両国で審査登録が必須で、計1年は掛かる。計画的に、戦略的に動く必要があり労力を要求されるが、競合が少ないので、狙い目だと見ている。中国・香港については、人口や経済規模からしてマーケットとしては魅力があるものの、政治的リスクが高く、慎重になる日本企業がより増えるのではないか。イギリスがTPPに加盟するというニュースを見て、ヨーロッパ進出を視野に、新しい可能性が広がると感じた」
ー組合活動について。
「4月の総会のセミナーでは、まるや八丁味噌の社長をお呼びして、八丁味噌の歴史と伝統食品の近代化についてお話しいただく。6月には研修旅行でベトナムに行く。ハノイの日系スーパー・現地系スーパーを視察して、技能実習生の送り出し会社でお話を聞き、JETROのブリーフィングを通じ、現地の熱気を体感する」
ー今後について。
「米シリコンバレー銀行が3月に破綻した。相次ぐ銀行破綻で、最悪の場合、リーマンショック級の金融危機が起きても不思議ではない。景気低迷のシナリオも頭に入れながら、柔軟に対応していく必要がある。消費者の節約志向は高まっているが、メーカーと小売が一体となり、新しい売場を作ることを仕掛けていく必要がある。海外輸出を含め、ある程度リスクを取らなければ、未来の果実は得られないと考えている」
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
ー昨年の年末・おせち商戦。
「行動制限の緩和があり、年末・おせち関連の売上は落ち着くかと思ったが、結果的にはまずまずの成績で着地した。弊社で扱う甘露煮の市場はある程度集約されているため、飛び抜けて動くことはないが、にしん甘露煮については、年越しそばの具材として近年コンスタントに推移している。おせちの売上を牽引したのが、地元三河産の本はぜ甘露煮だ。昨年開催した三河湾産マハゼを釣り人から買い取る『ハゼ釣りんピック』のスキームは成功で、今年も実施する。近年、地元漁師の減少により、おせち原料として使用する三河湾産マハゼが不安定になっていたが、この取組により原料確保への道筋が見えた。安定した原料が見込めれば、戦略が組めるため、今後は甘露煮やそれに付随するマーケットへ提案を行っていきたい」
ー2月の節分いわしの動向。
「3月から全体的に5%ほど値上げを実施する、と事前案内していたので、1月と2月に駆け込みがあると予想していたが、あまりその動きは少なく、いわし甘露煮金ごま包みがけん引した。節分いわしは各地域で年々売上を伸ばしており、発祥の地と言われる関西はもとより、東海や関東圏も伸びてきているので、いかに需要に応えていくか、生産体制を整えるかが課題だ」
ー平松食品のブランドを高めている。
「自社商品は『豊川ブランド』を取得しており、地元でも評価が高い。4月4日、イオンモール豊川がオープンし、豊川市観光協会でブース出展するので、自社の商品も陳列してもらっている。これら地元で知名度が上がることで認知度が拡大し、『平松食品で働きたい』と思ってもらえる企業にしていき、求人活動の支援にもつなげていきたい」
ー海外輸出にも力を入れている。
「ベトナムが有望と思っている。継続した経済成長、勤勉な国民性ともに平均年齢も若く、将来有望だ。現在同国のイオン全店に当社の製品が導入され、滞在している日本人に加え、現地の方にも手に取ってもらっている。しかし、水産加工品の輸出には、日本とベトナムの両国で審査登録が必須で、計1年は掛かる。計画的に、戦略的に動く必要があり労力を要求されるが、競合が少ないので、狙い目だと見ている。中国・香港については、人口や経済規模からしてマーケットとしては魅力があるものの、政治的リスクが高く、慎重になる日本企業がより増えるのではないか。イギリスがTPPに加盟するというニュースを見て、ヨーロッパ進出を視野に、新しい可能性が広がると感じた」
ー組合活動について。
「4月の総会のセミナーでは、まるや八丁味噌の社長をお呼びして、八丁味噌の歴史と伝統食品の近代化についてお話しいただく。6月には研修旅行でベトナムに行く。ハノイの日系スーパー・現地系スーパーを視察して、技能実習生の送り出し会社でお話を聞き、JETROのブリーフィングを通じ、現地の熱気を体感する」
ー今後について。
「米シリコンバレー銀行が3月に破綻した。相次ぐ銀行破綻で、最悪の場合、リーマンショック級の金融危機が起きても不思議ではない。景気低迷のシナリオも頭に入れながら、柔軟に対応していく必要がある。消費者の節約志向は高まっているが、メーカーと小売が一体となり、新しい売場を作ることを仕掛けていく必要がある。海外輸出を含め、ある程度リスクを取らなければ、未来の果実は得られないと考えている」
【2023(令和5)年4月11日第5125号7面】
株式会社おかわりJAPAN 代表取締役社長 長船邦彦氏
「ご飯のお供専門家」としてECや催事で“体験”伝える
「ご飯のお供専門家」として数々のメディアに出演する、株式会社おかわりJAPAN代表取締役社長の長船邦彦氏。ご飯好きが高じて趣味としてブログを始めたが、いつしか「ご飯の素晴らしさを知ってほしい」という夢を持つようになり、独立。詰め合わせセットを販売するECサイト運営やメディア出演、イベント企画へ取り組んでいる。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ーおかわりJAPANとは。
「私は子供の頃から食べることが大好きで、食品会社に勤めながら、趣味として食べたものを書き留めておくために始めたブログが始まりです。続けていくうちに、地域差や共通点が見えるようになってきて、それを体系化するようになりました。すると、多くの方に見て頂き、メディアからも声がかかるようになりました。勤め先にも副業として認めていただいていたのですが、活動に本格的に取り組むため、2021年10月に独立起業しました」
ー独立のきっかけは。
「地方の小規模メーカーの多くは発信が苦手で、せっかく良いものを作っても見つけてもらえないケースがとても多いです。中には廃業される会社もあります。私が紹介して注文が増えたと感謝のお言葉を頂くこともあります。日本の隠れた名品をもっと多くの方に知って欲しい、ご飯の素晴らしさを伝えたいと考えて独立しました。現在はEC、メディア出演、イベント企画の3本を軸としています」
ーECサイトについて。
「色々なコンセプトを立てて、詰め合わせセットを販売しています。商品単体ではなく“体験”を販売しているイメージです。オリジナル商品にはあまり取り組まず、今ある地方の美味しいものを紹介していくというスタンスを大切にしていきたいと考えています」
ーメディア出演の状況は。
「昨年は約30番組に出演しました。以前は会社員としての仕事優先で出演をお断りするケースもありましたが、今後は積極的に出演できそうです。例年9~11月の新米時期にオファーが集中して、その時期にはブログやECのアクセスも倍増しています」
ーイベントの計画は。
「全国各地で実施していく計画中です。3月には名古屋の名鉄百貨店本店TSUTAYA BOOKSTOREシェアラウンジで、美味しいお米とご飯のお供を楽しむセミナー形式のイベントを開催しました。地元米穀卸の㈱米由様、AKOMEYA TOKYO様にもご協力頂いて、お米を色々な炊飯器で食べ比べたり、AKOMEYA様の商品の魅力を解説したりと“体験”を重視したイベントとしました」
ー今後について。
「これまでは食べて美味しいものを紹介していくのがメインでした。今後は生産者の現場や思いを伝えることが出来れば“体験”の質も高まっていくと思います。共感いただけるメーカー様がいらっしゃれば、ぜひお声がけください」
◇ ◇
ーおかわりJAPANとは。
「私は子供の頃から食べることが大好きで、食品会社に勤めながら、趣味として食べたものを書き留めておくために始めたブログが始まりです。続けていくうちに、地域差や共通点が見えるようになってきて、それを体系化するようになりました。すると、多くの方に見て頂き、メディアからも声がかかるようになりました。勤め先にも副業として認めていただいていたのですが、活動に本格的に取り組むため、2021年10月に独立起業しました」
ー独立のきっかけは。
「地方の小規模メーカーの多くは発信が苦手で、せっかく良いものを作っても見つけてもらえないケースがとても多いです。中には廃業される会社もあります。私が紹介して注文が増えたと感謝のお言葉を頂くこともあります。日本の隠れた名品をもっと多くの方に知って欲しい、ご飯の素晴らしさを伝えたいと考えて独立しました。現在はEC、メディア出演、イベント企画の3本を軸としています」
ーECサイトについて。
「色々なコンセプトを立てて、詰め合わせセットを販売しています。商品単体ではなく“体験”を販売しているイメージです。オリジナル商品にはあまり取り組まず、今ある地方の美味しいものを紹介していくというスタンスを大切にしていきたいと考えています」
ーメディア出演の状況は。
「昨年は約30番組に出演しました。以前は会社員としての仕事優先で出演をお断りするケースもありましたが、今後は積極的に出演できそうです。例年9~11月の新米時期にオファーが集中して、その時期にはブログやECのアクセスも倍増しています」
ーイベントの計画は。
「全国各地で実施していく計画中です。3月には名古屋の名鉄百貨店本店TSUTAYA BOOKSTOREシェアラウンジで、美味しいお米とご飯のお供を楽しむセミナー形式のイベントを開催しました。地元米穀卸の㈱米由様、AKOMEYA TOKYO様にもご協力頂いて、お米を色々な炊飯器で食べ比べたり、AKOMEYA様の商品の魅力を解説したりと“体験”を重視したイベントとしました」
ー今後について。
「これまでは食べて美味しいものを紹介していくのがメインでした。今後は生産者の現場や思いを伝えることが出来れば“体験”の質も高まっていくと思います。共感いただけるメーカー様がいらっしゃれば、ぜひお声がけください」
【2023(令和5)年4月11日第5125号8面】
おかわりJAPAN
4月11日号 栃木特集インタビュー
栃木県漬物工業協同組合 理事長 秋本 薫氏
栃木は少数精鋭で共同体
加工技術を磨き明るい未来へ
3月に開催された総会で留任が決まり、6期目を迎えた栃木県漬物工業協同組合の秋本薫理事長(株式会社アキモ代表取締役社長、栃木県宇都宮市)にインタビュー。6期目の抱負や今後の活動方針、10月17日に開催される全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会について話を聞いた。漬物産業や農業はIT化が遅れていることを指摘した上で「逆に言えばIT化を進められる余地があるので伸び代があるということ」と明言し、改めて漬物の魅力や可能性を強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐3月の総会で留任し、理事長として6期目を迎えた。
「理事長を10年務めたことになるが、長くは感じなかった。諸先輩方をはじめ、組合員の方々、業界の方に支えられて組合活動を行うことができてとても感謝している。自分たちの役目は次の世代にバトンを渡すこと。そのようなことも考えながら、活動していきたいと考えている」
‐組合員が減少している。
「25年前に栃木県で1回目の青年部会全国大会を開催したのだが、当時の組合員数は43社だった。現在は14社で、業者数は大幅に減少している。残った企業についてはそれぞれの個性や特徴を活かしながら、しっかりと事業を行っている。都道府県別の漬物出荷金額を見ると、栃木県は毎年5位以上に位置している。まさに少数精鋭といったところで、時代が大きく変化する中でも協力関係を築き、共同体として進んでいきたい」
‐栃木の魅力は。
「首都圏に位置し、消費地である東京と距離が近いことが大きい。東西南北を連携する高速道路をはじめ、新幹線を利用すれば通勤圏内でもある。開発が進んでいる宇都宮の発展、日光や鬼怒川などの観光地、いちごを代表とする農産物など全国に誇るものが数多くある。漬物においても日本一の生産量を誇る酢漬の他、バラエティー豊かな漬物を製造している。売り先も量販店から外食向けの業務用、観光土産と幅広く、色々なものが集約されている。全国大会では餃子をテーマにした記念講演を開催させていただくので、楽しみにしていただきたい」
‐今後の漬物業界について。
「漬物は食物繊維を効率良く摂取できるサプリメントのようなもの。世界の人は日本食を健康食品だと認知していて、その中には日本が誇るべき食品である漬物も含まれている、ということをPRしていく必要がある。漬物産業と日本の農業はIT化が遅れているのだが、逆に言えばIT化を進められる余地があるので伸び代があるということ。農業の発展とともに加工技術を磨き、漬物にこだわらず野菜を美味しく楽しく健康的に食べられるものに加工できれば、新たな市場が生まれる。農業との関りを強くすれば行政の支援も期待でき、国民の健康と食料自給率の向上に貢献することができる。ネガティブな意見も耳にするが、私は明るい未来しか想像できない」
【2023(令和5)年4月11日第5125号12面】
加工技術を磨き明るい未来へ
3月に開催された総会で留任が決まり、6期目を迎えた栃木県漬物工業協同組合の秋本薫理事長(株式会社アキモ代表取締役社長、栃木県宇都宮市)にインタビュー。6期目の抱負や今後の活動方針、10月17日に開催される全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会について話を聞いた。漬物産業や農業はIT化が遅れていることを指摘した上で「逆に言えばIT化を進められる余地があるので伸び代があるということ」と明言し、改めて漬物の魅力や可能性を強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐3月の総会で留任し、理事長として6期目を迎えた。
「理事長を10年務めたことになるが、長くは感じなかった。諸先輩方をはじめ、組合員の方々、業界の方に支えられて組合活動を行うことができてとても感謝している。自分たちの役目は次の世代にバトンを渡すこと。そのようなことも考えながら、活動していきたいと考えている」
‐組合員が減少している。
「25年前に栃木県で1回目の青年部会全国大会を開催したのだが、当時の組合員数は43社だった。現在は14社で、業者数は大幅に減少している。残った企業についてはそれぞれの個性や特徴を活かしながら、しっかりと事業を行っている。都道府県別の漬物出荷金額を見ると、栃木県は毎年5位以上に位置している。まさに少数精鋭といったところで、時代が大きく変化する中でも協力関係を築き、共同体として進んでいきたい」
‐栃木の魅力は。
「首都圏に位置し、消費地である東京と距離が近いことが大きい。東西南北を連携する高速道路をはじめ、新幹線を利用すれば通勤圏内でもある。開発が進んでいる宇都宮の発展、日光や鬼怒川などの観光地、いちごを代表とする農産物など全国に誇るものが数多くある。漬物においても日本一の生産量を誇る酢漬の他、バラエティー豊かな漬物を製造している。売り先も量販店から外食向けの業務用、観光土産と幅広く、色々なものが集約されている。全国大会では餃子をテーマにした記念講演を開催させていただくので、楽しみにしていただきたい」
‐今後の漬物業界について。
「漬物は食物繊維を効率良く摂取できるサプリメントのようなもの。世界の人は日本食を健康食品だと認知していて、その中には日本が誇るべき食品である漬物も含まれている、ということをPRしていく必要がある。漬物産業と日本の農業はIT化が遅れているのだが、逆に言えばIT化を進められる余地があるので伸び代があるということ。農業の発展とともに加工技術を磨き、漬物にこだわらず野菜を美味しく楽しく健康的に食べられるものに加工できれば、新たな市場が生まれる。農業との関りを強くすれば行政の支援も期待でき、国民の健康と食料自給率の向上に貢献することができる。ネガティブな意見も耳にするが、私は明るい未来しか想像できない」
【2023(令和5)年4月11日第5125号12面】
全日本漬物協同組合連合会青年部会 第41回全国大会栃木大会 大会会長 遠藤栄一氏
青年部員4名で栃木大会開催
適正価格化の意識共有へ
3月15日に開催された栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の総会で副理事長に就任した遠藤食品株式会社(栃木県佐野市下彦間町)の遠藤栄一社長にインタビュー。同組合青年部部長でもある遠藤社長は、10月17日に開催される全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会の大会会長として業界を盛り上げる役割を担っている。遠藤社長はSDGsをテーマに青年部員4名で開催する栃木大会を通して適正価格化の意識共有を図り、全国に元気と勇気を発信する意向を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐全国大会の会場となる宇都宮の開発が進んでいる。
「宇都宮駅東口地区整備事業によって誕生した『ウツノミヤテラス』は、使いやすさと上質さを兼ね備えたライフスタイル型商業施設で、関東最大級の収容人数を誇るライトキューブ宇都宮の他、緑あふれる広場などを備える宇都宮の新たなランドマークとなる大型複合施設。次世代型路面電車『LRT』の運行も今年8月にスタートする。栃木には日本酒、焼酎、ワインなどのお酒や日光東照宮、鬼怒川温泉、足利学校などの観光地、名物の餃子や生産量日本一を誇るいちごなどがある。多くの方に進化した栃木の魅力や良さを伝えたい」
‐全国大会で伝えたいことは。
「青年部会のメンバーは業界の未来を担っている。そのような方たちに何かを学んでいただきたい、ということではなく全国の方たちとの出会いの場を提供したいと考えている。異なる風土や地域の方が集まれば、自分にはなかった発想やアイデアに触れることができる。人脈だけでなく固定されがちな考え方を広げるチャンスになる。それこそが全国大会の大きな意義だと思っているので、多くの方にお越しいただきたい」
‐全国の青年部会員と共有したい考えは。
「原材料をはじめ、調味料や包装資材の他、物流費やエネルギーコストも上昇し続けている。本来ならば価格転嫁をスムーズに行う必要があるのだが、漬物業界は思うように進んでいないように見える。持続可能な会社経営、未来ある業界を作っていくためには適正価格を追求する必要がある。物価が上昇し、消費者の節約志向は以前にも増して高まっているが、消費者に支持される商品を提供し続けることがメーカーの使命で、価格競争は誰のためにもならない。全国大会はそのようなことを意識していただくきっかになれば良いと思っている」
‐青年部員4名で栃木大会を開催する。
「青年部は私と菅野嘉弘実行委員長(すが野専務)、新規入会2名の合計4名だが、不安はない。秋本薫理事長にはいつも貴重な意見をいただいており、企画や運営の面でも協力をいただいている。月1回程度のペースで打合せを行っているが、人数が少ない分、スピーディーに準備を進めることができている。初のオンライン開催となった新潟大会、岸田首相の挨拶など素晴らしい内容を披露した広島大会と良い流れで迎える栃木大会は、SDGsに対応した取組を行いながら『~愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ~』をテーマに開催する。少ない人数でも開催できる、ということを見ていただき、全国の方に元気と勇気を発信できればと思っている」
【2023(令和5)年4月11日第5125号10面】
適正価格化の意識共有へ
3月15日に開催された栃木県漬物工業協同組合(秋本薫理事長)の総会で副理事長に就任した遠藤食品株式会社(栃木県佐野市下彦間町)の遠藤栄一社長にインタビュー。同組合青年部部長でもある遠藤社長は、10月17日に開催される全日本漬物協同組合連合会青年部会第41回全国大会栃木大会の大会会長として業界を盛り上げる役割を担っている。遠藤社長はSDGsをテーマに青年部員4名で開催する栃木大会を通して適正価格化の意識共有を図り、全国に元気と勇気を発信する意向を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐全国大会の会場となる宇都宮の開発が進んでいる。
「宇都宮駅東口地区整備事業によって誕生した『ウツノミヤテラス』は、使いやすさと上質さを兼ね備えたライフスタイル型商業施設で、関東最大級の収容人数を誇るライトキューブ宇都宮の他、緑あふれる広場などを備える宇都宮の新たなランドマークとなる大型複合施設。次世代型路面電車『LRT』の運行も今年8月にスタートする。栃木には日本酒、焼酎、ワインなどのお酒や日光東照宮、鬼怒川温泉、足利学校などの観光地、名物の餃子や生産量日本一を誇るいちごなどがある。多くの方に進化した栃木の魅力や良さを伝えたい」
‐全国大会で伝えたいことは。
「青年部会のメンバーは業界の未来を担っている。そのような方たちに何かを学んでいただきたい、ということではなく全国の方たちとの出会いの場を提供したいと考えている。異なる風土や地域の方が集まれば、自分にはなかった発想やアイデアに触れることができる。人脈だけでなく固定されがちな考え方を広げるチャンスになる。それこそが全国大会の大きな意義だと思っているので、多くの方にお越しいただきたい」
‐全国の青年部会員と共有したい考えは。
「原材料をはじめ、調味料や包装資材の他、物流費やエネルギーコストも上昇し続けている。本来ならば価格転嫁をスムーズに行う必要があるのだが、漬物業界は思うように進んでいないように見える。持続可能な会社経営、未来ある業界を作っていくためには適正価格を追求する必要がある。物価が上昇し、消費者の節約志向は以前にも増して高まっているが、消費者に支持される商品を提供し続けることがメーカーの使命で、価格競争は誰のためにもならない。全国大会はそのようなことを意識していただくきっかになれば良いと思っている」
‐青年部員4名で栃木大会を開催する。
「青年部は私と菅野嘉弘実行委員長(すが野専務)、新規入会2名の合計4名だが、不安はない。秋本薫理事長にはいつも貴重な意見をいただいており、企画や運営の面でも協力をいただいている。月1回程度のペースで打合せを行っているが、人数が少ない分、スピーディーに準備を進めることができている。初のオンライン開催となった新潟大会、岸田首相の挨拶など素晴らしい内容を披露した広島大会と良い流れで迎える栃木大会は、SDGsに対応した取組を行いながら『~愛を込めて、自然・健康、そして、持続可能な開発へ~』をテーマに開催する。少ない人数でも開催できる、ということを見ていただき、全国の方に元気と勇気を発信できればと思っている」
【2023(令和5)年4月11日第5125号10面】
4月1日号 高菜漬特集 トップに聞く
オギハラ食品株式会社 代表取締役社長 荻原浩幸氏
4年連続不作で原料不足 付加価値ある商品作り重要
大正5年創業、オギハラ食品株式会社(荻原浩幸社長、福岡県大牟田市)は、創業100年を超える高菜漬の老舗メーカー。荻原社長は、九州産高菜原料が不足する中、付加価値のある商品作りに取り組むことが重要だと強調する。
(小林悟空)
◇ ◇
‐高菜の原料状況は。
「収穫は4月上旬に終わる予定で、今のペースのままなら4年連続の減収になりそうだ。1月25日に『最強寒波』が日本を襲い、九州でも氷点下になり降雪があった。高菜の外葉が霜焼けになり生育も悪く、全体的に小株傾向。厳しい作柄が続いているため、大切に売っていく一年間となっていきそうだ」
‐対応は。
「原料価格を上げ、儲かる農業を実現してもらうのが最も根本的な解決方法であり、そのためには付加価値のある商品を作り、我々メーカーから生産者へ還元を図っていかなければいけない。付加価値とは何かを考える良い例となるのがごま高菜。当社は約30年前に『元祖三池ごまたかな』をいち早く商品化したが、その背景には当時は姿物が主流であったため、刻んでごまをまぶすことで差別化する狙いがあったようだ。発売当初は苦労があったようだが、今では刻み高菜の方が主流となるほど定着している。流行を捉えることは重要だが、時には自ら革新を生み出そうとする気概も必要という好例だ」
‐販促活動について。
「原料の不足傾向が続いているので、積極的な販路拡大には踏み切れない。コロナで減っていた商談も再開してきたので、歯がゆい思いをしている。その分、消費者向けの発信や、社内体制の整備に力を入れている。消費者へ向けて力を入れているのがSNS。宣伝ではなく、まずは高菜や当社に興味を持ってもらうためのレシピ提案や、製造風景の公開を行っている。一気に話題にならなくても、コツコツと蓄積していけば会社の財産になると考えている」
‐社内体制の整備は。
「働く目的はお金や向上心などそれぞれだが、一言でまとめると幸せになることに行き着く。社長就任して5年目の年にコロナ禍となって以来このことを意識するようになり、業績第一の姿勢から『志』の経営へシフトしている。その指針となるのが経営理念『伝統を守り、革新を続け、食文化に貢献する。高菜漬の可能性を追求し、さらにおいしく、食生活をもっと豊かに』。3月25日に社内で経営方針発表を行い、組織として目指すべき姿を共有した」
‐高菜漬への思い。
「高菜漬作りは決して楽な仕事ではなく、機械やマニュアルがあっても、それ任せではなく高菜に対して理解を持って現場で判断していかなければ完璧な仕事は出来ない。今期の全社目標は『スマイル』。高菜漬に対し誇りと喜びを持って笑顔で働ける職場を作れば、自然とパフォーマンスが上がり、結果として業績にも繋がると信じている。当社の頑張りが原料生産者や関連する全ての人々も笑顔に繋がることを胸に、努力していく」
【2023(令和5)年4月1日第5124号7面】
電子版「九州うまかモン」
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/254/
大正5年創業、オギハラ食品株式会社(荻原浩幸社長、福岡県大牟田市)は、創業100年を超える高菜漬の老舗メーカー。荻原社長は、九州産高菜原料が不足する中、付加価値のある商品作りに取り組むことが重要だと強調する。
(小林悟空)
◇ ◇
‐高菜の原料状況は。
「収穫は4月上旬に終わる予定で、今のペースのままなら4年連続の減収になりそうだ。1月25日に『最強寒波』が日本を襲い、九州でも氷点下になり降雪があった。高菜の外葉が霜焼けになり生育も悪く、全体的に小株傾向。厳しい作柄が続いているため、大切に売っていく一年間となっていきそうだ」
‐対応は。
「原料価格を上げ、儲かる農業を実現してもらうのが最も根本的な解決方法であり、そのためには付加価値のある商品を作り、我々メーカーから生産者へ還元を図っていかなければいけない。付加価値とは何かを考える良い例となるのがごま高菜。当社は約30年前に『元祖三池ごまたかな』をいち早く商品化したが、その背景には当時は姿物が主流であったため、刻んでごまをまぶすことで差別化する狙いがあったようだ。発売当初は苦労があったようだが、今では刻み高菜の方が主流となるほど定着している。流行を捉えることは重要だが、時には自ら革新を生み出そうとする気概も必要という好例だ」
‐販促活動について。
「原料の不足傾向が続いているので、積極的な販路拡大には踏み切れない。コロナで減っていた商談も再開してきたので、歯がゆい思いをしている。その分、消費者向けの発信や、社内体制の整備に力を入れている。消費者へ向けて力を入れているのがSNS。宣伝ではなく、まずは高菜や当社に興味を持ってもらうためのレシピ提案や、製造風景の公開を行っている。一気に話題にならなくても、コツコツと蓄積していけば会社の財産になると考えている」
‐社内体制の整備は。
「働く目的はお金や向上心などそれぞれだが、一言でまとめると幸せになることに行き着く。社長就任して5年目の年にコロナ禍となって以来このことを意識するようになり、業績第一の姿勢から『志』の経営へシフトしている。その指針となるのが経営理念『伝統を守り、革新を続け、食文化に貢献する。高菜漬の可能性を追求し、さらにおいしく、食生活をもっと豊かに』。3月25日に社内で経営方針発表を行い、組織として目指すべき姿を共有した」
‐高菜漬への思い。
「高菜漬作りは決して楽な仕事ではなく、機械やマニュアルがあっても、それ任せではなく高菜に対して理解を持って現場で判断していかなければ完璧な仕事は出来ない。今期の全社目標は『スマイル』。高菜漬に対し誇りと喜びを持って笑顔で働ける職場を作れば、自然とパフォーマンスが上がり、結果として業績にも繋がると信じている。当社の頑張りが原料生産者や関連する全ての人々も笑顔に繋がることを胸に、努力していく」
【2023(令和5)年4月1日第5124号7面】
電子版「九州うまかモン」
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/254/
3月21日号 梅特集
中田食品株式会社 代表取締役社長 中田吉昭氏
今年度は増収の見通し
SNSで若年層にアプローチ
SNSで若年層にアプローチ
中田食品株式会社(和歌山県田辺市)の中田吉昭社長にインタビュー。今年の梅の開花状況きや梅干しの売れ行きなどについて話を聞いた。コロナ禍でやや低調だった売れ行きは底を打ち、今年度の業績(3月決算)については増収で着地する見通し。また、若い世代へのアプローチやファン作りのツールとしてSNSによる情報発信に手応えを感じており、今後も積極的に取り組んでいく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――今年の梅の開花状況は。
「開花状況は例年並みとなっている。2月の半ばから20日くらいに満開期を迎えた。開花後は寒い日が続かなかったので、ミツバチも良く飛んでいた。色々な品種の花が一気に咲いた感じで、南高の交配にもつながったと思う。ここまでは順調にきている」
――2022年の梅干しの売れ行きと産地の原料在庫状況は。
「量販店の売れ行きはPOSデータの通り、数%下がっている。1年を通して見ると、夏は梅雨明けが早く、暑い日も多かったので売れ行きは良かったが、夏以外はやや低調で、全体でも5%くらいのマイナスとなっていると思う。売れ筋は低級原料の普及品で、中国産の梅も根強い人気がある。昨年は円安の影響があったので値上げを実施したが、値上げしても売れ行きは変わらなかった。ただ、今後は物価が上昇している中で消費者の生活防衛意識がますます高まっていくため、梅干し業界はさらに厳しい状況になると予想している」
――ここ数年の御社の業績について。
「弊社の数年間の売上げは、2018年にテレビ番組と猛暑の影響で特需が発生し、弊社も1年間で約20億円伸びたが、その翌年は紀州梅が凶作となり原料価格高騰で、値上げを余儀なくされ売上が6%ほど落ちた。2020年からのコロナ禍に於いて、売上げは若干落ちたが減少を最小限に抑える努力を続け、本年度は売上げを維持して前年と変わらない着地を予想している」
――在庫状況と値上げの動きについて。
「在庫状況は各社で異なるが、紀州は2年続けて良い作柄となっていることもあり、産地在庫としては余裕がある状況。販売面が課題となる。昨年は一昨年と比較して作柄はやや悪かったが、原料価格が落ち着いていたこともあり製品価格も値上げにはならなかった。包装資材、調味料、段ボールの他、物流費や電気代など、様々な製造コストが上がっているが、原料価格が安定していることと企業努力によって吸収している形だ」
――若年層へのアプローチについて。
「梅干し業界はこれからも買い続けていただくための努力をしていく必要がある。梅干しの主な購買層は中高年世代だが、梅干しが好きな若い人も多い。2月11日に和歌山市で開催された東京ガールズコレクション(TGC)で、ケータリングのブースを出したところ、モデルさんたちから大変好評をいただいた。若い女性への発信力が大きい人気モデルやタレントが『梅干しが美味しい!大好き』とSNSにアップしてくれて大きな反響を呼んでいる。若い人は梅干しが嫌い、梅干しを食べない、といったイメージを持っている人も多いと思うが、実際はそうではないことがうかがえる。そのような意味でも潜在需要はまだまだあると思っている」
――今年1月に和歌山の梅干しメーカーが発信したSNSの情報が話題となった。
「かなり大きな話題になり、改めてそういう時代なのか、ということを実感した。表現の仕方には注意が必要だが、個人的には梅干しが話題になったことはポジティブに捉えている。弊社もSNSによる情報発信に取り組んでいるが、着実にファンが増えていると感じている。今後も上手く活用して梅と弊社の魅力を発信していきたいと考えている」
◇ ◇
――今年の梅の開花状況は。
「開花状況は例年並みとなっている。2月の半ばから20日くらいに満開期を迎えた。開花後は寒い日が続かなかったので、ミツバチも良く飛んでいた。色々な品種の花が一気に咲いた感じで、南高の交配にもつながったと思う。ここまでは順調にきている」
――2022年の梅干しの売れ行きと産地の原料在庫状況は。
「量販店の売れ行きはPOSデータの通り、数%下がっている。1年を通して見ると、夏は梅雨明けが早く、暑い日も多かったので売れ行きは良かったが、夏以外はやや低調で、全体でも5%くらいのマイナスとなっていると思う。売れ筋は低級原料の普及品で、中国産の梅も根強い人気がある。昨年は円安の影響があったので値上げを実施したが、値上げしても売れ行きは変わらなかった。ただ、今後は物価が上昇している中で消費者の生活防衛意識がますます高まっていくため、梅干し業界はさらに厳しい状況になると予想している」
――ここ数年の御社の業績について。
「弊社の数年間の売上げは、2018年にテレビ番組と猛暑の影響で特需が発生し、弊社も1年間で約20億円伸びたが、その翌年は紀州梅が凶作となり原料価格高騰で、値上げを余儀なくされ売上が6%ほど落ちた。2020年からのコロナ禍に於いて、売上げは若干落ちたが減少を最小限に抑える努力を続け、本年度は売上げを維持して前年と変わらない着地を予想している」
――在庫状況と値上げの動きについて。
「在庫状況は各社で異なるが、紀州は2年続けて良い作柄となっていることもあり、産地在庫としては余裕がある状況。販売面が課題となる。昨年は一昨年と比較して作柄はやや悪かったが、原料価格が落ち着いていたこともあり製品価格も値上げにはならなかった。包装資材、調味料、段ボールの他、物流費や電気代など、様々な製造コストが上がっているが、原料価格が安定していることと企業努力によって吸収している形だ」
――若年層へのアプローチについて。
「梅干し業界はこれからも買い続けていただくための努力をしていく必要がある。梅干しの主な購買層は中高年世代だが、梅干しが好きな若い人も多い。2月11日に和歌山市で開催された東京ガールズコレクション(TGC)で、ケータリングのブースを出したところ、モデルさんたちから大変好評をいただいた。若い女性への発信力が大きい人気モデルやタレントが『梅干しが美味しい!大好き』とSNSにアップしてくれて大きな反響を呼んでいる。若い人は梅干しが嫌い、梅干しを食べない、といったイメージを持っている人も多いと思うが、実際はそうではないことがうかがえる。そのような意味でも潜在需要はまだまだあると思っている」
――今年1月に和歌山の梅干しメーカーが発信したSNSの情報が話題となった。
「かなり大きな話題になり、改めてそういう時代なのか、ということを実感した。表現の仕方には注意が必要だが、個人的には梅干しが話題になったことはポジティブに捉えている。弊社もSNSによる情報発信に取り組んでいるが、着実にファンが増えていると感じている。今後も上手く活用して梅と弊社の魅力を発信していきたいと考えている」
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合 理事長 殿畑雅敏氏
利益の確保が課題
農家とともに歩み産地を維持
紀州みなべ梅干協同組合殿畑雅敏理事長(株式会社トノハタ社長)にインタビュー。梅干しの売れ行きや在庫状況などについて話を聞いた。ここ2年は良い作柄が続いており、今年も良好な開花状況となっている。原料在庫は問題ない状況だが、紀州梅産地も農家の後継ぎが課題となっている。殿畑理事長は農家の収入の安定化を図ることが産地の維持につながると指摘。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示す必要性を強調した。
◇ ◇
――梅干しの売れ行きは。
「全般的に良くない。昨年から物価高が続き、日常生活に必要なものかどうかの線引きが厳しくなったことが影響していると思う。中国産の梅は円安の影響で仕入れ価格が上がっている。それに加え、製造コストも上昇しており、各社値上げを行っている。国産についても製造コストは上がっているものの、原料に余裕があり価格も安定しているため価格改定の動きにはなっていない。ただ、調味資材、物流費、電気代などの製造コストが短いサイクルで上昇を続けており、利益の確保は大きな課題となっている」
――中国と紀州の開花状況は。
「中国の主産地は6、7割作という話も聞いているが、紀州は順調に開花している。日本の作柄は中国と連動することが多いので、終わってみないとはっきりとしたことは分からない。今の時点で一喜一憂することはあまり意味がない」
――農家の生産意欲について。
「農家は価格の安定を求めている。一昨年は豊作で、昨年は平年作となったが、原料価格が大きく下がることはなかったのでこの2年の収入は良かったと思う。今年は作柄にもよるが、極端な動きにはならないと予想しており、そのような意味では安定した価格で推移すると見ている。紀州も農家の後継ぎの問題が浮上しているが、後を継いでもらうためにも価格の安定化を図っていかなければならない。過去には再生産が難しい価格となったこともあるが、農家、加工業者、流通、消費者のみんなが納得できる価格帯を模索していくことが重要だ」
――今年は価格訴求の動きが出てくる可能性もある。
「各社自由競争の下で経営されているので、コメントは控えたい。紀州梅産地では豊作時に価格が下がり、不作時に価格が上がる、ということが繰り返されてきた。農家の後継者がしっかりと後を継いで産地を維持していくためには原料価格の安定が必要。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示さなければ産地が30年、50年、100年後まで続くことはない。年によって作柄が異なるので、多少の変動はあったとしても目先の数字のために動くのではなく、5年、10年といったスパンでとらえる必要がある」
――今後の見通しは。
「予報では今年の夏は暑くなるとのことなので、梅干しが売れる環境になることを期待している。また、5月には新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行するため、より外出機会が増えることが想定される。暑い日の外出は熱中症対策が必要になってくるため、梅干しが活躍する場は増えると見ている」
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合の加盟社一覧
トノハタ HP
◇ ◇
――梅干しの売れ行きは。
「全般的に良くない。昨年から物価高が続き、日常生活に必要なものかどうかの線引きが厳しくなったことが影響していると思う。中国産の梅は円安の影響で仕入れ価格が上がっている。それに加え、製造コストも上昇しており、各社値上げを行っている。国産についても製造コストは上がっているものの、原料に余裕があり価格も安定しているため価格改定の動きにはなっていない。ただ、調味資材、物流費、電気代などの製造コストが短いサイクルで上昇を続けており、利益の確保は大きな課題となっている」
――中国と紀州の開花状況は。
「中国の主産地は6、7割作という話も聞いているが、紀州は順調に開花している。日本の作柄は中国と連動することが多いので、終わってみないとはっきりとしたことは分からない。今の時点で一喜一憂することはあまり意味がない」
――農家の生産意欲について。
「農家は価格の安定を求めている。一昨年は豊作で、昨年は平年作となったが、原料価格が大きく下がることはなかったのでこの2年の収入は良かったと思う。今年は作柄にもよるが、極端な動きにはならないと予想しており、そのような意味では安定した価格で推移すると見ている。紀州も農家の後継ぎの問題が浮上しているが、後を継いでもらうためにも価格の安定化を図っていかなければならない。過去には再生産が難しい価格となったこともあるが、農家、加工業者、流通、消費者のみんなが納得できる価格帯を模索していくことが重要だ」
――今年は価格訴求の動きが出てくる可能性もある。
「各社自由競争の下で経営されているので、コメントは控えたい。紀州梅産地では豊作時に価格が下がり、不作時に価格が上がる、ということが繰り返されてきた。農家の後継者がしっかりと後を継いで産地を維持していくためには原料価格の安定が必要。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示さなければ産地が30年、50年、100年後まで続くことはない。年によって作柄が異なるので、多少の変動はあったとしても目先の数字のために動くのではなく、5年、10年といったスパンでとらえる必要がある」
――今後の見通しは。
「予報では今年の夏は暑くなるとのことなので、梅干しが売れる環境になることを期待している。また、5月には新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行するため、より外出機会が増えることが想定される。暑い日の外出は熱中症対策が必要になってくるため、梅干しが活躍する場は増えると見ている」
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合の加盟社一覧
トノハタ HP
紀州田辺梅干協同組合 理事長 大谷喜則氏
春夏に向けて販売強化
求められるイノベーション
紀州田辺梅干協同組合の大谷喜則理事長にインタビュー。梅業界の現状や今後の見通しなどについて話を聞いた。現在、売場で主流となっている調味梅は市場に登場してから約50年が経っており、その歴史とともに歩んできた大谷理事長は梅産業の更なる発展に向けてイノベーションの必要性を指摘。若い世代が力を発揮できる環境を整え、持続可能な梅産業を構築していく意向を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――梅の開花状況は。
「今年は気温が低く、花が咲くタイミングがやや遅くなった。紀州では開花が遅い年は豊作になると言われており、気候も安定しているので現時点では良い作柄になると予想されている」
――梅干しの売れ行きは。
「紀州の作柄は2年続けて良かったのだが、梅干しは漬物売場の中でも高価格帯で、コロナの影響や物価高による節約志向が高まっているため売れ行きは芳しくない。産地の原料在庫は余裕がある状況で、タンクを空けて新物を漬けられるように春夏に向けて販売を強化していく必要がある。農家の生産意欲を維持するためにも原料をバランス良く動かしてくことが重要で、今年は豊富な原料をどのように販売につなげていくか、ということが課題だ」
――梅メーカーのSNSが話題となった。
「SNSは情報が一気に拡散されるので、怖さを感じた部分もある。だが、その影響力が良い方向に向けば良いPRになるし、漬物があまりアプローチできなかった若年層にも情報を発信できる可能性もある。青年部組織の若梅会では、SNSを活用して梅をPRする事業がスタートしている。内容についてはこれから詰めていく方向で取り組んでいる。食べ方や梅の健康機能性に関する情報を発信できればと思っている」
――調味梅の歴史について。
「紀州で調味梅が生まれて約55年が経つ。昔は白干しが一般的だった。梅を調味液に漬け込む調味梅は異端的な存在で、当時は批判的な意見もあったようだが、干しの逆の発想でドリップも出るが、塩分や酸味は抑えられ、美味しい味付けで食べやすくなったことで、支持されるようになっていった。ご飯を食べるのに白干しは1粒で十分だったが、調味梅は3粒4粒と食され、消費量も増加した。かなり前の話では、紀州で漬けられる梅の量は年間50万樽(1樽10㎏)だったが、現在は平年作の年で250万樽と言われている。そのような流れで生産者も業者も増えて現在の梅産業が形成された」
――今後の見通しは。
「紀州の梅産業でも世代交代が進んでいる。まだ後を継いでいない企業でも子息が会社で働いているなど、世代交代の準備を進めているように見受けられる。デジタル社会となり、今後も予想を上回る速度で時代が進んでいくだろう。若い人が力を発揮しなければ企業も産業も置いていかれてしまう。現在、梅干し売場の主流となっているのは調味梅だが、これまでは大きな変化もなく売場を維持できた。しかし、これからは次の時代、世代に向けて持続可能な梅産業を構築していくためにもイノベーションが必要な時にきている。コロナ禍で思うような事業を行うことができなかったが、若梅会を始め、これからの梅産業を支える若い力に期待している」
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
紀州田辺梅干協同組合の加盟社一覧
大谷屋 HP
求められるイノベーション
紀州田辺梅干協同組合の大谷喜則理事長にインタビュー。梅業界の現状や今後の見通しなどについて話を聞いた。現在、売場で主流となっている調味梅は市場に登場してから約50年が経っており、その歴史とともに歩んできた大谷理事長は梅産業の更なる発展に向けてイノベーションの必要性を指摘。若い世代が力を発揮できる環境を整え、持続可能な梅産業を構築していく意向を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――梅の開花状況は。
「今年は気温が低く、花が咲くタイミングがやや遅くなった。紀州では開花が遅い年は豊作になると言われており、気候も安定しているので現時点では良い作柄になると予想されている」
――梅干しの売れ行きは。
「紀州の作柄は2年続けて良かったのだが、梅干しは漬物売場の中でも高価格帯で、コロナの影響や物価高による節約志向が高まっているため売れ行きは芳しくない。産地の原料在庫は余裕がある状況で、タンクを空けて新物を漬けられるように春夏に向けて販売を強化していく必要がある。農家の生産意欲を維持するためにも原料をバランス良く動かしてくことが重要で、今年は豊富な原料をどのように販売につなげていくか、ということが課題だ」
――梅メーカーのSNSが話題となった。
「SNSは情報が一気に拡散されるので、怖さを感じた部分もある。だが、その影響力が良い方向に向けば良いPRになるし、漬物があまりアプローチできなかった若年層にも情報を発信できる可能性もある。青年部組織の若梅会では、SNSを活用して梅をPRする事業がスタートしている。内容についてはこれから詰めていく方向で取り組んでいる。食べ方や梅の健康機能性に関する情報を発信できればと思っている」
――調味梅の歴史について。
「紀州で調味梅が生まれて約55年が経つ。昔は白干しが一般的だった。梅を調味液に漬け込む調味梅は異端的な存在で、当時は批判的な意見もあったようだが、干しの逆の発想でドリップも出るが、塩分や酸味は抑えられ、美味しい味付けで食べやすくなったことで、支持されるようになっていった。ご飯を食べるのに白干しは1粒で十分だったが、調味梅は3粒4粒と食され、消費量も増加した。かなり前の話では、紀州で漬けられる梅の量は年間50万樽(1樽10㎏)だったが、現在は平年作の年で250万樽と言われている。そのような流れで生産者も業者も増えて現在の梅産業が形成された」
――今後の見通しは。
「紀州の梅産業でも世代交代が進んでいる。まだ後を継いでいない企業でも子息が会社で働いているなど、世代交代の準備を進めているように見受けられる。デジタル社会となり、今後も予想を上回る速度で時代が進んでいくだろう。若い人が力を発揮しなければ企業も産業も置いていかれてしまう。現在、梅干し売場の主流となっているのは調味梅だが、これまでは大きな変化もなく売場を維持できた。しかし、これからは次の時代、世代に向けて持続可能な梅産業を構築していくためにもイノベーションが必要な時にきている。コロナ禍で思うような事業を行うことができなかったが、若梅会を始め、これからの梅産業を支える若い力に期待している」
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
紀州田辺梅干協同組合の加盟社一覧
大谷屋 HP
3月21日号 塩特集
一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会 代表理事 青山志穂氏
漬物と塩の共創を
減塩より「適塩」推進
一般社団法人日本ソルトコーディネーター協会代表理事の青山志穂氏にインタビュー。塩は人間になくてはならないもので、食品の味付けに必須の存在である。しかし、近年の減塩ブームが「塩=悪」というイメージを持たせ、塩の摂取を控える消費者が出てきている。青山代表は、2月の全国漬物検査協会の漬物技術研究セミナーで講演し、「適塩」推進と、漬物業界がもっと塩に関心を持つことで共創できると訴えた。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
ー塩に関心を持ったきっかけ。
「大学を卒業後、食品業界に携わりたいという思いから大手食品メーカーに入社し、商品開発やマーケティングを学んだ。山形のイタリアン『アル・ケッチァーノ』の奥田政行シェフに出会い、塩が食材の味を引き立たせることに驚き、塩のことをもっと知りたいと思った。沖縄に移住し、塩の販売店へ転職、塩の買い付けから販売まで担当させてもらった。そこで得た人脈が、今の仕事に活きている。塩を販売するよりも、塩の魅力を啓蒙したいという思いが高まり、協会を設立した」
ーソルトコーディネーターとは。
「ジュニアソルトコーディネーター、ソルトコーディネーター、シニアソルトコーディネーターの3つを用意し、順に難易度が高くなっていく。ジュニアは塩の基礎知識(原料・製法・特性)や歴史など、入門編。ソルトコーディネータ‐は塩と食材の相性についてグループディスカッション付きで学ぶ。塩と美容は女性受講者の関心が高いテーマだ。この2つはオンライン講座だが、シニアは講師として塩の魅力を語れるまで知識とプレゼン力を身に着けてほしい。そのため、対面で2日間じっくり受講し、実技試験も実施する。シニア取得者の経歴は、ダイビング好きで大の海好きになり塩に関心を持った方がいたり、美容から入ったりと幅広い。和歌山の梅干メーカーの方までいる」
ーソルトコーディネーター取得のメリットは。
「塩への理解が深まることが1番。当協会のウェブサイトでコーディネータ‐の紹介を行っており、講師として講演依頼を受けることもできる。また、コーディネーターが在籍のお店も紹介しており、ネットコスメショップや焼肉屋、塩がコンセプトのレストランまで閲覧できる。ウェブサイトでは、コーディネーター同士が交流できる特別ページもあり、取得後も協会の担当者だけでなく、取得者同士でフォローしあえる」
ー塩のトレンドは。
「『減塩市場』は2015年から頭打ちで、実は思ったほど伸びていない。食品メーカーとしては、塩チョコ、塩やきそばを発売し、定番化している。環境への優しさをアピールする製塩メーカーは、パッケージにもこだわっている。減塩よりもむしろ『適塩』の時代が来ていると感じ、塩業界の関係者も同じ方向を向いている。お肉と塩、そばと塩など食材と合わせる店が増えている。味の相性はもちろん、塩の粒の大きさも重要で、味の濃いお肉は粒が大きいのがおすすめだ」
ー漬物における塩の役割
「漬物の塩は『粗塩』が良いと一般的に言われる。だが粗塩とは正式な名称でなく、塩化ナトリウムの純度が低い塩を指す。にがり成分やマグネシウム、カルシウムが野菜に含まれるペクチンと結合し、マグネシウム塩やカルシウム塩を作り、漬物の歯切れが良くなる。漬物の野菜には豊富にカリウムが含まれており、ナトリウムの排出を促し、血圧上昇を抑制する働きがある。『漬物は塩分が高いからダメ』と決めつけるのではなく、ぜひ理解してほしい。吟味した塩を使うと、食への意識が高い層の支持がより得られそうだ。漬物と塩が共創することで、両者への関心を高められる」
【2023(令和5)年3月21日第5123号8面】
ソルトコーディネーター協会
株式会社天塩 代表取締役社長 鈴木恵氏
7月で創業50周年
”赤穂の塩作り”啓蒙幅広く
株式会社天塩(鈴木恵社長、東京都新宿区)は、江戸時代から続くにがりを多く含ませた塩づくり〝差塩製法”を継承した「にがりを含んだ塩」にこだわり、日本の伝統食文化の良さを未来につなげている。同社は赤穂化成が製造する「赤穂の天塩」の家庭用塩および関連商品の販売専門会社である。「赤穂の塩作り」は文化庁より日本遺産に認定され、その歴史的な価値が証明されている。同社では、今年7月11日に創業50周年を迎える。2026年には赤穂で塩田が開墾されてから400年のメモリアルイヤーが控えており、今年から4年間をかけ、”赤穂の塩作り”の啓蒙を幅広く行っていく予定だ。同社代表取締役社長の鈴木恵氏に塩の動向や50周年の取組について聞いた。
(藤井大碁)
◇ ◇
――足元の状況。
「昨年12月までは前年並で推移していたが、年明け1月、2月は塩の動きが良くない。消費者物価指数が上昇し、節約志向が高まっている。塩だけではないが、余計な物は買わないという消費行動が浸透している。また卵の高騰や不足により料理メニューが限定されていることもマイナス要因となっている。例年春先から需要が増え、6月には梅の漬け込みも控えているので、動きが活発化していくことを期待したい」
――値上げについて。
「塩業界も製法により差はあるがエネルギーコストや物流費の高騰により大きな影響を受けている。弊社においても、輸入する天日塩が大幅に上昇し、電気代などの燃料代の高騰も影響が大きい。そのため今年7月に2019年以来の価格改定を実施する予定だ」
――厳しい環境下、どのような施策があるか。
「塩は一世帯あたりの購入数量は減っているが、購入単価は上がっている。量をたくさん買う人は減少しているが、健康性や美味しさといったこだわりを持って、付加価値の高い塩を選ぶ人は増えていることが分かる。マーケティングに力を入れ、消費者一人ひとりが何を求めているか、細分化したニーズを汲み取り、商品開発に生かしていく」
――業務用の引き合いが増えている。
「SDGsなど環境配慮の流れが強まる中、自然の力を利用して作る天日塩は環境への負荷が少ないということで、我々の塩を選んでもらえる機会が増えている。また価格と品質の二極化が進む中で、塩で差別化を図り、製品に付加価値を付けようとする食品メーカーからの引き合いも多い」
――キッチンカーの販売やイベントに積極的だ。
「子供からシニア層まで幅広い年齢層に”赤穂の天塩”を使用した料理を食べてもらう貴重な機会になっている。食べてもらうだけでなく、対話やサンプリングをすることで消費者ニーズを汲み取ることもできる。塩や調味料は、消費者が使い方を認知しなければ購入に結びつかいないため、売場に並べているだけでは消費は増えない。イベントで塩や調味料の使い方を説明しながら草の根的に広めていく必要がある」
――50周年を迎える。
「おかげ様で7月11日に50周年を迎える。これまで弊社を支えてくれたお得意様や取引先様、その他関係者の方々に深く感謝を申し上げたい。また2026年には、赤穂で塩田が開墾されて400年を迎える。弊社では今年から2026年までの4年間をかけて、赤穂の塩作りの歴史や赤穂という場所について認知してもらうための活動を行っていく予定だ。イベント出店やキャンペーンなども積極的に行い、50周年の感謝の気持ちを伝えていく。また〝天塩ファン〟の方との交流にも力を入れる。ファンの方を集めて天塩のことをもっと知ってもらうイベントを4年間通して開催し、さらにファンの方との絆を深めていく」
【2023(令和5)年3月21日第5123号9面】
電子版 Web展示会 天塩
”赤穂の塩作り”啓蒙幅広く
株式会社天塩(鈴木恵社長、東京都新宿区)は、江戸時代から続くにがりを多く含ませた塩づくり〝差塩製法”を継承した「にがりを含んだ塩」にこだわり、日本の伝統食文化の良さを未来につなげている。同社は赤穂化成が製造する「赤穂の天塩」の家庭用塩および関連商品の販売専門会社である。「赤穂の塩作り」は文化庁より日本遺産に認定され、その歴史的な価値が証明されている。同社では、今年7月11日に創業50周年を迎える。2026年には赤穂で塩田が開墾されてから400年のメモリアルイヤーが控えており、今年から4年間をかけ、”赤穂の塩作り”の啓蒙を幅広く行っていく予定だ。同社代表取締役社長の鈴木恵氏に塩の動向や50周年の取組について聞いた。
(藤井大碁)
◇ ◇
――足元の状況。
「昨年12月までは前年並で推移していたが、年明け1月、2月は塩の動きが良くない。消費者物価指数が上昇し、節約志向が高まっている。塩だけではないが、余計な物は買わないという消費行動が浸透している。また卵の高騰や不足により料理メニューが限定されていることもマイナス要因となっている。例年春先から需要が増え、6月には梅の漬け込みも控えているので、動きが活発化していくことを期待したい」
――値上げについて。
「塩業界も製法により差はあるがエネルギーコストや物流費の高騰により大きな影響を受けている。弊社においても、輸入する天日塩が大幅に上昇し、電気代などの燃料代の高騰も影響が大きい。そのため今年7月に2019年以来の価格改定を実施する予定だ」
――厳しい環境下、どのような施策があるか。
「塩は一世帯あたりの購入数量は減っているが、購入単価は上がっている。量をたくさん買う人は減少しているが、健康性や美味しさといったこだわりを持って、付加価値の高い塩を選ぶ人は増えていることが分かる。マーケティングに力を入れ、消費者一人ひとりが何を求めているか、細分化したニーズを汲み取り、商品開発に生かしていく」
――業務用の引き合いが増えている。
「SDGsなど環境配慮の流れが強まる中、自然の力を利用して作る天日塩は環境への負荷が少ないということで、我々の塩を選んでもらえる機会が増えている。また価格と品質の二極化が進む中で、塩で差別化を図り、製品に付加価値を付けようとする食品メーカーからの引き合いも多い」
――キッチンカーの販売やイベントに積極的だ。
「子供からシニア層まで幅広い年齢層に”赤穂の天塩”を使用した料理を食べてもらう貴重な機会になっている。食べてもらうだけでなく、対話やサンプリングをすることで消費者ニーズを汲み取ることもできる。塩や調味料は、消費者が使い方を認知しなければ購入に結びつかいないため、売場に並べているだけでは消費は増えない。イベントで塩や調味料の使い方を説明しながら草の根的に広めていく必要がある」
――50周年を迎える。
「おかげ様で7月11日に50周年を迎える。これまで弊社を支えてくれたお得意様や取引先様、その他関係者の方々に深く感謝を申し上げたい。また2026年には、赤穂で塩田が開墾されて400年を迎える。弊社では今年から2026年までの4年間をかけて、赤穂の塩作りの歴史や赤穂という場所について認知してもらうための活動を行っていく予定だ。イベント出店やキャンペーンなども積極的に行い、50周年の感謝の気持ちを伝えていく。また〝天塩ファン〟の方との交流にも力を入れる。ファンの方を集めて天塩のことをもっと知ってもらうイベントを4年間通して開催し、さらにファンの方との絆を深めていく」
【2023(令和5)年3月21日第5123号9面】
電子版 Web展示会 天塩
マルニ株式会社 代表取締役社長 脇田慎一氏
小袋塩強化で増収増益 7月から価格改定を決断
昨年、特殊製法塩協会4代目会長に就任したのがマルニ株式会社(大阪府八尾市)の脇田慎一社長だ。異業種で磨いた経営手腕を買われた脇田社長は2017年にマルニへ入社し、2020年に社長就任。小袋塩の設備投資を推進し売上拡大を実現した。塩業界の競争やコスト上昇への考えを聞いた。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--略歴を。
「パナソニックで35年間働き、うち20年以上を海外で過ごし、各地の現地法人経営に携わってきた。2017年、日本帰国を機に人材バンクに登録したところ、マルニからオファーがあり入社した」
--経営課題とは。
「マルニは1962年から『エンリッチ塩』を発売、業容を拡大してきた。しかし2002年に塩の専売制度が廃止(自由化)され新規参入が増え競争が激化したこと、減塩志向が強まったことから、売上を大きく落とし赤字経営が続いていた。一方で小袋塩の注文は増えていたものの、生産設備の能力不足からお断りせざるを得ない場面が度々発生していた。そこで小袋塩の需要増を見込んで工場拡張、設備投資を行った」
--小袋塩の動き。
「小袋の受注は順調に増え、本社移転等の経営改革実施により黒字転換できた。弁当や惣菜に添付する利用が多くコロナ禍でテイクアウトやデリバリーが増加したのも当社にとって好機となった。工場拡張・設備投資により生産能力を2・5倍程まで強化したのだが、それでもフル稼働という状態が続いている」
--選ばれる理由。
「味・品質は当然として、小回りが利く点を評価頂いている。設備投資は大型機1台でなく小型機を複数導入する形とした。小袋塩のフレーバーや外装など要望に応じ、小ロットで対応可能だ。授業員30人規模なので意思疎通がスムーズで、依頼対応の速さもある。そうして実績が増えてきたことにより問屋・商社様からも小袋塩といえばマルニと定着して依頼が舞い込む好循環が生まれている」
--今後の方針は。
「売上は改善したが、それと同時に原料塩や各種資材、電気代などコスト上昇が襲いかかっている。このままコスト増が続けば再び赤字転落は避けられず、今年7月から価格改定を実施する決断をした。しかし中外食業界においても他のあらゆるコストが上がっている中、小袋塩がカット対象になることも出てくる。この状況をただ受け入れるのではなく攻めの姿勢で、来年からは第2期工事としてエンリッチ塩生産設備の刷新に取り組む。小袋塩の生産能力に余裕を持たせるとともに『エンリッチ塩』のリニューアルやSDGs対応も進めていく計画だ」
--御社の強みは。
「製造、開発、営業、総務など各部署に30年以上勤続しているプロフェッショナルが居るのは、塩について素人である私にとって大変ありがたかった。課題と目標を示せば具体策は彼らが自ら立案し実践してくれる。私が前職で習得した松下幸之助の全員経営を実践できる環境が揃っていた」
--特殊製法塩協会会長として。
「協会が第一に掲げるのが『適塩』の普及。塩が悪者扱いされることは私達にとって市場縮小に直結する。何より、誇りを持って作っているものなのだからその価値をしっかり伝えていかなければいけない。人が集まるイベントへの協賛など、塩は適切に摂るべきものであると伝えていきたい。会員の意見を汲み取り関連省庁や塩に関わる業界団体が集まる全国塩業懇話会へ伝えていくことも重要だ。燃料や資材コストの上昇による価格改定、ゼロカーボンへの対応など、特殊製法塩業界の実情に寄り添い、サポートしていける協会でありたい」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--略歴を。
「パナソニックで35年間働き、うち20年以上を海外で過ごし、各地の現地法人経営に携わってきた。2017年、日本帰国を機に人材バンクに登録したところ、マルニからオファーがあり入社した」
--経営課題とは。
「マルニは1962年から『エンリッチ塩』を発売、業容を拡大してきた。しかし2002年に塩の専売制度が廃止(自由化)され新規参入が増え競争が激化したこと、減塩志向が強まったことから、売上を大きく落とし赤字経営が続いていた。一方で小袋塩の注文は増えていたものの、生産設備の能力不足からお断りせざるを得ない場面が度々発生していた。そこで小袋塩の需要増を見込んで工場拡張、設備投資を行った」
--小袋塩の動き。
「小袋の受注は順調に増え、本社移転等の経営改革実施により黒字転換できた。弁当や惣菜に添付する利用が多くコロナ禍でテイクアウトやデリバリーが増加したのも当社にとって好機となった。工場拡張・設備投資により生産能力を2・5倍程まで強化したのだが、それでもフル稼働という状態が続いている」
--選ばれる理由。
「味・品質は当然として、小回りが利く点を評価頂いている。設備投資は大型機1台でなく小型機を複数導入する形とした。小袋塩のフレーバーや外装など要望に応じ、小ロットで対応可能だ。授業員30人規模なので意思疎通がスムーズで、依頼対応の速さもある。そうして実績が増えてきたことにより問屋・商社様からも小袋塩といえばマルニと定着して依頼が舞い込む好循環が生まれている」
--今後の方針は。
「売上は改善したが、それと同時に原料塩や各種資材、電気代などコスト上昇が襲いかかっている。このままコスト増が続けば再び赤字転落は避けられず、今年7月から価格改定を実施する決断をした。しかし中外食業界においても他のあらゆるコストが上がっている中、小袋塩がカット対象になることも出てくる。この状況をただ受け入れるのではなく攻めの姿勢で、来年からは第2期工事としてエンリッチ塩生産設備の刷新に取り組む。小袋塩の生産能力に余裕を持たせるとともに『エンリッチ塩』のリニューアルやSDGs対応も進めていく計画だ」
--御社の強みは。
「製造、開発、営業、総務など各部署に30年以上勤続しているプロフェッショナルが居るのは、塩について素人である私にとって大変ありがたかった。課題と目標を示せば具体策は彼らが自ら立案し実践してくれる。私が前職で習得した松下幸之助の全員経営を実践できる環境が揃っていた」
--特殊製法塩協会会長として。
「協会が第一に掲げるのが『適塩』の普及。塩が悪者扱いされることは私達にとって市場縮小に直結する。何より、誇りを持って作っているものなのだからその価値をしっかり伝えていかなければいけない。人が集まるイベントへの協賛など、塩は適切に摂るべきものであると伝えていきたい。会員の意見を汲み取り関連省庁や塩に関わる業界団体が集まる全国塩業懇話会へ伝えていくことも重要だ。燃料や資材コストの上昇による価格改定、ゼロカーボンへの対応など、特殊製法塩業界の実情に寄り添い、サポートしていける協会でありたい」
【2023(令和5)年3月21日第5123号9面】
伯方塩業株式会社 代表取締役社長 石丸一三氏
業務筋のシェア拡大強化 価格以上の価値あるブランドへ
伯方塩業株式会社(愛媛県松山市)の石丸一三社長へインタビュー。2023年度は創業50周年を迎える年であり、中期経営計画の最終年度となる。コロナ下で外食向けの出荷減や、現在の諸コスト高騰といった困難に直面しながらも国内シェア拡大に力を注いできた。今年7月には価格改定を実施するが、10年ビジョン『世界で1番有名な塩メーカーになる』に基づくブランド育成へ取り組むことで、価格以上の価値を提供していく。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--創業50周年の取組は。
「対外的には、キャンペーンや広告等で発信し、塩について考え、関心を持って頂く機会を作っていく。社内的には、一過性のイベントで終わらせずこれを機にさらなる飛躍が目指せるような変革の年と位置づけている」
--中期経営計画の達成状況は。
「営業面では、新型コロナウイルスの影響から外食店など業務筋の動きが鈍り、目標から遅れている。しかしその一方で新規にビールのノベルティ採用や、コンビニPBの原料採用など大口の供給が始まっている。ポストコロナの時代へと移れば、この3年間の取組が芽を出していくと期待している」
--新規取引獲得に積極的だ。
「当社が成長していくには国内シェアを拡大することが必要になる。特に業務筋にはまだまだ伸びしろがある。中外食向けの『味香塩』シリーズについても新規取引獲得の武器として、提案先を広げている」
--価格改定について。
「今年7月出荷分より価格改定を実施する予定。輸入原料の調達コストや燃料代、輸送費などが上昇している。合理化を尽くしてきたが、これ以上の自助努力による吸収は不可能と判断した」
--価格改定の進捗は。
「家庭用は大半のお取引先様にご理解いただけているのだが、その先に居る消費者の目は厳しい。固定ファンを手放さず、売場を見て決める浮動層をどう取り込めるかが重要となってくる。現在は若い世代へ向けてWebでの発信に力を入れている。『伯方の塩』の宣伝だけでなく塩そのものへの理解関心を引き出せるよう、戦略的な発信を模索している」
--業務用は。
「当社だけでなく食に関わるあらゆるコストが上昇している状況下、全体的な原材料見直しをされているお客様もいる。そういう時に、伯方の塩は代えずに今まで通り使おうと思ってもらえなければいけない。そのためには対消費者のブランド育成や、50年間大切にしてきた誠実できめ細かい対応をさらに徹底することが必要」
--ブランドについて。
「2019年度からの10年ビジョンとして『世界で1番有名な塩メーカーになる』を掲げている。宣伝をバンバン打つということではなくて、1番の核は『社員が自らの仕事に誇りを持ちイキイキと働ける会社を目指そう』ということ。このビジョンに向かって取組を進める過程や結果を通して、顧客サービスの向上や地域社会への貢献を達成し、周囲からの評判が上がり、自然と伯方塩業というブランドが認知されることを目指している」
--脱炭素が求められている。
「自然塩存続運動から生まれた当社にとって、環境保護への取組は重要課題。現在は塩水を煮詰める釜を入れ替え熱効率を改善するなど設備更新に取り組んでいる。将来的にはA重油からより効率の良い燃料へ切り替える、工場の太陽光発電を増設する、発生したCO2を有効利用するなど様々な観点からカーボンニュートラルを実現し、世界に誇れる塩メーカーを目指したい」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--創業50周年の取組は。
「対外的には、キャンペーンや広告等で発信し、塩について考え、関心を持って頂く機会を作っていく。社内的には、一過性のイベントで終わらせずこれを機にさらなる飛躍が目指せるような変革の年と位置づけている」
--中期経営計画の達成状況は。
「営業面では、新型コロナウイルスの影響から外食店など業務筋の動きが鈍り、目標から遅れている。しかしその一方で新規にビールのノベルティ採用や、コンビニPBの原料採用など大口の供給が始まっている。ポストコロナの時代へと移れば、この3年間の取組が芽を出していくと期待している」
--新規取引獲得に積極的だ。
「当社が成長していくには国内シェアを拡大することが必要になる。特に業務筋にはまだまだ伸びしろがある。中外食向けの『味香塩』シリーズについても新規取引獲得の武器として、提案先を広げている」
--価格改定について。
「今年7月出荷分より価格改定を実施する予定。輸入原料の調達コストや燃料代、輸送費などが上昇している。合理化を尽くしてきたが、これ以上の自助努力による吸収は不可能と判断した」
--価格改定の進捗は。
「家庭用は大半のお取引先様にご理解いただけているのだが、その先に居る消費者の目は厳しい。固定ファンを手放さず、売場を見て決める浮動層をどう取り込めるかが重要となってくる。現在は若い世代へ向けてWebでの発信に力を入れている。『伯方の塩』の宣伝だけでなく塩そのものへの理解関心を引き出せるよう、戦略的な発信を模索している」
--業務用は。
「当社だけでなく食に関わるあらゆるコストが上昇している状況下、全体的な原材料見直しをされているお客様もいる。そういう時に、伯方の塩は代えずに今まで通り使おうと思ってもらえなければいけない。そのためには対消費者のブランド育成や、50年間大切にしてきた誠実できめ細かい対応をさらに徹底することが必要」
--ブランドについて。
「2019年度からの10年ビジョンとして『世界で1番有名な塩メーカーになる』を掲げている。宣伝をバンバン打つということではなくて、1番の核は『社員が自らの仕事に誇りを持ちイキイキと働ける会社を目指そう』ということ。このビジョンに向かって取組を進める過程や結果を通して、顧客サービスの向上や地域社会への貢献を達成し、周囲からの評判が上がり、自然と伯方塩業というブランドが認知されることを目指している」
--脱炭素が求められている。
「自然塩存続運動から生まれた当社にとって、環境保護への取組は重要課題。現在は塩水を煮詰める釜を入れ替え熱効率を改善するなど設備更新に取り組んでいる。将来的にはA重油からより効率の良い燃料へ切り替える、工場の太陽光発電を増設する、発生したCO2を有効利用するなど様々な観点からカーボンニュートラルを実現し、世界に誇れる塩メーカーを目指したい」
【2023(令和5)年3月21日第5123号9面】
鳴門塩業株式会社 専務取締役 石井英年氏・取締役営業本部長 青木貴嗣氏
二次値上げ95%完了へ 安全安心な国産塩の価値発信
鳴門塩業株式会社(安藝順社長、徳島県鳴門市)は、年間最大20万tの製塩プラントを有する国内製塩大手である。昨年4月に業務用塩を1㎏当たり10円以上、11月に同14円以上の値上げを実施。年に2度の値上げは塩業界として極めて異例かつ、値上げ幅も過去最大である。石井英年専務と青木貴嗣部長は石炭価格を筆頭にコスト上昇が自助努力の範囲を超えていることを指摘。安全安心な国産塩の供給には、適正価格の追求が必要であると訴える。(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--値上げの背景は。
石井専務「当社を含め日本塩工業会3社は膜濃縮製塩法を採っている。これはイオン交換膜という特別な装置で海水から塩の成分を集めて濃い塩水を作り、最後にそれを燃料で煮詰めて塩にするというもの。製塩時の燃料、人件費、設備維持修繕費や輸送費が国産塩の価格を決定していることになる。これらのコストが一斉に上がっているのは皆様もご承知の通り。合理化で吸収できる範囲を越え、昨年11月に1㎏当たり14円以上の値上げを実施する決断へ至った。1年で2度、大幅な値上げとなり、ご負担をおかけするが理解いただきたい」
--進捗は。
青木部長「年度内に95%以上のお客様において値上げが完了する。輸入塩への切替を検討されるお客様でも、国産塩の長所をしっかりお伝えすることで納得いただいている。一方、他の国産塩メーカー様も同様に価格改定をされているようで、当社へ代替の相談をいただくこともあるのだが、提示される単価では請けられないケースが増えているのが正直なところ」
--国産塩の長所とは。
石井専務「一番は安全安心であること。イオン交換膜は分子レベルで海水を処理するので目に見える異物は勿論のこと、海水中に含まれる環境ホルモンやダイオキシン、ヒ素などの物質も除去できる。仮に海が汚染されていたとしても安全ということになる。この製塩法は日本が生み出したものであり、世界に誇れる技術だと言える。また万が一のクレーム発生時にも国産であれば迅速な対応が可能で、あらゆる点でリスクを減らせる」
--御社ならではの強みは。
青木部長「当社は2002年に医薬品製造許可を取得し、医薬品GMP管理のもと、日本薬局方塩化ナトリウム(医薬用原薬)を生産するようになった。医薬品の製造は食品よりさらに厳しい管理が求められる。この経験が食品製造においても意識を高め、衛生管理レベルは格段に向上している」
--家庭用塩の値上げは。
石井専務「業務用と同じく価格改定を実施する方針。ただ家庭用の場合、一度棚落ちしてしまうとその後の再導入が難しく、長期的な損失が発生してしまう。塩は日配品等と違いサイクルが長いので慎重にならざるを得ない。時期や改定率を検討するとともに、価格以外の価値を訴求をしていく努力が必要と感じている」
--塩の価値について。
青木部長「日本独自の製塩法による品質や安全性の面の発信、またカーボンニュートラルで環境に優しい塩作りを実現し、積極的に国産塩を選んでいただける未来を作っていきたい。国産塩はこれまで食のインフラ的側面が強く、またこれほど強烈なコスト上昇は今までなかった。困難な状況だが、塩の価値を見つめ直し発信する機会になったと前向きに捉えていきたい」
◇ ◇
--値上げの背景は。
石井専務「当社を含め日本塩工業会3社は膜濃縮製塩法を採っている。これはイオン交換膜という特別な装置で海水から塩の成分を集めて濃い塩水を作り、最後にそれを燃料で煮詰めて塩にするというもの。製塩時の燃料、人件費、設備維持修繕費や輸送費が国産塩の価格を決定していることになる。これらのコストが一斉に上がっているのは皆様もご承知の通り。合理化で吸収できる範囲を越え、昨年11月に1㎏当たり14円以上の値上げを実施する決断へ至った。1年で2度、大幅な値上げとなり、ご負担をおかけするが理解いただきたい」
--進捗は。
青木部長「年度内に95%以上のお客様において値上げが完了する。輸入塩への切替を検討されるお客様でも、国産塩の長所をしっかりお伝えすることで納得いただいている。一方、他の国産塩メーカー様も同様に価格改定をされているようで、当社へ代替の相談をいただくこともあるのだが、提示される単価では請けられないケースが増えているのが正直なところ」
--国産塩の長所とは。
石井専務「一番は安全安心であること。イオン交換膜は分子レベルで海水を処理するので目に見える異物は勿論のこと、海水中に含まれる環境ホルモンやダイオキシン、ヒ素などの物質も除去できる。仮に海が汚染されていたとしても安全ということになる。この製塩法は日本が生み出したものであり、世界に誇れる技術だと言える。また万が一のクレーム発生時にも国産であれば迅速な対応が可能で、あらゆる点でリスクを減らせる」
--御社ならではの強みは。
青木部長「当社は2002年に医薬品製造許可を取得し、医薬品GMP管理のもと、日本薬局方塩化ナトリウム(医薬用原薬)を生産するようになった。医薬品の製造は食品よりさらに厳しい管理が求められる。この経験が食品製造においても意識を高め、衛生管理レベルは格段に向上している」
--家庭用塩の値上げは。
石井専務「業務用と同じく価格改定を実施する方針。ただ家庭用の場合、一度棚落ちしてしまうとその後の再導入が難しく、長期的な損失が発生してしまう。塩は日配品等と違いサイクルが長いので慎重にならざるを得ない。時期や改定率を検討するとともに、価格以外の価値を訴求をしていく努力が必要と感じている」
--塩の価値について。
青木部長「日本独自の製塩法による品質や安全性の面の発信、またカーボンニュートラルで環境に優しい塩作りを実現し、積極的に国産塩を選んでいただける未来を作っていきたい。国産塩はこれまで食のインフラ的側面が強く、またこれほど強烈なコスト上昇は今までなかった。困難な状況だが、塩の価値を見つめ直し発信する機会になったと前向きに捉えていきたい」
【2023(令和5)年3月21日第5123号10面】
株式会社九州ソルト 代表取締役社長 髙本公利氏
塩の売上キープが課題 食品以外にも積極的に着手
株式会社九州ソルト(福岡県福岡市東区)は、平成8年(1996年)2月に九州の塩元売9社により設立された「九州塩業協業組合」を礎とし、平成13年(2001年)10月に現行の株式会社に組織変更。同社は昨年6月、髙本公利氏が代表取締役社長に就任した。髙本社長に九州の業界動向、同社の今後の方針などについて話を聞いた。
株式会社九州ソルト(福岡県福岡市東区)は、平成8年(1996年)2月に九州の塩元売9社により設立された「九州塩業協業組合」を礎とし、平成13年(2001年)10月に現行の株式会社に組織変更。同社は昨年6月、髙本公利氏が代表取締役社長に就任した。髙本社長に九州の業界動向、同社の今後の方針などについて話を聞いた。
(菰田隆行)
◇ ◇
‐九州業界の現況。
「九州はそもそも農業や水産業が盛んで、漬物や海産物の加工品に塩を使用する頻度は高いが、天候や季節に大きく左右されやすい。また、九州の西海岸での漁獲高は年々減少しており、熊本県の阿蘇たかなも、農家の高齢化、担い手問題で収穫高の減少が大きく影響してきている。昨今では塩蔵から冷凍保存へと変わってきていることもあり、加工食品向けの販売をどうキープしていくか、どうやって伸ばしていくのかが課題だ」
‐塩以外の製品動向。
「現在、塩と添加物等の一般商品の販売比率は7‥3ぐらいだが、それを6‥4くらいに持っていきたいと考えている。一般商品は糖類、グルソー、うまみ調味料、ビタミン剤、クエン酸などになるが、他にも食品添加物をはじめ工業用薬品等も増やしていきたいと考えている。ただ、それらの製品は輸入に頼っているので価格も不安定であり、どう対応していけるかがこれからの検討課題だ。工業用では、クリーニング業向けで水処理用の塩の取引からクリーニング用の糊として使用される澱粉、現在ではアルカリ剤での実績も上がってきている。外の業種でも横に広げられる製品を見つけていきたい」
‐SDGsへの対応。
「営業車はハイブリッドなどの低公害車を導入しているが、配送トラックもアイドリングストップ機能付きトラックとか、ハイブリッドトラックなどの低公害車の導入を検討しなければならないと考えている。今後は、SDGs対応した商品が求められてくるので、対応商品の取り揃え、対応した容器や包材なども取り扱っていきたい。なかなか難しい課題ではあるが、できるところからやっていきたいと考えている」
【2023(令和5)年3月21日第5123号11面】
九州ソルト HP
https://www.kyushu-salt.com/
◇ ◇
‐九州業界の現況。
「九州はそもそも農業や水産業が盛んで、漬物や海産物の加工品に塩を使用する頻度は高いが、天候や季節に大きく左右されやすい。また、九州の西海岸での漁獲高は年々減少しており、熊本県の阿蘇たかなも、農家の高齢化、担い手問題で収穫高の減少が大きく影響してきている。昨今では塩蔵から冷凍保存へと変わってきていることもあり、加工食品向けの販売をどうキープしていくか、どうやって伸ばしていくのかが課題だ」
‐塩以外の製品動向。
「現在、塩と添加物等の一般商品の販売比率は7‥3ぐらいだが、それを6‥4くらいに持っていきたいと考えている。一般商品は糖類、グルソー、うまみ調味料、ビタミン剤、クエン酸などになるが、他にも食品添加物をはじめ工業用薬品等も増やしていきたいと考えている。ただ、それらの製品は輸入に頼っているので価格も不安定であり、どう対応していけるかがこれからの検討課題だ。工業用では、クリーニング業向けで水処理用の塩の取引からクリーニング用の糊として使用される澱粉、現在ではアルカリ剤での実績も上がってきている。外の業種でも横に広げられる製品を見つけていきたい」
‐SDGsへの対応。
「営業車はハイブリッドなどの低公害車を導入しているが、配送トラックもアイドリングストップ機能付きトラックとか、ハイブリッドトラックなどの低公害車の導入を検討しなければならないと考えている。今後は、SDGs対応した商品が求められてくるので、対応商品の取り揃え、対応した容器や包材なども取り扱っていきたい。なかなか難しい課題ではあるが、できるところからやっていきたいと考えている」
【2023(令和5)年3月21日第5123号11面】
九州ソルト HP
https://www.kyushu-salt.com/
株式会社ソルト関西代表取締役社長 山本博氏
約200社の塩が値上げ 脱炭素を製配両面で議論尽くす
株式会社ソルト関西(山本博社長、大阪市中央区)は、平成13年に関西域内の卸売会社6社が事業統合して設立された塩の元売企業。山本社長は、全国塩元売協会会長、塩元売協同組合理事長、そして塩の各団体が垣根を越えて業界を取り巻く共通課題へ取り組むべく結成された全国塩業懇話会初代会長の要職を務めている。元売企業と業界団体両方の立場から、塩の価格改定へ理解を求めるとともに、共通課題である脱炭素実現への取組を語った。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--塩の値上げについて。
「業務用の国産塩値上げが昨年中に出揃い、現在はほぼ全てのお取引先様へご案内し、了承いただけた。塩は製造時の燃料代や人件費、輸送費などが価格決定の要素であり、その全てが上がっている。年に2度の値上げというのは初めての事態だったが、切羽詰まった状況であることを真摯に説明してきた。各社で値上げ幅が似通っていることもあり値上げによる切り替えなどもほとんど起こらなかった。現在は業務用の値上げが済み、家庭用塩の値上げ商談が始まっている」
--家庭用塩の値上げ状況。
「当社が取引する約200社の大半が値上げされ、大手各社は揃って7月に実施される。家庭用塩は製法が輸入天日塩を国内で再加工するものや、グルソー等添加物を加えたもの、岩塩など製法や原料がまちまちで値上げ幅にも差はあるが、この物価上昇の影響を受けていない製品は皆無と言える状況だ」
--御社の業績は。
「塩の出荷量はほぼ変わらず、値上げした分がそのまま売上にも反映された。食用としての塩は急に抑えられるものではなく、コロナや物価高といった突発的な影響はほとんど受けていない。また当社では塩以外の調味料や資材関係も扱っているのだが、それらも同様の状況だ。ただし利益面はほぼ横ばいで、売上増加分もその案内に掛かる営業コストや輸送費上昇で相殺されている」
--懇話会の取組は。
「懇話会では我々元売業界やメーカーらが集まってそれぞれの意見を集約している。業界が最も頭を悩ませているのが脱炭素の取組。政府は2030年度までに温室効果ガス46%削減(2013年度比)、2050年には実質排出ゼロとすることを目標に掲げており、塩業界においても製造や輸送時の燃料を削減する責任がある。本来であればその実現へ向けて投資を始めている時期なのだが、物価上昇によりその資金が食いつぶされたのは痛い誤算だった。値上げ対応に終われ議論も停滞しているのが実情」
--脱炭素への構想は。
「製造面で言えば、燃料を石炭や重油からクリーンエネルギーへ切り替えるには新たな設備が必要で莫大な時間も費用もかかる。当面は、発生したCO2を炭酸マグネシウムなど別の物質に変換して活用する、また発生するCO2を相殺する植樹に投資する、など収支をゼロへ近づける方法など現実的なアイデアが出ている。各企業任せにするのでなく、懇話会を通じて研究機関や塩事業センターから知恵を借りるなど取り組んでいる。また輸送面では共同配送や、鉄道・船の活用拡大など具体的な実現方法について詳細な議論をしている。塩は低単価高重量だが消費期限はないので、柔軟な対応が可能だろう」
--塩の情報発信については。
「減塩志向が強まっているが、塩は身体に必要不可欠であることもまた『くらしお』で活動いただき広く知られるようになってきたと思う。味や製法の違い等は各社発信に取り組まれているが、その後押しを業界団体としてどう取り組んでいけるか模索中だ。また少子高齢化への対策として、海外市場の開拓も視野に入れる必要がある。日本の塩は異物混入や汚染がなく、世界トップレベルの品質を持つことを主体的に発信していけるよう議論を進めていきたい」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
--塩の値上げについて。
「業務用の国産塩値上げが昨年中に出揃い、現在はほぼ全てのお取引先様へご案内し、了承いただけた。塩は製造時の燃料代や人件費、輸送費などが価格決定の要素であり、その全てが上がっている。年に2度の値上げというのは初めての事態だったが、切羽詰まった状況であることを真摯に説明してきた。各社で値上げ幅が似通っていることもあり値上げによる切り替えなどもほとんど起こらなかった。現在は業務用の値上げが済み、家庭用塩の値上げ商談が始まっている」
--家庭用塩の値上げ状況。
「当社が取引する約200社の大半が値上げされ、大手各社は揃って7月に実施される。家庭用塩は製法が輸入天日塩を国内で再加工するものや、グルソー等添加物を加えたもの、岩塩など製法や原料がまちまちで値上げ幅にも差はあるが、この物価上昇の影響を受けていない製品は皆無と言える状況だ」
--御社の業績は。
「塩の出荷量はほぼ変わらず、値上げした分がそのまま売上にも反映された。食用としての塩は急に抑えられるものではなく、コロナや物価高といった突発的な影響はほとんど受けていない。また当社では塩以外の調味料や資材関係も扱っているのだが、それらも同様の状況だ。ただし利益面はほぼ横ばいで、売上増加分もその案内に掛かる営業コストや輸送費上昇で相殺されている」
--懇話会の取組は。
「懇話会では我々元売業界やメーカーらが集まってそれぞれの意見を集約している。業界が最も頭を悩ませているのが脱炭素の取組。政府は2030年度までに温室効果ガス46%削減(2013年度比)、2050年には実質排出ゼロとすることを目標に掲げており、塩業界においても製造や輸送時の燃料を削減する責任がある。本来であればその実現へ向けて投資を始めている時期なのだが、物価上昇によりその資金が食いつぶされたのは痛い誤算だった。値上げ対応に終われ議論も停滞しているのが実情」
--脱炭素への構想は。
「製造面で言えば、燃料を石炭や重油からクリーンエネルギーへ切り替えるには新たな設備が必要で莫大な時間も費用もかかる。当面は、発生したCO2を炭酸マグネシウムなど別の物質に変換して活用する、また発生するCO2を相殺する植樹に投資する、など収支をゼロへ近づける方法など現実的なアイデアが出ている。各企業任せにするのでなく、懇話会を通じて研究機関や塩事業センターから知恵を借りるなど取り組んでいる。また輸送面では共同配送や、鉄道・船の活用拡大など具体的な実現方法について詳細な議論をしている。塩は低単価高重量だが消費期限はないので、柔軟な対応が可能だろう」
--塩の情報発信については。
「減塩志向が強まっているが、塩は身体に必要不可欠であることもまた『くらしお』で活動いただき広く知られるようになってきたと思う。味や製法の違い等は各社発信に取り組まれているが、その後押しを業界団体としてどう取り組んでいけるか模索中だ。また少子高齢化への対策として、海外市場の開拓も視野に入れる必要がある。日本の塩は異物混入や汚染がなく、世界トップレベルの品質を持つことを主体的に発信していけるよう議論を進めていきたい」
【2023(令和5)年3月21日第5123号11面】
3月11日号 トップに聞く
株式会社大安 代表取締役社長 大角安史氏
亀岡工房概要 素材の味生かす伝統技術
【大阪支社】株式会社大安(大角安史社長、京都市左京区)は2月20日より「伏見工房」から移転し「亀岡工房」を稼働開始した。コンセプトは「人とモノの流れがスムーズで安全清潔な工房 smooth! safety! Cleanliness!」。大角社長は、効率的で衛生的、また職員にとっても安全で働きやすい作業環境を実現できたと話す。
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー移転の経緯は。
「伏見工房が稼働開始したのが平成2年。一般的に言えば老朽化というほど古くないが、当時の基準で建てられており現在求められている衛生レベルに完璧に対応していくには改修が必要だったことや、3階建てで作業効率が悪かったことから移転を検討していた。背中を押したのが新型コロナウイルス。当社もお土産販売に大打撃を受けたことで、抜本的な改革を強く意識した。そんな折にこの地に新しい企業団地を立ち上げるお話を頂き、2020年7月に決断した」
ー亀岡移転の利点は。
「亀岡は当社の主力で京都三大漬物の一つである千枚漬の原料である聖護院かぶらの産地。農業離れにより原料確保が難しくなっていく時代において、産地と連携を密に取れるメリットは大きい。河川の氾濫や土砂崩れといった災害に強い点も魅力だった。ただ通勤の問題から退職を余儀なくされた職員さんがいたことを申し訳なく思う。新しい土地でより良い会社になることを誓いたい」
ースムーズ、安全、清潔がコンセプトだ。
「ワンフロアで、人もモノも一方通行とした。初日から早速『動線に従えば良いので迷いなく動ける。3階建てだった頃より作業性が段違いに良い』と好評だ。また陰陽圧管理やインターロック方式の設備を整えたことで異物の侵入を徹底的に防ぐなど工夫を凝らした。『安全』は食品安全の意味だけでなく、職員にとっての安全を含んでいる。前述の通り災害に強いことや、工房内でのフォークリフトを廃止したことで事故の原因を断っている」
(大阪支社・小林悟空)
◇ ◇
ー移転の経緯は。
「伏見工房が稼働開始したのが平成2年。一般的に言えば老朽化というほど古くないが、当時の基準で建てられており現在求められている衛生レベルに完璧に対応していくには改修が必要だったことや、3階建てで作業効率が悪かったことから移転を検討していた。背中を押したのが新型コロナウイルス。当社もお土産販売に大打撃を受けたことで、抜本的な改革を強く意識した。そんな折にこの地に新しい企業団地を立ち上げるお話を頂き、2020年7月に決断した」
ー亀岡移転の利点は。
「亀岡は当社の主力で京都三大漬物の一つである千枚漬の原料である聖護院かぶらの産地。農業離れにより原料確保が難しくなっていく時代において、産地と連携を密に取れるメリットは大きい。河川の氾濫や土砂崩れといった災害に強い点も魅力だった。ただ通勤の問題から退職を余儀なくされた職員さんがいたことを申し訳なく思う。新しい土地でより良い会社になることを誓いたい」
ースムーズ、安全、清潔がコンセプトだ。
「ワンフロアで、人もモノも一方通行とした。初日から早速『動線に従えば良いので迷いなく動ける。3階建てだった頃より作業性が段違いに良い』と好評だ。また陰陽圧管理やインターロック方式の設備を整えたことで異物の侵入を徹底的に防ぐなど工夫を凝らした。『安全』は食品安全の意味だけでなく、職員にとっての安全を含んでいる。前述の通り災害に強いことや、工房内でのフォークリフトを廃止したことで事故の原因を断っている」
ーSDGsについて。
「工房の屋根に太陽光パネルを敷くことで、工房内の冷蔵庫や空調にかかる電気の大部分を賄えるようになる。また今回の移転を機に女性事務員専用の制服を廃止して男女統一のジャンパーへ切り替えるなど男女の待遇差解消を推進している。食品ロス関連の取組としては、削減だけでなく有効活用や負荷低減の方向で取り組んでいる。京都市動物園の餌として野菜残渣を提供する取組を京都漬協とともに2年前から実施している。また今年5月には、野菜残渣の発酵化粧品『至貴ーShikiー』を発売する。さらに今春以降、生ゴミ処理機を設置する予定で、回収や償却にかかる燃料使用を削減する計画だ」
ー今後の方針は。
「環境としてはコロナ禍が収束ムードで観光客が戻ってきているし、価格より品質を重視される店から卸売りの商談を頂く機会も増えている。スムーズ、安全、清潔を実現した環境で、さらに品質を高めて、お届けしていきたい」
亀岡工房外観
【住所】亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1
【電話番号】(0771)21‐1171(代)
【FAX】(0771)21‐1173
【面積】敷地面積1万906平米、建物延床面積4406平米
【変更点・特徴的な設備】
▼上着掛室=コートやウィンドブレーカーなど汚れの付着しやすい上着専用のロッカーを設置した。
【底見せ長靴ラック】 長靴を突起に引っ掛けるように保管するラックを導入。底面のカビ防止や、汚れ発見に繋がる。
▼レンタル作業着=作業着の自宅洗濯をやめ、クリーニング店のレンタルサービスを活用。従業員の負担軽減と衛生レベル向上に。
▼工房内のフォークリフト廃止=事故防止のためハンドリフトに切り替えた。
▼一方通行の動線=原料入荷から加工、出荷までを一方通行で行える。下漬熟成庫、本漬熟成庫も動線上に設置。
▼空調・陰陽圧管理=工房内を陽圧にし異物、害虫の飛来を防止する。工房全館に空調が利き、品質管理や働きやすさの改善にも貢献。
▼生ゴミの低温保管庫=害獣、害虫の発生を防ぐため生ゴミを低温保管する。
▼太陽光発電=工房屋根部分に太陽光発電システムを設置。日中の電力使用の大半を賄える。
▼惣菜製造室=ちりめん山椒などの佃煮・惣菜用設備は別室で設置。
「工房の屋根に太陽光パネルを敷くことで、工房内の冷蔵庫や空調にかかる電気の大部分を賄えるようになる。また今回の移転を機に女性事務員専用の制服を廃止して男女統一のジャンパーへ切り替えるなど男女の待遇差解消を推進している。食品ロス関連の取組としては、削減だけでなく有効活用や負荷低減の方向で取り組んでいる。京都市動物園の餌として野菜残渣を提供する取組を京都漬協とともに2年前から実施している。また今年5月には、野菜残渣の発酵化粧品『至貴ーShikiー』を発売する。さらに今春以降、生ゴミ処理機を設置する予定で、回収や償却にかかる燃料使用を削減する計画だ」
ー今後の方針は。
「環境としてはコロナ禍が収束ムードで観光客が戻ってきているし、価格より品質を重視される店から卸売りの商談を頂く機会も増えている。スムーズ、安全、清潔を実現した環境で、さらに品質を高めて、お届けしていきたい」
亀岡工房外観
【住所】亀岡市篠町夕日ヶ丘四丁目3番地1
【電話番号】(0771)21‐1171(代)
【FAX】(0771)21‐1173
【面積】敷地面積1万906平米、建物延床面積4406平米
【変更点・特徴的な設備】
▼上着掛室=コートやウィンドブレーカーなど汚れの付着しやすい上着専用のロッカーを設置した。
【底見せ長靴ラック】 長靴を突起に引っ掛けるように保管するラックを導入。底面のカビ防止や、汚れ発見に繋がる。
▼レンタル作業着=作業着の自宅洗濯をやめ、クリーニング店のレンタルサービスを活用。従業員の負担軽減と衛生レベル向上に。
▼工房内のフォークリフト廃止=事故防止のためハンドリフトに切り替えた。
▼一方通行の動線=原料入荷から加工、出荷までを一方通行で行える。下漬熟成庫、本漬熟成庫も動線上に設置。
▼空調・陰陽圧管理=工房内を陽圧にし異物、害虫の飛来を防止する。工房全館に空調が利き、品質管理や働きやすさの改善にも貢献。
▼生ゴミの低温保管庫=害獣、害虫の発生を防ぐため生ゴミを低温保管する。
▼太陽光発電=工房屋根部分に太陽光発電システムを設置。日中の電力使用の大半を賄える。
▼惣菜製造室=ちりめん山椒などの佃煮・惣菜用設備は別室で設置。
【2023(令和5)年3月11日第5122号8面】
大安
3月11日号 クローズアップ
株式会社新進 企画開発本部係長 調理師 藤重俊行氏
バームクーヘンで新規事業
地元食材とバターにこだわり
株式会社新進のグループ会社である新進物産株式会社(金児正成社長、前橋市鳥羽町)では、3月21日開業予定の「道の駅まえばし赤城」(前橋市田口町)にバームクーヘン専門店「The Butter Baum」をオープンする。新規事業を担当する株式会社新進企画開発本部係長調理師の藤重俊行氏に新たなチャレンジのきっかけやバームクーヘンへのこだわりについて聞いた。
(藤井大碁)
◇ ◇
―新規事業をスタートする経緯。
「新たな道の駅が開設されることを機に、前橋市より道の駅の出店者の公募があり、その運営事業者の一社として弊社が選ばれたのが新規事業のきっかけ。新進では小麦澱粉を作っており、製菓材料として幅広く販売していることに加え、グループ会社である新進物産ではお菓子の取り扱いがあり、販路も持っているので、グループの強みを生かせる事業として菓子事業をスタートすることになった」
―バームクーヘンの製造販売を行う。
「バームクーヘンであればオープン設計の〝見せる工場〟を作ることができる、というのが大きな理由となった。新進グループでは安心安全をモットーにしており、見える工場を作れば、それをお客様にアピールすることができる。また、クルクル回転する製造工程が見えることで、幅広い年齢層の方に興味を持ってもらうことができるのもバームクーヘンの強みではないかと考えている」
―「The Butter Baum」のこだわり。
「小麦澱粉は自社製、小麦粉は県内産、鶏卵は前橋市内の養鶏所のものを使用するなど、できる限り地元原料を使用することにこだわっている。また、ブランド名にあるように、特に〝バター”の風味を重視した。厳選した国産の発酵バターを使用。手作業でバターを熱して、焦げるギリギリで香りを際立たせた〝焦がしバター〟を使用することで、味わいに違いを出している。店内のカフェでは、バームクーヘンの上から県内製造の特製バターをかけ、熱々のバームクーヘンでバターを溶かして食べてもらうメニューも提供する予定だ」
―開発の苦労。
「国内外の30種類以上のバームクーヘンを試食し、今までにないバームクーヘンを目指した。ふんわりしているもの、しっとりしているものはあったが、ふんわりとしっとりを両立しているバームクーヘンはなかなか無く、そこを目指した。配合が難しく、繊細なので、生地の調整に苦労した。直火焼と蒸し焼きを繰り返すことで、これまでにない新しい食感を生み出すことに成功した」
―道の駅ではオリジナル漬物も販売する。
「前橋産の大根、胡瓜、茄子、生姜、椎茸といった5種類の野菜を使用した福神漬や、前橋産のきのこを使用した漬物など、地場の素材を使用した特別感のある商品を販売していく予定だ」
―最後に。
「新進の創業は、焼麩の製造からスタートしており、小麦粉を使用した事業はある意味で原点回帰と言えるものかもしれない。新規事業なので目標を高く持ち、いずれは群馬県を代表するスイーツとして弊社のバームクーヘンを育てていきたい」
【2023(令和5)年3月11日第5122号4面】
地元食材とバターにこだわり
株式会社新進のグループ会社である新進物産株式会社(金児正成社長、前橋市鳥羽町)では、3月21日開業予定の「道の駅まえばし赤城」(前橋市田口町)にバームクーヘン専門店「The Butter Baum」をオープンする。新規事業を担当する株式会社新進企画開発本部係長調理師の藤重俊行氏に新たなチャレンジのきっかけやバームクーヘンへのこだわりについて聞いた。
(藤井大碁)
◇ ◇
―新規事業をスタートする経緯。
「新たな道の駅が開設されることを機に、前橋市より道の駅の出店者の公募があり、その運営事業者の一社として弊社が選ばれたのが新規事業のきっかけ。新進では小麦澱粉を作っており、製菓材料として幅広く販売していることに加え、グループ会社である新進物産ではお菓子の取り扱いがあり、販路も持っているので、グループの強みを生かせる事業として菓子事業をスタートすることになった」
―バームクーヘンの製造販売を行う。
「バームクーヘンであればオープン設計の〝見せる工場〟を作ることができる、というのが大きな理由となった。新進グループでは安心安全をモットーにしており、見える工場を作れば、それをお客様にアピールすることができる。また、クルクル回転する製造工程が見えることで、幅広い年齢層の方に興味を持ってもらうことができるのもバームクーヘンの強みではないかと考えている」
―「The Butter Baum」のこだわり。
「小麦澱粉は自社製、小麦粉は県内産、鶏卵は前橋市内の養鶏所のものを使用するなど、できる限り地元原料を使用することにこだわっている。また、ブランド名にあるように、特に〝バター”の風味を重視した。厳選した国産の発酵バターを使用。手作業でバターを熱して、焦げるギリギリで香りを際立たせた〝焦がしバター〟を使用することで、味わいに違いを出している。店内のカフェでは、バームクーヘンの上から県内製造の特製バターをかけ、熱々のバームクーヘンでバターを溶かして食べてもらうメニューも提供する予定だ」
―開発の苦労。
「国内外の30種類以上のバームクーヘンを試食し、今までにないバームクーヘンを目指した。ふんわりしているもの、しっとりしているものはあったが、ふんわりとしっとりを両立しているバームクーヘンはなかなか無く、そこを目指した。配合が難しく、繊細なので、生地の調整に苦労した。直火焼と蒸し焼きを繰り返すことで、これまでにない新しい食感を生み出すことに成功した」
―道の駅ではオリジナル漬物も販売する。
「前橋産の大根、胡瓜、茄子、生姜、椎茸といった5種類の野菜を使用した福神漬や、前橋産のきのこを使用した漬物など、地場の素材を使用した特別感のある商品を販売していく予定だ」
―最後に。
「新進の創業は、焼麩の製造からスタートしており、小麦粉を使用した事業はある意味で原点回帰と言えるものかもしれない。新規事業なので目標を高く持ち、いずれは群馬県を代表するスイーツとして弊社のバームクーヘンを育てていきたい」
【2023(令和5)年3月11日第5122号4面】
新進HP
3月1日号 トップに聞く
東京中央漬物株式会社 代表取締役社長 齋藤 正久氏
惣菜やおつまみを強化
SNSで若い世代にPR
東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。23年3月期下半期の業績や今後の展望などについて話を聞いた。漬物市場がシュリンクする中で、漬物以外の商品や売場に目を向ける必要性を強調。また、漬物離れが進む若い世代に向けてはSNSの活用を提言した。(千葉友寛)
◇ ◇
‐23年下半期の業績予想は。
「一言で言えば苦戦している。コロナ禍で無利子無担保の融資政策が行われたが、業績が改善せずに倒産、廃業している企業が増加している。年明け以降、漬物業界でも数社の倒産があり、その部分でも影響があった。弊社の売上は1年間で12月が一番多くなるのだが、今後の影響を考えて絞ったところもある。上半期は99・6%となったが、10月~1月は97・9%と落ち込んだ。最終的な着地としては99・2%を予想している」
‐小売用と業務用の売れ行きは。
「小売用は値上げの影響もあって苦戦している。業務用についてはインバウンド需要の増加も見込めるので、売上を伸ばしたいと思っている。昨年3月にまん延防止等重点措置が全面解除となったことで、外食関係の売れ行きが回復し、7割~8割戻ってきている。ただ、納め先でもコロナ禍で倒産、廃業したところもあるので、そこの部分は回復しない。今後はインバウンド需要も含めて新たな販路を開拓していく必要がある」
‐新たな販路とは。
「弊社は漬物専業問屋だが、漬物以外の商品でも新しい商品を取り入れていきたいと考えている。具体的には惣菜に近い商品を注視していて、売場も漬物ではなく惣菜や青果に置けるもの、人気のある土産品も魅力だ。取引のあるメーカーは漬物を提案しようという意識が強いと思うが、漬物以外の商品も案内してほしい。そのような商品があれば弊社のところで止めずにバイヤーに紹介し、これまでとは異なる売場に展開していきたいと考えている」
‐ニーズのトレンドは。
「スーパーの動きを見ると、個食向けや簡便性の高い商品が売れている。単身世帯が増加し、世帯人数も減少している中で、食べ切りサイズの商品や蓋を開けたら食べられるスライスのカップ製品が伸長している。その他にはザーサイなど、漬物というよりはお酒のおつまみのような商品も良い動きとなっている。若い人は料理をする機会が減っており、惣菜やおつまみを購入して家でご飯を食べてお酒を飲む、という流れになっている。そのようなところで売れる商品の提案を強化していきたいと思っている。そうしなければ売上は伸びない」
‐漬物の値上げの動きについて。
「昨年からずっと続いており、値上げの案内があればその都度得意先と商談している。現在は5月くらいまで話がきているが、その先はない。まだ様子を見ている企業もあるが、時期や金額などメーカーの希望通りにはいかないケースも多い。そのため、案内は早く出すことを推奨している」
‐若い世代へのPRについて。
「私の友人の子供でも漬物を食べたことがない、と言っていた。漬物に対してネガティブなイメージを持っている人はまだまだ多く、私もこの業界にいなければ食べず嫌いだったかもしれない。その部分は業界にとって大きな課題だ。特に若い人は漬物に興味を持っていないし、食べる機会もない。ではどうすれば良いのかということを考えると、若い人の多くが利用しているSNSでの情報発信が有効だと考えている。各企業でも漬物を素材としたレシピ提案を行っているが、このような活動を通してPRを行ってほしい。弊社もSNSの活用を検討している」
‐市場がシュリンクする中で御社の役割は。
「原材料の高騰や後継者不足など、多くの問題を抱えていることに加え、時代の移り変わりが速く対応していくことが困難になっている。取引先がついていけるように先頭に立って次の一手を考え、情報交換やアドバイスを継続的に行っていきたいと考えている。弊社が主力とする得意先は約200社あり、幅広い売場や販路がある。今後も情報と関係を密にして互いに利益を出せる形を構築していきたい」
【2023(令和5)年3月1日第5121号1面】
東京中央漬物 HP
2月11日号 SMTS特別インタビュー
秋本食品株式会社 代表取締役専務 秋本善明氏
持続可能な事業を推進
変化に対応し100周年へ
今年10月に創業90周年を迎える秋本食品株式会社(秋本大典社長、神奈川県綾瀬市)の代表取締役専務食品事業本部長(兼)マーケティング部長の秋本善明氏にインタビュー。年末年始の売れ行きや値上げの動きなどについて話を聞いた。同社はSDGsの観点から賞味期限延長の取組に注力して食品ロス削減などに貢献していく方針で、100周年に向けて持続可能な事業を推進していく姿勢を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
‐年末年始の売れ行き。
「全体的に見ると前年並みで推移している。中でも浅漬が苦戦した。白菜漬は売れたのだが、千枚漬やなますなど年末商材の動きが悪かった。キムチについても市場としては前年をクリアしているのだが、自社の動きは販促ができていないこともあり、あまり良くなかった。悪かった要因としては野菜安、生活費の上昇、物価高などが上げられる。その他の品目については、酢漬が値上げの影響で厳しい数字となっていて、沢庵は原料不足で一時期は販促を行うことができなかったが、年末には間に合った。在庫がある梅干しは、年末の動きも悪くなく、春夏に向けても期待している。あと、本漬の売れ行きはまずまずだった」
‐製造コストが上昇している。
「調味料、副資材、電気代とあらゆるコストが上がっていて、毎日のように値上げ要請が届いている。我々が使用する原料はほぼ国産のため、海外原料より上がり幅は小さいが、肥料代も上がっていることから国内の農家からも来年度は価格を上げる、という話もある。国内においても人件費、運賃が上がっている他、ハウス栽培で必要となる燃料やガスの価格も上昇しており、国産原料の価格は確実に上がる。これまで国産原料は価格が上がらないという前提で取り組んできたのだが、来年度は現在の製品価格を維持することは困難になることが予想される。製造コストは前年を大きく上回るペースで増えており、企業努力で吸収できるレベルをはるかに超えている。持続可能な事業を推進していくためにも、しっかりと価格転嫁していくことが重要だ」
‐値上げの動きは。
「弊社では昨年の春から案内を行い、夏以降に値上げを実施した。主力商品の一部は量目調整だが、大半の商品は価格改定。弊社は先行する形だったこともあって商品を差し替えられるケースもあったが、それは商品力がなかったということでもあり、ある意味で仕方がないことだと思っている。特に浅漬は差別化が難しい品目で、こだわって作った商品の価格が例えば1・5倍になった場合、価値を認めて購入していただけるのか。近年、浅漬についてはお客様が何を求め、どこに価値を感じるのか見極めるのが難しくなっている。弊社の値上げは一巡したが、製造コストが上昇し続けているため、第2弾の対策をどのような形で行っていくか検討している段階だ」
‐御社の取組について。
「弊社では、『あとひきだいこん』や『王道キムチ』といったオンリーワンの商品を安売りすることなく、味と品質にこだわって大事に販売していきたいと考えている。また、ここ数年の継続課題として賞味期限延長にトライしている。賞味期限が延長できれば売場のロス率低下につながり、お客様にもメリットがある。昨年9月には主力商品の一つである『オモニの極旨キムチ』の賞味期限を21日間から31日間に延長した。これらはSDGsの観点からも重要なポイントとなっており、今後も重要課題として取り組んでいく」
‐漬物市場の将来性。
「私見だが、漬物はデリカの売場でもすでに販売され実績を出している事例もあるが、お客様に部門の境目はない。お客様が商品を購入するのに便利か便利じゃないか、ということが重要で、関連販売でメニューをイメージできる商品を提供できれば支持されるはずだ。ただそういった商品を既存の漬物売場に置いても埋もれてしまうし、そもそも漬物売場を通らない人も多い。画一化された売場ではなく、クロスMDを活用するなど、売場そのものをコーディネートしていきながら漬物に興味を持ってもらう仕掛けが必要だと思っている。その為には店側の協力も必要となる」
‐自社のPRを。
「弊社は今年10月に創業90周年を迎える。『味の逸品』を掲げ、先々代から受け継いできた『味』と『品質』をこれからも守り続けていきたいと考えている。創業当時は沢庵が主力商品だったが、時代のニーズに合わせて浅漬やキムチに主軸を移してきた。全国の有力な漬物メーカーとパイプがあり、幅広い得意先を持つ漬物製造ベンダーとしての強みを活かしながら、100周年に向けて時代の変化にしっかりと対応し、『秋本の商品は美味しい』と言っていただけるような商品を作り続けていきたい」
‐年末年始の売れ行き。
「全体的に見ると前年並みで推移している。中でも浅漬が苦戦した。白菜漬は売れたのだが、千枚漬やなますなど年末商材の動きが悪かった。キムチについても市場としては前年をクリアしているのだが、自社の動きは販促ができていないこともあり、あまり良くなかった。悪かった要因としては野菜安、生活費の上昇、物価高などが上げられる。その他の品目については、酢漬が値上げの影響で厳しい数字となっていて、沢庵は原料不足で一時期は販促を行うことができなかったが、年末には間に合った。在庫がある梅干しは、年末の動きも悪くなく、春夏に向けても期待している。あと、本漬の売れ行きはまずまずだった」
‐製造コストが上昇している。
「調味料、副資材、電気代とあらゆるコストが上がっていて、毎日のように値上げ要請が届いている。我々が使用する原料はほぼ国産のため、海外原料より上がり幅は小さいが、肥料代も上がっていることから国内の農家からも来年度は価格を上げる、という話もある。国内においても人件費、運賃が上がっている他、ハウス栽培で必要となる燃料やガスの価格も上昇しており、国産原料の価格は確実に上がる。これまで国産原料は価格が上がらないという前提で取り組んできたのだが、来年度は現在の製品価格を維持することは困難になることが予想される。製造コストは前年を大きく上回るペースで増えており、企業努力で吸収できるレベルをはるかに超えている。持続可能な事業を推進していくためにも、しっかりと価格転嫁していくことが重要だ」
‐値上げの動きは。
「弊社では昨年の春から案内を行い、夏以降に値上げを実施した。主力商品の一部は量目調整だが、大半の商品は価格改定。弊社は先行する形だったこともあって商品を差し替えられるケースもあったが、それは商品力がなかったということでもあり、ある意味で仕方がないことだと思っている。特に浅漬は差別化が難しい品目で、こだわって作った商品の価格が例えば1・5倍になった場合、価値を認めて購入していただけるのか。近年、浅漬についてはお客様が何を求め、どこに価値を感じるのか見極めるのが難しくなっている。弊社の値上げは一巡したが、製造コストが上昇し続けているため、第2弾の対策をどのような形で行っていくか検討している段階だ」
‐御社の取組について。
「弊社では、『あとひきだいこん』や『王道キムチ』といったオンリーワンの商品を安売りすることなく、味と品質にこだわって大事に販売していきたいと考えている。また、ここ数年の継続課題として賞味期限延長にトライしている。賞味期限が延長できれば売場のロス率低下につながり、お客様にもメリットがある。昨年9月には主力商品の一つである『オモニの極旨キムチ』の賞味期限を21日間から31日間に延長した。これらはSDGsの観点からも重要なポイントとなっており、今後も重要課題として取り組んでいく」
‐漬物市場の将来性。
「私見だが、漬物はデリカの売場でもすでに販売され実績を出している事例もあるが、お客様に部門の境目はない。お客様が商品を購入するのに便利か便利じゃないか、ということが重要で、関連販売でメニューをイメージできる商品を提供できれば支持されるはずだ。ただそういった商品を既存の漬物売場に置いても埋もれてしまうし、そもそも漬物売場を通らない人も多い。画一化された売場ではなく、クロスMDを活用するなど、売場そのものをコーディネートしていきながら漬物に興味を持ってもらう仕掛けが必要だと思っている。その為には店側の協力も必要となる」
‐自社のPRを。
「弊社は今年10月に創業90周年を迎える。『味の逸品』を掲げ、先々代から受け継いできた『味』と『品質』をこれからも守り続けていきたいと考えている。創業当時は沢庵が主力商品だったが、時代のニーズに合わせて浅漬やキムチに主軸を移してきた。全国の有力な漬物メーカーとパイプがあり、幅広い得意先を持つ漬物製造ベンダーとしての強みを活かしながら、100周年に向けて時代の変化にしっかりと対応し、『秋本の商品は美味しい』と言っていただけるような商品を作り続けていきたい」
【2023(令和5)年2月11日第5119号2面】
秋本食品株式会社
2月11日号 SMTS特別インタビュー
株式会社山重 代表取締役社長 杉山博氏
原点回帰で新たなスタート
ニーズを創造し需要開拓
株式会社山重(東京都葛飾区)は、漬物をはじめ日配のプロとして全国に物流網を持つ一次荷受問屋。取引先は全国44都道府県、仕入れ件数は346件と地方の名産品も数多く取り扱っている。同社は単に商品を物流に乗せるだけではなく、メーカーと商品を共同開発して企画・売場提案を行いながら量販店、外食、中食、ベンダーなど様々な販売チャネルに供給。開発力と提案力を併せ持つ同社は業界内外から高く評価され、厚い信頼を寄せられている。杉山博社長に今期の業績及び来期の見通しについて話を聞いた。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐漬物の売れ行きと今期の業績について。
「漬物の売れ行きは全般的に増加要因が見当たらない。巣ごもり需要の反動もあるが、特に浅漬の動きが悪く、売場も縮小傾向にある。コロナ禍で需要が増えたキムチも落ち着いている。消費者の所得が増えない中、燃料費高騰による様々な物価上昇が家計を圧迫し、購買意欲の低下対象商品として漬物が含まれている感がある。弊社は3月決算で未だ確定していないが、厳しい外的要因の中、前年比並みの売上を維持したものの、事務所移転に伴うコストにより減益の見通しだ」
‐昨年10月に事務所を埼玉から東京に移転した。
「弊社は4月から61期となる。漬物業界の構造的問題を打破するためには、創業者が築いた経営理念に改めて向き合うことが大事であると考え、原点回帰の意味を込めて、葛飾の事務所に5年ぶりに戻ってくる形となった。内装も一新し、新たな気持ちで事業を行っていきたいと考えている」
‐漬物売場について。
「消費者は生野菜を食べるが、野菜の加工品は食べない。漬物の歴史を振り返ると、『生野菜を食す』『主食のお供』としての関係がマッチして漬物が広まったが、現代ではこの2つに何か見えない壁のようなものがあると思っている。その壁を打ち崩さない限り、漬物の需要は増えない。この壁を取り崩す提案を行うことこそが当社の使命だと考えており、61期より仕掛ける予定でいる。一方、現状の商品群に目を置くと、新商品が消費者の購買意欲を沸かせる大きな差別化までには至っていないのではないかと考えている。そこで注目されるのが地方の名産品だ。近年では、『山形のだし』や『いぶりがっこ』が地方で発掘されて広域流通につながった。日頃からアンテナを高く張り、そのような商品を見つけて提案するのが問屋の本質であるが、その部分こそが他社にない当社の強みだと思っている」
‐昨年から続く値上げの動きは。
「漬物売場でも値上げの動きは増えているが、肌感では全体の6、7割くらいに留まっている。カテゴリーにもよるが、商品の切り替えや消費者離れを懸念して値上げに踏み切れないメーカーも数多く存在する。弊社は値上げの要請があれば得意先に案内を行うが、まだ様子を見ているところもある。原材料価格が上がり、包装資材や調味料の他、電気代、燃料代、物流費などのコストが上昇する中、価格転嫁しなければ採算が合わなくなる。更に、巣ごもり需要の反動による漬物業界の規模縮小によって体力勝負の様相となっており、特に、価格転嫁をストレートに反映できない中小企業には大きな影響が出てくるだろう」
‐ 一次荷受問屋である御社の役割は。
「我々に求められているのは提案力。メーカーと協力して新たな商品を開発し、ニーズを創造していくことは経営方針でもある。少子高齢化や単身世帯の増加などを考えると、食品業界において伸びていくのは惣菜と冷凍食品。漬物を従来の売場だけで販売していても市場を維持することはできない。それならば、惣菜売場で販売できる惣菜風の漬物を開発したり、関連販売で漬物を置けるような提案を行っていくことが必要だ」
‐新しい事業や取組について。
「まだ詳細は言えないのだが、新しい需要の開拓という意味では幅広い人へのPRが重要で、漬物をより身近に、より便利に利用できる情報を提供していきたいと考えている。価値のある、すなわち『食したい、買いたい』という購買意欲を湧き立たせる漬物ならば、適正価格でも販売が可能であると考えている。間もなく迎える61期から新たな仕掛けを行っていきたいので、ご期待いただきたい」
◇ ◇
‐漬物の売れ行きと今期の業績について。
「漬物の売れ行きは全般的に増加要因が見当たらない。巣ごもり需要の反動もあるが、特に浅漬の動きが悪く、売場も縮小傾向にある。コロナ禍で需要が増えたキムチも落ち着いている。消費者の所得が増えない中、燃料費高騰による様々な物価上昇が家計を圧迫し、購買意欲の低下対象商品として漬物が含まれている感がある。弊社は3月決算で未だ確定していないが、厳しい外的要因の中、前年比並みの売上を維持したものの、事務所移転に伴うコストにより減益の見通しだ」
‐昨年10月に事務所を埼玉から東京に移転した。
「弊社は4月から61期となる。漬物業界の構造的問題を打破するためには、創業者が築いた経営理念に改めて向き合うことが大事であると考え、原点回帰の意味を込めて、葛飾の事務所に5年ぶりに戻ってくる形となった。内装も一新し、新たな気持ちで事業を行っていきたいと考えている」
‐漬物売場について。
「消費者は生野菜を食べるが、野菜の加工品は食べない。漬物の歴史を振り返ると、『生野菜を食す』『主食のお供』としての関係がマッチして漬物が広まったが、現代ではこの2つに何か見えない壁のようなものがあると思っている。その壁を打ち崩さない限り、漬物の需要は増えない。この壁を取り崩す提案を行うことこそが当社の使命だと考えており、61期より仕掛ける予定でいる。一方、現状の商品群に目を置くと、新商品が消費者の購買意欲を沸かせる大きな差別化までには至っていないのではないかと考えている。そこで注目されるのが地方の名産品だ。近年では、『山形のだし』や『いぶりがっこ』が地方で発掘されて広域流通につながった。日頃からアンテナを高く張り、そのような商品を見つけて提案するのが問屋の本質であるが、その部分こそが他社にない当社の強みだと思っている」
‐昨年から続く値上げの動きは。
「漬物売場でも値上げの動きは増えているが、肌感では全体の6、7割くらいに留まっている。カテゴリーにもよるが、商品の切り替えや消費者離れを懸念して値上げに踏み切れないメーカーも数多く存在する。弊社は値上げの要請があれば得意先に案内を行うが、まだ様子を見ているところもある。原材料価格が上がり、包装資材や調味料の他、電気代、燃料代、物流費などのコストが上昇する中、価格転嫁しなければ採算が合わなくなる。更に、巣ごもり需要の反動による漬物業界の規模縮小によって体力勝負の様相となっており、特に、価格転嫁をストレートに反映できない中小企業には大きな影響が出てくるだろう」
‐ 一次荷受問屋である御社の役割は。
「我々に求められているのは提案力。メーカーと協力して新たな商品を開発し、ニーズを創造していくことは経営方針でもある。少子高齢化や単身世帯の増加などを考えると、食品業界において伸びていくのは惣菜と冷凍食品。漬物を従来の売場だけで販売していても市場を維持することはできない。それならば、惣菜売場で販売できる惣菜風の漬物を開発したり、関連販売で漬物を置けるような提案を行っていくことが必要だ」
‐新しい事業や取組について。
「まだ詳細は言えないのだが、新しい需要の開拓という意味では幅広い人へのPRが重要で、漬物をより身近に、より便利に利用できる情報を提供していきたいと考えている。価値のある、すなわち『食したい、買いたい』という購買意欲を湧き立たせる漬物ならば、適正価格でも販売が可能であると考えている。間もなく迎える61期から新たな仕掛けを行っていきたいので、ご期待いただきたい」
【2023(令和5)年2月11日第5119号19面】
株式会社山重
2月11日号 SMTS特別インタビュー
株式会社五味商店 代表取締役社長 寺谷健治氏
過去最多140社が出展
『冷凍食品』『全国銘菓』コーナーも
『スーパーマーケット・トレードショー2023』(2月15日~17日・幕張メッセ)において、全国から厳選した食品を紹介する株式会社五味商店(千葉県我孫子市)の「こだわり商品コーナー」(会場9ホール)は今回で24回目の出展となる。スーパーマーケット・トレードショーの出展者代表委員も務める五味商店の寺谷健治社長に、今回の見どころや現在の消費トレンドについて聞いた。(藤井大碁)
◇ ◇
――今回の見どころ。
「今回の出展者数は昨年より32社多い140社で、過去最多となる。ブース面積も前回より広がる。全国商工会連合会から新規で20社が出展するなど新規出展者も39社あり、今回もたくさんの発見をして頂けると思う。ブース内では、夏の展示会の際にバイヤーさんから要望が多かった『冷凍食品』と『全国銘菓』のコーナーを展開する。今、一番有益な情報をタイムリーに提案することで、来て良かったと思って頂けるブース作りを行っている」
――足元の状況。
「3月決算は前年並の売上を見込んでいる。コロナ下の3年間で売上は上昇を続けてきたが、ピークは過ぎ、昨年夏以降は動きが落ち着いてきている。だが引き続きこだわり商品へのニーズは高止まりしている。様々な物が値上がりし、節約志向が強まっているが、自分の欲しいものにはしっかりとお金を払う〝メリハリ消費〟が定着した。こうした消費者ニーズに対応していけば、まだまだ売上が伸ばせると考えている」
――消費者トレンド。
「現在、出展者の皆様に出品をお願いしているのは〝サステナブル”や〝SDGs〟の要素を持つ商品だ。時代の変化や、世代による価値観の違いもあり、価値のある商品は十人十色になっている。これまでのような大きな市場はシュリンクし、今後は細分化した市場への対応が求められる。美味しさや安全安心が商品の絶対条件だとすれば、サステナブルやSDGsといった要素は必要条件と言える。だがZ世代のように、そうした価値観に基づいて商品を選択する人たちが増えてきている。また、甘すぎる商品も時代が変わり受け入れられなくなってきている。減塩、添加物や砂糖の不使用等素材を生かした薄味への変化が求められている」
――新しい売場。
「ある農協の直営店舗では、弊社から商品を卸すようになり、商品単価が1割以上上昇し、全体の売上も伸長した。各地の農作物直売所では生鮮品については地元農家から仕入れられるが、加工品の品揃えに課題を持つ店舗もある。この部分を弊社が補うことで売上増に貢献できる事例が出てきている。近年、食品を取り扱う雑貨店が増え、売り先が広がっているが、まだまだこうした新しい売り先を開拓できると考えている」
――食品メーカーにとって厳しい環境が続いている。
「様々なコスト増により、経営のプロでないと生き残るのが難しい時代になっている。前述の通り、消費者ニーズは多様化しており〝付加価値のある市場〟は確かに存在する。だが、その市場にあった商品を作り、販売していくためには、経営力・販売力・商品力といった3つの力が必要で、どれかが欠けても競争に勝てない。この中で一番大切なのは経営力を磨くことだ。そのために、経営者のマインドを外向きに変えていく作業が必要で、トレードショーへの出展はその一つのステップとなる。昨年初めて出展した事業者は、経営者が新しい世界を見てやる気になり、新工場を建設することになった。新工場ができれば、雇用が生まれ、地域活性化につながる。弊社の目標はこうしたケースを1つでも多く作っていくことだ」
――今後の見通し。
「時代の変化は早いが、〝人間が生活の豊かさを求めること〟はいつの時代も変わらない。その豊かさは時代と共に変化し、サステナブルやSDGsといった自然との共生という価値観が広がっている。豊かな生活をしたいというのは、人間の本質的なものであり、それがある限りは、我々の商品を供給することで喜んで頂けるのではないか」
【2023(令和5)年2月11日第5119号5面】
株式会社五味商店
『冷凍食品』『全国銘菓』コーナーも
『スーパーマーケット・トレードショー2023』(2月15日~17日・幕張メッセ)において、全国から厳選した食品を紹介する株式会社五味商店(千葉県我孫子市)の「こだわり商品コーナー」(会場9ホール)は今回で24回目の出展となる。スーパーマーケット・トレードショーの出展者代表委員も務める五味商店の寺谷健治社長に、今回の見どころや現在の消費トレンドについて聞いた。(藤井大碁)
◇ ◇
――今回の見どころ。
「今回の出展者数は昨年より32社多い140社で、過去最多となる。ブース面積も前回より広がる。全国商工会連合会から新規で20社が出展するなど新規出展者も39社あり、今回もたくさんの発見をして頂けると思う。ブース内では、夏の展示会の際にバイヤーさんから要望が多かった『冷凍食品』と『全国銘菓』のコーナーを展開する。今、一番有益な情報をタイムリーに提案することで、来て良かったと思って頂けるブース作りを行っている」
――足元の状況。
「3月決算は前年並の売上を見込んでいる。コロナ下の3年間で売上は上昇を続けてきたが、ピークは過ぎ、昨年夏以降は動きが落ち着いてきている。だが引き続きこだわり商品へのニーズは高止まりしている。様々な物が値上がりし、節約志向が強まっているが、自分の欲しいものにはしっかりとお金を払う〝メリハリ消費〟が定着した。こうした消費者ニーズに対応していけば、まだまだ売上が伸ばせると考えている」
――消費者トレンド。
「現在、出展者の皆様に出品をお願いしているのは〝サステナブル”や〝SDGs〟の要素を持つ商品だ。時代の変化や、世代による価値観の違いもあり、価値のある商品は十人十色になっている。これまでのような大きな市場はシュリンクし、今後は細分化した市場への対応が求められる。美味しさや安全安心が商品の絶対条件だとすれば、サステナブルやSDGsといった要素は必要条件と言える。だがZ世代のように、そうした価値観に基づいて商品を選択する人たちが増えてきている。また、甘すぎる商品も時代が変わり受け入れられなくなってきている。減塩、添加物や砂糖の不使用等素材を生かした薄味への変化が求められている」
――新しい売場。
「ある農協の直営店舗では、弊社から商品を卸すようになり、商品単価が1割以上上昇し、全体の売上も伸長した。各地の農作物直売所では生鮮品については地元農家から仕入れられるが、加工品の品揃えに課題を持つ店舗もある。この部分を弊社が補うことで売上増に貢献できる事例が出てきている。近年、食品を取り扱う雑貨店が増え、売り先が広がっているが、まだまだこうした新しい売り先を開拓できると考えている」
――食品メーカーにとって厳しい環境が続いている。
「様々なコスト増により、経営のプロでないと生き残るのが難しい時代になっている。前述の通り、消費者ニーズは多様化しており〝付加価値のある市場〟は確かに存在する。だが、その市場にあった商品を作り、販売していくためには、経営力・販売力・商品力といった3つの力が必要で、どれかが欠けても競争に勝てない。この中で一番大切なのは経営力を磨くことだ。そのために、経営者のマインドを外向きに変えていく作業が必要で、トレードショーへの出展はその一つのステップとなる。昨年初めて出展した事業者は、経営者が新しい世界を見てやる気になり、新工場を建設することになった。新工場ができれば、雇用が生まれ、地域活性化につながる。弊社の目標はこうしたケースを1つでも多く作っていくことだ」
――今後の見通し。
「時代の変化は早いが、〝人間が生活の豊かさを求めること〟はいつの時代も変わらない。その豊かさは時代と共に変化し、サステナブルやSDGsといった自然との共生という価値観が広がっている。豊かな生活をしたいというのは、人間の本質的なものであり、それがある限りは、我々の商品を供給することで喜んで頂けるのではないか」
【2023(令和5)年2月11日第5119号5面】
株式会社五味商店
https://www.syokuryou-shinbun.com/pages/477/(電子版地域セレクション)
1月21日号 DTS特別インタビュー
全国スーパーマーケット協会 事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター 籾山朋輝氏
「お弁当・お惣菜大賞」注目度上昇
今年は“プラントベース元年”に
デリカテッセン・トレードショー2023(以下、DTS)が2月15日から17日まで幕張メッセにて開催される。DTSは中食産業の最新情報を発信する商談展示会。主催者企画「お弁当・お惣菜大賞」は近年注目度が上昇、売場の販促ツールとして大きな存在になりつつある。DTS会場内では今年も受賞商品の一部を実食できるフードコートを展開する予定だ。DTSを主催する一般社団法人全国スーパーマーケット協会事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター・籾山朋輝氏にインタビュー。籾山氏はデリカ売場の動向やトレンドについて語った。
今年は“プラントベース元年”に
デリカテッセン・トレードショー2023(以下、DTS)が2月15日から17日まで幕張メッセにて開催される。DTSは中食産業の最新情報を発信する商談展示会。主催者企画「お弁当・お惣菜大賞」は近年注目度が上昇、売場の販促ツールとして大きな存在になりつつある。DTS会場内では今年も受賞商品の一部を実食できるフードコートを展開する予定だ。DTSを主催する一般社団法人全国スーパーマーケット協会事業部展示会課兼事業創造室チーフディレクター・籾山朋輝氏にインタビュー。籾山氏はデリカ売場の動向やトレンドについて語った。
(藤井大碁)
―デリカ売場の動向。
「昨年一年間のデリカカテゴリーの売上推移は他のカテゴリーと比較して突出して良かった。直近のSM3団体統計調査のデータを見ても、12月は全店ベースで106・9%となっており、全カテゴリーで一番伸び率が高い。即食や簡便性を求める生活スタイルがコロナ前に戻りつつあり、さらに加速している。当初は、外食の復調により、スーパーの売上は落ち込むと予想されていたが、現状は惣菜以外のカテゴリーもそこまで落ちていない。直近の数字は値上げの影響もあり、詳細分析が難しい部分もあるが、スーパーへの来店頻度や購買額が上がっていると推測できる。コロナ特需が薄れて他業態に売上がシフトしそうなところだが、食品スーパーは健闘しており、その中でも惣菜カテゴリーは大健闘している」
―惣菜カテゴリーが好調な要因。
「コロナを機に消費者の生活スタイルが変化したことが大きい。外食の中でも居酒屋の売上はコロナ前に戻り切っておらず、その需要の一部がスーパーでの購買に流れていると考えられる。デリカ売場では、家飲み需要に対応するため、おつまみ系のラインナップを増やしており、好調を持続している。様々な物が値上がりして節約志向が高まる中、外食より中食、内食を選択する消費者が多く、そうした流れも追い風になっている」
―DTS2023の見どころ。
「出展者数は前回とほぼ同様で、約40社・団体の220小間。今回は新規の惣菜ベンダーが出展する。惣菜ベンダーは、現在の惣菜売場の課題である人手不足を補完する役割を担っており、今回の展示会においても注目を集めそうだ」
―お弁当・お惣菜大賞への注目度が上昇している。
「メディアで取り上げられる機会が増えたこともあり、おかげ様で反響が大きい。店舗の売場活性化のためにうまく活用して頂いている。専門店や大手スーパーのエントリーも年々増加している。過年度の受賞商品をリバイバルしてフェアを実施した店舗では、売上が大きく伸びたと聞いている。また従業員の商品開発のモチベーションを上げるためにお弁当・お惣菜大賞を活用する企業も増えてきている。商品開発の枠組みの中に、お弁当・お惣菜大賞のエントリーを紐づけ、明確なゴールを設定することで、開発チームのモチベーションアップにつなげている」
―売場のトレンド。
「今年、お弁当・お惣菜大賞のエントリーで際立って増えたのが、プラントベース由来の食材を使用した商品だ。SDGsの流れに加えて、健康のために手に取る消費賞が増えている。コンビニでの販売や外食での提供も増えており、消費者にとってより身近な存在になってきた。今後も売上が伸びていくことが予想され、各社の商品開発が活発化している。今年は、デリカ売場にとって〝プラントベース元年〟と言える年になるのではないか」
―売場の課題。
「人手不足が深刻化している。事業者側も手間をかけた商品が売れるのは分かっているが、それを全店で展開する際の人時を考えた時に商品化できないというジレンマがある。うまく人を集めて独自商品を開発したり、プロセスセンターをフル活用するなど、各事業者が知恵を絞って対応している。ただ足元では、他の売場と同じようにベンダーからの仕入れ商品を販売せざるを得ない状況もある。理想と現実をすり合わせて、インストアとアウトパックをうまく使い分ける必要が出てきている」
―今後の見通し。
「デリカ売場は好調を維持している。新商品開発に加え、唐揚げや餃子といった定番品のブラッシュアップや粗利率の改善も重要になってきている。今までは、価格訴求型の商品が多かったが、外食ニーズを取り込むために、もうワンランク上の惣菜開発が活性化し、それが消費者に受け入れられている。来店頻度を下げない仕掛けをしつつ、商品開発をさらに推し進めていけば、まだまだ売上を伸ばせるのではないか」
【2023(令和5)年1月21日第5118号6面】
デリカテッセン・トレードショー公式サイト
https://www.delica.jp/
―デリカ売場の動向。
「昨年一年間のデリカカテゴリーの売上推移は他のカテゴリーと比較して突出して良かった。直近のSM3団体統計調査のデータを見ても、12月は全店ベースで106・9%となっており、全カテゴリーで一番伸び率が高い。即食や簡便性を求める生活スタイルがコロナ前に戻りつつあり、さらに加速している。当初は、外食の復調により、スーパーの売上は落ち込むと予想されていたが、現状は惣菜以外のカテゴリーもそこまで落ちていない。直近の数字は値上げの影響もあり、詳細分析が難しい部分もあるが、スーパーへの来店頻度や購買額が上がっていると推測できる。コロナ特需が薄れて他業態に売上がシフトしそうなところだが、食品スーパーは健闘しており、その中でも惣菜カテゴリーは大健闘している」
―惣菜カテゴリーが好調な要因。
「コロナを機に消費者の生活スタイルが変化したことが大きい。外食の中でも居酒屋の売上はコロナ前に戻り切っておらず、その需要の一部がスーパーでの購買に流れていると考えられる。デリカ売場では、家飲み需要に対応するため、おつまみ系のラインナップを増やしており、好調を持続している。様々な物が値上がりして節約志向が高まる中、外食より中食、内食を選択する消費者が多く、そうした流れも追い風になっている」
―DTS2023の見どころ。
「出展者数は前回とほぼ同様で、約40社・団体の220小間。今回は新規の惣菜ベンダーが出展する。惣菜ベンダーは、現在の惣菜売場の課題である人手不足を補完する役割を担っており、今回の展示会においても注目を集めそうだ」
―お弁当・お惣菜大賞への注目度が上昇している。
「メディアで取り上げられる機会が増えたこともあり、おかげ様で反響が大きい。店舗の売場活性化のためにうまく活用して頂いている。専門店や大手スーパーのエントリーも年々増加している。過年度の受賞商品をリバイバルしてフェアを実施した店舗では、売上が大きく伸びたと聞いている。また従業員の商品開発のモチベーションを上げるためにお弁当・お惣菜大賞を活用する企業も増えてきている。商品開発の枠組みの中に、お弁当・お惣菜大賞のエントリーを紐づけ、明確なゴールを設定することで、開発チームのモチベーションアップにつなげている」
―売場のトレンド。
「今年、お弁当・お惣菜大賞のエントリーで際立って増えたのが、プラントベース由来の食材を使用した商品だ。SDGsの流れに加えて、健康のために手に取る消費賞が増えている。コンビニでの販売や外食での提供も増えており、消費者にとってより身近な存在になってきた。今後も売上が伸びていくことが予想され、各社の商品開発が活発化している。今年は、デリカ売場にとって〝プラントベース元年〟と言える年になるのではないか」
―売場の課題。
「人手不足が深刻化している。事業者側も手間をかけた商品が売れるのは分かっているが、それを全店で展開する際の人時を考えた時に商品化できないというジレンマがある。うまく人を集めて独自商品を開発したり、プロセスセンターをフル活用するなど、各事業者が知恵を絞って対応している。ただ足元では、他の売場と同じようにベンダーからの仕入れ商品を販売せざるを得ない状況もある。理想と現実をすり合わせて、インストアとアウトパックをうまく使い分ける必要が出てきている」
―今後の見通し。
「デリカ売場は好調を維持している。新商品開発に加え、唐揚げや餃子といった定番品のブラッシュアップや粗利率の改善も重要になってきている。今までは、価格訴求型の商品が多かったが、外食ニーズを取り込むために、もうワンランク上の惣菜開発が活性化し、それが消費者に受け入れられている。来店頻度を下げない仕掛けをしつつ、商品開発をさらに推し進めていけば、まだまだ売上を伸ばせるのではないか」
【2023(令和5)年1月21日第5118号6面】
デリカテッセン・トレードショー公式サイト
https://www.delica.jp/
1月11日号 トップに聞く
三井食品工業株式会社 代表取締役社長 岩田浩行氏
盤石な利益体質の構造作る
新しい事業で販路拡大
三井食品工業株式会社(愛知県一宮市)の岩田浩行社長にインタビュー。昨年8月から今期を迎え、製品の売れ行きや原料動向、今後の方針などについて話を聞いた。3カ年計画では盤石な利益体質の構造を作ることを目標に掲げていることを明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
-製品の売れ行きについて。
「前期は減収増益となったが、今期は非常に厳しい1年になると予測している。3カ年計画では盤石な利益体質の構造を作ることを柱としている。利益面については原材料の部分で大きく変わってくるため、原料仕入れは重要なポイントとなる。従来は旬の素材を安く購入しようとしていたが、天候の影響などによるリスクも大きいため、一定の価格で安定供給できればその方が良い、ということで原料野菜の契約率を高める取組を進めている。原料野菜の契約率を高めていくために、安定した収益の確保を目指している」
-値上げの動きについて。
「当社の浅漬製品は、量目調整か価格改定のどちらかでの対応で、昨年9月から10月に平均6%の値上げを行った。当社は他社より先行した動きとなり、切り替えられることもあったし、売れ行きは苦戦している。経営者の考え方次第だが、かつてない程に製造コストが上がっている中で値上げをせず、売上を優先しても未来はないと思っている。当社では過去に全品の値上げを行ったことがなく、今回の値上げはある意味で訓練だと思っている。もちろん、原材料や製造コストが下がれば製品価格も下げる。この10年、20年の間、製品の価格が変わっていない、ということ事態がおかしいことだが、現在の流れで価格を維持することはとてもできない。コロナ禍で政府は無利子無担保の融資を行った。融資の返済は年明けから本格的に始まるので、業界問わず様々な話が出てくるだろう」
-進行する円安の影響も大きい。
「漬物も含めて日本は多くの原材料を輸入に依存している。だが、進行する円安の影響もあり、日本の優位性は失われつつある。また、日本が他国に買い負ける事例も出てきており、海外のものが日本に入ってこなくなるかもしれないし、今後数年で海外の原料や製品の方が高くなる可能性もある。そこでクローズアップされるのが国産原料や国内製造の製品だ。生産の維持と拡大には大きな課題があるが、需要があれば減っていくばかりではないと考えている」
-漬物のマーケットや未来像は。
「正直に言って、明るい材料は少ない。ベンダーとしては新規取引先も増えて良い話もいただいているが、業界はシュリンクしており、これからの5年で淘汰も進むだろう。当社の本漬製品も5年後を見据えた時、どこまで売上に貢献できているのか分からない。事業継続の最善策として考えられるのは、適正価格での販売、健康機能性の訴求、新商品開発などが上げられるが、それらは過去にもやっていることで、新しい施策はない。だが、明るい話題もある。当社の事業を見直してみると、やはり野菜加工が強みであり特徴でもある。漬物を製造しなくても味付けした野菜をこれまでとは違うルートに販売できれば販路を広げていくことができる。詳細は言えないが、私が社長に就任してから新しい取組を進めている。その事業はまだスタートの段階だが、全体の売上の3~5%まで増えていて、10%を目指している。その市場にはまだまだ伸び代があり、さらに拡大していく可能性がある。そのようなところにスポットを当て、前向きに進んでいきたいと考えている」
【2023(令和5)年1月11日第5117号11面】
三井食品工業 HP
https://mitsuishokuhin.jimdo.com/
新しい事業で販路拡大
三井食品工業株式会社(愛知県一宮市)の岩田浩行社長にインタビュー。昨年8月から今期を迎え、製品の売れ行きや原料動向、今後の方針などについて話を聞いた。3カ年計画では盤石な利益体質の構造を作ることを目標に掲げていることを明かした。
(千葉友寛)
◇ ◇
-製品の売れ行きについて。
「前期は減収増益となったが、今期は非常に厳しい1年になると予測している。3カ年計画では盤石な利益体質の構造を作ることを柱としている。利益面については原材料の部分で大きく変わってくるため、原料仕入れは重要なポイントとなる。従来は旬の素材を安く購入しようとしていたが、天候の影響などによるリスクも大きいため、一定の価格で安定供給できればその方が良い、ということで原料野菜の契約率を高める取組を進めている。原料野菜の契約率を高めていくために、安定した収益の確保を目指している」
-値上げの動きについて。
「当社の浅漬製品は、量目調整か価格改定のどちらかでの対応で、昨年9月から10月に平均6%の値上げを行った。当社は他社より先行した動きとなり、切り替えられることもあったし、売れ行きは苦戦している。経営者の考え方次第だが、かつてない程に製造コストが上がっている中で値上げをせず、売上を優先しても未来はないと思っている。当社では過去に全品の値上げを行ったことがなく、今回の値上げはある意味で訓練だと思っている。もちろん、原材料や製造コストが下がれば製品価格も下げる。この10年、20年の間、製品の価格が変わっていない、ということ事態がおかしいことだが、現在の流れで価格を維持することはとてもできない。コロナ禍で政府は無利子無担保の融資を行った。融資の返済は年明けから本格的に始まるので、業界問わず様々な話が出てくるだろう」
-進行する円安の影響も大きい。
「漬物も含めて日本は多くの原材料を輸入に依存している。だが、進行する円安の影響もあり、日本の優位性は失われつつある。また、日本が他国に買い負ける事例も出てきており、海外のものが日本に入ってこなくなるかもしれないし、今後数年で海外の原料や製品の方が高くなる可能性もある。そこでクローズアップされるのが国産原料や国内製造の製品だ。生産の維持と拡大には大きな課題があるが、需要があれば減っていくばかりではないと考えている」
-漬物のマーケットや未来像は。
「正直に言って、明るい材料は少ない。ベンダーとしては新規取引先も増えて良い話もいただいているが、業界はシュリンクしており、これからの5年で淘汰も進むだろう。当社の本漬製品も5年後を見据えた時、どこまで売上に貢献できているのか分からない。事業継続の最善策として考えられるのは、適正価格での販売、健康機能性の訴求、新商品開発などが上げられるが、それらは過去にもやっていることで、新しい施策はない。だが、明るい話題もある。当社の事業を見直してみると、やはり野菜加工が強みであり特徴でもある。漬物を製造しなくても味付けした野菜をこれまでとは違うルートに販売できれば販路を広げていくことができる。詳細は言えないが、私が社長に就任してから新しい取組を進めている。その事業はまだスタートの段階だが、全体の売上の3~5%まで増えていて、10%を目指している。その市場にはまだまだ伸び代があり、さらに拡大していく可能性がある。そのようなところにスポットを当て、前向きに進んでいきたいと考えている」
【2023(令和5)年1月11日第5117号11面】
三井食品工業 HP
https://mitsuishokuhin.jimdo.com/
小西酒造株式会社 代表取締役 小西新右衛門氏
伝統食の再評価期待
SDGsを後押しにPR
小西酒造株式会社(兵庫県伊丹市)の小西新右衛門社長にインタビュー。同社は、清酒「白雪」を製造し、関連会社の白雪食品は、その酒粕を使用した奈良漬で知られる。小西社長は、日本酒造組合中央会副会長を始めとする要職を歴任し、現在は白雪食品の社長、伊丹商工会議所会頭、兵庫県公安委員会委員長の役職も担う。昨秋には旭日小綬章を受章した。日本酒、奈良漬、仕事への思いを聞いた。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
‐コロナ禍で何を考えていましたか。
「コミュニケーションの機会がいかに大切かということに気付かされた。そして、コミュニケーションの場において、日本酒や奈良漬といった嗜好品が果たす役割は少なからずあり、ポストコロナでどう展開していくかを考えた。これから、嗜好品は量の多さではなく、生活により華を添える存在として求められていき、少量良質が主流になっていくだろう」
‐若い人の間では日本酒や奈良漬への親しみが薄れている。
「ライフスタイルや食の好みは時代によって確かに変化していく。しかし、シェアが少なくなっても戦略を練ってPRし続ければ、増やしていくことは可能だ。日本酒や奈良漬を試さずに先入観で苦手意識を持っている方もいる。改めて好きになってもらうこと、また新しく好きになってもらうように粘り強く提案する必要がある」
‐新しく好きになってもらうためには。
「1つは海外に輸出して新規顧客を開拓することだ。すでに強化している。伊丹の土地で470年以上も清酒を作り続けていることを現地で話すと、伝統とストーリーに関心を持ってくださる。グローカルという言葉があり、地元に太い根があるから、自信を持って外へ出ていける。もう1つは、SDGsだ。白雪奈良漬は清酒『白雪』の酒粕を使って製造する伝統的な保存食。伝統食が再評価されるチャンスと捉え、まだまだ魅力があると期待している。SDGsが後押しになると見て、PRしていきたい」
‐小西社長が仕事で大切にされていること。
「まず仕事を好きでいること、職人技やもの作りへの思いを重視することだ。メーカーとして1番大事なことだと考えている。DXの推進は行っていくが、基本があってこそと感じる。また、いかに企業と企業で新しいものや価値を生み出せるかを考えている。コラボレーション先を常に探している」
【2023(令和5)年1月11日第5117号18面】
小西酒造 HP
https://www.konishi.co.jp/
SDGsを後押しにPR
小西酒造株式会社(兵庫県伊丹市)の小西新右衛門社長にインタビュー。同社は、清酒「白雪」を製造し、関連会社の白雪食品は、その酒粕を使用した奈良漬で知られる。小西社長は、日本酒造組合中央会副会長を始めとする要職を歴任し、現在は白雪食品の社長、伊丹商工会議所会頭、兵庫県公安委員会委員長の役職も担う。昨秋には旭日小綬章を受章した。日本酒、奈良漬、仕事への思いを聞いた。
(大阪支社・高澤尚揮)
◇ ◇
‐コロナ禍で何を考えていましたか。
「コミュニケーションの機会がいかに大切かということに気付かされた。そして、コミュニケーションの場において、日本酒や奈良漬といった嗜好品が果たす役割は少なからずあり、ポストコロナでどう展開していくかを考えた。これから、嗜好品は量の多さではなく、生活により華を添える存在として求められていき、少量良質が主流になっていくだろう」
‐若い人の間では日本酒や奈良漬への親しみが薄れている。
「ライフスタイルや食の好みは時代によって確かに変化していく。しかし、シェアが少なくなっても戦略を練ってPRし続ければ、増やしていくことは可能だ。日本酒や奈良漬を試さずに先入観で苦手意識を持っている方もいる。改めて好きになってもらうこと、また新しく好きになってもらうように粘り強く提案する必要がある」
‐新しく好きになってもらうためには。
「1つは海外に輸出して新規顧客を開拓することだ。すでに強化している。伊丹の土地で470年以上も清酒を作り続けていることを現地で話すと、伝統とストーリーに関心を持ってくださる。グローカルという言葉があり、地元に太い根があるから、自信を持って外へ出ていける。もう1つは、SDGsだ。白雪奈良漬は清酒『白雪』の酒粕を使って製造する伝統的な保存食。伝統食が再評価されるチャンスと捉え、まだまだ魅力があると期待している。SDGsが後押しになると見て、PRしていきたい」
‐小西社長が仕事で大切にされていること。
「まず仕事を好きでいること、職人技やもの作りへの思いを重視することだ。メーカーとして1番大事なことだと考えている。DXの推進は行っていくが、基本があってこそと感じる。また、いかに企業と企業で新しいものや価値を生み出せるかを考えている。コラボレーション先を常に探している」
【2023(令和5)年1月11日第5117号18面】
小西酒造 HP
https://www.konishi.co.jp/
1月1日号 トップに聞く
東海漬物株式会社 代表取締役社長 永井英朗氏
東海漬物株式会社(愛知県豊橋市)の永井英朗社長にインタビュー。第81期(2021年9月~2022年8月)の業績と第82期期首及び値上げの状況などについて話を聞いた。2023年の展望などについては、高品質と差別化を中心に浅漬市場(約800億円)のシェア10%獲得を目標に掲げ、野菜加工のメーカーとして売場を拡大していく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
ー第81期決算について。
「過去最高の収益となった2021年8月期(80期)と比較すると、81期は減収減益となった。売上は前期比2・5%減の微減で、利益は更に前期を大きく下回った。80期はコロナの影響による巣ごもり需要のプラスと原料状況が安定していたこともあって、81期はその反動が出た結果となった。当社は9月が期首であり、比較障害のないコロナ禍のプラス影響は2020年3月から2023年2月までと考えている。2023年3月以降は前年対比で比較することになる」
ー値上げについて。
「7月に『きゅうりのキューちゃん』の内容量を10g減量し、9月に一部本漬刻み製品の価格改定を行い、11月から『こくうま熟うま辛キムチ』の320gを20g減量し、『特級福神漬』と『カレー福神漬』をそれぞれ10g減量した。原料の他、調味料、添加物、包装資材、物流費とあらゆるコストが上がっており、海外原料については円安の影響も大きい。82期は出だしからコストが上がっており、80期の基準と比べても150~160%となっている。原料比率も5~10円上がっており、『キューちゃん』においても10g減量しただけではとても吸収できるレベルではない。だが、これ以上の減量や価格改定は支持を得られない可能性もあり、手探りで対応している状況。2023年春以降に向けては、原材料等の状況を見ながら様々なことを検討していく」
ー値上げの影響は。
「『きゅうりのキューちゃん』の内容量調整を行った時は約1カ月、パッケージの裏面に理由とお詫びを掲載した。いまのところ、他の商品も含めて影響は見られない。『こくうま熟うま辛キムチ』は、切り替えを行っているところなので注視しているが、大きな影響はないと予想している」
ーキムチ、本漬、浅漬の売上構成比は。
「キムチ65%、本漬は沢庵を含めて25%、浅漬10%。今後は浅漬を強化していきたいと考えており、浅漬市場(約800億円)の10%シェア獲得を目指している」
ー原料面と製造面の課題は。
「国内の原料野菜については、天候リスク、生産者高齢化リスク、農業資材・エネルギー価格の高騰による原価アップを懸念している。特に生産者の高齢化はどうしようもない問題で、事業継承が可能なのか確認させていただいている。主力原料である白菜の契約率は70%で、足りない時は市場から購入する。契約率を100%にしないのは、豊作になっても不作になってもリスクを最小限に留めるためで、青果会社とのパイプをつなぐ意味もある。製造面は2022年の中京工場(物流併設)と所沢工場(物流併設)の2工場の旧工場からの建て替えを行い、生産能力のアップ、品質保証の拡充、新機械設備導入による新商品開発を進める。品質管理については、全工場でGFSIスキームとなるFSSC22000、JFS‐C規格を取得する方針で、その準備を進めている。今後は新工場を活かす新商品の開発を行っていく」
ー今後の見通し。
「コロナで打撃を受けた企業は数多くある。無利子、無担保の融資を受けた企業もあるが、返済が本格的に始まる。販路にもよるが、小規模事業者にとっては厳しい状況になると思う。当社としては市場がシュリンクする中でも生き残れる企業になるため、10年後を見据えて行動していかなければならない。普通に考えても、売上を増やすためには他社のシェアを取るしかない。野菜加工のメーカーとして売場を広げていくために市場がシュリンクしても残る商品を開発することが重要で、高品質や差別化、お得意先様とのパイプがポイントになる。自分たちの強みをブラッシュアップし、供給体制を整えていく必要もある。FSSC22000などの認証資格取得は最低条件で、それがなければPBを受けることが難しく、PBを受けなければNBも受けにくいという流れもある。認証のコストも増えているが、当たり前のことを当たり前のようにやっていかなければ生き残ることができない時代になっている。SDGsの取組も必要で、全工場で生野菜残渣のたい肥化システム導入を目指している」
ー漬物の需要拡大の方策は。
「当社の経営理念である『野菜をもっと、野菜にもっと』を数値で出せるようにベジメーター(緑黄色野菜の数値を計測する機器)を会社としてレンタルしていて、展示会・各種イベントで活用している。ベジメーターで計測するべジスコアは緑黄色野菜の摂取状態を反映する。1日の目標野菜摂取量は350gで、健康につながるバランスの良い食事の中に漬物も入れてほしいと思っている」
ー2023年に向けて。
「今年の干支は『卯(うさぎ)』、十干は『癸(みずのと)』。干支は十二支・十支の組み合わせで60通りある。今年の干支は『癸・卯』。私が生まれた1956年の楽曲『ケ・セラ・セラ』(ドリス・デイ)は、『ケ・セラ・セラ=何とかなるさ』と訳されていることが多いのだが、本当の意味は『人生は自分次第でどうにでもしていける』ということだそうだ。ウィズコロナと厳しい経済状況が続くと思うが、みんなで力を合わせ、『ケ・セラ・セラ』の気持ちと『これまでとこれからの努力が花開き、実り始める』といった縁起の良さを表している『癸・卯』のごとく、難局を飛び越えていきたいと思っている」
【2023(令和5)年1月1日第5116号5面】
東京中央漬物株式会社 代表取締役社長 齋藤正久氏
東京都公認の漬物荷受機関である東京中央漬物株式会社(東京都江東区豊洲)の齋藤正久社長にインタビュー。23年3月期上半期の業績や2023年の展望などについて話を聞いた。人口減や少子高齢化で漬物の需要減少が見込まれる中、漬物以外の品目にも目を向ける必要性を指摘。現在は惣菜を強化しているが、将来的には冷凍食品も視野に入れる意向を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
ー23年3月期上半期の売上は。
「上半期の売上は0・4%減で、10月を含めると99・7%と昨対に近い数字に戻ってきている。主力の量販向けはやや低調だが、業務用が回復傾向でカバーしている。漬物業界もコロナの影響で倒産、廃業といった話も出てきているが、良い企業は関係なく業績を伸ばしている。皆川会長からもよく言われているのだが、いつまでもコロナのせいにはできない。少しずつではあるが、新規のお得意先様も増えており、12月も倉庫を目一杯使っている」
ー御社の強みは。
「全国の漬物を一手に引き受けて、供給することができる。主要な取引先は約300社で、取扱い数は1000品を超え、小ロットにも対応している。弊社の強みは引き出しの多さと経験、それと知識。全国にパイプがあり、ある商品が原料不足で供給が難しい時も全力で類似品を探す。それが無理なら供給可能な代替品を提案する。漬物のことは弊社に任せていただきたい、と思っている」
ー今後の見通し。
「漬物の市場は年々縮小している。少子高齢化が進む中、漬物だけを取り扱っていても売上は落ちていくだけだ。漬物以外の品目にも目を向けていく必要がある。近年、当社では売れ行きが好調な惣菜に近い商材に力を入れており、アイテム数を増やしている。量販店の惣菜売場は商品が充実しており、人の往来も多い。人が来る売場に商品を置くことが重要で、そのような商品の取り扱いも少しずつ増えている。また、コロナ禍で伸びた市場として冷凍食品があるが、今後は取り扱わなければならない状況になることも予想される。将来的にメーカーが冷凍食品を製造するようになれば、弊社もそれに対応できるように取り組んでいく必要がある」
ー漬物の動きは。
「新生姜は好調で、8月まで112%だった。9月は値上げの影響で少し後退したが、その後もプラスで推移している。沢庵は上半期108%で、10月も良かった。一部の国産製品で値上げが実施されたが、本格的には来春からになる。量販店では微減の浅漬だが、業務用の需要が回復して全体としてはプラスとなった。キムチは巣ごもり需要が増加したことで昨年まで好調だったが、その反動で数%のマイナスとなっている。梅干しは梅雨明けが早くて猛暑となったこともあって、7月は106%となったが、8月は80%台まで落ちた。9月は110%と持ち直したが、上半期は96~98%となった。これからの動きに期待したい」
ー値上げについて。
「漬物業界は他の食品よりも遅れていたが、秋冬から本格化し、来春までに大半の商品が量目調整または価格改定を実施する見通しだ。メーカーから弊社に申請が届いている商品については順次商談を行っていて、案内があったところについては7割方値上げが実施できている。得意先によっては時間がかかったり、1年に1回しか改定できない、といったケースもあるが、全体的にはスムーズに商談することができている。ただ、このような状況でも値上げの案内が届いていないメーカーもある。様々なコストが上昇している状況で、すでに企業努力で吸収できるレベルではなくなっている。もともと薄利でやっているケースが多いと思うので、赤字での製造を余儀なくされているケースもあるだろう。状況としては適正価格で販売できなければ会社の存続が危ぶまれるところまできており、まだアクションを起こしていない企業の状況を懸念している」
ー2023年の展望は。
「政府は、コロナの感染者が増えても以前のように規制を厳しくすることはないだろう。そうなれば、円安効果もあるのでインバウンド需要が期待でき、観光関連、飲食関係が良くなっていく。コロナの影響で巣ごもり需要が増加し、量販店は好調となって観光や飲食関係は低迷することとなったが、それが元に戻っている流れだ。利益を確保することは年々難しくなっているが、業務用の方が利益を取りやすい。企業としては利益率を高められるように何をすれば良いのか、どこの取引をメインにしていくのか定めていく必要がある」
(千葉友寛)
◇ ◇
ー23年3月期上半期の売上は。
「上半期の売上は0・4%減で、10月を含めると99・7%と昨対に近い数字に戻ってきている。主力の量販向けはやや低調だが、業務用が回復傾向でカバーしている。漬物業界もコロナの影響で倒産、廃業といった話も出てきているが、良い企業は関係なく業績を伸ばしている。皆川会長からもよく言われているのだが、いつまでもコロナのせいにはできない。少しずつではあるが、新規のお得意先様も増えており、12月も倉庫を目一杯使っている」
ー御社の強みは。
「全国の漬物を一手に引き受けて、供給することができる。主要な取引先は約300社で、取扱い数は1000品を超え、小ロットにも対応している。弊社の強みは引き出しの多さと経験、それと知識。全国にパイプがあり、ある商品が原料不足で供給が難しい時も全力で類似品を探す。それが無理なら供給可能な代替品を提案する。漬物のことは弊社に任せていただきたい、と思っている」
ー今後の見通し。
「漬物の市場は年々縮小している。少子高齢化が進む中、漬物だけを取り扱っていても売上は落ちていくだけだ。漬物以外の品目にも目を向けていく必要がある。近年、当社では売れ行きが好調な惣菜に近い商材に力を入れており、アイテム数を増やしている。量販店の惣菜売場は商品が充実しており、人の往来も多い。人が来る売場に商品を置くことが重要で、そのような商品の取り扱いも少しずつ増えている。また、コロナ禍で伸びた市場として冷凍食品があるが、今後は取り扱わなければならない状況になることも予想される。将来的にメーカーが冷凍食品を製造するようになれば、弊社もそれに対応できるように取り組んでいく必要がある」
ー漬物の動きは。
「新生姜は好調で、8月まで112%だった。9月は値上げの影響で少し後退したが、その後もプラスで推移している。沢庵は上半期108%で、10月も良かった。一部の国産製品で値上げが実施されたが、本格的には来春からになる。量販店では微減の浅漬だが、業務用の需要が回復して全体としてはプラスとなった。キムチは巣ごもり需要が増加したことで昨年まで好調だったが、その反動で数%のマイナスとなっている。梅干しは梅雨明けが早くて猛暑となったこともあって、7月は106%となったが、8月は80%台まで落ちた。9月は110%と持ち直したが、上半期は96~98%となった。これからの動きに期待したい」
ー値上げについて。
「漬物業界は他の食品よりも遅れていたが、秋冬から本格化し、来春までに大半の商品が量目調整または価格改定を実施する見通しだ。メーカーから弊社に申請が届いている商品については順次商談を行っていて、案内があったところについては7割方値上げが実施できている。得意先によっては時間がかかったり、1年に1回しか改定できない、といったケースもあるが、全体的にはスムーズに商談することができている。ただ、このような状況でも値上げの案内が届いていないメーカーもある。様々なコストが上昇している状況で、すでに企業努力で吸収できるレベルではなくなっている。もともと薄利でやっているケースが多いと思うので、赤字での製造を余儀なくされているケースもあるだろう。状況としては適正価格で販売できなければ会社の存続が危ぶまれるところまできており、まだアクションを起こしていない企業の状況を懸念している」
ー2023年の展望は。
「政府は、コロナの感染者が増えても以前のように規制を厳しくすることはないだろう。そうなれば、円安効果もあるのでインバウンド需要が期待でき、観光関連、飲食関係が良くなっていく。コロナの影響で巣ごもり需要が増加し、量販店は好調となって観光や飲食関係は低迷することとなったが、それが元に戻っている流れだ。利益を確保することは年々難しくなっているが、業務用の方が利益を取りやすい。企業としては利益率を高められるように何をすれば良いのか、どこの取引をメインにしていくのか定めていく必要がある」
【2023(令和5)年1月1日第5116号14面】