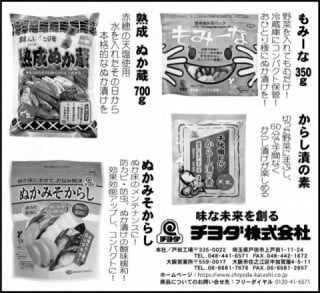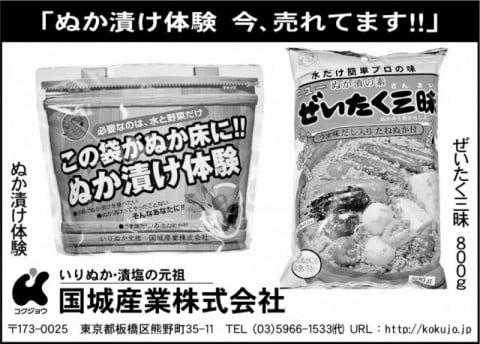【大阪支社】全国ぬかづけのもと工業会(山西健司会長)は3月22日、株式会社向井珍味堂(大阪市)で第58期通常総会を開催した。
冒頭、挨拶に立った山西会長は年初に発生した能登半島地震に触れ、会員の長﨑産業(石川県)が復興活動へ尽力していることへ敬意を示して見舞金を贈呈した。また「コロナ禍で控えていた研修活動や日本いりぬか工業会との交流を再開させる年としたい」と述べた。
また主に東日本の企業が所属している『日本いりぬか工業会』の甲斐義人前会長が来賓として挨拶。いりぬか工業会では昨年からSNSを用いたプレゼントキャンペーンなどを通じてぬか漬けの普及に努めていると紹介した上で、「貴工業会とはコロナ前までは合同で展示会出展や研修活動を行っていた。全国規模のPR活動も行っていきたいということで、交流を復活させたいという声が高まっている」と協調を呼びかけた。
山西会長が議長に就き議事へ移った。①前年度の事業報告及び収支決算、②本年度事業計画及び予算承認、③年会費の件、④萱津神社ご祈祷の件が上程され承認された。
②の本年度事業計画については、日本いりぬか工業会との交流委員として長崎成任衛氏、里村大像氏を選定して、今後の活動内容を協議していくこととなった。また11月8~9日の1泊2日で小豆島で研修旅行を実施することを承認。島内の醤油や佃煮、素麺の工場視察と、紅葉ガストロノミーツーリズムをテーマとした。
④の萱津神社ご祈祷については、コロナ禍以来、代表者による参拝のみとしていたが、会員参加を再開させていく方針とした。
議事を終えた後は各社情報交換の時間が設けられた。ぬかづけの素の売れ行きについては「コロナ禍でのぬか漬けブームからの反動で昨年上期までは前年比減が続いていたが、下期から回復してきている。業務筋からの引き合いも多い」との声があった。
また米ぬか原料については「食用油全般の値上がりに応じ、米油原料となる米ぬかも高騰が続いている。しかし、トウモロコシ、大豆が海外産地で豊作だったため、下げ圧力が働くことに期待している」と報告があった。
その後は会場を移して懇親会も開催され、ぬかづけの魅力や、PRの道筋など情報交換や意見交換が行われた。
冒頭、挨拶に立った山西会長は年初に発生した能登半島地震に触れ、会員の長﨑産業(石川県)が復興活動へ尽力していることへ敬意を示して見舞金を贈呈した。また「コロナ禍で控えていた研修活動や日本いりぬか工業会との交流を再開させる年としたい」と述べた。
また主に東日本の企業が所属している『日本いりぬか工業会』の甲斐義人前会長が来賓として挨拶。いりぬか工業会では昨年からSNSを用いたプレゼントキャンペーンなどを通じてぬか漬けの普及に努めていると紹介した上で、「貴工業会とはコロナ前までは合同で展示会出展や研修活動を行っていた。全国規模のPR活動も行っていきたいということで、交流を復活させたいという声が高まっている」と協調を呼びかけた。
山西会長が議長に就き議事へ移った。①前年度の事業報告及び収支決算、②本年度事業計画及び予算承認、③年会費の件、④萱津神社ご祈祷の件が上程され承認された。
②の本年度事業計画については、日本いりぬか工業会との交流委員として長崎成任衛氏、里村大像氏を選定して、今後の活動内容を協議していくこととなった。また11月8~9日の1泊2日で小豆島で研修旅行を実施することを承認。島内の醤油や佃煮、素麺の工場視察と、紅葉ガストロノミーツーリズムをテーマとした。
④の萱津神社ご祈祷については、コロナ禍以来、代表者による参拝のみとしていたが、会員参加を再開させていく方針とした。
議事を終えた後は各社情報交換の時間が設けられた。ぬかづけの素の売れ行きについては「コロナ禍でのぬか漬けブームからの反動で昨年上期までは前年比減が続いていたが、下期から回復してきている。業務筋からの引き合いも多い」との声があった。
また米ぬか原料については「食用油全般の値上がりに応じ、米油原料となる米ぬかも高騰が続いている。しかし、トウモロコシ、大豆が海外産地で豊作だったため、下げ圧力が働くことに期待している」と報告があった。
その後は会場を移して懇親会も開催され、ぬかづけの魅力や、PRの道筋など情報交換や意見交換が行われた。
【2024(令和6)年4月1日第5158号2面】
全国ぬかづけのもと工業会 http://www.nukaduke-kogyo.com/
SNSプレゼントキャンペーン継続へ
日本いりぬか工業会(足立昇司会長)では7日、令和6年度通常総会を東京都中央区の日本食糧新聞社で開催した。
開会挨拶で足立会長は業界動向に触れ、「コロナ禍でおうち時間が増え、普段ぬか漬けをやらない人もぬか漬けを始めたことで2020年から2021年にかけて需要が増えた。ぬか床、ぬか漬けが発酵食品であり、健康美容に良いということがメディアで紹介され、新たに若い女性や男性にも趣味の一環としてぬか漬けを漬ける動きが広まった」と説明した。
また近年、いりぬか原料である米ぬかが、米ぬか油としての需要が増加していることにより品不足になり、コストが大幅に増加していることや、国内の米消費量減少により、米の副産物である米ぬかの確保がより一層厳しくなっていることを指摘。「米ぬかの集荷は今後も厳しい環境が続いていくと懸念している。様々な課題はあるが、本日はいろいろな情報交換を実施していきたい」と話した。
来賓として出席した農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課課長補佐の二井敬司氏が挨拶。2月27日に閣議決定された「食料・農業・農村基本法」の改正案について説明。「食品産業のサプライチェーンの持続的発展に向けて取り組んでいきたい」と述べた。
総会では、令和5年度事業報告承認の件、令和6年度事業計画承認の件、理事・役員改選に関する件といった6つの議案が上程され、満場一致で採択された。 令和5年度事業報告では、業界紙2社のSNS上で実施した「ぬか漬けの日プレゼントキャンペーン」などの事業について報告がなされた。
令和6年度事業については、引き続き業界紙のSNSを活用したキャンペーンを実施していくことが決議された。ぬか漬け教室などリアルイベントの開催については、来年度事業で実施するかどうかを会員へのアンケートにより判断することが示された。
役員改選では、足立会長始め全役員の留任が決定。その他事項では、全国ぬかづけのもと工業会との交流や、組合年間会費の改定などについて意見交換が行われた。
開会挨拶で足立会長は業界動向に触れ、「コロナ禍でおうち時間が増え、普段ぬか漬けをやらない人もぬか漬けを始めたことで2020年から2021年にかけて需要が増えた。ぬか床、ぬか漬けが発酵食品であり、健康美容に良いということがメディアで紹介され、新たに若い女性や男性にも趣味の一環としてぬか漬けを漬ける動きが広まった」と説明した。
また近年、いりぬか原料である米ぬかが、米ぬか油としての需要が増加していることにより品不足になり、コストが大幅に増加していることや、国内の米消費量減少により、米の副産物である米ぬかの確保がより一層厳しくなっていることを指摘。「米ぬかの集荷は今後も厳しい環境が続いていくと懸念している。様々な課題はあるが、本日はいろいろな情報交換を実施していきたい」と話した。
来賓として出席した農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課課長補佐の二井敬司氏が挨拶。2月27日に閣議決定された「食料・農業・農村基本法」の改正案について説明。「食品産業のサプライチェーンの持続的発展に向けて取り組んでいきたい」と述べた。
総会では、令和5年度事業報告承認の件、令和6年度事業計画承認の件、理事・役員改選に関する件といった6つの議案が上程され、満場一致で採択された。 令和5年度事業報告では、業界紙2社のSNS上で実施した「ぬか漬けの日プレゼントキャンペーン」などの事業について報告がなされた。
令和6年度事業については、引き続き業界紙のSNSを活用したキャンペーンを実施していくことが決議された。ぬか漬け教室などリアルイベントの開催については、来年度事業で実施するかどうかを会員へのアンケートにより判断することが示された。
役員改選では、足立会長始め全役員の留任が決定。その他事項では、全国ぬかづけのもと工業会との交流や、組合年間会費の改定などについて意見交換が行われた。
【2024(令和6)年3月11日第5156号5面】
日本いりぬか工業会
全国ぬかづけのもと工業会 萱津神社へぬか床奉納
大寒の「ぬか床の日」に
【大阪支社】全国ぬかづけのもと工業会(山西健司会長)は2015年より毎年の大寒の日(2052年まで1月20日)を「ぬか床の日」と定めている。
「ぬか床の日」には日本唯一の漬物祖神である愛知県あま市の萱津神社へ、各社のぬか床を奉納し、ぬか床文化の発展を祈願するのが恒例行事となっている。
今年は能登半島地震があった影響などを考慮し、堀川敬生会計(宏昌食糧研究所・愛知県)が代表して参拝した。
また総会は3月22日、大阪市平野区の株式会社向井珍味堂で第58回通常総会を開催することが決まった。
<会員9社(五十音順)>厚生産業株式会社(岐阜県)、株式会社宏昌食糧研究所(愛知県)、株式会社高橋商店(香川県)、有限会社樽の味(和歌山県)、つけもと株式会社(奈良県)、長崎産業株式会社(石川県)、丸島醤油株式会社(香川県)、株式会社向井珍味堂(大阪府)、株式会社山清(香川県)
【2024(令和6)年2月1日第5152号5面】