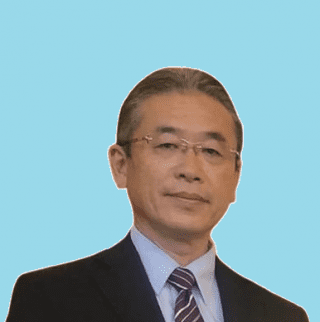7月21日号 梅特集
中田食品株式会社 代表取締役社長 中田吉昭氏
増収で売上は90億円台に
定番のNB商品が安定した動き
定番のNB商品が安定した動き
中田食品株式会社(和歌山県田辺市)の中田吉昭社長にインタビュー。今年の梅の作柄や漬け込み状況、販売動向などについて話を聞いた。同社は定番のNB商品が安定した売れ行きを見せ、昨年度の決算で増収となり、売上は90億円台に戻った。7月に入り、全国で記録的な暑さとなっているが、梅は塩分補給や疲労回復効果などが期待できることから、「熱中症対策のアイテムとして注目され、活用されることを願っている」と語った。(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年の作柄は。
「今年は5月に雨が多く、若干早い生育状況だった。5月末までは順調だったが、6月のはじめに襲来した台風2号の影響で1、2割の梅が落ちたと見ている。また、落ちなかった梅も傷が入ったり、病気が発生したため品質の低下を懸念している。台風の影響がなければ平年より多い玉数になっていたと思うが、全体的な収穫量は天候の影響もあって平年より少し少ないと感じている。サイズは例年3Lが中心だが、今年は量販店で取り扱いやすい中粒の2Lが多くなっている」
‐御社の漬け込み状況は。
「タンクに多少の余裕があったので、ある程度の量は漬け込んだ。だが、良い品質の梅が出てこなかったので、計画数量には達していない。当社は品質重視なので、良い梅だけを漬け込んでいる」
‐落ち梅の価格が下がった。
「台風によって出鼻をくじかれてしまった。落下した梅が市場に一気に集まったことで価格が下がり、品質の悪い梅も多かった。その後も落ち梅の価格はスタートの価格に引っ張られ、中盤以降も上がらなかった。そのため、農家は市場に出さず、自分のところで漬けるケースが多かったようだ」
‐梅干しの販売状況は。
「コロナが落ち着き、人も物も動き始めた。梅干しはコロナ禍で売れ行きが落ちていたが、当社の最近の数字を見ると昨対並みとなっており、ようやく下げ止まったと感じている。当社の昨年度の売上は前年度から少し増えて90億円台に戻った。一部で値上げを行ったのだが、季節の販促、増量企画、定番のNB商品が安定的に売れたことが売上を押し上げた。販路としては量販店、ドラッグストア、ディスカウント系の店舗など、全般的に広がっている」
‐中国産の状況は。
「昨年に続いて今年も不作となっており、価格も上昇している。当社は昨年の秋、急激な円安の進行と原料価格の上昇を受けて値上げを行った。今年も同じ傾向が続いているので、売場と他社の状況を見ながら今後の対応を慎重に考えていきたい」
‐梅の需要拡大について。
「先日、梅の高血圧抑制作用の研究成果が発表されていたが、梅には多くの健康機能性があり、それらの情報を発信することが重要だと考えている。しかし、組合で健康機能性の情報を発信することは難しい部分もあるので、組合青年組織の若梅会を中心に、SNSなどを活用して消費拡大を目指していく。若い世代の消費が増えなければ梅業界の未来はない。若い人にどのように梅を食べていただくか、ということは大きな課題。引き続き知恵を出しながら取り組んでいきたいと考えている。梅は暑くなると売れる商材。7月に入り、日本全国で記録的な暑さとなっているため、熱中症対策として塩分補給や疲労回復効果が期待できる梅が多くの場面で注目され、活用されることを願っている」
◇ ◇
‐今年の作柄は。
「今年は5月に雨が多く、若干早い生育状況だった。5月末までは順調だったが、6月のはじめに襲来した台風2号の影響で1、2割の梅が落ちたと見ている。また、落ちなかった梅も傷が入ったり、病気が発生したため品質の低下を懸念している。台風の影響がなければ平年より多い玉数になっていたと思うが、全体的な収穫量は天候の影響もあって平年より少し少ないと感じている。サイズは例年3Lが中心だが、今年は量販店で取り扱いやすい中粒の2Lが多くなっている」
‐御社の漬け込み状況は。
「タンクに多少の余裕があったので、ある程度の量は漬け込んだ。だが、良い品質の梅が出てこなかったので、計画数量には達していない。当社は品質重視なので、良い梅だけを漬け込んでいる」
‐落ち梅の価格が下がった。
「台風によって出鼻をくじかれてしまった。落下した梅が市場に一気に集まったことで価格が下がり、品質の悪い梅も多かった。その後も落ち梅の価格はスタートの価格に引っ張られ、中盤以降も上がらなかった。そのため、農家は市場に出さず、自分のところで漬けるケースが多かったようだ」
‐梅干しの販売状況は。
「コロナが落ち着き、人も物も動き始めた。梅干しはコロナ禍で売れ行きが落ちていたが、当社の最近の数字を見ると昨対並みとなっており、ようやく下げ止まったと感じている。当社の昨年度の売上は前年度から少し増えて90億円台に戻った。一部で値上げを行ったのだが、季節の販促、増量企画、定番のNB商品が安定的に売れたことが売上を押し上げた。販路としては量販店、ドラッグストア、ディスカウント系の店舗など、全般的に広がっている」
‐中国産の状況は。
「昨年に続いて今年も不作となっており、価格も上昇している。当社は昨年の秋、急激な円安の進行と原料価格の上昇を受けて値上げを行った。今年も同じ傾向が続いているので、売場と他社の状況を見ながら今後の対応を慎重に考えていきたい」
‐梅の需要拡大について。
「先日、梅の高血圧抑制作用の研究成果が発表されていたが、梅には多くの健康機能性があり、それらの情報を発信することが重要だと考えている。しかし、組合で健康機能性の情報を発信することは難しい部分もあるので、組合青年組織の若梅会を中心に、SNSなどを活用して消費拡大を目指していく。若い世代の消費が増えなければ梅業界の未来はない。若い人にどのように梅を食べていただくか、ということは大きな課題。引き続き知恵を出しながら取り組んでいきたいと考えている。梅は暑くなると売れる商材。7月に入り、日本全国で記録的な暑さとなっているため、熱中症対策として塩分補給や疲労回復効果が期待できる梅が多くの場面で注目され、活用されることを願っている」
【2023(令和5)年7月21日第5135号2面】
中田食品
紀州みなべ梅干協同組合 理事長 殿畑雅敏氏
新たなマーケットを創造
国内の潜在需要開拓へ
国内の潜在需要開拓へ
紀州みなべ梅干協同組合理事長の殿畑雅敏氏(株式会社トノハタ社長)にインタビュー。今年の作柄や在庫状況などについて話を聞いた。梅の消費拡大については長期的な視野で取り組んでいく必要性を強調。人口が減少する国内の市場はシュリンクしていくことが予想されるが、輸出よりも国内の潜在需要の開拓を模索していく意向を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年の作柄について。
「今年の作柄は平年作より少し悪いと見ている。品質は大きな変化がなく、サイズは平年通り。落ち梅の価格は下がったが、それは需給バランスによるものなので仕方がない。生梅は青果向けと加工向けに分かれるが、青果市場向け生梅はしっかりとした価格で推移し、途中から足りない状況となった。加工向けは昨年、おととしの繰り越し原料があり、全体的に漬け込みタンク余力が少なく漬け込み意欲が弱かったため、昨年よりも安値となった。また、加工向け生梅価格が下がったとは言え、それに比例して農家漬け樽原料の価格が下がるとは限らない。重要なポイントは全体の需給バランス」
‐梅の消費拡大は。
「消費を増やすことは簡単なことではない。消費を増やすためには長期的に業界、行政、農協、生産者が協力して3年、5年、10年と時間をかけて取り組み、相当な時間と労力を必要とする。梅は先人たちがより美味しく、よりたくさん食べていただくための努力を続け、その結果として今の市場がある。梅もそのままの形ではなく、おにぎりの具材やお菓子など、より多くの人に食べてもらうように形を変えてきた。一つの商品で爆発的に市場が広がる、ということは難しい。各社で努力を継続しているが、もう少し大きい枠の視点で新たなマーケットを創造していくことが重要だ。行政、農協、生産者、業界で構成される紀州梅の会では、梅の日(6月6日)のPRや記念行事など様々な活動を行っているが、紀州梅をもっと深く認知していただく取組を行っていく必要がある」
‐短期的な取組は。
「短期的に消費を増やす唯一の可能性として気温の上昇が挙げられる。梅は熱中症対策や予防に最適な素材で、売れ行きは気温に比例して暑くなれば消費が増える。予報では今年の夏も暑くなるということで、9月いっぱいまで残暑が続き梅の消費が増えることを期待している。また、みなべ町では学校給食への提供についてもアプローチを行っていただいているが、塩分が課題となって採用までのハードルは予想以上に高いとのこと。現在は梅議連を通じて引き続き動いていただいていると聞いている」
‐梅市場の未来像は。
「梅干しや梅関連製品の輸出は少しずつ伸びているようだが、それぞれの国にはそれぞれの食文化があり、梅干しが世界の人に受け入れてもらうのは簡単なことではない。日本のマーケットに目を向けると、人口減少や少子高齢化によりシュリンクしていくことは避けられない。推計調査では2050年頃に人口が1億人を割るとされているが、先進国の中でも1億人の人口は上位に位置し、内需も大きい。日本の対外純資産は31年連続世界1位で、現在の株価はバブル後最高値を更新するなど、底力もある。梅干しを知らない日本人はいないと思うが、梅干しを食べていない人はまだまだいる。そのような人たちに1日1粒食べていただくように取り組めば消費を伸ばせるはずだ。海外に目を向けるよりも国内の潜在需要の開拓を模索していくことが重要だ」
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年の作柄について。
「今年の作柄は平年作より少し悪いと見ている。品質は大きな変化がなく、サイズは平年通り。落ち梅の価格は下がったが、それは需給バランスによるものなので仕方がない。生梅は青果向けと加工向けに分かれるが、青果市場向け生梅はしっかりとした価格で推移し、途中から足りない状況となった。加工向けは昨年、おととしの繰り越し原料があり、全体的に漬け込みタンク余力が少なく漬け込み意欲が弱かったため、昨年よりも安値となった。また、加工向け生梅価格が下がったとは言え、それに比例して農家漬け樽原料の価格が下がるとは限らない。重要なポイントは全体の需給バランス」
‐梅の消費拡大は。
「消費を増やすことは簡単なことではない。消費を増やすためには長期的に業界、行政、農協、生産者が協力して3年、5年、10年と時間をかけて取り組み、相当な時間と労力を必要とする。梅は先人たちがより美味しく、よりたくさん食べていただくための努力を続け、その結果として今の市場がある。梅もそのままの形ではなく、おにぎりの具材やお菓子など、より多くの人に食べてもらうように形を変えてきた。一つの商品で爆発的に市場が広がる、ということは難しい。各社で努力を継続しているが、もう少し大きい枠の視点で新たなマーケットを創造していくことが重要だ。行政、農協、生産者、業界で構成される紀州梅の会では、梅の日(6月6日)のPRや記念行事など様々な活動を行っているが、紀州梅をもっと深く認知していただく取組を行っていく必要がある」
‐短期的な取組は。
「短期的に消費を増やす唯一の可能性として気温の上昇が挙げられる。梅は熱中症対策や予防に最適な素材で、売れ行きは気温に比例して暑くなれば消費が増える。予報では今年の夏も暑くなるということで、9月いっぱいまで残暑が続き梅の消費が増えることを期待している。また、みなべ町では学校給食への提供についてもアプローチを行っていただいているが、塩分が課題となって採用までのハードルは予想以上に高いとのこと。現在は梅議連を通じて引き続き動いていただいていると聞いている」
‐梅市場の未来像は。
「梅干しや梅関連製品の輸出は少しずつ伸びているようだが、それぞれの国にはそれぞれの食文化があり、梅干しが世界の人に受け入れてもらうのは簡単なことではない。日本のマーケットに目を向けると、人口減少や少子高齢化によりシュリンクしていくことは避けられない。推計調査では2050年頃に人口が1億人を割るとされているが、先進国の中でも1億人の人口は上位に位置し、内需も大きい。日本の対外純資産は31年連続世界1位で、現在の株価はバブル後最高値を更新するなど、底力もある。梅干しを知らない日本人はいないと思うが、梅干しを食べていない人はまだまだいる。そのような人たちに1日1粒食べていただくように取り組めば消費を伸ばせるはずだ。海外に目を向けるよりも国内の潜在需要の開拓を模索していくことが重要だ」
【2023(令和5)年7月21日第5135号3面】
田辺米穀株式会社 代表取締役社長 久保正氏
多様性のある物流を目指す
SDGsで地域に貢献
SDGsで地域に貢献
昨年7月に創立70周年を迎えた総合食品卸売問屋の田辺米穀株式会社(和歌山県西牟婁郡上富田町)の久保正社長にインタビュー。来年4月に控える物流問題や新しい取組などについて話を聞いた。2024年物流問題は同社にとっても大きな課題となっているが、昨年11月に緑ナンバーを取得した他、来年度中に3温度帯に対応した新物流センターを稼働する予定で、これまで以上に多様性のある物流の実現を目指す。また、廃棄する素材を使った弁当や総菜を提供する店を9月にオープンする予定で、地域貢献をテーマにしたSDGsの取組も本格化させている。(千葉友寛)
◇ ◇
‐新しい物流センターの稼働について。
「本来であれば来年度のスタートから稼働予定だったが、諸事情により予定が遅れている。今後のスケジュールとしては来年4月から半年かけてセンターの建設や準備を行い、来年度中に稼働する予定。場所は田辺市新庄町で、敷地は約1000坪、延床面積は約700坪となる。当社は昨年11月に貨物を運ぶ緑ナンバーを取得し、これまで以上に多様性のある物流が実現できる。『食と物流』のトータルサポートをテーマに3温度帯の物流倉庫を有効活用し、幅広いニーズに対応していきたいと考えている」
‐2024年物流問題は。
「来年4月1日から自動車運転業務(運送業ドライバー)に年間残業時間上限960時間の規制が設けられ、労働基準法の基本労働時間は原則1日8時間(休憩時間1時間除く)となる。この物流改革は運送事業者だけではなく問屋にとっても大きな課題で、これまでメーカーに注文して中1日か中2日で入ってきたものが1週間、2週間かかる可能性もある。当社としてはストックポイントの役割を果たせれば良いと思っている。主なカバーエリアは和歌山県の中南部から三重県の熊野地方。和歌山からスタートする荷物や他のエリアからの中継など、ドライバー不足や物流費の上昇などの課題を抱える中で、物流の路線に上手く乗れるケースがあれば活用していただきたいと思っている。当社の理念は地域と社会への貢献。まだまだできているとは言えないが、今後も地域と社会にどのような貢献ができるか、しっかりと考えていきたい」
‐SDGsの取組は。
「『つくる責任つかう責任』については、我々にも大きく関係している。当社は賞味期限が短くなってしまったことで廃棄を余儀なくされる商品が多数あり、毎年1000万円以上のロスが出ている。これを解消するため、9月より賞味期限が短くなった素材を使用した弁当や総菜を提供する店をオープンする。社員に対して常日頃から無駄をなくそう、と言っているのだが、仕入れたものを責任を持って使うということについて、社員にも意識してほしい思っている。また、廃棄してしまう素材を再利用し、弁当や総菜を少しでも安く提供できれば地域貢献になる。大事なことは1人の100歩より、100人の一歩。チームにスター選手が1人いても試合には勝てない。みんながヒットを打つことが重要で、時にはバントも必要だ。一気に進むことは難しいので、少しずつ進んでいきたいと思っている」
◇ ◇
‐新しい物流センターの稼働について。
「本来であれば来年度のスタートから稼働予定だったが、諸事情により予定が遅れている。今後のスケジュールとしては来年4月から半年かけてセンターの建設や準備を行い、来年度中に稼働する予定。場所は田辺市新庄町で、敷地は約1000坪、延床面積は約700坪となる。当社は昨年11月に貨物を運ぶ緑ナンバーを取得し、これまで以上に多様性のある物流が実現できる。『食と物流』のトータルサポートをテーマに3温度帯の物流倉庫を有効活用し、幅広いニーズに対応していきたいと考えている」
‐2024年物流問題は。
「来年4月1日から自動車運転業務(運送業ドライバー)に年間残業時間上限960時間の規制が設けられ、労働基準法の基本労働時間は原則1日8時間(休憩時間1時間除く)となる。この物流改革は運送事業者だけではなく問屋にとっても大きな課題で、これまでメーカーに注文して中1日か中2日で入ってきたものが1週間、2週間かかる可能性もある。当社としてはストックポイントの役割を果たせれば良いと思っている。主なカバーエリアは和歌山県の中南部から三重県の熊野地方。和歌山からスタートする荷物や他のエリアからの中継など、ドライバー不足や物流費の上昇などの課題を抱える中で、物流の路線に上手く乗れるケースがあれば活用していただきたいと思っている。当社の理念は地域と社会への貢献。まだまだできているとは言えないが、今後も地域と社会にどのような貢献ができるか、しっかりと考えていきたい」
‐SDGsの取組は。
「『つくる責任つかう責任』については、我々にも大きく関係している。当社は賞味期限が短くなってしまったことで廃棄を余儀なくされる商品が多数あり、毎年1000万円以上のロスが出ている。これを解消するため、9月より賞味期限が短くなった素材を使用した弁当や総菜を提供する店をオープンする。社員に対して常日頃から無駄をなくそう、と言っているのだが、仕入れたものを責任を持って使うということについて、社員にも意識してほしい思っている。また、廃棄してしまう素材を再利用し、弁当や総菜を少しでも安く提供できれば地域貢献になる。大事なことは1人の100歩より、100人の一歩。チームにスター選手が1人いても試合には勝てない。みんながヒットを打つことが重要で、時にはバントも必要だ。一気に進むことは難しいので、少しずつ進んでいきたいと思っている」
【2023(令和5)年7月21日第5135号4面】
田辺米穀
若梅会 会長 濱田朝康氏
梅のプラットフォームを構築
イベントで若い世代にPR
イベントで若い世代にPR
株式会社濱田(濱田洋社長、和歌山県田辺市)の濱田朝康専務取締役にインタビュー。同氏は紀州田辺梅干協同組合(前田雅雄理事長)と紀州みなべ梅干協同組合(殿畑雅敏理事長)を合わせた青年部組織「若梅会」の会長を務めている。紀州梅の会梅干部会(杉本宗一部会長)は6月30日に会合を開き、今後の活動について協議。その中で、濱田会長は梅産業全体で梅の魅力を継続的に発信し、次世代の消費者を獲得するため、梅に関する情報の集約・発信を行うプラットフォームの構築を提言。SNSなどを活用した情報発信やイベントへの出店で梅をPRしていく方針を示した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐若梅会の活動について。
「先日開催された会合に若梅会の会長として出席し、『梅ノ香リハ何処マデモ』プロジェクトについて説明させていただいた。このプロジェクトは主に2つの活動を行うというもので、一つは梅の情報を発信するプラットフォームの構築、もう一つはイベントへの参加及び実施する、というものだ」
‐プラットフォームの内容は。
「梅産業全体で梅の魅力を継続的に発信することが重要で、次世代の消費者を獲得するため、梅に関する情報の集約・発信の場を構築することが必要だと考えた。また、行政、農家、加工業など、梅産業全体で連携し、消費者にとって有益な情報の他、魅力的なサービスや体験をSNS・WEB等を活用して継続的に発信することが重要だと思っている。プロジェクトでは発信カテゴリーごとに役割を分担し、各ターゲットに応じた最適な発信ツールを活用して情報を届けていく」
‐カテゴリーについて。
「カテゴリーは主に農業、就農、飲食、食育、ライフスタイル、新たなチャレンジに分かれるが、それぞれに合ったSNSやWEB媒体を活用して情報を発信する。また、アフターコロナでイベントが各地で開催されるようになってきているが、梅の団体としてイベントに出店したいと思っている」
‐出店の狙いは。
「リアルな梅の登場シーンを作り、新規ファンの獲得やプラットフォームからの発信で獲得したオンライン上の消費者との接点を強固なものにしたいと考えている。今後の予定としては8月20日に大阪で開催される音楽イベント『サマーソニック2023』に出店し、若い層に梅を広めたいと思っている」
‐若い世代への対応や課題は。
「現在、梅を食べているのは年齢層が高めの人たちで、これからのことを考えると40代以下の人たちにアプローチしていく必要がある。個人的な考えとして、ネット販売は長距離戦、店舗での販売は中距離戦、対面での販売は近距離戦と位置付けているのだが、梅は近距離戦の武器が少なく、弱い部分でもある。若い人はギフトを贈る習慣がなく、日常的に梅を食べない人もいる。我々としては梅干しを大事にしながら梅を素材にした新しい加工品の開発など、別のフィールドを見つけていく必要がある。若梅会には40名以上が所属しており、20代の人もいる。2つの組合の青年部組織だが、フラットな関係で多くの人と交流でき、情報も入ってくる。若梅会に参加すれば業界や梅のことを学ぶことができる、というような認識を持っていただけるような会になれば参加者がさらに増えるので、それを目指して活動していきたい」
(千葉友寛)
◇ ◇
‐若梅会の活動について。
「先日開催された会合に若梅会の会長として出席し、『梅ノ香リハ何処マデモ』プロジェクトについて説明させていただいた。このプロジェクトは主に2つの活動を行うというもので、一つは梅の情報を発信するプラットフォームの構築、もう一つはイベントへの参加及び実施する、というものだ」
‐プラットフォームの内容は。
「梅産業全体で梅の魅力を継続的に発信することが重要で、次世代の消費者を獲得するため、梅に関する情報の集約・発信の場を構築することが必要だと考えた。また、行政、農家、加工業など、梅産業全体で連携し、消費者にとって有益な情報の他、魅力的なサービスや体験をSNS・WEB等を活用して継続的に発信することが重要だと思っている。プロジェクトでは発信カテゴリーごとに役割を分担し、各ターゲットに応じた最適な発信ツールを活用して情報を届けていく」
‐カテゴリーについて。
「カテゴリーは主に農業、就農、飲食、食育、ライフスタイル、新たなチャレンジに分かれるが、それぞれに合ったSNSやWEB媒体を活用して情報を発信する。また、アフターコロナでイベントが各地で開催されるようになってきているが、梅の団体としてイベントに出店したいと思っている」
‐出店の狙いは。
「リアルな梅の登場シーンを作り、新規ファンの獲得やプラットフォームからの発信で獲得したオンライン上の消費者との接点を強固なものにしたいと考えている。今後の予定としては8月20日に大阪で開催される音楽イベント『サマーソニック2023』に出店し、若い層に梅を広めたいと思っている」
‐若い世代への対応や課題は。
「現在、梅を食べているのは年齢層が高めの人たちで、これからのことを考えると40代以下の人たちにアプローチしていく必要がある。個人的な考えとして、ネット販売は長距離戦、店舗での販売は中距離戦、対面での販売は近距離戦と位置付けているのだが、梅は近距離戦の武器が少なく、弱い部分でもある。若い人はギフトを贈る習慣がなく、日常的に梅を食べない人もいる。我々としては梅干しを大事にしながら梅を素材にした新しい加工品の開発など、別のフィールドを見つけていく必要がある。若梅会には40名以上が所属しており、20代の人もいる。2つの組合の青年部組織だが、フラットな関係で多くの人と交流でき、情報も入ってくる。若梅会に参加すれば業界や梅のことを学ぶことができる、というような認識を持っていただけるような会になれば参加者がさらに増えるので、それを目指して活動していきたい」
【2023(令和5)年7月21日第5135号4面】
濱田
紀州田辺梅干協同組合 理事長 前田雅雄氏
生産者の意欲低下を懸念
協力して安定した産地作り
協力して安定した産地作り
4月27日に開催された紀州田辺梅干協同組合の総会で新理事長に就任した前田雅雄氏にインタビュー。第13代理事長としての抱負などについて話を聞いた。今年の作柄は3年連続の豊作型となり、加工向けの価格が不安定になったことで生産者の生産意欲の低下が懸念されるが、生産者、加工業者、行政が協力して安定した産地作りを行っていくことが重要だと強調した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐梅の生育や作柄状況について。
「今年は把握するのが難しい状況だ。作柄は平年作以上で、豊作型だと思っているが、落ち梅が特異な動きをしていたので、どれだけの量が塩漬に回ったのか予想するのが困難だ。もともと生育が早かったことに加え、台風などの影響で6月のはじめに相当量が集まってしまった。そのため、市場の価格も下がり、生産者は採算が合わないと判断し、一部では収穫放棄や廃棄も見られた。メーカーや加工業者が購入する野買いの価格も安値となってしまったのだが、生産者にとって厳しかったのが数量制限や規格制限、新規は購入してもらえない、といった条件が出されたケースも多かったようだ」
‐紀州梅の漬け込み状況は。
「原料の安定供給の観点から近年はメーカーが自社で梅を漬けるメーカー漬が増えていたが、今年を含めて3年連続の豊作型になっていることで在庫を抱えているメーカーの割合が多く、全体的な漬け込み意欲は弱かったと感じている。だが、タンクを増設して相当量を漬け込んだところもあれば、自社漬をゼロにしたところもあり、戦略としては両極端な動きとなっている。また、手間がかかることから漬け込みを抑えていた生産者は落ち梅の価格が安かったので、例年以上に漬け込んだと見ている」
‐落ち梅の価格が下がった要因は。
「3年連続の豊作型は過去に例がなく、そうなれば原料に余裕が出てくるのは当然のことだ。ただ、ここ数年はコロナの影響もあって売れ行きが低調となっており、販売量と生産量の差が大きくなってしまっている。この5年は良い作柄の年でも落ち梅、塩蔵ともにやや高い価格で推移しており、生産者の収入も良かった。生産意欲の低下が懸念されるが、今年だけの価格で生産を止める、ということはないと思う。だが、この状況が2、3年続くと今後は分からない」
‐梅の販売状況は。
「おととしくらいから動きは芳しくなく、前年の売上をクリアした企業は限りなく少ないと思う。そのため、産地としても2年前の原料を消化できていない。節約志向が高まる中、他の漬物と比べて単価が高い梅は買い物の対象から外れやすくなってしまっている。梅の健康機能性は広く知られていると思うが、これまで以上にPRしていくことが重要だ」
‐4月の総会で紀州田辺梅干協同組合の理事長に就任した。
「第13代目となる理事長という大役を仰せつかった。諸先輩方の功績を思い出すと大変身が引き締まる思いだ。皆さんのご理解とご協力をいただきながら、組合活動を行っていきたい。今後については販売に力を入れていきたいと考えている。梅の魅力を発信し、1日一粒食べていただけるように取り組んでいきたい。コロナも5類に移行したので前向きな方法を考えたい。紀州梅産地としては、一体となることが重要だと思っている。生産者、加工業者、行政が協力して地道ながらもPR活動を推進しつつ、安定した産地作りと梅の更なる普及に向けて尽力していきたい」
(千葉友寛)
◇ ◇
‐梅の生育や作柄状況について。
「今年は把握するのが難しい状況だ。作柄は平年作以上で、豊作型だと思っているが、落ち梅が特異な動きをしていたので、どれだけの量が塩漬に回ったのか予想するのが困難だ。もともと生育が早かったことに加え、台風などの影響で6月のはじめに相当量が集まってしまった。そのため、市場の価格も下がり、生産者は採算が合わないと判断し、一部では収穫放棄や廃棄も見られた。メーカーや加工業者が購入する野買いの価格も安値となってしまったのだが、生産者にとって厳しかったのが数量制限や規格制限、新規は購入してもらえない、といった条件が出されたケースも多かったようだ」
‐紀州梅の漬け込み状況は。
「原料の安定供給の観点から近年はメーカーが自社で梅を漬けるメーカー漬が増えていたが、今年を含めて3年連続の豊作型になっていることで在庫を抱えているメーカーの割合が多く、全体的な漬け込み意欲は弱かったと感じている。だが、タンクを増設して相当量を漬け込んだところもあれば、自社漬をゼロにしたところもあり、戦略としては両極端な動きとなっている。また、手間がかかることから漬け込みを抑えていた生産者は落ち梅の価格が安かったので、例年以上に漬け込んだと見ている」
‐落ち梅の価格が下がった要因は。
「3年連続の豊作型は過去に例がなく、そうなれば原料に余裕が出てくるのは当然のことだ。ただ、ここ数年はコロナの影響もあって売れ行きが低調となっており、販売量と生産量の差が大きくなってしまっている。この5年は良い作柄の年でも落ち梅、塩蔵ともにやや高い価格で推移しており、生産者の収入も良かった。生産意欲の低下が懸念されるが、今年だけの価格で生産を止める、ということはないと思う。だが、この状況が2、3年続くと今後は分からない」
‐梅の販売状況は。
「おととしくらいから動きは芳しくなく、前年の売上をクリアした企業は限りなく少ないと思う。そのため、産地としても2年前の原料を消化できていない。節約志向が高まる中、他の漬物と比べて単価が高い梅は買い物の対象から外れやすくなってしまっている。梅の健康機能性は広く知られていると思うが、これまで以上にPRしていくことが重要だ」
‐4月の総会で紀州田辺梅干協同組合の理事長に就任した。
「第13代目となる理事長という大役を仰せつかった。諸先輩方の功績を思い出すと大変身が引き締まる思いだ。皆さんのご理解とご協力をいただきながら、組合活動を行っていきたい。今後については販売に力を入れていきたいと考えている。梅の魅力を発信し、1日一粒食べていただけるように取り組んでいきたい。コロナも5類に移行したので前向きな方法を考えたい。紀州梅産地としては、一体となることが重要だと思っている。生産者、加工業者、行政が協力して地道ながらもPR活動を推進しつつ、安定した産地作りと梅の更なる普及に向けて尽力していきたい」
【2023(令和5)年7月21日第5135号6面】
紀州田辺梅干協同組合 https://kishu-tanabe-umeboshikumiai.com/
紀州うめまさ http://www.umemasa.co.jp/
山梨県漬物協同組合 理事長 長谷川正一郎氏
カリカリ用は1~2割減
今年も価格改定実施へ
今年も価格改定実施へ
小梅の生産量日本一を誇る山梨県。特産品ブランドとして著名な〝甲州小梅〟の作柄や原料状況、販売動向などについて、山梨県漬物協同組合理事長の長谷川正一郎氏に話を聞いた。今年の作柄は豊作型だったが、収穫期の降雨で収穫しきれず収量は平年の1~2割減、昨年並みの収量となった。ここ数年は不作が続き、原料はタイトな状況となっている。今年も価格改定が実施される見通しだが、小梅市場の維持に向けた取組の一端を披露した。
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年の甲州小梅の作柄は。
「今年の生育は概ね順調で、作柄は豊作型だった。だが、収穫期の5月7日と14日(ともに日曜日)に雨が降った影響で収穫しきれなかった。小梅は兼業農家が多く、収穫期になると農家の家族が収穫を手伝うケースが主流なのだが、休みとなる週末に雨が降ると収穫することができず、収量の減少につながってしまう。今年は収穫期の日曜日に雨が降ったため、カリカリ用の収穫を諦めたところもある。そのため、産地の漬け込み量は不作だった昨年並みに留まっているようで、平年の1~2割減と見ている。カリカリ用の原料については、1年間余裕を持って販売できるという業者はない。干し用は若干増えたかもしれないが、いずれにしても厳しい状況に変わりはなく、今年も限られた原料を大事に販売していく年になる」
‐生産農家の現状について。
「毎年、生産者が5%くらい減っている感覚で、当社も約300軒の農家から原料を仕入れているが、毎年10~15軒減っている。主な理由は高齢化と後継者不足。畑の管理や手入れはできても、収穫は人の手や力が必要になる。農家の子供たちは普段仕事をしているので、週末しか手伝うことができない。そのため、雨が降ると収穫に入れず、収穫量が減少する。新規で小梅の生産を始める人はいないので、収穫量が減ることはあっても増えることはない」
‐在庫状況は。
「サイズによってはかなりタイトになっている。特にSサイズは新物の出荷が始まるお盆過ぎまでつながらない可能性がある。今年もSサイズが少ないので、来年はもっと早く切れる可能性がある。厳密に言えば今年は不作ではなかったと思うが、天候要因で収穫しきれず量を確保することができなかった。収量減が5年続いていることもあり、今年も価格改定が必要になる」
‐価格改定が続いている。
「今年も価格改定を実施すれば3年連続となるので、消費者やユーザーが離れることを懸念している。市販用は切らすことができないため、業務用から撤退した業者も多い。市販用は量目調整や価格改定を行っても大きな需要の減少はない。だが、業務用は供給不足によって弁当から外れてしまった。仮に供給できるようになったとしても、その需要が元に戻ることはないだろう。業務用の市場は確実にシュリンクしている」
‐市場維持に向けた取組について。
「当社では地元の農協と協力し、小梅生産の維持を目的に、農協を通して苗を購入すれば当社が代金の半額を負担する、という取組を今年から始める。農家の負担を軽減し、少しでも小梅生産の減少を食い止めたいと考えている」
‐小梅業界の課題について。
「収穫量と市場をこれ以上減らさないようにすること。基本的な手段としては梅の買い上げ価格を上げるしかない。当社では仕入れが終わって、7月に生産者に代金を取りに来ていただくのだが、その時に『来年の価格も少し上げるので引き続き頑張って下さい』と声をかけている。また、今年はその時に『JAを通して苗を購入すれば長谷川醸造が半額を補助します』と記載した用紙を添えた。生産者のモチベーションを維持することが小梅市場の維持につながると思っている」
(千葉友寛)
◇ ◇
‐今年の甲州小梅の作柄は。
「今年の生育は概ね順調で、作柄は豊作型だった。だが、収穫期の5月7日と14日(ともに日曜日)に雨が降った影響で収穫しきれなかった。小梅は兼業農家が多く、収穫期になると農家の家族が収穫を手伝うケースが主流なのだが、休みとなる週末に雨が降ると収穫することができず、収量の減少につながってしまう。今年は収穫期の日曜日に雨が降ったため、カリカリ用の収穫を諦めたところもある。そのため、産地の漬け込み量は不作だった昨年並みに留まっているようで、平年の1~2割減と見ている。カリカリ用の原料については、1年間余裕を持って販売できるという業者はない。干し用は若干増えたかもしれないが、いずれにしても厳しい状況に変わりはなく、今年も限られた原料を大事に販売していく年になる」
‐生産農家の現状について。
「毎年、生産者が5%くらい減っている感覚で、当社も約300軒の農家から原料を仕入れているが、毎年10~15軒減っている。主な理由は高齢化と後継者不足。畑の管理や手入れはできても、収穫は人の手や力が必要になる。農家の子供たちは普段仕事をしているので、週末しか手伝うことができない。そのため、雨が降ると収穫に入れず、収穫量が減少する。新規で小梅の生産を始める人はいないので、収穫量が減ることはあっても増えることはない」
‐在庫状況は。
「サイズによってはかなりタイトになっている。特にSサイズは新物の出荷が始まるお盆過ぎまでつながらない可能性がある。今年もSサイズが少ないので、来年はもっと早く切れる可能性がある。厳密に言えば今年は不作ではなかったと思うが、天候要因で収穫しきれず量を確保することができなかった。収量減が5年続いていることもあり、今年も価格改定が必要になる」
‐価格改定が続いている。
「今年も価格改定を実施すれば3年連続となるので、消費者やユーザーが離れることを懸念している。市販用は切らすことができないため、業務用から撤退した業者も多い。市販用は量目調整や価格改定を行っても大きな需要の減少はない。だが、業務用は供給不足によって弁当から外れてしまった。仮に供給できるようになったとしても、その需要が元に戻ることはないだろう。業務用の市場は確実にシュリンクしている」
‐市場維持に向けた取組について。
「当社では地元の農協と協力し、小梅生産の維持を目的に、農協を通して苗を購入すれば当社が代金の半額を負担する、という取組を今年から始める。農家の負担を軽減し、少しでも小梅生産の減少を食い止めたいと考えている」
‐小梅業界の課題について。
「収穫量と市場をこれ以上減らさないようにすること。基本的な手段としては梅の買い上げ価格を上げるしかない。当社では仕入れが終わって、7月に生産者に代金を取りに来ていただくのだが、その時に『来年の価格も少し上げるので引き続き頑張って下さい』と声をかけている。また、今年はその時に『JAを通して苗を購入すれば長谷川醸造が半額を補助します』と記載した用紙を添えた。生産者のモチベーションを維持することが小梅市場の維持につながると思っている」
【2023(令和5)年7月21日第5135号6面】
長谷川醸造
3月21日号 梅特集インタビュー
中田食品株式会社 代表取締役社長 中田吉昭氏
今年度は増収の見通し
SNSで若年層にアプローチ
SNSで若年層にアプローチ
中田食品株式会社(和歌山県田辺市)の中田吉昭社長にインタビュー。今年の梅の開花状況きや梅干しの売れ行きなどについて話を聞いた。コロナ禍でやや低調だった売れ行きは底を打ち、今年度の業績(3月決算)については増収で着地する見通し。また、若い世代へのアプローチやファン作りのツールとしてSNSによる情報発信に手応えを感じており、今後も積極的に取り組んでいく方針を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――今年の梅の開花状況は。
「開花状況は例年並みとなっている。2月の半ばから20日くらいに満開期を迎えた。開花後は寒い日が続かなかったので、ミツバチも良く飛んでいた。色々な品種の花が一気に咲いた感じで、南高の交配にもつながったと思う。ここまでは順調にきている」
――2022年の梅干しの売れ行きと産地の原料在庫状況は。
「量販店の売れ行きはPOSデータの通り、数%下がっている。1年を通して見ると、夏は梅雨明けが早く、暑い日も多かったので売れ行きは良かったが、夏以外はやや低調で、全体でも5%くらいのマイナスとなっていると思う。売れ筋は低級原料の普及品で、中国産の梅も根強い人気がある。昨年は円安の影響があったので値上げを実施したが、値上げしても売れ行きは変わらなかった。ただ、今後は物価が上昇している中で消費者の生活防衛意識がますます高まっていくため、梅干し業界はさらに厳しい状況になると予想している」
――ここ数年の御社の業績について。
「弊社の数年間の売上げは、2018年にテレビ番組と猛暑の影響で特需が発生し、弊社も1年間で約20億円伸びたが、その翌年は紀州梅が凶作となり原料価格高騰で、値上げを余儀なくされ売上が6%ほど落ちた。2020年からのコロナ禍に於いて、売上げは若干落ちたが減少を最小限に抑える努力を続け、本年度は売上げを維持して前年と変わらない着地を予想している」
――在庫状況と値上げの動きについて。
「在庫状況は各社で異なるが、紀州は2年続けて良い作柄となっていることもあり、産地在庫としては余裕がある状況。販売面が課題となる。昨年は一昨年と比較して作柄はやや悪かったが、原料価格が落ち着いていたこともあり製品価格も値上げにはならなかった。包装資材、調味料、段ボールの他、物流費や電気代など、様々な製造コストが上がっているが、原料価格が安定していることと企業努力によって吸収している形だ」
――若年層へのアプローチについて。
「梅干し業界はこれからも買い続けていただくための努力をしていく必要がある。梅干しの主な購買層は中高年世代だが、梅干しが好きな若い人も多い。2月11日に和歌山市で開催された東京ガールズコレクション(TGC)で、ケータリングのブースを出したところ、モデルさんたちから大変好評をいただいた。若い女性への発信力が大きい人気モデルやタレントが『梅干しが美味しい!大好き』とSNSにアップしてくれて大きな反響を呼んでいる。若い人は梅干しが嫌い、梅干しを食べない、といったイメージを持っている人も多いと思うが、実際はそうではないことがうかがえる。そのような意味でも潜在需要はまだまだあると思っている」
――今年1月に和歌山の梅干しメーカーが発信したSNSの情報が話題となった。
「かなり大きな話題になり、改めてそういう時代なのか、ということを実感した。表現の仕方には注意が必要だが、個人的には梅干しが話題になったことはポジティブに捉えている。弊社もSNSによる情報発信に取り組んでいるが、着実にファンが増えていると感じている。今後も上手く活用して梅と弊社の魅力を発信していきたいと考えている」
◇ ◇
――今年の梅の開花状況は。
「開花状況は例年並みとなっている。2月の半ばから20日くらいに満開期を迎えた。開花後は寒い日が続かなかったので、ミツバチも良く飛んでいた。色々な品種の花が一気に咲いた感じで、南高の交配にもつながったと思う。ここまでは順調にきている」
――2022年の梅干しの売れ行きと産地の原料在庫状況は。
「量販店の売れ行きはPOSデータの通り、数%下がっている。1年を通して見ると、夏は梅雨明けが早く、暑い日も多かったので売れ行きは良かったが、夏以外はやや低調で、全体でも5%くらいのマイナスとなっていると思う。売れ筋は低級原料の普及品で、中国産の梅も根強い人気がある。昨年は円安の影響があったので値上げを実施したが、値上げしても売れ行きは変わらなかった。ただ、今後は物価が上昇している中で消費者の生活防衛意識がますます高まっていくため、梅干し業界はさらに厳しい状況になると予想している」
――ここ数年の御社の業績について。
「弊社の数年間の売上げは、2018年にテレビ番組と猛暑の影響で特需が発生し、弊社も1年間で約20億円伸びたが、その翌年は紀州梅が凶作となり原料価格高騰で、値上げを余儀なくされ売上が6%ほど落ちた。2020年からのコロナ禍に於いて、売上げは若干落ちたが減少を最小限に抑える努力を続け、本年度は売上げを維持して前年と変わらない着地を予想している」
――在庫状況と値上げの動きについて。
「在庫状況は各社で異なるが、紀州は2年続けて良い作柄となっていることもあり、産地在庫としては余裕がある状況。販売面が課題となる。昨年は一昨年と比較して作柄はやや悪かったが、原料価格が落ち着いていたこともあり製品価格も値上げにはならなかった。包装資材、調味料、段ボールの他、物流費や電気代など、様々な製造コストが上がっているが、原料価格が安定していることと企業努力によって吸収している形だ」
――若年層へのアプローチについて。
「梅干し業界はこれからも買い続けていただくための努力をしていく必要がある。梅干しの主な購買層は中高年世代だが、梅干しが好きな若い人も多い。2月11日に和歌山市で開催された東京ガールズコレクション(TGC)で、ケータリングのブースを出したところ、モデルさんたちから大変好評をいただいた。若い女性への発信力が大きい人気モデルやタレントが『梅干しが美味しい!大好き』とSNSにアップしてくれて大きな反響を呼んでいる。若い人は梅干しが嫌い、梅干しを食べない、といったイメージを持っている人も多いと思うが、実際はそうではないことがうかがえる。そのような意味でも潜在需要はまだまだあると思っている」
――今年1月に和歌山の梅干しメーカーが発信したSNSの情報が話題となった。
「かなり大きな話題になり、改めてそういう時代なのか、ということを実感した。表現の仕方には注意が必要だが、個人的には梅干しが話題になったことはポジティブに捉えている。弊社もSNSによる情報発信に取り組んでいるが、着実にファンが増えていると感じている。今後も上手く活用して梅と弊社の魅力を発信していきたいと考えている」
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合 理事長 殿畑雅敏氏
利益の確保が課題
農家とともに歩み産地を維持
紀州みなべ梅干協同組合殿畑雅敏理事長(株式会社トノハタ社長)にインタビュー。梅干しの売れ行きや在庫状況などについて話を聞いた。ここ2年は良い作柄が続いており、今年も良好な開花状況となっている。原料在庫は問題ない状況だが、紀州梅産地も農家の後継ぎが課題となっている。殿畑理事長は農家の収入の安定化を図ることが産地の維持につながると指摘。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示す必要性を強調した。
◇ ◇
――梅干しの売れ行きは。
「全般的に良くない。昨年から物価高が続き、日常生活に必要なものかどうかの線引きが厳しくなったことが影響していると思う。中国産の梅は円安の影響で仕入れ価格が上がっている。それに加え、製造コストも上昇しており、各社値上げを行っている。国産についても製造コストは上がっているものの、原料に余裕があり価格も安定しているため価格改定の動きにはなっていない。ただ、調味資材、物流費、電気代などの製造コストが短いサイクルで上昇を続けており、利益の確保は大きな課題となっている」
――中国と紀州の開花状況は。
「中国の主産地は6、7割作という話も聞いているが、紀州は順調に開花している。日本の作柄は中国と連動することが多いので、終わってみないとはっきりとしたことは分からない。今の時点で一喜一憂することはあまり意味がない」
――農家の生産意欲について。
「農家は価格の安定を求めている。一昨年は豊作で、昨年は平年作となったが、原料価格が大きく下がることはなかったのでこの2年の収入は良かったと思う。今年は作柄にもよるが、極端な動きにはならないと予想しており、そのような意味では安定した価格で推移すると見ている。紀州も農家の後継ぎの問題が浮上しているが、後を継いでもらうためにも価格の安定化を図っていかなければならない。過去には再生産が難しい価格となったこともあるが、農家、加工業者、流通、消費者のみんなが納得できる価格帯を模索していくことが重要だ」
――今年は価格訴求の動きが出てくる可能性もある。
「各社自由競争の下で経営されているので、コメントは控えたい。紀州梅産地では豊作時に価格が下がり、不作時に価格が上がる、ということが繰り返されてきた。農家の後継者がしっかりと後を継いで産地を維持していくためには原料価格の安定が必要。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示さなければ産地が30年、50年、100年後まで続くことはない。年によって作柄が異なるので、多少の変動はあったとしても目先の数字のために動くのではなく、5年、10年といったスパンでとらえる必要がある」
――今後の見通しは。
「予報では今年の夏は暑くなるとのことなので、梅干しが売れる環境になることを期待している。また、5月には新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行するため、より外出機会が増えることが想定される。暑い日の外出は熱中症対策が必要になってくるため、梅干しが活躍する場は増えると見ている」
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合の加盟社一覧
トノハタ HP
◇ ◇
――梅干しの売れ行きは。
「全般的に良くない。昨年から物価高が続き、日常生活に必要なものかどうかの線引きが厳しくなったことが影響していると思う。中国産の梅は円安の影響で仕入れ価格が上がっている。それに加え、製造コストも上昇しており、各社値上げを行っている。国産についても製造コストは上がっているものの、原料に余裕があり価格も安定しているため価格改定の動きにはなっていない。ただ、調味資材、物流費、電気代などの製造コストが短いサイクルで上昇を続けており、利益の確保は大きな課題となっている」
――中国と紀州の開花状況は。
「中国の主産地は6、7割作という話も聞いているが、紀州は順調に開花している。日本の作柄は中国と連動することが多いので、終わってみないとはっきりとしたことは分からない。今の時点で一喜一憂することはあまり意味がない」
――農家の生産意欲について。
「農家は価格の安定を求めている。一昨年は豊作で、昨年は平年作となったが、原料価格が大きく下がることはなかったのでこの2年の収入は良かったと思う。今年は作柄にもよるが、極端な動きにはならないと予想しており、そのような意味では安定した価格で推移すると見ている。紀州も農家の後継ぎの問題が浮上しているが、後を継いでもらうためにも価格の安定化を図っていかなければならない。過去には再生産が難しい価格となったこともあるが、農家、加工業者、流通、消費者のみんなが納得できる価格帯を模索していくことが重要だ」
――今年は価格訴求の動きが出てくる可能性もある。
「各社自由競争の下で経営されているので、コメントは控えたい。紀州梅産地では豊作時に価格が下がり、不作時に価格が上がる、ということが繰り返されてきた。農家の後継者がしっかりと後を継いで産地を維持していくためには原料価格の安定が必要。再生産可能な価格を提示し、ともに歩んでいく姿勢を示さなければ産地が30年、50年、100年後まで続くことはない。年によって作柄が異なるので、多少の変動はあったとしても目先の数字のために動くのではなく、5年、10年といったスパンでとらえる必要がある」
――今後の見通しは。
「予報では今年の夏は暑くなるとのことなので、梅干しが売れる環境になることを期待している。また、5月には新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に移行するため、より外出機会が増えることが想定される。暑い日の外出は熱中症対策が必要になってくるため、梅干しが活躍する場は増えると見ている」
(千葉友寛)
【2023(令和5)年3月21日第5123号2面】
紀州みなべ梅干協同組合の加盟社一覧
トノハタ HP
紀州田辺梅干協同組合 理事長 大谷喜則氏
春夏に向けて販売強化
求められるイノベーション
紀州田辺梅干協同組合の大谷喜則理事長にインタビュー。梅業界の現状や今後の見通しなどについて話を聞いた。現在、売場で主流となっている調味梅は市場に登場してから約50年が経っており、その歴史とともに歩んできた大谷理事長は梅産業の更なる発展に向けてイノベーションの必要性を指摘。若い世代が力を発揮できる環境を整え、持続可能な梅産業を構築していく意向を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――梅の開花状況は。
「今年は気温が低く、花が咲くタイミングがやや遅くなった。紀州では開花が遅い年は豊作になると言われており、気候も安定しているので現時点では良い作柄になると予想されている」
――梅干しの売れ行きは。
「紀州の作柄は2年続けて良かったのだが、梅干しは漬物売場の中でも高価格帯で、コロナの影響や物価高による節約志向が高まっているため売れ行きは芳しくない。産地の原料在庫は余裕がある状況で、タンクを空けて新物を漬けられるように春夏に向けて販売を強化していく必要がある。農家の生産意欲を維持するためにも原料をバランス良く動かしてくことが重要で、今年は豊富な原料をどのように販売につなげていくか、ということが課題だ」
――梅メーカーのSNSが話題となった。
「SNSは情報が一気に拡散されるので、怖さを感じた部分もある。だが、その影響力が良い方向に向けば良いPRになるし、漬物があまりアプローチできなかった若年層にも情報を発信できる可能性もある。青年部組織の若梅会では、SNSを活用して梅をPRする事業がスタートしている。内容についてはこれから詰めていく方向で取り組んでいる。食べ方や梅の健康機能性に関する情報を発信できればと思っている」
――調味梅の歴史について。
「紀州で調味梅が生まれて約55年が経つ。昔は白干しが一般的だった。梅を調味液に漬け込む調味梅は異端的な存在で、当時は批判的な意見もあったようだが、干しの逆の発想でドリップも出るが、塩分や酸味は抑えられ、美味しい味付けで食べやすくなったことで、支持されるようになっていった。ご飯を食べるのに白干しは1粒で十分だったが、調味梅は3粒4粒と食され、消費量も増加した。かなり前の話では、紀州で漬けられる梅の量は年間50万樽(1樽10㎏)だったが、現在は平年作の年で250万樽と言われている。そのような流れで生産者も業者も増えて現在の梅産業が形成された」
――今後の見通しは。
「紀州の梅産業でも世代交代が進んでいる。まだ後を継いでいない企業でも子息が会社で働いているなど、世代交代の準備を進めているように見受けられる。デジタル社会となり、今後も予想を上回る速度で時代が進んでいくだろう。若い人が力を発揮しなければ企業も産業も置いていかれてしまう。現在、梅干し売場の主流となっているのは調味梅だが、これまでは大きな変化もなく売場を維持できた。しかし、これからは次の時代、世代に向けて持続可能な梅産業を構築していくためにもイノベーションが必要な時にきている。コロナ禍で思うような事業を行うことができなかったが、若梅会を始め、これからの梅産業を支える若い力に期待している」
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
紀州田辺梅干協同組合の加盟社一覧
大谷屋 HP
求められるイノベーション
紀州田辺梅干協同組合の大谷喜則理事長にインタビュー。梅業界の現状や今後の見通しなどについて話を聞いた。現在、売場で主流となっている調味梅は市場に登場してから約50年が経っており、その歴史とともに歩んできた大谷理事長は梅産業の更なる発展に向けてイノベーションの必要性を指摘。若い世代が力を発揮できる環境を整え、持続可能な梅産業を構築していく意向を示した。(千葉友寛)
◇ ◇
――梅の開花状況は。
「今年は気温が低く、花が咲くタイミングがやや遅くなった。紀州では開花が遅い年は豊作になると言われており、気候も安定しているので現時点では良い作柄になると予想されている」
――梅干しの売れ行きは。
「紀州の作柄は2年続けて良かったのだが、梅干しは漬物売場の中でも高価格帯で、コロナの影響や物価高による節約志向が高まっているため売れ行きは芳しくない。産地の原料在庫は余裕がある状況で、タンクを空けて新物を漬けられるように春夏に向けて販売を強化していく必要がある。農家の生産意欲を維持するためにも原料をバランス良く動かしてくことが重要で、今年は豊富な原料をどのように販売につなげていくか、ということが課題だ」
――梅メーカーのSNSが話題となった。
「SNSは情報が一気に拡散されるので、怖さを感じた部分もある。だが、その影響力が良い方向に向けば良いPRになるし、漬物があまりアプローチできなかった若年層にも情報を発信できる可能性もある。青年部組織の若梅会では、SNSを活用して梅をPRする事業がスタートしている。内容についてはこれから詰めていく方向で取り組んでいる。食べ方や梅の健康機能性に関する情報を発信できればと思っている」
――調味梅の歴史について。
「紀州で調味梅が生まれて約55年が経つ。昔は白干しが一般的だった。梅を調味液に漬け込む調味梅は異端的な存在で、当時は批判的な意見もあったようだが、干しの逆の発想でドリップも出るが、塩分や酸味は抑えられ、美味しい味付けで食べやすくなったことで、支持されるようになっていった。ご飯を食べるのに白干しは1粒で十分だったが、調味梅は3粒4粒と食され、消費量も増加した。かなり前の話では、紀州で漬けられる梅の量は年間50万樽(1樽10㎏)だったが、現在は平年作の年で250万樽と言われている。そのような流れで生産者も業者も増えて現在の梅産業が形成された」
――今後の見通しは。
「紀州の梅産業でも世代交代が進んでいる。まだ後を継いでいない企業でも子息が会社で働いているなど、世代交代の準備を進めているように見受けられる。デジタル社会となり、今後も予想を上回る速度で時代が進んでいくだろう。若い人が力を発揮しなければ企業も産業も置いていかれてしまう。現在、梅干し売場の主流となっているのは調味梅だが、これまでは大きな変化もなく売場を維持できた。しかし、これからは次の時代、世代に向けて持続可能な梅産業を構築していくためにもイノベーションが必要な時にきている。コロナ禍で思うような事業を行うことができなかったが、若梅会を始め、これからの梅産業を支える若い力に期待している」
【2023(令和5)年3月21日第5123号4面】
紀州田辺梅干協同組合の加盟社一覧
大谷屋 HP